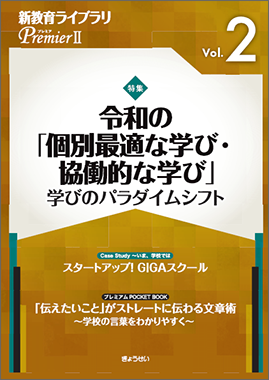特集 「指導の個別化」「学習の個性化」で授業のモードを変える
授業づくりと評価
2021.11.19
特集 令和の「 個別最適な学び・協働的な学び」 〜学びのパラダイムシフト〜
「指導の個別化」「学習の個性化」で授業のモードを変える
上智大学名誉教授
加藤幸次
(『新教育ライブラリ Premier II』Vol.2 2021年6月)
歴史軸からみる個性重視の教育

──個性重視の教育にはどのような背景があるのでしょうか。
まず、個に応じた指導や個性重視の考えは古くからあり、イギリスのインフォーマル教育やアメリカのオープン教育にそのルーツが見られます。イギリスのインフォーマル教育は、主に子どもの興味・関心に即し、教科の枠を取り払ったトピック学習などが特色の一つで、アメリカのオープン教育は、それを取り入れ、学校建築など学習環境にも配慮された児童中心の教育として、1970年代をピークに実践されていました。
日本では、1984年までに出された臨時教育審議会答申において、自己教育力の育成や生涯学習体系への移行とともに、個性尊重の原則が打ち出されました。そうした中で、いくつかの学校現場では個性重視の教育が試みられ、オープンスペースを持つ学校も登場し、いわゆる「オープン教育」の実践が1990年から2000年頃をピークに進められました。
しかし、「ゆとり教育」といわれた1998年の学習指導要領改訂を契機に、学力低下論が台頭し、個性重視の教育も矢面に立たされます。
そこで、個性化教育を進めようとする学際や現場では、系統的な知識を教える部分ではできるだけ指導を個別化していき、一方では子どもたちが選んだテーマを子どもたち自身が中心となって学びを展開していくことが目指されていきます。当時の学習指導要領が学力向上を図っていこうとする動きの一方で、学校現場では、「指導の個別化」「学習の個性化」に取り組む動きもあったわけです。
こうした中で、今回の学習指導要領が求める資質・能力の育成と合致する形で、「指導の個別化」
「学習の個性化」が打ち出されたことを押さえておく必要があるでしょう。要するに、この二つはこれまでの理論的・実践的な背景をもったものとして登場してきたと捉えてよいと思います。
──今回の答申では、「指導の個別化」「学習の個性化」が打ち出されてきました。
そもそも「指導の個別化」という概念は以前からあり、例えば、京都教育大学の佐伯正一教授(現名誉教授)によって1960年代から唱えられていました。
それは、明治期にそれまでの等級という習得主義の学級編制から同年齢集団による学級編制に大転換したことが背景にあります。しかし、年齢主義が確立してくると、学力格差が生まれてきます。そこで1930年代に能力別の学級編制を取り入れる試みがなされましたが、今度は年齢差による差別感が問題になりました。そうした中で、佐伯教授を中心に個別指導の考え方が出てきます。能力別指導を個別指導によって進めていこうという考えが生まれてきたわけです。つまり、「指導の個別化」の原初は能力別指導であったと言えます。
一方、「学習の個性化」については、1964年の第1回国際数学教育調査(TIMSS〈国際数学・理科教育動向調査〉の前身)において日本が参加国中第2位となる一方で日本の子どもたちには創造力が足りないということも指摘されました。そこで、創造性を開発するため、「学習の個性化」が東京大学の東洋教授(故人)らによって提唱されることになります。
「指導の個別化」は、理念として当時の教育に合致し、生徒指導の分野も含めて多くの学校に受け入れられて、その後「個に応じた指導」として定着していきます。子どもの創造性を養う観点からの「学習の個性化」については、「生きる力」を育む上でも必要なものとされ、生活科・総合的な学習の時間の創設につながっていきました。
「指導の個別化」には個に応じた指導法の開発が不可欠

──「指導の個別化」は、どのように捉えたらよいでしょうか。
1957年のソビエト連邦(当時)によるスプートニク打ち上げという衝撃(スプートニク・ショック)を受け、1960〜70年代にかけてアメリカでも日本でも、自然科学教育の振興を図っていきます。
日本では、1968年の学習指導要領改訂において「教育内容の現代化」を打ち出し、最先端の科学技術の成果を反映させた教育に取り組みます。しかし、一方で知識の習得を重視したために、いわゆる「落ちこぼれ」となる子どもたちが数多く現れることとなり、社会問題化していきました。
一方、アメリカでは、同様に「国防教育法」(1958年)に基づいて自然科学教育を進めていましたが、教育内容と併せて教育方法の改善についても大々的に研究が進められていました。私が所属したウィスコンシン大でもIGE(Individual Guided Education;個別にガイドされた教育)を研究する政府出資のセンターを持っており、私も教鞭を取って実践開発に携わることになりました。そこで特に問題となったのは、何を基準に学力別・能力別指導を行うかということでした。そもそもアメリカには学力という概念がないので、到達度という概念を基準として採用しました。つまり、子どもの学習ペースに着目したわけです。同じ課題に取り組んでも答えに到達する速さは子どもによって違います。この問題を解決するためには指導法の開発が欠かせません。そこで、スタンフォード大のリー・クロンバック教授(アメリカの教育心理学者・故人)は「学習適性」という概念を作り出します。人にはそれぞれ適性があり、志向に違いがある。それとマッチングさせる指導法を開発する必要性を説き、「適性処遇交互作用」(学習者の適性によって教授方法の効果が異なること)を提唱し、日本でも慶應義塾大学の並木博氏(現早稲田大学名誉教授)によって研究が進められました。これはまさに迷路をさまようような難しい課題ですし、突き詰めると無学年制につながっていきますが、同年齢集団による学級編制は、日本でもアメリカでも、その成り立ちや社会情勢などから壊せないシステムとなっていました。つまり、「学習適性」に応じた指導を行うためには、指導法の開発しかないわけです。そこで、到達度の違いを単に学習ペースの問題として捉えるのではなく、子どもの思考や流儀のようなものを見とることが求められました。例えば、この子は演繹的な思考をもっているのか、帰納的思考をもっているのか、論理で考えるタイプか、視覚的に思考するタイプか、などといった子どもの思考のスタイルに合わせた教材を処遇し、指導を行う研究が進められていきました。つまり、「指導の個別化」には、できるだけ子ども一人一人にアプローチできる指導法の開発が不可欠であるということなのです。
このことを踏まえて、これからの学習指導について考えれば、「指導の個別化」を、「主体的・対話的で深い学び」や「学習の自己調整力」など、子どもの思考や学び方へのアプローチが求められている新たな学習指導課題として捉え、実践していくことが必要だと思います。従来の「個に応じた指導」の延長として平板に捉えるのではなく、これまでの研究や実践に基づいた理念と方法論を勉強し、自分自身の指導法として確立させ、しっかりと取り組んでいかなければ、「令和の日本型学校教育」も校門を通ったとたんに骨抜きになってしまいかねません。子どもの適性に合った指導法の開発に、ぜひ学校全体で取り組んでいってほしいと思います。