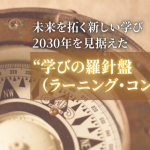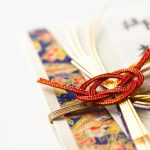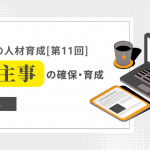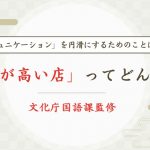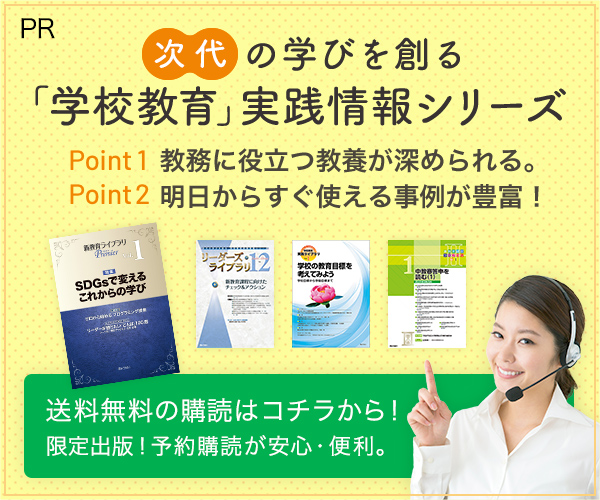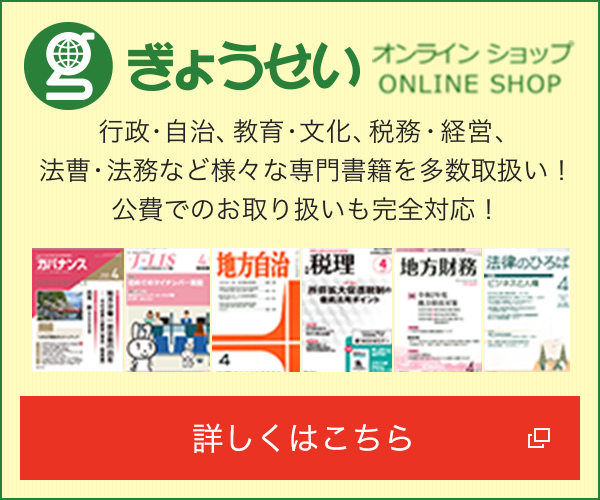theme 6 学び続ける校長
授業づくりと評価
2023.07.12
サークルは「頭蓋」のよう

社長と副社長は、社長と守衛さんくらいの距離があると言われる。つまり経営者は孤独だ。これまでの話から分かるように、対話相手として本をオススメする。詩人のブロツキイは「話相手としては友人や恋人よりも書物のほうが頼りになる」と述べている(『私人』)。ただ本以外にもその孤独を共有できる相手はいる。
ある出版関係の社長をしている方は、自宅に帰る際に、たまに立ち寄る服屋があるそうである。そのお店で扱っている洋服そのものは少し趣味に合わないそうだが、店主とは自営業としての悩みや課題を共有でき、語り合っているなかで、様々なヒントが得られるそうである(話すだけでは申し訳ないから、月に一度は洋服を買うことにしているそうだ)。
またある副校長さんは周囲の校長さんを見ていて、あまり参考になるモデルがいないと感じ、反面教師にも限界があるため、自分で学びたいと人づてに私に連絡をくれた。私が「何を勉強したいですか」と尋ねると「それが分かっていたら連絡しません」とおっしゃった。「ではとにかく本を一緒に読みましょう」とお伝えした。
小林秀雄は「行動するように考え、考えるように行動する」と言ったが、学内外を問わず、気になったら出かけて行って、そこにいる人と話し、何かを得ようとするという別の先生も知っている。彼女の学校経営上の判断や若い人の育成の仕方は自ずと洗練されていく。「知識」とは頭で「知る」だけではダメで、「識る」ということのためには、自己内対話と他者との対話が必要である。
以上の例は、その対話の場を家庭(第一の場所)、職場(第二の場所)以外に持っているということである。そういう学習のための対話の場を「サードプレイス(第三の場所)」と呼ぶ。行政研修が「フォーマル」であり、家庭や趣味が単に「プライベート」であるのに対して、「インフォーマル(自主的)」かつ「パブリック(他者がいて公共的)」というのがポイントである。
「分かりやすい知識」は、私たちの思考や行動を多くの場合、硬直化させ、結果的に問題解決を遅らせる。「すぐに使える知識」は使い捨ての発想に基づき、長期的には自分の学びが使い捨てされる事態も生じかねない。そのような学びを超えるものとして、日常的なサークル的な学びの重要性を再確認したい。
長年、それを追求した鶴見俊輔さんは、「サークルは、私にとっては、自分の頭蓋のように感じられる。ものを考える場であり、そこで思いつくことが多い」と述べた(『教育再定義への試み』)。肩肘張らずに、新聞記事や小説、絵画、映画など気楽に話し合える場を一つでも見つけてみてほしい。
本を読もう

先日、私のゼミに所属する大学生と話をしていたら、「一日にスマートフォンを6時間使っている」と言っていた。オンライン授業などを含めずにである。とても真面目で熱心な学生である。「忙しい」「時間がない」となるわけであるが、この状況をいかに学習によって変えるか、経験の質を高めるかが教育にとって重要になる。私は「一日に一句、スマホについての川柳を詠んでみてはどうですか」と提案してみた。次の週に会うと、まだ慣れてはいないが一生懸命一日一句ノートに書いてつくっていた。
句作の際には鍵のかかる郵便受けにスマホをしまうなどの工夫もしたそうで、スマホの使用時間は3時間半になったそうである。そして、さらに次の週に会うと、「川柳では物足りないので、俳句にして、歳時記も買った」と彼は言い、「景色や季節を肌で感じるようになり、生活リズムも変わってきた」と。わずか2週間であるが、スマホの使用時間も一日2時間ほどになったそうで、非常に素敵な句を朗詠してくれた。さらに私は「どの俳人をモデルにしますか」と尋ね、「松尾芭蕉や飯田蛇笏はどうですか」と伝え、金子光晴と中原中也の本をプレゼントした。
「学ぶ」とは「真似ぶ」であるので、鍛錬はこのようにちょっとしたきっかけで始まる。詩人の茨木のり子さんは「ほんとうに教育の名に値するものがあるとすれば、それは自分で自分を教育できたときではないのかしら」と言っている(『詩のこころを読む』)。小林秀雄は「対話とは、相手の魂のうちに、言葉を知識とともに植えつける事だ」とソクラテスの言葉を引いて言った。
「本を読もう。もっと本を読もう。もっともっと本を読もう。」「どんなことでもない。生きるとは、考えることができるということだ。」長田弘さんの有名なこの詩をいつも私は想い出している。2022年サッカーW杯の対ドイツ戦後に、岡田武史さんが「歩いていて勝手に富士山の頂上に辿り着くことはない。高い志とそのための準備が必要だ」と言っていた。学習の継続には根気が必要である。新しい環境や仕事に向き合う際には、不安を感じるのは自然なことである。それ自体を抑え込む必要はない(そういうことができると主張する人や本は多いが)。そういう自然な感情は自然に抱いたまま、日々、決められた時間に決められた対話を行ってほしい。私もタイマーを7分セットして、毎朝、行っている。日記や詩の朗読もオススメである。体力も必要なので、食事、睡眠に加え、散歩や筋トレなどフィジカル面の向上もぜひ一緒に意識してほしい。最初から欲張らずに何か一つでいいと思う(そのうちできることが増えてくる)。
本だとまずは小林秀雄の『読書について』。池田雅延さんの「随筆 小林秀雄」と若松英輔さんの「私の本」という連載記事もインターネットで簡単に読めるのでオススメである。池田さんの連載第25回には、小林秀雄が恩師・辰野隆さんの最終講義で教え子として謝辞を述べた感動的なシーンが次のように紹介されている。
「真の良師とは、弟子に何物かを教える者ではない、弟子をして弟子自身に巡り会わせる者である、とは、周知のようにソクラテスの言葉であるが、その意味で辰野先生は、まことに真の良師であった。僕たちが乱脈な青春を通じて、先生のお蔭でどうやって自分自身に巡り会うことができたかは、僕たち銘々が身に徹して知っていることである。」
学ぶ際、ぜひ、良書に出逢ってほしいと思う。選書の基準は再読、再々読に値するか。読書百遍。小道に由って自分を浪費せず、どこまでも自分には期待してほしい。
ちなみに、私の読書の師匠は、元高校教員であり、出版社社長をし、作家、詩人、俳人でもある三浦衛さんだ。私にとっての大道は、彼の教えと彼の著書(『文の風景―ときどきマンガ、音楽、映画』)が示してくれている。
大学の授業で彼の会社を訪問したことがある。彼の詩を一つ朗読してほしいとお願いしたところ、出身地の秋田弁にして朗読してくれた。すると、彼は途中で感極まり涙を流した。学生はどう受け止めればいいか戸惑っていたが、私は三浦さんらしいと感じた。後日、お礼を伝えるとあっけらかんと「母親のお腹の中にいる時から聴いている言葉を声に出し耳で聴いて感情が込み上げてくるのは至って当然のことですよ」とおっしゃった。人と正対し、自分の言葉で生きるとはこのようなことを言うのだと感じた。
Profile
末松裕基 すえまつ・ひろき
東京学芸大学准教授。専門は学校経営学。学校経営政策、スクールリーダー育成を研究。編著書に『現代の学校を読み解く』(春風社、2016年)、『教育経営論』(学文社、2017年)、『未来をつかむ学級経営』(学文社、2016年)、訳書に『教育のリーダーシップとハンナ・アーレント』(春風社、2020年)。