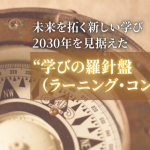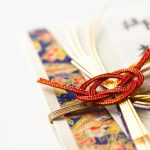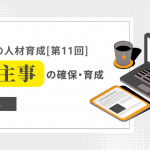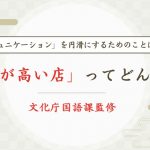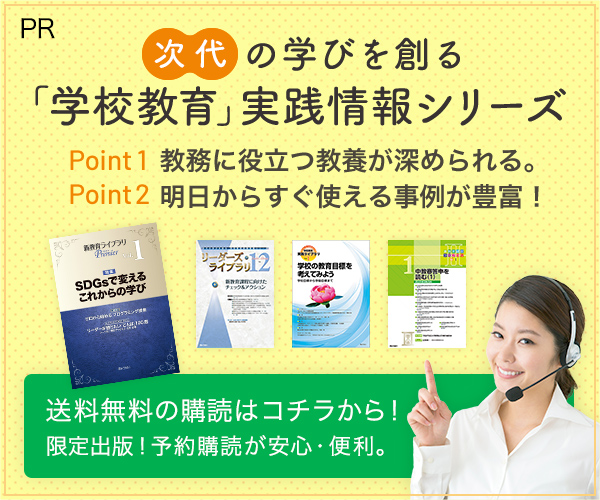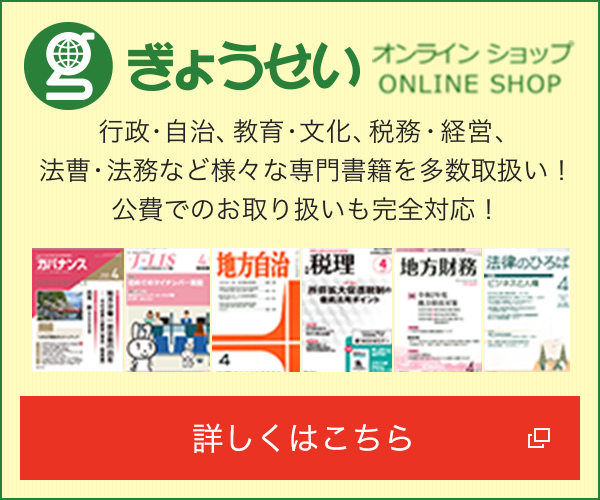theme 6 学び続ける校長
授業づくりと評価
2023.07.12
theme 6 学び続ける校長
東京学芸大学准教授
末松裕基
行くに径(こみち)に由らず
これは論語で紹介されている言葉で、漢学者の諸橋轍次(てつじ)さんの本で知った(『誠は天の道―東洋道徳講話』)。何かを学ぶ時、極める時に一つの指針になるのではないだろうか。私も最近、学校の先生と接する時、特に、先生方の学習を支援する際に、繰り返し反芻し、大切にしている言葉である。
新たなことに接し、見通しを立てにくい時、私たちは不安を抱いてしまうことから、どうしても安易なテクニックや答えを求めてしまう。状況を打破しようと焦ってしまうことも多い。それで結局、どん詰まり、来た道を引き返すか、問題を無かったことにするか、問題にすら気づかずに周囲を疲弊させるということが起きうる。目先の損得や打算でごまかさず、つまり、小道を通らず、大道を歩もうということである。
「焦慮は罪である」とカフカは言ったそうだが物事を考え、学ぶというのはどういうことだろうか。小林秀雄が指摘しているが、「かんがえる」はもともと「かむかふ」で、「か」は「か・ぼそい」や「か・よわい」のように特段意味はない。「むかふ」の「む」は「み」の古語で「身」を意味する。「かふ」は「かう」で「交う」を意味する。つまり、何か事前に分析視点を持って、それを偉そうに物事や状況に当てはめることが「考える」ことを意味するのではない。全身で物事そのものと向き合い交わり、その中で感じ悶え浮かび上がってきたことを受け止めていく、そういうことが「考える」ということだと小林秀雄は私たちに教える。小手先の科学的装い、今で言えば、ハウツー本やエビデンスに私たちが囚われてしまうことへの警鐘を鳴らしていると言える。
続けるのが難しい

校長として日々の現実に向き合うことは、皆さんが努力されていることだと思う。小林秀雄は「困難は現実の同義語であり、現実は努力の同義語である」とも言った。現実と向き合うことは決して簡単なことではないが、小道に由らずに、何をどう努力するかが大切になってくる。
「鍛錬ということほど美しいものは他にない」とポール・ヴァレリーは言ったそうだが、何かを学ぼうとする時に、続けるのが一番難しかったりする。「ひらめきと持続力、この二つを満たす人は本当に少ない」と鶴見俊輔さんも言っていた。
こういうことを考える際に私が思い出すことは、「寝ていて人を起すことなかれ」という石川理紀之助の言葉である。明治・大正の過酷な時代を生き抜き農聖と呼ばれた人で、当時、深刻な問題を抱えることの多かった農村を訪ね歩き、身を挺して農民を指導した。彼は毎日午前1時に起き、その日に自らがなすべきことを考え、午前3時に農民を起こしたそうである。つまり、自分は肩肘を付き、人に指図ばかり偉そうにするようなことは決してなく、また、自らがまず身を起こし正して日々努力を重ねたという二つの意味を先の言葉は表している。
時代は変る

それでは、何をどのように学ぶか。至る所にヒントはある。
例えば、私は最近、若い人に接する際に、理解できないことが以前より増えてきた。若い人が何を考え、どう感じているか、すぐには掴めないことが多くなった。直接、様々な形でコミュニケーションを取ろうとすることももちろんするが、やはりこちらに都合よく解釈したり、自分の正しさに囚われそうになったりする。その際、ボブ・ディランの「時代は変る」(The Times They Are A-Changin’)を何度も聴く。歌詞を書き写し、一緒に声に出し、目の前で起きたことを改めて考えてみたりする。「自分が理解できないことを批判するな」という歌詞は突き刺さる。
また、知り合いにこんな先生もいる。彼は教員生活が10年を過ぎようとした頃、授業をしていて「自分が教員というだけで、生徒が黙って話を聴いてくれているのはなんだかおかしい。このままでは自分がダメになるかもしれない」とふと感じたそうである。それで「自分の話がおもしろくない場合、誰も聴いてくれないような環境に身を置こう」と思い立ち、落語を始めたそうである。それから40年経つ今も、日々、落語に向き合い研鑽している。大学にもゲストとして来ていただき授業をしてもらっているが、誰に対しても懐に入り、受け止め、話をし、躍動する議論の空間をつくるのがとても上手い。決して威張らない。授業の最後には落語を一席披露してもらうが一級品である。彼は国内外の歴史や古典落語に造詣が深い。
古典から学ぶことは大切にしたい。古典は「クラシック」のことだが、もともとはラテン語である。古代ローマでは軍艦を税金では造っておらず、国家の危機の際に、寄付によって艦隊をつくった。その寄付による艦隊や寄付ができる人々のことを「クラシス」や「クラシクス」と言い、転じて、精神的な危機の際に人々の拠り所となる文化や叡智を「クラシック」と称するようになった。ちなみに、危機に際して拠り所となるものがなく、自分の子ども(プローレー)をなくなく差し出すしかすべがない人々を「プロレタリアート」と言う。日々の業務に追われ、自らを消耗させるだけでなく、子どもすらも売り渡してしまうような労働は避けたい(なお、このような議論について私は古典を論じた今道友信さんの『ダンテ『神曲』講義』を読んで学んだ)。