
AI時代「教師」考 [第5回]「教師を越える学習者」を、育てる!
トピック教育課題
2022.04.18
AI時代「教師」考 [第5回]「教師を越える学習者」を、育てる!
東北大学大学院教授
渡部信一
(『新教育ライブラリ Premier II』Vol.5 2022年1月)
最新AIは、「問いの解き方」を見つけ出す!

前回、私は「AIはどのように学習するのか?」について、「ひと昔前のAI(1980年代から2010年頃まで)」と「新しいAI(2010年以降)」に分けて示した(渡部2021a)。簡単に振り返れば、「ひと昔前のAI」は「人間がAIにさせたいことをすべてひとつひとつ教えていた(プログラミングしていた)」。このようなAIは「教えた通りにきちんと作業を行う」ことには優れていたが、「想定外の出来事」にはまったく対応できなかった(AI研究領域では「フレーム問題」と呼ばれている)。
それから20年以上の研究の積み重ねにより誕生したのは、「自律的に学習を進めるAI」そして「AI同士が学習し合うAI」である。
このようなAIの発展は、私がかつて教員養成大学で学生指導をしていたときに感じていた疑問に対し、ひとつの回答を示してくれた。その疑問とは、次のようなものだった。
教育現場において、「教師が子どもたちに知識やスキルを系統的に教える」ことは『教育』の本質から外れているのではないか?「子どもたち自身が自ら学んだり、子どもたち同士が学び合う」のが、『教育』の本来の姿なのではないのか?
日々学生と一緒に子どもたちを指導したり、教育実習指導で学校現場を訪れる中で、私は「教え方が上手い教師」ではなく、子どもたちに対して「学ばせ方が上手い教師」を育成しなければならないと強く考えるようになっていたのである(渡部2021a)。
さらに私は前回、最新のAI「アルファ碁」が囲碁の分野で(人間の)世界チャンピオンに勝利したことを紹介した。「アルファ碁」は開発当初、囲碁のルールすらプログラミングされていなかったが、自律的な学習を行うことにより囲碁のルールや定石を獲得し、さらにはAI同士で対戦を繰り返す中で世界チャンピオンに勝利するほどまで能力を高めていった(渡部2021a)。
今回、私が着目したいことは、「アルファ碁は、どのように学習したか?」についてのさらに詳しいメカニズムである。結論を先取りすれば、アルファ碁はWeb上にある囲碁対局サイトで公開されている膨大な数の棋譜(指し手の記録)の中から「問いと答えのセット」を取り出して学習し、その学習を通してアルファ碁自身が「その解き方を見つけ出す」のである。もう少しわかりやすく説明しよう。
まず、アルファ碁はWeb上に公開されている膨大な数の棋譜の中から「問いと答えのセット」を取り出す。ここで「アルファ碁」にとっての「問い」は、「ある場面における次の一手とは、どのような手なのか?」ということである。これは棋士が対戦の中で常に考えている「次のベストな一手は何か?」と同じである。「アルファ碁」の場合、Web上の棋譜に記録されている「次の一手」がその「答え」になる。そして、その「答えの一手」を指した場面が次の「問い」になり、さらに棋譜に記録されている「次の一手」がその「答え」になる。「アルファ碁」は、このような「問いと答えのセット」を約3000万局面読み込み、学習する。そして、この学習により「アルファ碁」は囲碁のルールや定石を獲得し、さらに様々な棋譜の特徴を学習することで強くなっていくのである(渡部2018、2021b)。
このような「アルファ碁」の学習過程は、近代教育(特に、理数系の教育)が「問いとその解き方」を教えることにより「学習者に答えを出させる」ことを基本としているのとは大きく異なっているという点は非常に興味深い。近代教育では一般に、教師は学習者に対し「問い(例えば「2+3=?」)」とともにその「問いの解き方」を教示する。学習者は、その「問いの解き方」を使って様々な問いを繰り返し解くことにより「答えの出し方」を習得していく。近代教育と最新AIの学習過程の違いは、どのような結果の違いをもたらすのだろう?
どのように学習しているのか、わからない!

「アルファ碁」はWeb上にある膨大な棋譜の「ビッグデータ」を読み込み学習するが、データのひとつひとつの善し悪しを吟味することはない。ここで気になるのは、Web上のデータはすべて「正しい指し手」とは限らない、「間違って指した手」もたくさん存在しているということである。また、間違ってはいないけれども、アマチュアがWeb上に掲載した「レベルの低い手」もたくさんあるだろう。それは「アルファ碁」の学習に対し、どのように影響するのか?
結論を言えば、最新のAIが「ビッグデータ」を対象として学習し何らかの問いを解こうとするとき、それは統計的・確率論的に判断しており、データが膨大な数ゆえその解答は「だいたい正しい」という結果になる。これは、「ひと昔前のAI(エキスパートシステム)」が採用していた「きちんと正しい答えを出す」という考え方とは本質的に異なっている。
そしてこのとき、もうひとつ大変興味深いことは、最新AIが「ビッグデータ」を統計的・確率論的に判断していることは確かなのだが、AIを開発した研究者自身は自分が開発したAIが「どのように学習しているのか、その詳細についてはわからない」ということである。例えば、2015年から2年間、世界コンピュータ将棋選手権で優勝したAI「ポナンザ」の開発者である山本によれば、開発の途中から「ポナンザ」がどのように学習しているのか「わからなくなった」という(山本2017)。
開発当初の2007年、「ポナンザ」はプロ棋士が実際に指した手を手本として山本自身がプログラミングしていた(「エキスパートシステム」を採用していた)ので、AIの内部について「すべてわかっていた」。しかし、2014年以降「機械学習」を導入し「ポナンザ」自身にデータを学習させるようになってから、「ポナンザ」がどのように学習しているのか「わからなくなった」という。それにもかかわらず、2014年以降の「ポナンザ」の能力は「指数関数的に」成長し続けた。そして、あっという間に開発者の山本自身が戦ってもまったく相手にならないほど強くなり、間もなくトップレベルのプロ棋士と対等な、あるいはそれ以上の「強さ」を獲得してしまった。この現象は、約2年間(2014年から2016年まで)に起こったという。そして、世界コンピュータ将棋選手権で優勝したのである。
さらに「ポナンザ」は、単に強くなっただけではなく、どんどん新戦法を指すようになった。人間同士の戦いではありえないような手順が、次々と湧き出てきたのである。そして、そのような奇妙な手はその後、若い棋士たちの研究対象となり、現在では若い棋士がAIの考え出した手を積極的に取り入れているという(山本2017)。これが、最新のAI研究開発における「問いと答えのセット」を学習させるという方法の特徴なのである。
私はこのような最新AIの「学習」の特徴を知り、これからの「教育」を検討しようとしている私たちにとっても大きなヒントになると考えている。つまり私は、AI時代の「教育」では「答えを出す能力」よりも「課題の解き方を探し出す能力」の重要性が増すと考えているのである。
(※最新AIと「教育」に関しては、「渡部2018、2021b」において詳しく示した。)
伝統的教育に、「教師を越える学習者」の姿を見る!
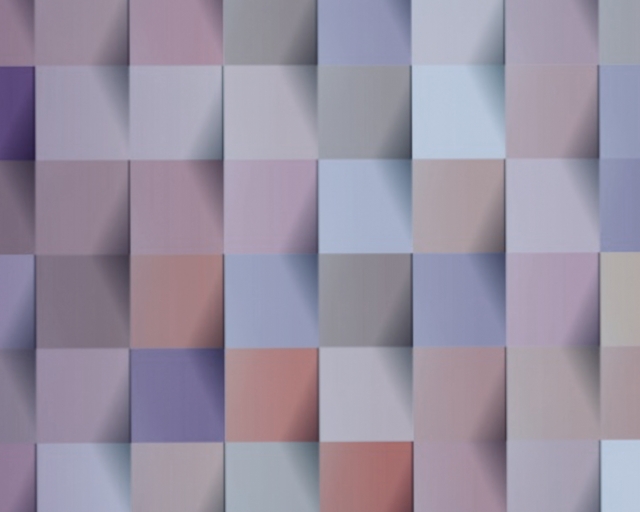
課題の「解き方」を自分の頭で考えるようになった学習者には、何が起こるのか? 私は、この疑問を明らかにするためのヒントを「日本の伝統的教育」に求め、様々な検討を行ってきた(渡部2007、2018、2021b)。
検討の対象としてきたのは、伝統芸道(民俗芸能や日本舞踊など)やミュージカル役者養成所における伝統舞踊教育などである。私は、そのような現場にあえて「モーションキャプチャMotion Capture」システムや3DCGアニメーションなど最先端のデジタル・テクノロジーを持ち込むことにより、最先端のテクノロジーでは捉えきれない「教育の本質」を浮き上がらせようと試みてきた(副次的に、「伝統芸道の保存と若者への継承支援」という目的もある)。具体的には、師匠(教師)および学習者に対して「モーションキャプチャ」システムを活用することにより舞などの身体動作をデータ化し、そのデータを用いて3DCGアニメーションとして再現した教材を作成した。その教材を民俗芸能を学ぶ子どもたちの稽古場面や役者養成所の授業で活用していただき、その効果を確認した。学習者は師匠(教師)のデータや3DCGを詳細に検討したり、自分の動作データや3DCGと比較検討することにより、それらの教材は「学習に役立つ」と評価した(詳しくは「渡部2007、2018、2021b」参照のこと)。
そのような試みを行う中で私に見えてきたことは、「近代教育」とは異なる「日本の伝統的教育が持っている本質」である。まず伝統芸道の師匠は、学習者に対し「知識」や「スキル」よりも、その伝統芸道が持つ「世界観(意味)」を伝えようと意図している。つまり、「なぜ、その芸道が長い年月を経て受け継がれてきたのか?」そして「その芸道は、私たちの生活にとってどうして必要なのか?」などを伝えようとしているという。そして師匠は、その伝統芸道が持つ「世界観(意味)」がわかるようになれば、「知識」や「スキル」は自然に後からついてくるという。
例えば、地方に伝わる民俗芸能「神楽」では、師匠がまず手本を見せる。そして「見て覚えろ」「わざを盗め」と指導する。これはすなわち、学習者に対し「答え(ひとつの完成形)」を示し、学習者は自分もその「答え(ひとつの完成形)」を獲得するために、日々稽古をしながら「師匠のように舞うためにはどうすればよいのか?」を自ら考え再び稽古に励む。
稽古を続けていくと、師匠の手本はいつも同じであるとは限らないことに気づく。雨の日の舞と晴れているときの舞では、その舞い方も異なっている。春、夏、秋、そして冬でも、その手本となる舞は変わってくる。師匠が風邪をひいたとき、あるいは歳をとって腰が痛いときでもその手本は大きく変わる。そのような手本を見て、学習者は師匠の舞を学び、自分の舞を作り上げていく。師匠はなぜ雨の日は(晴れの日とは違う)あのような舞になるのか? なぜ神社のお祭りで披露する舞と街中で開催されるイベントの舞では違うのか? なぜ歳をとってダイナミックさが欠けた舞でも師匠の舞はすばらしいと感じるのか? これはまさに「○○の状況のときは、どのように舞うのか?」という問いと実際に自分の目の前で実演している師匠の舞という解答であり、学習者は日々稽古に打ち込みながら「問いと解答」の関係性を探究し続けるのである。
さらに、師匠の学習者に対する「評価」も興味深い。師匠の「評価」は絶対的な権威を持つが、例えば、神楽の師匠は評価に対し「だいたいでよい」と発言していることは非常に興味深い(渡部2007)。このとき師匠は、具体的に「何々を学んだ」とか「何々ができるようになった」と表現できるようなものを評価の対象とはしていない。このとき評価の中心にあるのは、その伝統芸能が本質的に持っている「世界観」や「価値観」に対して学習者自身が「どれだけ馴染めるようになったのか」ということである。「馴染めるようになる」ということは、その世界に対し自分なりの「リアリティ」を持つことができるようになったことを意味する。そして、その世界においてどのような状況においても「何とかうまくこなすことができる」という能力が身についたことを意味する。このような能力は日々の稽古により「段階的に発達していくものではない」という点もまた、非常に興味深い。つまり、ある日ふっと気づいたら「いつの間にか上手くできるようになっていた」ということが普通なのである。師匠は、そのような能力を重視することにより学習者を評価している(渡部2007、2018、2021b)。
このような「やわらかな評価」は、学習者に思わぬ結果をもたらす。「なぜ、師匠はあのように舞うのか? 師匠の舞に近づくためには、どうしたらよいのか?」という課題の解答を求めながら稽古に励み続けた学習者の中から、「師匠を越える学習者」が出てくるのである。それも、「いついつ師匠を越えた」というものではなく、「気がついたら師匠を越えていた」というのが普通である。
私は、「教育」においてもまったく同様であると考えている。「やわらかな評価」は、学習者の「学び」が教師の求める方向性と多少異なっていても、それを否定したりつぶしたりしないという特徴を持つ。このことは、学習者の「主体的な学び」を生み出す上で非常に重要である。そして、教師が意図していないにもかかわらず、学習者は「自分自身の学び」によって「教師を越えた能力」を獲得することさえあるのだ。
これがまさに、子どもたち自身が自ら学んだり、子どもたち同士が学び合うという「教育」の本来の姿なのではないだろうか?
AI時代の「教育」を考えるとき、このような視点が重要になってくると、私は考えている。
[引用・参考文献]
・渡部信一編著『日本の「わざ」をデジタルで伝える』大修館書店、2007年
・渡部信一著『AIに負けない「教育」』大修館書店、2018年
・渡部信一連載:AI時代「教師」考「第4回:『教え方が上手い教師』伝説が、崩れる!」『新教育ライブラリPremierII』ぎょうせい、2021年a、pp.108-111
・渡部信一著『AI×データ時代の「教育」戦略』大修館書店、2021年b
・山本一成著『人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか?─最強の将棋AIポナンザの開発者が教える機械学習・深層学習・強化学習の本質』ダイヤモンド社、2017年
Profile
渡部 信一 わたべ・しんいち
1957年、仙台市生まれ。東北大学大学院教育学研究科博士課程前期修了。博士(教育学)。福岡教育大学助教授、東北大学大学院教育情報学研究部教授及び同研究部長・教育部長(5期・10年)などを経て、現在、東北大学大学院教育学研究科教授。主な著書に『鉄腕アトムと晋平君─ロボット研究の進化と自閉症児の発達─』『ロボット化する子どもたち─「学び」の認知科学─』『AIに負けない「教育」』などがある。



















