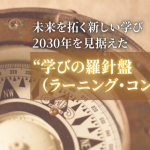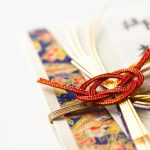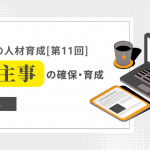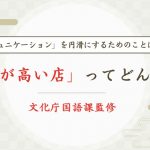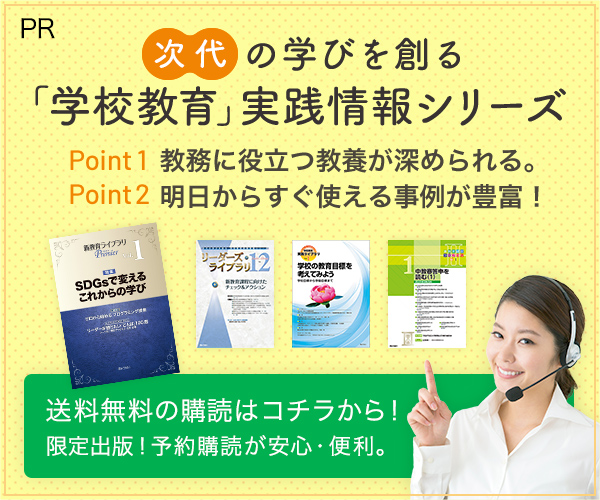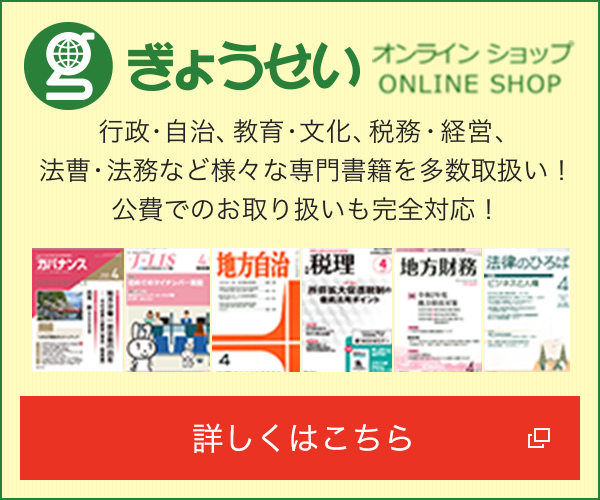theme 4 家庭・地域と共創する校長のセンスと人間性
授業づくりと評価
2023.07.07
theme 4 家庭・地域と共創する校長のセンスと人間性
日本大学教授
佐藤晴雄
家庭・地域とともに歩む校長
(1)「共創」とは
「共創」とはコ・クリエーションとも呼ばれ、経営学で用いられるようになった概念である。これは、企業本位に価値を追求するのではなく、顧客や従業員等の関係者相互の交流によって価値を創造していくという考え方である1。したがって、「協働」よりも一歩進んだ取組みになる。
注1 ベンカト・ラマスワミほか著、山田美明訳『生き残る企業のコ・クリエーション』徳間書店、2011年
「共創」が求められる背景には、消費者が単なる受け身に徹するのではなく、多くの情報を入手し、サービスを厳しく見極めるようになったことが指摘できる。こうした状況は今日の教育界にも当てはまることから、学校経営も「共創」の考え方に立つことが重要であり、校長にはそのための新たなセンスと人間性が求められることになる。
(2)「共創」的センスあふれる二人の校長
まずは、家庭・地域協働・共創に努めた二人の校長を紹介しておこう。
①家庭・地域目線で支援を受けるA校長
かつて筆者がアドバイザーを務めていた都内小学校のA校長は、学校支援ボランティアの協力を依頼する時に、「必要でない時にもお願いするようにしている」と語った。誤解のないように説明しておくが、「必要でない」とは、従来協力を依頼していた授業が日によって教員一人で可能になる場合でも、継続して協力してもらうよう工夫するという意味である。そこには、学校の都合だけでなく、相手の立場を尊重する姿勢が読み取れる。
しかも、A校長は新しい実践の試みに直面した時、想定されるメリットとデメリットが半々ならば、新しい取組みに挑戦してみると言うのである。前例踏襲に陥ることなく、日々新たな実践を採り入れようとする進取のセンスを持つ校長なのであった。実際、地元商店街の協力を得て、独自の地域学を打ち立て、地域密着型の教育実践を展開するのである。
②「信じて語る」B校長
別の小学校のB校長は保護者や地域住民に学校支援を依頼すると、保護者たちからは、「先生たちを楽にさせるために協力するのですか」という疑問が寄せられたと言う。そこで、次のように理解を求めた。
「教員の仕事を『10』だとすると、そこに皆さんの力が『+2』加われば教育の成果は『12』になります」と説明した。図式で表せば「10(教員の業務量)+2(保護者による学校支援量)=12(教育成果)」だと分かりやすく説いた。当初、保護者は「10+2-2(教員の負担軽減)=10」だと誤解していたからである。その後、保護者の納得を得て、支援活動が広がり、ボランティアの人数は急速に増えていった。
同時に、その校長は教職員に対しても学校支援活動に取り組む方針の理解を求めた。教職員はボランティアが授業などに関わることに抵抗感を抱いていたからである。校長はその案件を職員会議で諮れば一部の反対意見に流されることを予想していたので、折を見て一人ひとりの教職員をつかまえて直接説得を試みた。個別に説得されれば、教職員は校長の熱意を受け止めて、当初の疑問も払拭されたのである。その際、B校長は、保護者・住民や教職員に対して「信じて語る」ことが重要だと語るのである。
二人の校長には家庭や地域とともに歩もうとする「共創」的なセンスと人間味あふれる姿が見出されるのである。
リーダーシップの在り方

以上の二人の校長は共創的センスとともに、的確なリーダーシップを発揮している。そこで、改めてリーダーシップの在り方について述べておきたい。
(1)リーダーシップのPM理論
家庭や地域と共創していくためには、保護者や地域住民に対するリーダーシップも求められる。
古くから知られるリーダーシップ論として、三隅二不二のPM理論がある2。Pはパフォーマンス(課題達成機能)であり、Mはメンテナンス(集団維持機能)である。このPとMの強弱をクロスさせると、図のような4タイプになる。
注2 三隅二不二著『リーダーシップ行動の科学』有斐閣、1978年
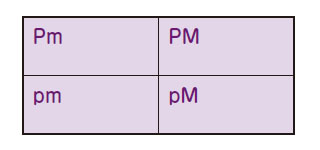
Pmは課題達成機能に優れるが、集団維持機能に劣るタイプで、pMはその反対で集団維持機能に優れても課題達成機能に劣るタイプである。PMは両機能に優れるタイプで、pmはその反対で両機能に劣る。いうまでもなく、PMが理想的になる。
三隅は、職員のモラールの在り方を探るために職場集団に実施した調査結果では、得点が優れた順にPM-pM(原著ではM)-Pm(同じくP)-pmとなったと言う。教師のリーダーシップ(児童も回答)に関しても総合的には同様の順位となった。具体的には学級連帯性はPMとMで高く、児童の規律遵守はPMが最も高い。児童の学校不満はPで最も高く、pmがこれに次ぐ(三隅 1978)。校長に対する調査ではないが、教師を校長に、そして児童を他者にそれぞれ読み替えるとすれば、PよりもMがリーダーシップの鍵を握ると言える。ちなみに、pが弱い場合でもMが強ければフォロアーがpを補強してくれるからである。
ところで、人間性を単純に「冷たい」と「温かい」に分けるとすれば、Pは冷たさを、Mは温かさを、それぞれ伴うと言えよう。つまり、温かい人間性を持つリーダーの方が望ましいのである。
(2)リーダーシップの要素
白樫は数多くの先行調査を集約したアメリカの研究3を紹介しているが、これらの研究を踏まえて、「社交性、友好性、対人関係技術などにおいてすぐれた個人は、リーダーシップを発揮しがちである」と述べている4。リーダーにとって重要なのは社交性などのM要素だということになる。
注3 アメリカの心理学者のStogdill,R.M.(1904-1978)及びBass,B.M.(1925-2007)による。
注4 白樫三四郎著『リーダーシップの心理学』有斐閣選書、2001年
筆者は校長の要素を以下の三つに見出している5。
●人柄(人間性)…この人の下なら安心して仕事ができるという雰囲気。それはMすなわち集団維持能力のベースになる。 ●ポストの価値…管理職としての校長の地位がフォロアーに及ぼす影響。 ●課題達成能力…平常の校務だけでなく、課題発生時の対応も含む。
注5 佐藤晴雄編集『教師の背中を押す校長・教頭の一言』教育開発研究所、2014年
理想的な校長はこれら3要素をバランスよく備えていることになる。しかし、温かい人柄(人間性)に欠け、課題達成能力とポストの価値が強すぎると冷たさを伴う独善的なリーダーになり、ポストの価値のみに傾斜すると権威主義型になってしまう。課題達成に偏りすぎると、あれもこれもやらねばとなって教職員がついて行けず、空回りしてしまう。
特に、家庭や地域に対して課題達成のための協力を強く求めれば、反感を買うことになるだろう。必要がない時にも協力をお願いしたA校長や保護者に学校支援の理解を求めたB校長は、課題達成を押しつけず、相手の立場や価値を重んじる温かい人間性を有するのである。
また、ポストの価値も重要な場合がある。初めての相手(保護者・住民・関係機関等)に協力を依頼する場合、校長というポストの価値が重要になる。一般教職員よりも校長からの依頼の方が相手は強く受けとめてくれ、見方を変えれば、校長が顔も出さないままだと相手は不快に思うからである。
むろん課題達成能力は欠かせない。課題には予期せず発生する「問題」と将来的に目指す目標としての課題がある。課題を見出すには、「何を埋め・何を正し・何をつくる」かという視点で検討するのである。現在不足している事項を補完・補塡し、問題視されることを解決し、新たに求められる取組みが何かを見出すのである。
二つの課題達成手法

(1)フォア・キャスティングとバック・キャスティング
課題達成を目標とする場合、二通りの迫り方がある。一つはフォア・キャスティングである。これは、現在抱える問題を徐々に解決していくための手順を前(フォア)に踏んでいく手法である。例えば、不登校が問題なら、次年度には何に取り組み、どの程度件数を減らすかを検討し、その何年後には件数をゼロにしていくという手順で計画していく。
一方のバック・キャスティングは、数年後の目指す理想的な学校像を実現するために、将来目標から現在までに取組みの手順を手前(バック)に計画してくる手法である。例えば、ある中学校は「全国に誇れる学校」という目標を掲げているが、それが3年後の目標だとすれば、2年後には何に取り組み、1年後には2年後の準備のために何に取り組めばよいかという逆算的手順で計画するのである。
(2)バック・キャスティングによる共創実現
家庭・地域共創の取組みにはバック・キャスティングの手法が望ましい。「共創」による理想の学校像や児童生徒像などを掲げて、その実現のための順を手前に位置付けていく。「学校教育目標」が継続的な目標であるのに対して、バック・キャスティングでは数年間に目指す目標を設定し、これを終えた後には進化した目標を新たに検討することになる。近年、高校では魅力化を目指して、様々な目標が示されている。例えば、長崎県立松浦高校の「“シン化する”学舎(まなびや)を目指して」は、「学びを深める」「進路指導の実現」「力を伸ばす」の三つのシン(深・進・伸)の実現を具体的目標にしている。島根県立隠岐島前高校は「魅力的で持続可能な学校と地域をつくる」を魅力化のビジョンとしている。
高校の魅力化は徐々に広がっているが、小中学校では就学指定の関係も影響してか、今ひとつ浸透していない。今後はすべての校種で共創的視点から魅力化を図り、そのための目標を設定して、バック・キャスティングの手法を用いることが期待される。
ネット・ワークとノット・ワーク
そうした課題達成の体制づくりにはノット・ワークが適する。ノット(knot)とは「連結」のことで、ノット・ワークとは、特定のタイトなつながりであるネット・ワークよりも穏やかなつながりを意味する。
ネット・ワークの場合、一定の固定したメンバー間で活動が取り組まれるが、課題によってはさほど関係性の強くないメンバーも関わらざるを得なくなるため形骸化しやすい。これに対して、ノット・ワークは、何か達成すべき課題が発生した場合、その課題に適したメンバー等を募り、課題解決後にはそのつながりを解くような協働の在り方になる。
つまり、目標が共創による「社会に開かれた教育課程」に関するものであれば、その課題に関わるメンバーで結び、働き方に関する課題であれば、企業等も交えた専門家等で結び、それぞれのノット・ワークを築いていくのである。
ボスとは異なるリーダーの在り方

最後に、トヨタ自動車の豊田社長(当時)が労使協議で語ったボスとリーダーの違いについて取り上げてみたい6。これはイギリスの高級百貨店チェーンの創業者であるハリー・ゴードン・セルフリッジの言葉だとされる。以下に簡単に紹介しておこう。
◆ボスは私という。リーダーは私たちという。 ◆ボスは失敗の責任を負わせる。リーダーは黙って処理する。 ◆ボスはやり方を胸にひめる。リーダーはやり方を教える。 ◆ボスは仕事を苦役に変える。リーダーは仕事をゲームに変える。 ◆ボスはやれと命令する。リーダーはやろうという。
注6 「ボスになるな リーダーになれ トヨタ春交渉2020第2回」トヨタイムズHPより。
豊田社長の語りにはないが、この後に「ボスは自分の考えと異なるものを排除する。リーダーはより良いアイデアをメンバーから吸い上げる」が続く。
したがって、ボスは独善的であり、リーダーには「共創」的センスがあると言ってよい。「共創」にあたって校長は、「ボス」にならないよう、保護者や住民と共に「私たち」として意識し、何か問題があれば黙って処理し、自らの方針を伝えると同時に保護者らのアイデアを汲み取り、活動を一緒に楽しく進める「リーダー」としてのセンスと人間性が望まれるであろう。まさに、前述のA校長とB校長はボスではなく、リーダーだったのである。
Profile
佐藤晴雄 さとう・はるお
日本大学文理学部教育学科教授、放送大学客員教授。大阪大学大学院博士後期課程修了、博士(人間科学)。東京都大田区教育委員会、帝京大学助教授などを経て2006年から現職。中央教育審議会専門委員、文部科学省コミュニティ・スクール企画委員などを歴任。主な著書に、『コミュニティ・スクール』(エイデル研究所)、『教育のリスクマネジメント』(時事通信社)ほか多数。