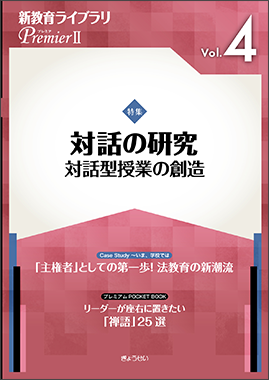教育実践史のクロスロード
教育実践史のクロスロード ActII [リレー連載・第4回] 河合隼雄 こころの物語を読み解く―教育のなかに生きる臨床心理学の智慧
学校マネジメント
2022.02.25
教育実践史のクロスロード ActII [リレー連載・第4回]
河合隼雄
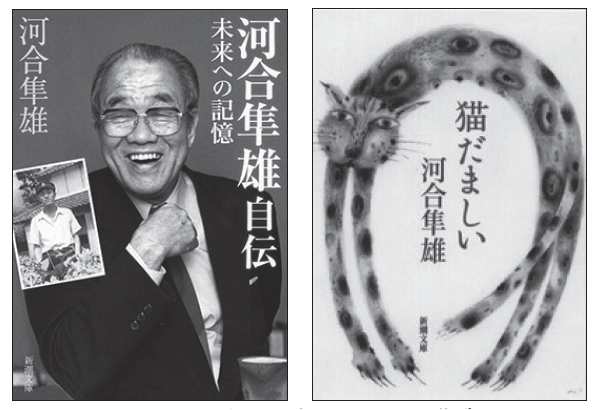
河合隼雄『河合隼雄自伝 未来への記憶』『猫だましい』(ともに新潮文庫刊)
こころの物語を読み解く
ー教育のなかに生きる臨床心理学の智慧
島根大学教授
岩宮恵子
(『新教育ライブラリ Premier II』Vol.4 2021年11月)
こういうオフィシャルな文章だから、「河合隼雄は……」と書くべきであるが、どうしても「河合先生は……」と記したくなる。それは専門分野での師だからという理由が大きいが、それだけではない何かが「河合先生」にはある。村上春樹は、自分はどんな人に対しても「先生」づけで呼ぶことはないのだけれど、臨床心理学者で心理療法家の故・河合隼雄に対してだけは、なぜかいつもつい自然に「河合先生」と呼んでしまうのだという。村上の周囲でも、「河合さん」と呼ぶ人もいるけれど、圧倒的に「河合先生」と呼ぶ人が多く、こういう人は他にはなかなか見当たらないとしている(『雑文集』新潮社、2011年)。
これは関わる人たちがごく自然に敬意を抱き、「河合先生」と呼びたくなるような雰囲気を「河合先生」が持っておられたからだろう。しかし、偉い人だから「先生」と呼んでおけばいいだろうという発想ではなく、なぜか「先生」と呼びたくなる存在感というのはどういうものなのだろう。このことについても考えながら、「河合先生」と教育について紹介していきたい。
教師としての視点から導かれるもの

京都大学教育学部の教授であり、中央教育審議会委員、「21世紀日本の構想」懇談会座長、そして文化庁長官など、日本の国家レベルでの教育や文化政策島根大学教授立案の中枢での役割を歴任し、スクールカウンセラー制度の発足に深く関わった──というのが、教育行政から見た河合先生のプロフィールになる。
河合先生の、日本神話や昔話から日本人の深層心理を鋭く読み解く著作を読み慣れている方には信じられないかもしれないが、もともと河合先生は科学的思考方法に関心が強く、曖昧な考え方を受け付けない人だったらしい。そして京都大学理学部数学科に進学したのちに、高校の数学教師になる。その教師としての仕事を「自分の天職とさえ感じていた」(『ユング心理学と仏教』岩波書店、1995年)と言っておられる。
ところがそんな河合先生に、多くの生徒たちが悩みの相談をしてくるようになる。生徒思いの熱心な教師だった河合先生は、彼らに対して、しっかりとした専門知識をベースにした「責任ある対応をするため」に臨床心理学を学ぶことを決意する。その決意の未来に、このような国家レベルでの教育との関わりが生まれてきているのだ。クリアで合理的で整然とした美しさを追求する数学と、人の悩みや苦しみという正解のない曖昧なプロセスに寄り添っていく臨床心理学という、一見、真反対の場所に位置するものが、河合先生のなかにはある。
いつだったか、「1メートルの紐を半分に切ると、片方の端から真ん中までが50センチの点だとしたら、もう片方は50センチよりも点の分だけ微妙に短くなるから、ほんとうに正しい半分ってないじゃないか」ということを話題にする不登校の子がいて、どういうことだろうねと一緒に考えているとお話ししたことがある。すると河合先生は「面白い子やなあ」とにっこり笑って「これは数学の連続体問題っていうのと関係するかもしれないなあ」と、説明してくださったことがある。たまたまこの連続体問題については当時連載中のエッセイにすでに書いておられて、その文章も紹介してくださった(『猫だましい』新潮社、2000年に所収)。
数学の「連続体」というのは、粒子をくっつけて全体をつくるのではなく、最初から全体として存在していると考えられている。そういう連続体は、なかなか明確に割りきって考えることはできない。これを、人間存在という連続体に当てはめて考えると、人間という全体存在を、あまりにきっぱりと割りきった考えによって分けてしまうと、その途端に失われるものがある──と考えられる。
心の問題と身体の問題はまったく別ものだとか、いろいろあっても割りきって学校に行くのが正しいとか、納得ができないけれど割りきったほうが前に進める、など、私たちはいろいろなところで複雑な想いや状態を割りきることを求められている。しかし、割りきることによって失われるもののほうにどうしても目が行ってしまう人もいる。まさに、この子はそういう子だった。
このような子どもの素朴な疑問を(その子は、そんなことにこだわらずにするべきことをしたほうがいいと周囲からは言われ続けていた)、河合先生はまったく違う次元から捉え直す視点をもっておられるのだ。数学と人の心を深く理解することということが、想像力を駆使しながら全体的な構造を掴むという点でこんなふうに河合先生のなかでは矛盾なく繋がっているのだ。
きっと河合先生は、数学教師をしておられるときには、「数学で」この世に生きていることの不思議や世界の構造を知ることの喜びを生徒たちに伝えておられたのだろうということをしみじみ感じる出来事だった。
日本人のこころの深層にあるもの

スクールカウンセラーとして小・中・高校の現場に派遣されるようになった1995年の頃、「不登校はどうしたら良くなりますか」「いじめをなくすのにはどうしたらいいですか」といった問いが先生や保護者から寄せられる度に、当時の私はたじろぎ、うろたえていた。そんなとき、河合先生の著作や講演録は、何をどう伝えたらいいのかを知るための、まさにバイブルだった。
特に『カウンセリングを考える』(創元社、1995年)は、『母性社会日本の病理』(中央公論社、1976年)など専門書で詳しく論じられていることが、教育現場の実情に落とし込んで話し言葉で分かりやすく示されている。ここに書かれていることは、まさに、目の前の現場で起こっていることそのものだ。もう25年以上も前に語られているものなのに、ネットをめぐる問題など、今起こっていることを考えるうえでのヒントに満ちている。河合先生の視点は、現実社会での表層的な変化だけではなく、常に普遍的な日本人の心の古層の動きに向けられている。だから、先生の言葉は年月の淘汰を受けることがないのだと実感する。
母性的な社会は、みんなが自分の言いたいことを言わずにちょっとずつ我慢して、察しながら生きることで成り立っている。そして日本では、自分の考えや、賛同を得にくい判断でもしっかりと言葉で伝えたりするような欧米での父性的な部分を取り入れようとしながらも、対立を避けるために何となく言葉にされないままにことが進んでいく。そのため欧米に比べると日本は表立っての闘いは少ないものの、モヤモヤを心のなかに溜めたままで生きていることが多い。そして母性社会に生きているみんなの何とも言えないモヤモヤが、誰かに全部、放り込まれたとき、それがいじめという一方的な攻撃になってしまうのだと河合先生は説く。
この構造は、今を生きる思春期の子どもたちのなかでも、ネットの問題として色濃く出ているように思う。思春期の子どもたちの問題に関わっていると、SNSをめぐる話題が必ずと言っていいほど出てくる。たとえば、自分が属するグループのメンバー(いつものメンバーという意味で、「イツメン」という)に対しては、空気をどこまでも読んで、相手の気持ちを察して、信じられないくらいの気遣いをする。「イツメン」という共同体に属してそこでの関係を維持していないと、学校に行くハードルが恐ろしく高くなるのだ。この傾向は年々、強まっている。場の空気が読めない発言をするということ自体、母性社会では悪の烙印を押されることになり、モヤモヤをぶつけていい相手として認定される危険が大きい。そのことを子どもたちはよく分かっているので、そこまでするかと言いたくなるほどの気遣いを絶やさない。
そして、イツメンのなかに母性的な一体感が存在していることを確認するために、彼らはSNSで寝る間も惜しんで繋がり続けている。しかしそれを心から楽しんでいる子は少ない。みんなどこかでモヤモヤしているのだ。そのため、イツメンへの気遣いの一方で、イツメン以外の人たちには平気で暴言を吐くこともあるし、イツメン内でも誰かを排除したラインのグループなどを別に作り、そこでは壮絶な悪口が吐露されることがある。これは、かなり深刻なネットいじめとして子どもの心を深く傷つける。
ネットという表現ツールが日常生活に入ることによって、河合先生によって指摘されている日本人が本来もっているこの心性が、よりクリアな問題の形をとって増幅して出てきているように思う。ネットの掲示板やコメント欄に存在する膨大な怨嗟の言葉の数々も、河合先生がよく指摘しておられた「母性社会のなかで表面的には争わずに生きるうえでの我慢と辛抱のモヤモヤのはけ口」になっているのだろう。