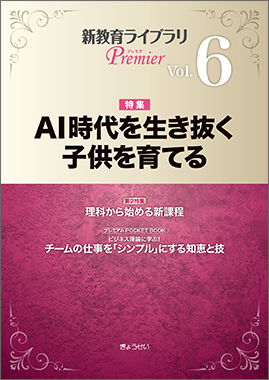教育実践史のクロスロード
教育実践史のクロスロード[リレー連載・最終回] 上田 薫 教師たちの自恃(じじ)を支えた思想––確かな「個」の育成を目指して
トピック教育課題
2021.07.01
教育実践史のクロスロード[リレー連載・最終回]
上田 薫
教師たちの自恃(じじ)を支えた思想––確かな「個」の育成を目指して
早稲田大学教育・総合科学学術院教授
藤井千春
(『新教育ライブラリ Premier』Vol.6 2021年3月)
「初期社会科」学習指導要領の作成

上田薫(1920−2019)は、哲学者・西田幾多郎の孫としても知られている。
京都大学文学部哲学科を応召のため仮卒業となる。復員後、文部省に勤務して小学校社会科学習指導要領の作成を行った。1947年版の学習指導要領(試案)の社会科は、短期間での編成であったため、アメリカのヴァージニア州で使用されていたコース・オブ・スタディの翻訳的な色彩が強かった。それに続く1951年の改訂版では、我が国の社会の実情に即した目標と単元例が示された。また、子どもたちが「実生活の中で直面する切実な問題をとりあげて、それを自主的に究明していくことを学習の方法とする」という問題解決学習が指導原理として掲げられた。
1951年に名古屋大学助教授に着任、以後、東京教育大学教授、立教大学教授、都留文科大学学長を歴任する。この間、信濃教育会教育研究所所長、教育哲学会代表理事などを務めた。
上田の経歴を最も彩るのは、1958年に長坂端午、重松鷹泰、大野連太郎とともに結成した社会科の初志をつらぬく会(初志の会)での主張と活動である。長坂たちは上田とともに、いわゆる「初期社会科」の作成メンバーである。1955年の社会科の系統学習への転換(社会科の学習指導要領のみ改訂された)に対して、初志の会は子どもの生活経験に基づく「初期社会科」の問題解決学習の実践をつらぬくことを目指して結成された。上田は、半世紀以上もの間、思想的・理論的に会を指導した。しかし、初志の会の主張と実践は、文部省への抵抗以上に、マルクス主義からのイデオロギー的な攻撃に曝された。上田は文部省の系統主義への批判と同時に、マルクス主義教育学者との論争に巻き込まれた。左右両面との論争を通じて、『知られざる教育』『人間形成の論理』『ずれによる創造』などの著作に、上田の教育思想がまとめられた。
また、1970年代から2010年まで、静岡市立安東小学校の校内研究を指導した。その成果は、子どもたちの学びとして毎年の発表会で広く公開されてきた。子どもたちが自ら動いて調べ、話し合って考えるという学習活動は、当時の教育界に大きな反響を呼んだ。「主体的・対話的で深い学び」のモデル的な学習活動であった。「揃えること・教えること」という観念が根強く支配していた当時、安東小学校の実践は、子どもたちが自主的・主体的に学ぶことの可能性を、多くの教師たちに示した。
教育科学研究会との論争

上田の思想が先鋭的に発信されたのは、1960年代前半の「上田-大槻論争」を通じてである。この論争は、教育科学研究会の機関紙『教育』1962年8月号に掲載の大槻健の「社会科教育における−態度−人格主義について」から開始された。大槻は、初志の会の機関誌『考える子ども』第3号で長坂端午が論じた社会科教育論を「態度主義」と批判した。そして「態度論に終始する限り、権力統制の強さの度合いに応じて、いつでも、『皇国民の錬成』に復元し得る」のであり、「徹底的に科学と教育とを結びつけてみることの方が、今日大切なのである」と論じた。批判には病気療養中の長坂に代わり、上田が同誌10月号「何を知識不信か」で反論した。
この論争は、後に「態度主義」論争と評価された。しかし、プラグマティズム的な教育論とマルクス主義教育論との間での論争という色彩が強い。それぞれの教育論の特色と対立点が明確にされた。
大槻は、次のように主張した。
「権力の提示する教科論は、態度をやしなうことに究極のねらいをおいて、その限りにおいて必要な知識を、子どもたちに与えようとするものである。(中略)要するに態度が大切なのだから、という理由で、知識内容の厳密さは二の次にまわされるのである。(中略)教科の指導をとおして、子どもたちの間に養わなければならない知識は、したがって、科学的法則に至るのに必要な知識としてあるものであり、どんな知識であってもよいということではない。」
大槻のいう「科学的法則」とは、マルクス主義の史的唯物論である。大槻はマルクス主義のいう科学と教育とを結びつけることを主張した。そのような立場からは、『考える子ども』で長坂が論じた「社会科の本質」、すなわち、一人一人の個としての主体的な生き方の確立を目指すという立場は、「文部省のそれと、実質的にかわりがない」と見えたのである。
「初期社会科」、及びそれを継承する初志の会は、戦前・戦中の教育における画一的な服従を強要する指導方法を批判した。そして、経験主義の問題解決学習の方法を通じて、自ら事実を調べて合理的・主体的に意思決定のできる近代的な個人の育成を目指した。それに対して、教育科学研究会をはじめマルクス主義の教育団体では、戦前・戦中の教育における恣意的・非合理な教授内容を批判した。そして、マルクス主義のいう唯物史観によって、科学的法則に基づく知識を所有した革命的な人間の育成を目指した。戦前・戦中の教育の方法を批判するか、内容を批判するかという相違から、戦後の教育において軍国主義・超国家主義を克服するためには、合理的・主体的な個人の育成に主眼をおくか、科学的知識の教授に主眼をおくかという対立軸が発生した。
動的相対主義
論争において、上田は「知識と態度が切断しがたい」と、次のように主張した。
「子どもになにかを与えるということは、子どもの個性的理解を媒介することによってのみ成立する。」
上田は、民主的な社会の形成者の育成に関して、個性的な「思考体制」の確立を重視した。つまり、子ども自身が社会の中での自らの生き方として、自ら知識を系統的に働かせることが重要なのである。主体的な思考の主体として、自らの生き方の中で自らの責任において知識を活用できる「個」を育てる教育を主張したのである。上田が目指した問題解決学習とは、子どもたちが社会の進展に力を尽くそうという態度で、自分たちで事実を究明してその意味について粘り強く考え抜くという、子どもたちの切実な追究を本質とした。民主的な社会は、知識を活用し自分自身で考えることのできる「思考体制」の育成により実現されると考えた。知識は子どもの個性的な「思考体制」を通じてこそ、民主的な社会の建設のために生かされるのである。
このような上田の反論に、大槻は「科学や客観的法則を一切放棄した暴力的な学習論」と非難した。しかし、上田から見れば、大槻の立場は「科学という美名によって、このような一方的屈従関係をつくりあげ、それを子どものところまで押しつけるということ」であった。個性的な「思考体制」を無視し、絶対に対する服従を強いるという点で、戦前・戦中の「修身」の授業の在り方と同じなのである。また、上田は、唯物史観の歴史法則を「客観的真理」として教えることは、「科学をきわめて静的なものととらえる」だけではなく、無批判的に「過去を未来に流しこもうとする」ことで、それにより「子どもたちの未来の可能性は無残に踏みにじられてしまう」と批判した。大槻の論では「独善的に科学の名が利用」されている。教育は科学に隷属させられる。
その後、吉田昇、滝沢武久、矢川徳光、大橋精夫が論争に加わり、プラグマティズム的な立場とマルクス主義との間での、教育を土俵とした哲学・イデオロギーの代理論争となった。論争は、「科学体系が『一』ではなく『多』である」という、上田の立場が主張されて終了した。この論争を通じて、子どもの「思考体制」の発展に相関して、必要とされる知識も、また知識の意味も発展するという、上田の「動的相対主義」の論理が明確にされていった。
教育界の対立・抗争の渦中で

この論争が展開された1960年代前半は、文部省対日本教職員組合(日教組)との対立・抗争が激化していた。1958年改訂の学習指導要領は「告示」として位置づけられた。教育課程の編成は国家的に一律に統制・拘束されることになった。それにより、マルクス主義思想が教育現場に入り込むことの防止が図られた。同時期に実施された勤務評定や全国学力テストも、教師たちに学習指導要領を遵守させ、思想教育を妨げることを意図するものであった。
文部省対日教組の対立・抗争が激化する中で、教師たちには自己の旗幟を鮮明にすることが求められていた。管理体制に従うか、抗争活動に参加するか、二者択一的な選択が迫られていた。
しかし、第三の立場があった。学習指導要領の系統学習にも、マルクス主義の系統学習にも反対し、目の前の子どもたちの個性的な成長を目指し、教師たちの主体的な授業実践を維持しようとする立場である。初志の会には、「初期社会科」の問題解決学習のこのような理念を大切にする教師たちが結集した。これらの教師たちは、授業実践に対する自己の信念を放棄して管理体制に服従することも、マルクス主義を信奉すること、すなわち、体制側の権力や「科学」を称する権威に身を委ねることを拒否した。自らを抽象化することに抗し、問題解決学習を通じて子どもたちとともに個性的な「個」としての生き方を追求した。上田の「動的相対主義」は、そのような教師たちを支える思想となった。
「いつも主義をになっていなければならない意識、絶対的真理をせおっていなければ安定しない意識、したがって敵か味方かに割りきらなくては落ち着かないという意識。そういう人はいつも受け身であり消極的であり、はっきりいえばずるいのである。科学体系の尊重ということは、左右を問わずその人びとの旗印であるが、それは一方的に恩恵に浴そうという考えかたであり、さらにいえばそれをうしろだてにして子どもの前に君臨しようというこんたんなのである。」
「科学」を権威としてその知識を注入する教育は、子どもの個性・具体性を剥奪して抽象化するにとどまらない。教師自身も権威の前に自分の個性・具体性を放棄して屈従することになる。それは、個性的・具体的に生きる一人の人間として、子どもたちに臨むことではない。また、それぞれの個性的・具体的に生きる存在として子どもを捉えることではない。科学によって、自分を権威づけて子どもたちの前に君臨して支配しようとすることである。教師と子どもは、権威を通じての関係の下での抽象化された存在となる。上田が求めたことは、「権威主義的な不合理に追従随順する」ことからの脱却であり、それに抗する確かな「個」の育成にあった。上田は、教師自身に確かな「個」であることを求めたのであった。
改めて求められる教師の自恃
2017年(小中)・2018年(高)の学習指導要領では今後の学校教育の役割が「持続可能な社会の創り手」を育てること、また「個性を生かし多様な人々と協働」する教育活動を促進することと示された。「足並みを揃えさせる」教育からの転換が遂げられた。各学校には個性的な教育活動を展開することが期待されている。
「主体的・対話的で深い学び」とは、子どもたちが自分の心の動きから生じた気付きを自分の言葉で語ること、そして、聞き合って相互の考えを擦り合わせて発展させ、互いに納得のできる最適解を構成していくという学び方である。相互の気付きを出発点に、相互の納得を目標にして、権威に依存せずに協働的に追究を深めることが学習活動の原理となる。子どもたちのそのような学びは、教師が子どもたちの追究に寄り添い支えることにより遂げられる。
したがって、教科書を「正解」が示された権威と見なし、教科書から離れられない教師には、子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」を指導・支援できない。問いは教科書を超えようとする主体的な知性によって生まれる。子どもたちの問いを大切にし、切実な追究を信頼して支えることに、教師の自らの個性的な生き方に対する自信が示される。
上田の思想の意義は、教師たちの自恃を支えたことにある。確かな「個」は、教師の自恃を基盤にして育てられる。ただし、左右から矢玉が浴びせられる戦況で、孤軍奮闘に耐える厳しさが求められる。
上田は、戦場体験を次のように語っている。
「戦争で死ぬのはやさしいことである。思いきりをつけてしまえば、もうそれでよい。諦めるか興奮するかしてしまえば、死というものはこわくない。しかしそれで人間はよいのか。」
(『よみがえれ教師の魅力と迫力』玉川大学出版、1999年)
戦場で正気を保つことは困難であろう。諦めることも興奮することも自分自身を投げ捨てることである。そうすれば悩むこと、精神的な苦しさからは解放される。同様に、対立・抗争の中でどちらかの権威に身を委ねてしまえば、自分一身の立場は保護される。しかし、上田は問う。「それでよいのか」。つまり、目の前の子どもたちの個性的な成長への支援から逃げ、子どもたちの前に個性的な成長を抑圧する権威として君臨することでよいのか、と。
上田の思想は、教師たちが具体的な現実に眼をそらさずに向き合い、そこから勇気をもって個性的に歩み出すことを支える。学校の自主的・主体的な教育活動が可能な時代となった。だからこそ、不確実性を引き受けて進むことのできる、教師自身の個としての強さと謙虚な自己信頼、すなわち、教師の自恃が求められている。
(注)「上田−大槻論争」の『教育』における論文は、上田薫他編『社会科教育史資料4』(東京法令、1977年)に集録のものによる。上田の著作は『上田薫著作集』(全18巻、黎明書房)に集録されている。
Profile
藤井千春(ふじい・ちはる) 1958年生。博士(教育学)。同志社大学文学部卒。筑波大学大学院博士課程教育学研究科修了。茨城大学教育学部助教授などを歴任。「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説総合的な探究の時間編」作成協力者。ジョン・デューイの哲学と教育学を研究。全国各地の小中学校の校内研究に参加して、子どもを中心に据えた問題解決学習の実践的研究を指導している。著書は『問題解決学習入門』(学芸みらい社)、『問題解決学習で育む「資質・能力」』(明治図書)など多数。