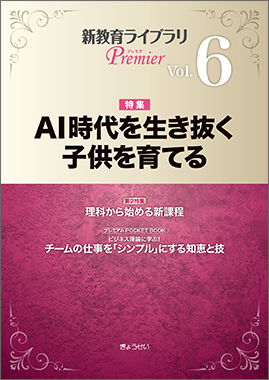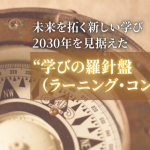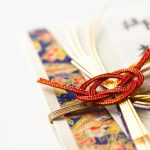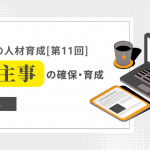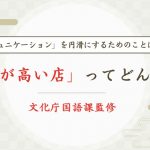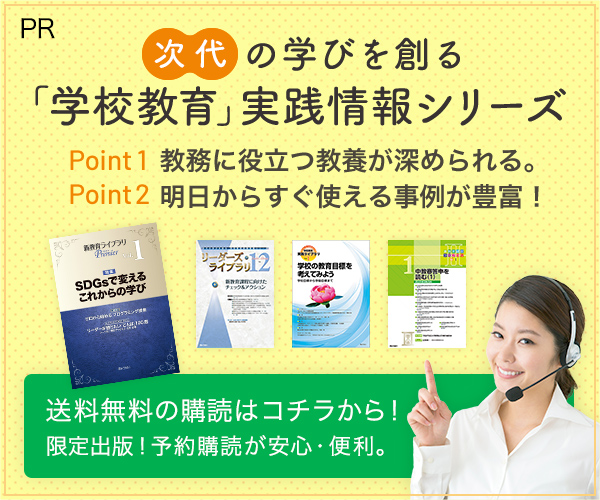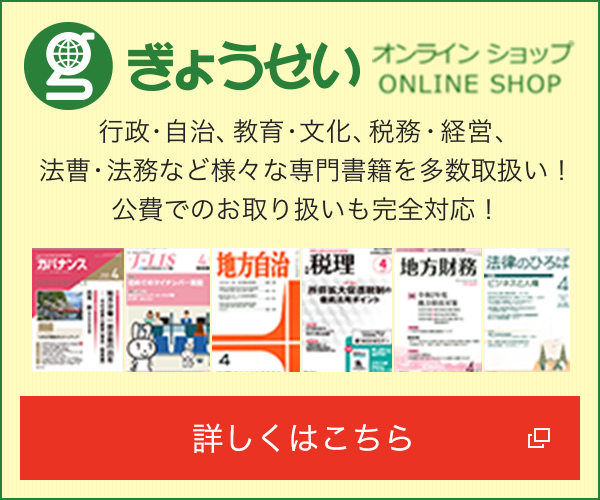ビジネス理論に学ぶ! チームの仕事を「シンプル」にする知恵と技 3.チームを伸ばす発想術
シリーズから絞り込む
2021.06.10
目次
Point4 常に「コンディション」を万全に

リーダーというのは、日々、自分の体の「コンディション」に気を配らなければならない。あなたが倒れれば、チームは機能しなくなってしまう。風邪などの病気にかかることは勿論、「やる気低下」などの心の不調にも注意が必要である。
しかし、「なんとなくやる気が出ない」も、その原因は、実は体の不調が原因なことが多いもの。昔から、心身一如、体と心はつながっているものといわれているが、人間は体が資本なのでこれは当然である。
最近では、できるビジネスパースンの間では、体のコンディションを整えるコーチをつけることが流行っているそうだ。コンディションを整えるためには、休息、栄養、運動が欠かせない。運動不足で、食事はコンビニ弁当ばかり、多忙で休日もしっかり休めないという状況では、リーダー失格である。とはいえ、学校のリーダーの場合、現実として休日に対応しなければならない業務が少なからずあるだろう。そういう場合は、週単位、旬単位、月単位で自分の勤務状況を見渡し、休養の時間を適切に配していってほしい。
体によくない影響が生じると、当然、パフォーマンスは落ち、心も折れやすくなる。無理や無茶をしすぎると、体のコンディションも悪くなる一方で、仕事の質も高まらない。休日にはしっかりと心身ともに休めるように、ウイークディで仕事を終わらせる計画を立てることである。
──「疲れたらたっぷり眠れ」(ニーチェ)
Point5 中国古典に学ぶ「ひらめき力」の磨き方
アイディアを出すときは、リラックスできる環境をつくることが重要である。リラックスした状態で考え続けていると、あるとき突然、いいアイディアがひらめいた、という経験はあなたにもあるはず。
例えば、机にかじりついてアイディアを考えたけれど、中々ひらめかず、疲れて帰宅し、お風呂にゆっくりと浸かっていたら、突然、いいアイディアがひらめいた、ということはよく起こる。
中国の古典から生まれた「三上(さんじょう)」という言葉がある。これは、「馬上=馬の上、つまり移動中」「枕上(ちんじょう)=寝床に入っているとき」「厠上(しじょう)=トイレの中、あるいはお風呂の中」の3つを意味する。
優れた詩やアイディアがひらめくのは、机に向かって考えているときではなく、日常の些細なことをしているときであると言っているのである。
Point6 部下に「小さな失敗」をどんどんさせる

元サントリー会長の佐治敬三氏は、「人生はとどのつまり賭けや。やってみなはれ」という有名な言葉を残しているが、サントリーには、「結果を恐れてやらないことを悪として、なさざることを罪と問う」という社風がある。
リーダーは、部下と一緒になってチームの知恵を結集し、協力して、大きなことを成し遂げていくもの。若くて経験の少ない人にもどんどん仕事を回して、見守ってあげるということが重要なのである。
ちょっと離れたところから見守るというのは、なかなか苦しいことではある。リーダーには経験もあるし、こうするともっとよくなる、という正解も分かっているからだ。
しかし、「仕事を任せる」ということをしなければ、リーダーにはいくら時間が合っても足りない。部下に大きな失敗をさせてはいけないが、小さな失敗はどんどん重ねてもらって成長してもらう。シンプルに割り切ることである。
元トリンプ・インターナショナル・ジャパン社長の吉越浩一郎氏は、「上司が部下を育てるという考え方はおこがましい。仕事そのものが部下を育てるのだ」と言われているが、まさにその通りだ。
Point7 「あえて行動しないこと」で道が開くとき

あるITコンテンツ系企業の企画部長は、売上至上主義という観点に囚われ、とにかく売上目標を達成させることだけに突っ走ってしまい、具体的な指示をしないまま部下を動かし、多大な負荷をかけたそうである。
お客さんのニーズがどこにあるのか、ヒット商品の共通点は何か、どんな商品提供するのか……ということを部下と力を合わせて調べ抜くこともせず、商品を売るために広告担当部署や営業部署への根回しもせず、中途半端な商品を開発し、なかなか売上を達成できない部下に、夜中でもお構いなしに電話をかけ叱責をしていた。結局、部署の職員の大半が退職の意思を示し、チームは完全に崩壊してしまった。
「耐える力」のあるリーダーは、結果を出すための下準備を緻密に積み重ね、ここぞというところでため込んでいたエネルギーを一点に集中させ、スピード感をもって行動を起こす。
つまり、結果を出すための「お膳立て」が万全に整った状態で行動を起こすので、当然、結果を出せる可能性が高い。繰り返しになるが、リーダーがやるべきことは、「イケイケどんどん」ではいけない。大声を張り上げ、部下を煽って、闇雲にあれをやれ、これをやれと命令し、動かそうとするリーダーは、チームや組織を迷走させてしまう。仕事を合理的、効率的、生産的にするために、「あえて行動しない」という局面が、リーダーにはあるのだ。
Point8 「トップは真っ先に苦しみ最後にいい思いをする」
リーダーは、誰よりも仕事を熟知して、誰よりも真剣に仕事に立ち向かう、ということを求められている。そのためには、目前にある仕事にどう対応するのかを深く考えることが必要である。
徹底して考え抜き、自分を追い込むことも、時には必要である。楽をしようと考えたら、油断が生まれ、大きな失敗につながる。心の平穏は捨てるべきである。
逆説的だが、リーダーは、自分を追い込むことでこそ心の平穏が訪れるのだ。元伊藤忠商事会長の丹羽宇一郎氏は、「トップは真っ先に苦しみ最後にいい思いをする」という考えをしていたそうだ。
自分を追い込んで真剣に考え抜けば、緻密な計画が立てられ、抜けのない提案もできる。例えば、現在進んでいるプロジェクトが好調でも、トコトン考え抜いて「本当にこれでいいのか?」と自問自答することが大切である。
トコトン考え抜かれた提案は、人の気持ちを動かし、リーダーとしての覚悟もできあがる。そうすれば、大きな成果を手にできるのだ。
profile
阿比留眞二 あびる・しんじ
1954年6月20日、東京・中野生まれ。1979年明治大学商学部卒業。1979年花王石鹸入社、管理部、和歌山工場にて原価計算、花王家庭品販売、花王化粧品販売にて販売、販売企画、販売教育を経て退職。事業再生会社、自己啓発会社を経て2005年株式会社ビズソルネッツを立ち上げ、現在に至る。得意は、問題解決・課題解決技法。これを駆使して経営コンサルティング、および従業員教育に成果を上げている。現在は、論理と心理学を併せた様々な有効な情報、解決策を顧客に提案している。趣味は、読書、庭の手入れ、ボウリング等。
■著書 『最高のリーダーは、チームの仕事をシンプルにする』(三笠書房)、『最高のリーダーは、この「仮説」でチームを動かす』(三笠書房)、『紙1枚で仕事の課題はすべて解決する』(ワニブックス)、『変化の時代のリーダーシップ』(みずほ総合研究所)