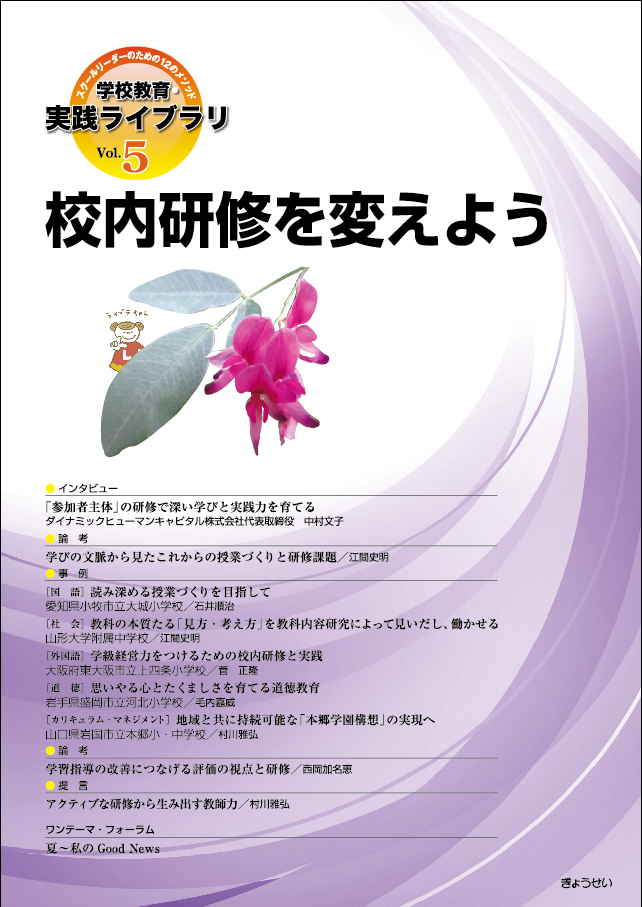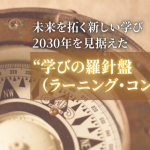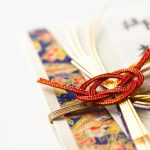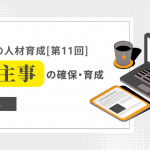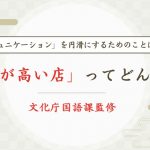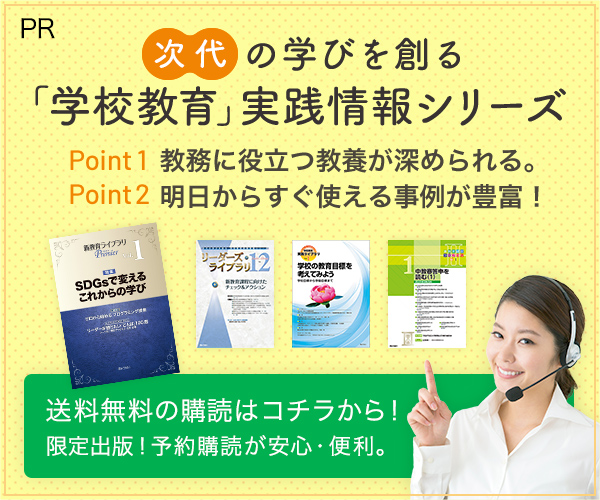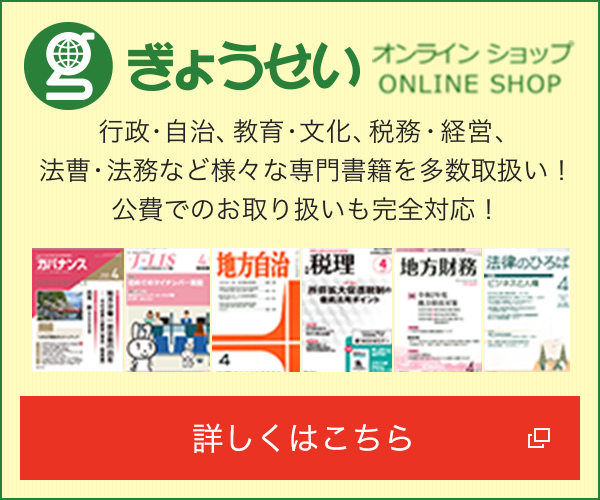田村 学の新課程往来
田村 学の新課程往来[第5回]学校という社会資本に求められる「探究」の学び
授業づくりと評価
2019.11.22
田村 学の新課程往来
[第5回]学校という社会資本に求められる「探究」の学び
國學院大學教授
田村 学
高等学校を中心に「探究モードへの変革」が始まっています。今回は、「探究」について記します。
求められる「探究」の学び
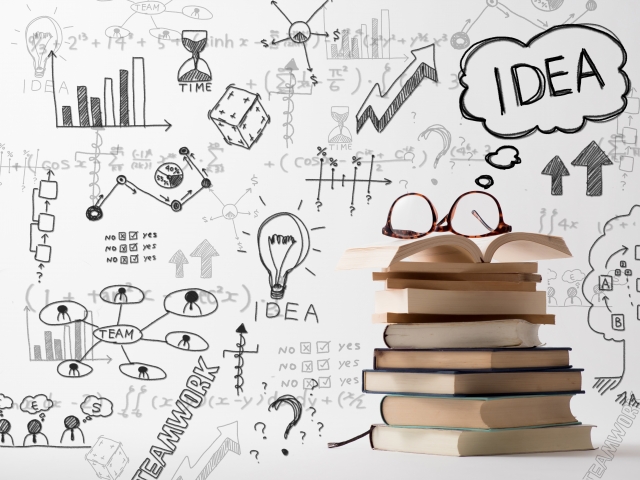
2030年の近未来においては、想像以上の大きな変化が現実味を帯びてきています。そうした社会では、ただ単に知識を暗記し、それを再現するだけの学習を行っていても社会で活躍できる人材にはなれそうにありません。あるいは、豊かな人生を送ることも難しそうです。知識の習得はもちろん重要です。しかし、これからの社会においては、身の回りに起きている様々な問題に自ら立ち向かい、その解決に向けて異なる多様な他者と協働して力を合わせながら、それぞれの状況に応じて最適な解決方法を探り出していく力をもった人材が求められているようです。また、様々な知識や情報を活用・発揮しながら自分の考えを形成したり、新しいアイディアを創造したりする力をもった人材が求められているようです。
こうした社会で豊かに生活し、活躍していくためには、実際の社会で活用できる資質・能力を身に付けることが大切になります。そのためにも、自ら設定した課題に対して、自ら学び共に学び、その成果を自らとつなげる「探究」の学びをすることが大切になってくるのです。
高等学校では、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」と名称変更したことなどもあり、多くの学校で「探究モードへの変革」が始まろうとしています。こうした動きは、小中学校でも、ますます顕著になっていくでしょう。
プロセスの充実と資質・能力の育成
では、実際の社会で活用できる資質・能力を身に付けるためには、どのような「探究」を行うことが求められるのでしょうか。私は、「探究のプロセス」が重要であると考えています。
資質・能力の育成は、その学習活動において、一人一人の子供が本気になって、真剣に、自らの思いや願いの実現や課題の解決に向けて取り組むことが欠かせません。なぜなら、資質・能力は本人が全力で取り組み、そうした力を発揮することの繰り返しや積み重ねによってこそ身に付くからです。
資質・能力の育成は力を発揮し続けるプロセスの充実にあると考えるべきです。解決せずにいられない課題を設定し、その課題の解決に向かって全力で取り組むことによって育成されるのです。相手にわかりやすく伝えたいと願い、発表の仕方を工夫したり実際に伝えたりしていくことで、プレゼンテーションの力は劇的に進歩していくのです。
「未来社会を創造する主体としての自覚」を確かにする

こうした「探究」を中核に据えて取り組んでいる学校が多くなっています。地域の課題を解決し、地域の活性化に向けてチャレンジした「探究」の学びのニュースが目にとまることが増えています。
この「探究」については、比較的小中学校の実践が充実している傾向にありました。しかし、最近では高等学校の優れた実践が各地に生まれ始めています。高校生の「探究」は小中学生とは比較できるようなものではありません。高校生の行動力、発想力、思考力などが、より深い本物の「探究」を実現するのです。
例えば高等学校の取組としては、次のような事例をイメージすることができます。
・サイエンスやテクノロジーと結び付けて課題を追究する
・SDGs(持続可能な開発目標)のようなグローバルな課題を自分の暮らしや地域の生活と関連付ける
・町の未来や将来に向けて行動し、町の元気を生み出す
こうした多様で豊かな「探究」の学びは、一人一人の進路を考えることにもつながり、自らのキャリアを考えることにも結び付いていきます。小学校で着実に積み重ねてきた「探究」を担う「総合的な学習の時間」は、中学校から高等学校へと確実に広がりを見せ、今現在、教育課程の中核として位置付くようになり始めています。「探究」に対する期待や役割は、今後一層高まり続けることとなるでしょう。
このことは、実は「未来社会を創造する主体としての自覚」を確かにしていくプロセスと考えることもできます。「探究」は変化する社会に対応する人材を育成することにとどまりません。社会の変化をただ単に受け身になって受容するのではなく、未来の社会、将来の社会を、自らの手で創り上げ、構築していくという極めて前向きで積極的な姿勢を育てることに役立つものと考えるべきでしょう。まさに、「未来社会を創造する主体」を育てるのです。
これからの教育は、変化の激しい社会に対応できる人材の育成が求められています。その一方で、変化に対して受け身ではなく、そうした変化自体を生み出す能動的な存在であることも重要な人材像としてイメージする必要があるのではないでしょうか。
地域社会の維持と活性化に貢献する教育課程の創造

各学校においては、一刻も早く「探究モードに変革」しなければならないでしょう。「探究」の学びは一人一人の子供を変え、教師の意識を変え、学校を変えていきます。そして、そのことが地域をも変容させていくからです。
その意味から考えるならば、教育課程の編成と実施は、地域を活性化させ、地域の維持と発展に大きく寄与するものとなることが求められる時代がやってきたと言えるのかもしれません。少子化や高齢化といった直近に迫る現実的な問題は、地方都市を中心とした地域の崩壊や縮小を懸念させています。そうした問題にも対応する重要な役割が、学校というソーシャルキャピタルには求められているのでしょう。
Profile
國學院大學教授
田村 学
たむら・まなぶ 1962年新潟県生まれ。新潟大学卒業。上越市立大手町小学校、上越教育大学附属小学校で生活科・総合的な学習の時間を実践、カリキュラム研究に取り組む。2005年4月より文部科学省へ転じ生活科・総合的な学習の時間担当の教科調査官、15年より視学官、17年より現職。主著書に『思考ツールの授業』(小学館)、『授業を磨く』(東洋館)、『平成29年改訂小学校教育課程実践講座総合的な学習の時間』(ぎょうせい)など。