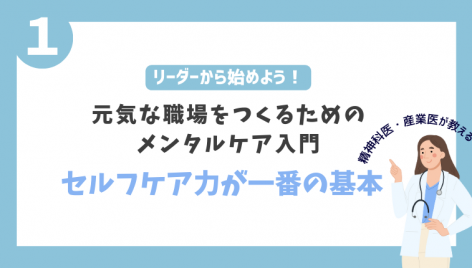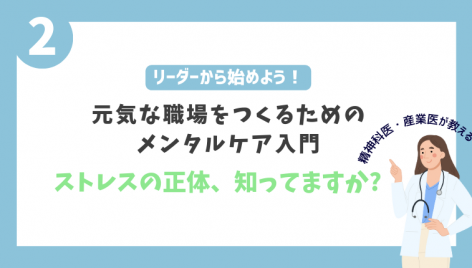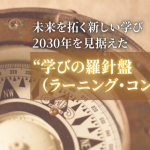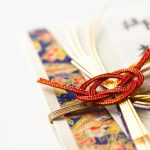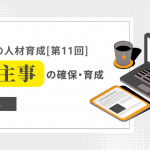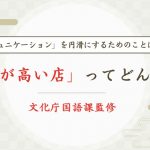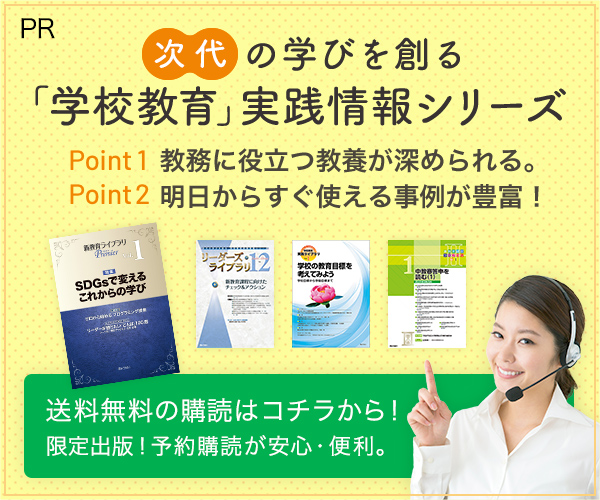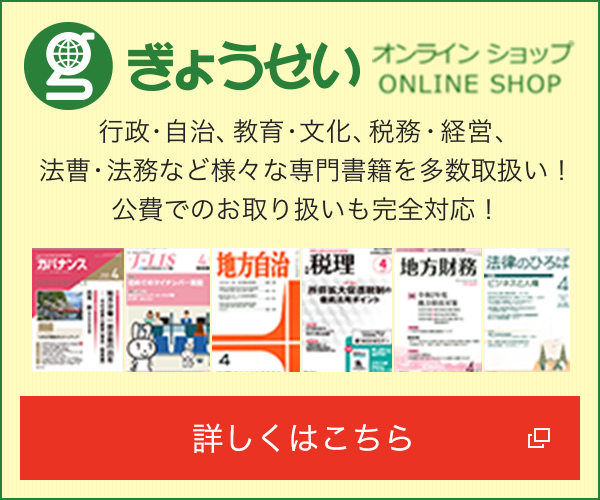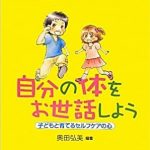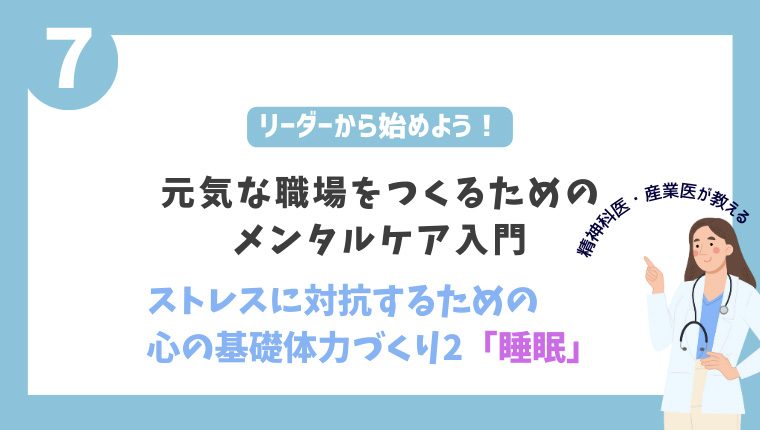
教師のためのメンタルケア入門
リーダーから始めよう! 元気な職場をつくるためのメンタルケア入門[第7回]ストレスに対抗するための心の基礎体力づくり2「睡眠」
学校マネジメント
2020.05.15
新型コロナウイルス感染症対策に伴う急激な環境の変化や病気への不安により、いわゆる自宅でコロナ鬱(うつ)に悩む方が増えています。ご自身やご家族に問題がなくとも、一緒に働く方の心の健康は大丈夫でしょうか。ここでは、精神科医・産業医として活躍する奥田弘美先生が学校の管理職層向けにメンタルヘルスを親しみやすく解説した「リーダーから始めよう! 元気な職場をつくるためのメンタルケア入門」(『学校教育・実践ライブラリ』連載)を12回にわたってご紹介いたします。(編集部)
リーダーから始めよう!
元気な職場をつくるためのメンタルケア入門[第7回]
ストレスに対抗するための心の基礎体力づくり2「睡眠」
精神科医(精神保健指定医)・産業医(労働衛生コンサルタント)
奥田弘美
(『学校教育・実践ライブラリ』Vol.7 2019年11月)

前回に引き続き「心に、ストレスに対抗する体力をつける」という観点から、今回は睡眠の重要性についてお伝えしたいと思います。
睡眠は体と心の健康の最も基盤となる大切な行為です。しかし働く人の中には、睡眠を軽視している人が少なくありません。
その結果、うつ病やパニック障害などの心の病気や眩暈、胃腸障害、ひどい頭痛などの身体不調に至る人も存在します。
人は睡眠中にただ体を休めているだけではなく、次のような心身の重要なメンテナンスを行っていることをまずはしっかりと理解しましょう。
●睡眠中に行われる心身のメンテナンスとは?

①身体面へのメンテナンス
• 前日の体の疲れを解消する。
体全体の疲労を回復させる重要な物質(疲労回復物質や成長ホルモンなど)はすべて、睡眠中にもっとも効果を発揮するしくみになっています。
• 免疫機能を活性化し、あらゆる病気にかかりにくくする。
ウィルスをやっつけるリンパ球は睡眠中に産生され活性化します。睡眠不足が続くと免疫が低下するため、感染症にかかりやすく、かつ重症化しやすくなります。
また健康な人の体でも、1日約5000個の癌細胞が生まれているといわれていますが、睡眠中にリンパ球が癌細胞を攻撃し、死滅させてくれています。
よって睡眠が不足すると癌も発生しやすくなります。
また睡眠不足が続いている人は、高血圧や糖尿病になりやすいこともわかっています。
②メンタル面(脳機能面)へのメンテナンス
• 脳の疲れをとり、記憶力、集中力、学習力をアップさせる。
睡眠不足になると、思考力、集中力、記憶力などの低下がおこり、作業効率が著明に落ち、ミスが発生しやすくなることがわかっています。
• 記憶の整理が行われ、感情を調え安定させる。
脳は、睡眠中に必要な記憶は残し、不必要な記憶や不快な感情は薄めることで、心を安定させます。睡眠が不足すると、ネガティブな感情がいつまでも残り、抑うつやイライラ、不安を感じやすく感情が不安定になります。
この状態が続くほどメンタル不調が発生しやすくなっていきます。
●良質かつ十分な睡眠時間を確保するためには?

これらの素晴らしい睡眠効果を十分に発揮するためには、最低でも6〜7時間は連続して睡眠をとる必要があるとされています。
レム睡眠とノンレム睡眠のセット(約90分)を最低4セット、連続して繰り返さないと、上述した睡眠中の心身のメンテナンスが十分に行えないからです。
また深く良質な睡眠をとるためには、睡眠に入る前の時間にリラックスして心身の緊張と解いておく必要があります。
就寝の2〜3時間前からは、「安眠のための大切な導入時間」として意識して、次のことに気をつけて過ごしてください。
①寝る1〜2時間前からは、スマフォやゲーム、SNSなどのIT機器に触れない。
IT機器のブルーライトや画面の激しい動き、SNSの不安定な文字だけのコミュニケーションなどはリラックスを阻害し、不眠を誘発しやすくなります。
②ゆったりと夕食、穏やかに団らん、入浴などを楽しむ。
食事をゆったり食べる、穏やかに団らんや入浴を楽しむことは、交感神経の緊張をほぐし副交感神経を活性化させて質の良いリラックスを促進します。
③夕方からはカフェイン飲料を避ける。
コーヒー、紅茶、緑茶などのカフェインは約5時間は覚醒効果が続くとされています。夕刻からは飲まない方が無難です。代わりに麦茶・ハトムギ茶・ハーブティーなどのノンカフェイン系飲料がおすすめです。
④寝る2〜3時間前からは食べない。
また寝る直前まで食事をすると胃腸の動きが活発化して眠りを阻害しますので、夕食は寝る時刻の2〜3時間前に摂り終えるのが理想です。
残業でどうしても遅くなる場合は、思い切って職場で夕食を済ませてしまう方が、質の良い睡眠が確保できます。
⑤適度な飲酒を心がけ、寝る3時間前からはアルコールを飲まない。
アルコールは睡眠の質を悪化させ、熟睡を阻害することがわかっています。
晩酌する場合は、適量飲酒量(ビールならば750ml程度、日本酒ならば1合、ワインならばグラス2杯程度)に留め、眠る約3時間前には飲み終えるようにすると、アルコールがほぼ代謝された状態で眠ることができます。
上司にあたる方は、部下がきちんと睡眠をとれているか時々ヒアリングしてみてください。
長時間残業や持ち帰り仕事が多い人は、睡眠が十分にとれていないため心身の不調が発生しやすくなります。
働き方改革で残業時間の規制が厳しくなった根本の理由も、睡眠時間をしっかり確保して働く人の心身の健康を守ることにあります。
管理職の皆さまには、ご自身はもとより部下の睡眠状況を常に考えつつ、適切な仕事量を管理監督していただきたいと思います。
Profile
おくだ・ひろみ
平成4年山口大学医学部卒業。都内クリニックでの診療および18か所の企業での産業医業務を通じて老若男女の心身のケアに携わっている。著書には『自分の体をお世話しよう~子どもと育てるセルフケアの心~』(ぎょうせい)、『1分間どこでもマインドフルネス』(日本能率協会マネジメントセンター)など多数。