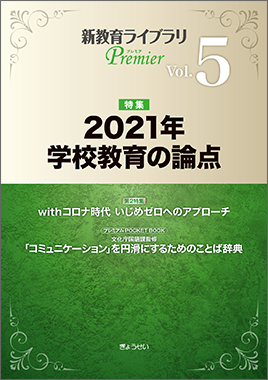教育実践史のクロスロード
教育実践史のクロスロード[リレー連載・第5回] 大村はま ことばを育てることは教育そのものである―国語単元学習の先達の教室
トピック教育課題
2021.03.23
教育実践史のクロスロード[リレー連載・第5回]
大村はま
ことばを育てることは教育そのものである―国語単元学習の先達の教室
大村はま記念国語教育の会事務局長
苅谷夏子
(『新教育ライブラリ Premier』Vol.5 2021年2月)
優れた言語生活者を育てる

昭和の時代に、質・量ともに圧倒的な単元学習を実践した国語教師・大村はまは、ある時期から著書にサインを求められると、こう書き添えるようになっていた。
ことばを育てることは 心を育てること 人を育てること 教育そのものである
大村が国語教師であるために、このことばは少しばかり収まりがよすぎるところがあり、「まあ、いかにも国語の先生の言いそうなこと」という範疇に置かれがちな気がする。けれども、大村にとって、「ことばの力」というのは教科としての国語の成績を遙かに超えて、すべての人が、考えながら、理解しながら、人と交わりながら、周囲の世界から学びながら、生きていく上で、正真正銘の土台となるものだった。国語教室の中のお勉強という限定的な話ではなかったのである。
「優れた言語生活者を育てたい」――大村はそういう言い方をしている。ことばを丁寧に正確に、豊かに誠実に使って、それぞれの人生を生きていく。ことばを、杖のようにも梃子のようにもして考えを進めていく。そういう力を子どもに持たせることを大村は文字通りに「教育そのものである」と確信して、国語教室を営み続けた。ことばの力はきっと一人ひとりの生涯にわたる力となって生きることを支えるだろう。ことばとはそういうものだ、と大村には確かな実感もあり、確信もあった。
大村の生徒の一人は、「大村教室で得たのは、OSだと思う」という言い方をしている(鳥飼玖美子、苅谷夏子、苅谷剛彦著『ことばの教育を問いなおす』筑摩書房、2019年)。OSはコンピュータのすべての働きの土台となるシステムである。人の知的な活動を貫く基本的なシステムとしての言語を鍛えることーー「情報」が社会のキーワードになるような時代を迎えた今、言語とその教育をそのくらい本質的なレベルで定義することは非常に重要なのではないか。大村はまの仕事の今日的意味はまずそこにある。
教室で伝えられたもの

私は、大村はまの52年にわたる教員生活の終わりから10~8年目という時期の生徒の一人だ。教室として使われていた図書室で、大村は堂々たることばの力の持ち主として(その素晴らしい代表として)、私たちの前に立ち続けた。大村のことばの豊かさ、的確さ、鋭さ、あたたかさ、無駄のなさなどは中学生の目にも耳にも届いた。一人の小柄な女性教員が、身をもって「優れたことばの使い手」の像を示したのである。「ことばの力」は、理屈や抽象的な理論ではなかった。体温の感じられる血の通った実例として日々刻々私たちの目の前にあって、生意気盛りの中学生たちを静かに脱帽させていた。
教養ある知的な大人とはどれほどのものか、その迫力やすごさを生々しく子どもに見せるのは、おそらく教育という営みの土台にあるはずのものだろう。子どもが見上げ、世界の広さと深さを知り、自分の力の未熟さを実感し、あこがれる。かっこいいなと思う。まねしてみようと思う。いつかああなろうと思う。そういう大人の役割を、大村は十分に果たしたのである。
そしてまた、大村教室で忘れられないのは、学ぶことの価値、ことばの力を鍛えることの価値を、大村はまが中学生たちに対して全身全霊をもって、はっきりと請け合っていたことだ。勉強は、みなさん一人ひとりにとって重い価値のあることだ、と大村は心から言い切った。あまりに大真面目にそう言うので、なんだか少しおかしくなって、くすりと笑いたくなるくらいに大村は本気だった。
こういう人の率いる教室が人を育てないわけがない。
力が伸びる時

しかし、ことばの力のようなものは、原理原則を言えば育つというものではない。「これは大事」「これができないと合格しないよ」といくら繰り返しても、「理解しなさい」「練習しなさい」と命じても、それで力が育つわけではない。教えるという仕事は、正しいことを述べ、覚えなさいと命じ、理解度を検査・評価することではなく、望ましい力を実際に付けさせることである、という厳しい職業観を大村は引き受けている。
合理的な人であった大村はまは、望ましい力が実際に育つにはどんな条件が必要か、どういう瞬間にどんな力が獲得されるか、それを徹底的に見抜こうとした。自分自身の頭の中のこと―これについて考えたい、知りたいという気持ちはどんなふうに湧くのか。わからなかったことがわかるのはどんな瞬間か。どんな導きが役に立つのか、立たないのか。わからない時には、どんな罠に落ちているのか。“わからない”から抜け出す契機は? ……そうした知の獲得にまつわる実体験がいつも大村の発想の根元にあったようである。
そして大村の合理性は、たとえばこんな事実もあっさりと認める。
自覚を持った、求めている子どもが話している時に、いろいろのやり方というか、話し方のことを話せば、それはもう乾いている土が水を吸うように、喜んでその、私のいわゆる話し方に関する注意というのを聞くでしょうし、また、聞きたいとも思うでしょうけれども、それほど話したいと思わないことについて、それを上手に話すこと、相手を説得する方法など聞いていても、まことにむなしいと思うのです。そのむなしいことをむなしいとも思わないで、先生が話し合いをしなさいと言うから話している、といったようなことになるのです。
(大村はま著『大村はまの国語教室』小学館、1981年)
求めていない子どもにいくら知恵を授けても、「○○しなさい」と命じても、むなしい受動性しか生まれない。ーー教える仕事に就いている人ならばだれでも痛感しているこの事実を、大村は平然と客観視した。そして次にどうしたかが、大村はまを大村はまたらしめている。子どもが思わず求めて乗り出してくるような、つまり、子どもの主体性を誘い出すだけの力のある学習を生み出すことを、大村は教師としての自分の責任として引き受けたのである。そこで生まれたのが単元学習と呼ばれる実践群であった。
単元学習の意味あい
大村はまの単元学習の実際を述べるには、残念ながら紙幅が足りない。ぜひ直接、大村の著作や研究書を読んでいただきたい。
大村は「子どもたちはおそろしくマンネリを嫌い、飽きやすい人たちである」ことを前提にしている。それを責めてどうなるものでもない。そういう人たちを真に自主的な姿にするには、教師の側に新鮮な、本物の興味、子どもたちと共にこのことを追求したいという熱意、それに足る魅力的な取り組みであることが必須と考えた。それを大村は仕事の基本とした。その結果、大村単元学習は繰り返しをしない常に新しいオリジナルなものになった。そうすれば自然に大村自身が新鮮な研究的意欲に包まれ、子どもを惹きつけるだけの“引力”を持つことになったからである。大村が後から後から教室に持ってくる学習は、子どもの想像を必ず超え、新鮮だった。新しい単元は、興味津々という空気の中で幕を開ける。世の中でここだけの試みだということが子どもにもわかり、その手応えは嬉しいものだった。苦労の多い、大変な学習であっても、嫌々渋々ではなく、武者震いとともに引き受ける。ある中学1年生は、単元を締めくくる「あとがき」の中で、「最初にこの単元の話を先生から聞いた時は、血わき肉おどり、『よしやるぞ!』と心に決めたものでした。」と書き記している。そういう生徒を生み出す力があの教室にはあったのだ。
現実問題としては、学習指導要領のもと、決められたスケジュールに沿って決められた教科書を用いて教えていく現場の先生方にとって、大村はまの「常に新しいオリジナルの単元学習」は、別世界の話としか思えないかもしれない。けれども、たとえ20年間、同じ教材で同じことを教えてきたとしても、今日、この子どもたちにこの興味深い実例を使って、これまでと違う入り口から切り込んでみよう、ということならば、可能なのではないか。今ここにいる私が、ここにいる子どもたちに、この新しい窓からの景色を見せよう、という試みは、新鮮な一回性を帯びるのではないだろうか。
教師のそうした知的な挑戦と冒険は、子どもにきっと探知される。彼らの若い好奇心をくすぐり、その挑戦に乗ってみようと思わせるだけの熱を持つ。それは大村教室の生徒であった私がぜひ伝えたいことだ。大村はまは、開拓精神に満ち航海術に長けたすごい船長で、私たちはその船に一緒に乗り組んで、勇躍ことばの海原に乗り出したものだ。
新しい単元を調えて出発する時の気持ち、それはほんとうに中学生を指導するのにふさわしい気持ちなのです。新鮮で、そして少し不安で、したがってつつましい気持ち。謙虚な気持ち。
なかなかそういう気持ちにはなれませんのに、新しいものであると、工夫しなくても自然にそういう気持ちになれるのです。そのすがすがしい気持ちがうれしくて、この気持ちを一度覚えると、その気持ちになりたくてどうしても新しく、と思ってしまいます。
(大村はま著、原田三朗聞き手『「日本一先生」は語る―大村はま自伝』国土社、1990年)
単元学習のむずかしさ

ただし、単元学習には、確かな目的・方法と的確なてびきが不可欠である。これこれの力をこの材料とこの方法で育てようという明快な指向性と、そこから子どもたちを逸らさず知的作業を確かに導いていく専門家の存在があってこそ、実を結ぶ。単に新奇な、面白そうな、子どもが好きそうなことをわいわいとやってみたところで、目的の絞り込みがなければ、また大事な点を大事なタイミングで押さえる手際が不十分であれば、教室は無残に散漫になる。活動が活発であっても、賑やかな興奮はあっても、力に結実することは難しい。アクティブ・ラーニングが強調される中で、それは非常に今日的な問題であるに違いない。教える専門家ならではの構え、冷静に子どもの頭の中を見抜く目、大切なことに目を向けさせ明らかにする技術などは、大村はまの実践のあちこちに見いだせるだろう。
また、他にも意外な落とし穴がある。特に国語科では、教科書の文章を逐一丁寧にすみずみまで理解させることが目標であるような姿勢が目立つ。それを繰り返す限り、新しい窓を開くのはまず時間的に難しくなり、可能性はかなり限られてしまう。単元的視点で編まれている今日の教科書は、「教科書を教えるのではなく、教科書で教える」ということになっているはずだが、どうしても丁寧に教科書を教えてからでないと先に進めないような気持ちが教員の側から抜けないようだ。
大村はたいへん大胆なところのある人で、目的をしっかり押さえたらそこにまっすぐに果敢に向かっていった。教材となる文章をすみずみまで細かに読み取らせなければ先には進めない、とは考えず、目的に必要な部分を確かに押さえさえすれば次の段階に進ませた。主体的になった子どもは、それを意外なくらいちゃんとやりこなし、必要なことは読み取ったものだ。力が弱い子どもには、大村が個人的に手助けをした。
そういう時にしばしば大村の武器になったのは優れた音読の力だった。大村はまの音読は、意味をその繋がり具合まで含め、非常に鮮明に伝え、聞く人の頭にすっと入った。大げさな演技的な読みではなく、ことばの力を信じた、整理の効いた、すっきりとした読みだった。だから難解な構造の文章であっても、テキストを目で追いながら大村の読みを耳で聞くと、不思議なくらいすんなりと頭に入ったのだった。
そうやって助けられながらバリバリと資料を読んでいき、興味深いあれこれを胸にいっぱいにした中学生たちは、何かに気付いたり作り上げたりし、それを自分の素晴らしい達成のように思い、大事にことばにした。その過程で力は着実に育ったのである。
98歳で亡くなる寸前まで、ことばを育てる仕事について考え続けた大村はまの仕事のほんの一角を述べたが、ICTの時代と騒がれる今において、まったく古びない知見の膨大な塊がここに存在する。
Profile
苅谷夏子(かりや・なつこ)
1956年生。大田区立石川台中学校で大村はまに学ぶ。東京大学国文科卒。大村の晩年の仕事を手伝い、現在は大村実践を伝える活動をする。著書に『優劣のかなたに─遺された60のことば―』『評伝 大村はま』『ことばの教育を問いなおす』など。