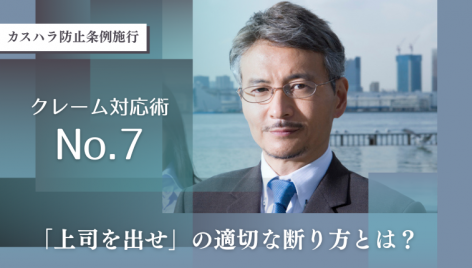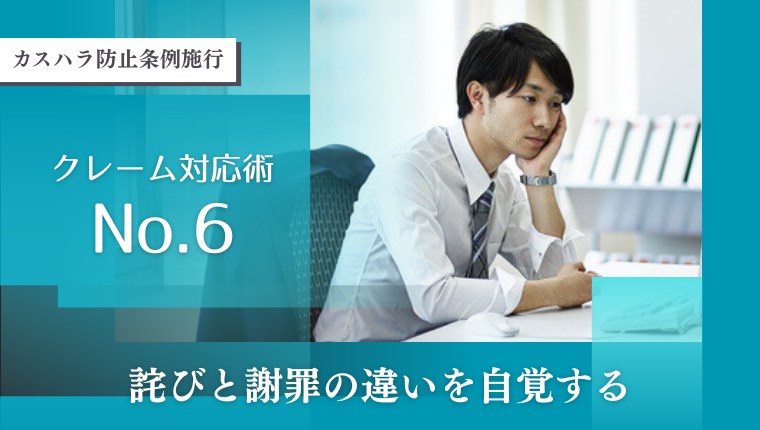
クレーム対応術
詫びと謝罪の違いとは?|クレーム対応術6【カスハラ対策】
キャリア
2025.04.04

この記事は4分くらいで読めます。

出典書籍:『ガバナンス』2014年9月号
今さら聞けないクレーム対応術 6
『上司から、「市民に謝ってはいけない」と言われましたが……』 /月刊ガバナンス 2014年9月号
2025年4月1日、東京都などで「カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例」が施行されました。
これにより、企業や自治体にも適切な対応策の整備が求められています。
しかし、すべての厳しい意見がカスハラにあたるわけではありません。
適切なクレームには真摯に対応しつつ、不当な要求には冷静に対処することが重要です。
本記事では「詫びと謝罪の違い」について解説します。
カスハラ・クレーム対応の参考としてチェックしてください!
この記事で分かること
・「詫び」や「謝罪」をしたら責任を取るべきか
・「詫び」と「謝罪」の違い・例文
・「詫び」と「謝罪」をするべき場合
・善良なお客様の見分け方
「申し訳ございません」と、謝ったら責任を取らされる?
クレームを受ける立場の職員の中には「申し訳ございません」などと謝ると、責任を取らされると思っている人がいる。事実、お客さまの中にも、こちらが詫び言葉を使うと「申し訳ございませんと言った以上は責任を取れ!」などと言ってくる人がいるものだ。だから、謝ってしまうと、こちらの立場が不利になると考える。
こちらには非がない、悪いのは相手方だ、下手に謝ると相手に高飛車に出られるなどと思うと、こういった詫び言葉を使うことが躊躇される。そうならないために、謝ってはいけないと思うようになるのだ。
これらの気持ちはわかるが、「詫び言葉の一つも言えないのか!」などと、謝らないことが事態を悪化させているケースも多い。
結論から申し上げると、「ごめんなさい」「すみません」「申し訳ありません」などと、相手方に詫び言葉を使って謝っても、責任を取らされることはない。詫びる、謝るという行為と、責任を取るということは、基本的に別の問題である。
詫びと謝罪は違う
そもそも、謝るという行為は、詫びの意味と謝罪の意味がある。同じ「申し訳ございません」「すみません」などの発言でも、詫びと謝罪は意味が違うのだ。場面に応じて詫びの意味で「申し訳ございません」と言ったのか、謝罪の意味で「申し訳ございません」と言ったのか、これを自覚することがクレーム対応では重要なポイントになる。
詫びることとは、相手方の不満や不快について言及することである。つまり、
「不快な思いをさせて、申し訳ございません」
「ご心配をおかけして、申し訳ございません」
というレベルであれば、これは相手方の気持ちに配慮しているわけで、相手方への心配りなのである。言い換えれば、このことでこちらが良いとか悪いとか、正しいとか間違っていたとかについては、一切言っていないのだ。
こちらに非があってもなくても、相手方は不快な思いをされたのであるから、まずは詫びることは、現実的に重要である。
「ご要望に応じることができず、申し訳ございません」
「お待たせして、申し訳ございません」
「ご不快な思いをされたのであれば、心からお詫びします。申し訳ございません」
このような言葉で素直に詫びの気持ちを表現すれば、たとえ相手方が気分を害していても、その事象がそれほど大きなものでない限りは気持ちの上で許されるだろう。むしろ、詫び言葉がないことで、事務的、冷たい、こちらの気持ちをわかっていないといった印象になり、相手方が感情的になることも少なくない。
一方、謝罪の場合は、明らかにこちらに非があったと認めることである。つまり、
「こちらの説明が明らかに間違っていました……」
「こちらの行動が明らかに不適当でした……」
などと言い切って、「申し訳ございません」と続けるのだ。まさに謝罪である。
小さなトラブルは、詫び、謝罪を繰り返す
では、詫び、謝罪をしたら、責任を取らなければならないのか。その答えは、詫び、謝罪が道義的な意味か、社会的な意味を持つものかを自覚することだ。ここでは、道義的な意味を個人のレベルでの詫び、謝罪と考える。社会的な意味は、社会的制裁を受けるべき、法的責任を受けるべきことと考える。
公務員も人間である以上、日常業務で小さなミスをすることがないとはいえない。例えば、お客さまを長く待たせてしまったり、折り返し連絡することを失念してタイミングを逸してしまったなどである。時には、お客さまの事情を十分に把握できず、必要書類の説明の一部に漏れがあり、そのことで相手方に不快な思いをさせることがあるかもしれない。
もしそれが、道義的な責任で済むことであれば、お詫びと謝罪を徹底的に繰り返すことで許されるだろう。常識的には、それしか方法はない。つまり、心から詫び、謝罪を繰り返すことが責任の取り方ということである。
もし起こしたミスが大きくて、社会的な意味での詫び、謝罪が必要だと判断されたら、それは担当者の個人的な詫び、謝罪では済まない。上司を呼んで一緒に詫び、謝罪をしてもらうことが現実的だろう。
これは、上司の肩書き、立場で行うものであるから組織として詫び、謝罪をしたことになる。場合によっては、それ以上の解決策を模索することもあるかもしれない。例えば、特別扱いを認める、金品で解決する、さらに言えば裁判を起こして法廷で何らかの決着をつけるなどということだ。
どのような場合でも、詫び、謝罪を繰り返しても、そのことで責任が重くなることは決してない。小さなミスで、いちいち「ご不満ならば訴えてもらっても結構です」などと理屈で返していては、人間関係は間違いなく悪くなる。それを自覚した上で、問題に誠意をもって対応する意味で、詫び、謝罪の言葉を使う必要があるのだ。
月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」を加筆修正、再構成し単行本化
クレーム対応のさまざまな悩みを解決!
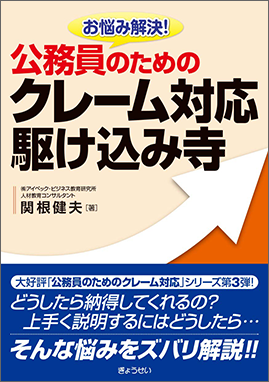
お悩み解決!
公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 編著者名:関根健夫/著
販売価格:2,420 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【こちらもおすすめ】
弁護士が相談を受けた“現場の困った”要求にどう対応するか(業界別に)分かる!!

Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック
-平時の備えと有事の対応- 編著者名:日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会
販売価格:3,630 円(税込み)
詳細はこちら ≫
カスハラをはじめとする不当要求行為等について、実際の事例から対応を学ぶ!

自治体職員のための
不当要求行為対応ブック
-事例からわかるトラブル回避策- 編著者名:宇都木法律事務所(代表弁護士 宇都木 寧)
販売価格:3,080 円(税込み)
詳細はこちら ≫
次のページ ≫ 【コラム】善良なお客さまと、そうでない人はどこで判断するか