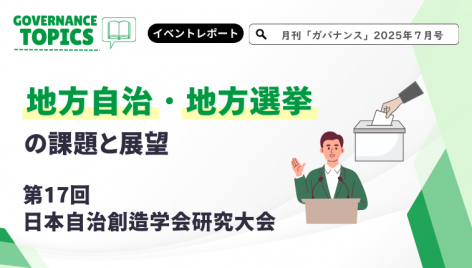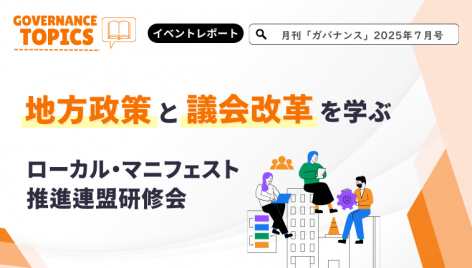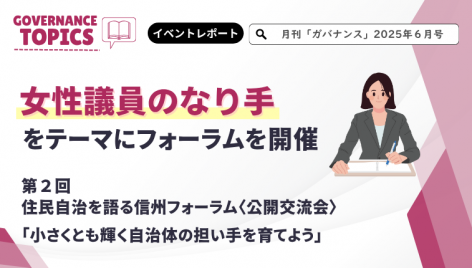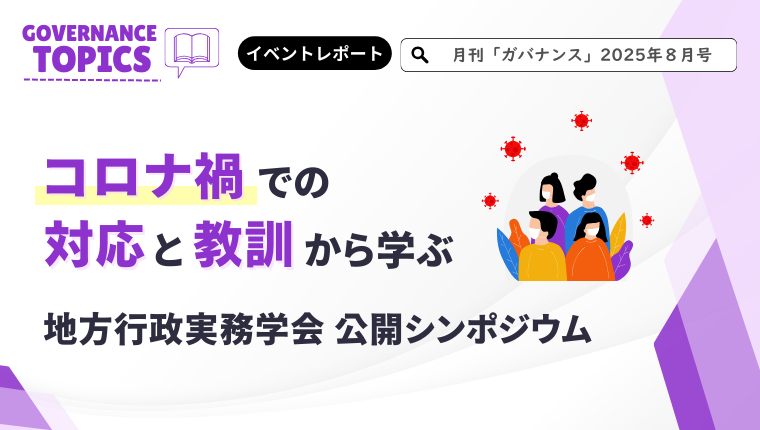
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【コロナ禍での対応と教訓】地方行政実務学会公開シンポジウム/イベントレポート
地方自治
2025.09.02

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年8月号
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
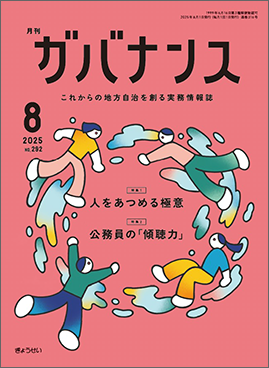
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【ガバナンス・トピックス】
コロナ禍での対応と教訓から学ぶ
──地方行政実務学会公開シンポジウム
自治体職員経験のある研究者や現役自治体職員らで構成される地方行政実務学会(理事長/礒崎初仁・中央大学教授)は6月7日に都内で公開シンポジウムを開催した。今回のシンポジウムは同学会内に設置した「新型コロナ対応検証研究会」が3年間の調査・研究成果をまとめた報告書が書籍化されたことを記念したもの。自然災害なども頻繁に発生する中、コロナ禍の経験からこれからの自治体の「危機管理力」を考える場となった。
3年間の研究成果を書籍化
同学会は、2020年3月に発足。自治体の実務経験を有する研究者や現職の自治体職員らが研究交流を行い、年2回研究大会を実施している。2022年6月に、会員有志によって「新型コロナ対応検証研究会」(座長=礒崎理事長、委員41人)を学会内に設置。コロナ禍での全国自治体の対応の実態について調査・検証し、その教訓を社会に還元しようと活動をしてきた。このほど、3年にわたる調査、研究の成果は報告書(書籍)としてまとめられ、『ポストコロナの自治体危機管理──徹底検証!全国自治体1300日の新型コロナ対応とその教訓』(第一法規)として発刊された(*)。
* 116 頁「リーダーズライブラリ」で新刊紹介。
今回のシンポジウムは書籍の発刊を記念し、「どうする?自治体の危機管理─新型コロナ対応1300日の検証をふまえて─」と題して、中央大学茗荷谷キャンパス(東京都文京区)を会場に開催された。

会場には約120人が参加した。
新型コロナ対応検証研究会(以下、研究会)は、
■新型コロナウイルス感染症という未知の感染症に対して、全国1788自治体は、特措法に基づく行動制限、感染症法に基づくクラスター対策・入院調整、学校・福祉施設等の感染対策、ワクチン接種、生活困窮者や中小企業に対する支援など、様々な措置の迅速な実施を求められた。
■全国の自治体は、こうした課題にどのように対応したのか。首長はいかにリーダーシップを発揮し、職員はいかにチームワークを発揮し、住民はいかに自治体の施策に協力したか。
■取り組みを総合的に検証することを通じて、感染症対策や防災対策など今後の危機管理のあり方を考えたい。同時に、日本の地方自治の強みと弱点を考える素材にする
──ことを目的に、2022年6月に同学会に設置。座長・副座長、部会長、委員を委嘱、41人(研究者会員25人、一般会員16人)で構成された。
2022年度~2024年度の3年間をかけ調査研究を行い、学会の研究大会などと併せて全体研究会を11回開催。さらに、7回のヒアリング調査と、2023年度には全自治体アンケートも行った。
同研究会では、6つの領域の部会を設置し、各部会長の音頭のもと調査研究が進められた。報告書(書籍)では、各部会の調査研究報告を各章立てとし、全7章(終章を含む)としてまとめられた。
様々な切り口から検証
まず、開催に先立ち西出順郎副理事長が、「研究会は、3年前から調査研究をしてきた。何十人ものメンバーが1つの研究プロジェクトを進めていくのは研究学会では珍しい取り組みなのではないか。シンポジウムで学びや得られる知見があれば非常に嬉しい」と挨拶をした。
第1部は調査研究のポイントの報告として研究会の各部会長等が登壇し、各部会(各章)の報告を行った。
まず、第1章「新型コロナ対応の経過と検証の視点」として、礒崎座長が国と自治体それぞれの対応の状況について整理した。
礒崎座長は、「新型コロナ対応では、基本的な方針の枠組みを国が定めた。全国的な視点で適切な方針を打ち出していく国の役割は大変重要」としながらも「感染は現場、地域で起こる。感染対策、経済対策ともに、基本的な対応は自治体が、地域の事情に合わせて工夫しながら進めなければいけない。その中でも広域的な対応は都道府県、そして生活に身近な対応は市町村。役割分担があり、“集権と分権の合わせ技”が重要なのではないか」と述べた。
また、国が実施してきことに関して「未知の感染症に対して、概ね精一杯の感染防止対策を講じてきた」と評価しつつも、
■緊急事態宣言等について明確な基準や指標を示せず、場当たり的な判断になった
■感染対策は行政指導中心になったため、感染防止の実効性や公平性に問題が生じた
■感染対策が効果を上げないうちに経済対策に着手し、感染の拡大と長期化を招いた
■政治の「決断」を強調する一方で、自治体の執行現場の実情を軽視した施策が多かった
──など問題点も挙げた。
危機管理体制についても、
■行政組織の縦割り(内閣官房、厚労省など)と、現場からの遠さ
■「政治主導」における、政治家の独りよがりな「決断」と官僚の迎合姿勢
■専門家の知見を尊重する姿勢の乏しさ、専門家集団との信頼関係の乏しさ
■国の行政組織における集権的発想、自治体との役割分担意識の希薄さ
──などの浮き彫りとなった点を指摘した。
さらに、自治体(都道府県、保健所設置市区など)の実施してきたことについても言及。<特措法>住民への外出自粛、施設管理者への休業等の要請、<感染症法>発熱者の検査・積極的疫学調査、入院や宿泊療養等の対応、<施設管理>学校や福祉施設等における感染対策などに「誠実に取り組んできた」と評価。特に、強力なリーダーシップのもと、
■独自の宣言や自粛呼びかけにより感染予防に寄与したこと
■検査体制・感染者への医療対応について、地域の実情に合った対策を打ち出した(神奈川モデル、和歌山モデル等)
■医療機関との連携によって医療を維持し、在宅療養者を支援した(墨田区モデル等)
■感染対策、差別禁止等のための独自条例を制定した
──などの注目すべき対応を紹介。「○○モデルという独自の対応を講じたことで、これによりむしろ国の方針を変えたという面もある」とした。
その上で、「自治体の対応の問題点(仮説)」として、
①保健所の職員体制のひっ迫、発熱者等への対応の遅れ(保健所の位置づけ変更、行革など)
②感染症法の施行等における国の通知・事務連絡への依存。
そして、「自治体の危機管理体制の特徴・強み(仮説)」として
①首長制による首長のリーダーシップの発揮しやすさ
②自治体行政における現場性(現場へのアクセスが容易)と応答性(当事者等への応答が容易)
③適度な形で専門性を生かせること(専門家の内部登用・外部登用)
――などについての仮説を分野別に各部会が具体的に検証を行ったことを紹介した。
続いて、第2章~終章までを担当した各部会長が報告を行った。
■第2章「新型コロナ対応における首長のリーダーシップと特措法・条例」=第2部会(首長・特措法・条例部会)津軽石昭彦部会長(関東学院大学、元岩手県)
■第3章「新型コロナ感染対策における保健所と医療機関の役割」=第3部会(保健所・医療施設部会)大谷基道部会長(獨協大学、元茨城県)
■第4章「コロナ禍の生活支援とワクチン接種の推進」=第4部会(生活支援・ワクチン部会)井上武史部会長(東洋大学、元福井県敦賀市)
■第5章「新型コロナ感染症が地方経済と自治体財政に与えた影響」=第5部会(経済対策・財政部会)竹内直人部会長(京都橘大学、元福井県)
■第6章「新型コロナ対応に伴う自治体の人事・組織運営・デジタル化」=第6部会(人事・組織・デジタル部会)和田一郎部会長(獨協大学、元茨城県)
■終章「新型コロナ対応検証の成果と残された課題」=礒崎座長が研究、調査について発表した。
第2部会の津軽石部会長は、首長のリーダーシップ、対策の展開、法運用等の部分について調査分析を報告。「都道府県知事には法権限の主体として、地域事情(エビデンス)に応じた対応もみられた」とし、「一般にコロナ対応は、ボトムアップ型の自然災害と異なり、国によるトップダウン型とみられがちだが、アンケートからは適正な執行のための国の補完措置、人員確保、地域経済対策、関係機関との連携などで独自の取り組みも散見された」と分析。
さらに、「国のタテの圧力のもと、首長たちは知事会、市長会等のヨコ連携を図るなど多様な合従連衡があった」とと振り返った。
また第4部会の井上部会長は、ワクチン接種の実務について自治体アンケート調査の結果からみえてきたこととして、「他の業務(自宅療養者支援、医療機関との調整、給付金支給等)より円滑に進んだ一方、都道府県は『人員上の課題』(職員に多様な役割が求められた)、市町村は『国の方針や姿勢の課題』(国→都道府県→市町村のプロセス)という課題の違いがみえた」と紹介した。
人事・組織運営・デジタル化分野について調査した第6部会の和田部会長は、
①保健所の疲弊:膨大な業務と人手不足で機能が限界に。精神的負担も深刻
②HER-SYSの導入と限界:感染者データの共有を目的としたが、複雑な操作性とサポート不足で現場は混乱。最終的には改善されたが、初期設計に現場視点の欠如
③給付金・支援業務の混乱システムの未整備とデジタル格差により、職員負担が集中
──などの教訓を整理し、デジタル対応から見る地方自治体のこれからのあり方として、「持続可能で柔軟な地域行政には、現場に根ざしたDXと強固な連携体制が不可欠だ」とした。
終章では、検証結果を踏まえた今後の提言として
①人材確保・育成と組織体制整備
②情報システム整備
③国と自治体の連携強化
④危機管理体制強化
⑤経済対策
の5つを示し、次なるパンデミックに備えた強靭で効果的な危機管理体制の構築の必要性を強調した。
各部会の発表に続き、福永一郎委員(高知県健康政策部医監・須崎福祉保健所保健監(保健所長))が「報告書の提言を保健行政にどう生かせるか」と題し、特別報告を行った。研究会委員で唯一公衆衛生の専門家であり、現職の保健所長でもある福永さんは、
■保健所業務:保健所は単なる出先ではなく地域保健法に基づく行政機関。業務遂行のキャパシティは有限である
■体制づくり(必要に応じて首長と関係機関とのトップ会談等)と医療機関の協力を得た全庁訓練(災害医療訓練を参考に)
■人材確保:トレーニングを受けた人員が平時から一定存在する必要があり、加えて応援人材の派遣を受ける必要性が高い
──などの現場からの課題を提起。「とりわけ首長や総務・政策企画部門の理解が必要であり、強いリーダーシップのもとに、平時から長期的視野を持って計画的に人材育成を行ってほしい」と述べた。
コメンテーターを交えディスカッション
第2部は部会長らによるパネルデスカッションが行われ、コメンテーター(ゲスト)として、金井利之教授(東京大学大学院)、田口祐子さん(品川区)が登壇した。
金井教授は、「現場などを経験した研究者らが、業界などから独立した立ち位置から研究した意義は大きい」と評価。その上で、報告書についての自身の見解も交えてコメント。「危機管理というと平時に危機を想定して準備、訓練すると考えがちだが、それで本当の危機に対応できるだろうか」と問いかけ、「日常(の業務)に対応できるシステムを埋め込まない限り難しいのではないか」と問題提起した。
品川区人材育成担当課長の田口さんは、2021年1月~2023年3月まで保健予防課で新型コロナ予防接種を担当。自身の経験を交えてコメントした。田口さんは、「ワクチン接種の際、応援職員など毎日のように職員が変わり、その都度の引き継ぎ、システムの使い方を教えるなど苦労した。また、ワクチン担当や保健所にいる職員とそれ以外の職員の間に危機感の差を感じた。有事の際は自治体として一つになれるような、心の面でも組織を横断して連携するような職員マインドを育成することが必要なのでは」と人材育成担当の視点からのコメントも加えた。
2人のコメントも受け、部会長ら、そして会場も交えて活発なディスカッションが行われた。会場には、保健所勤務の職員なども参加。当時の状況を振り返りながら、自治体の危機管理のこれからについて議論が交わされた。

パネルディスカッションでは、コロナ対応についての○×アンケートも実施。登壇者、コメンテーターらのそれぞれの見解も議論した。
最後に稲継裕昭副理事長が「新型コロナは政治と行政の関係、そして国と地方の関係を考え直す、学者・実務家に対する試練でもあった。感染症対応だけに限らず人材不足も顕著だ。考えなければならない話題はたくさんあるが、報告書(書籍)が役に立てば幸いだ」と挨拶し、シンポジウムを締めくくった。
(本誌/浦谷 收)
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
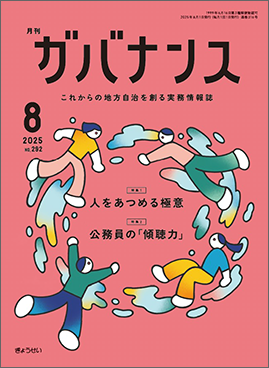
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫