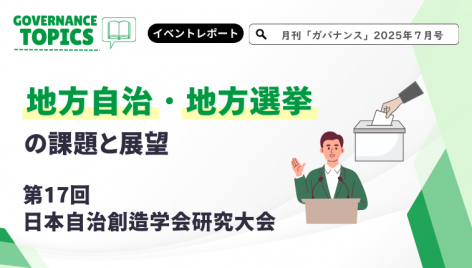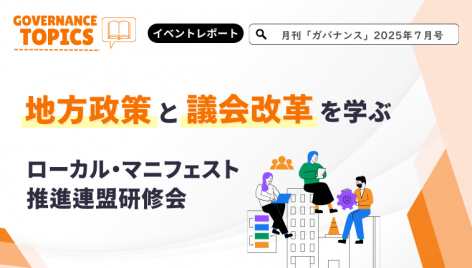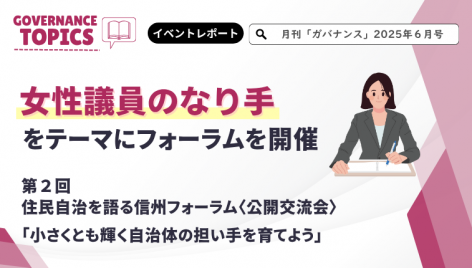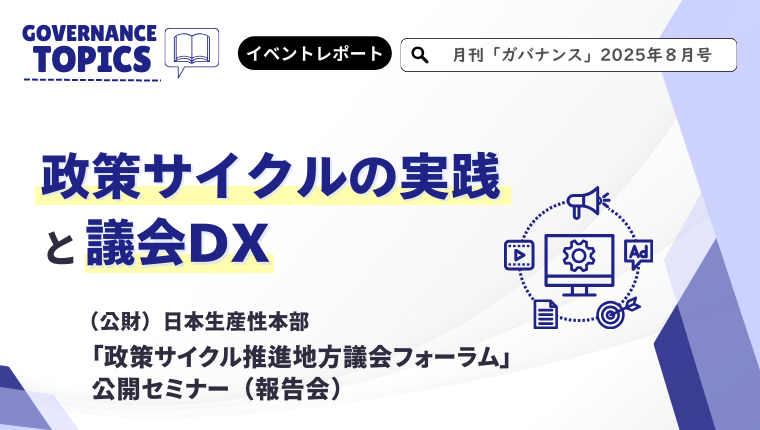
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
「政策サイクル推進地方議会フォーラム」公開セミナー(報告会)/イベントレポート
地方自治
2025.09.03
目次

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年8月号
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
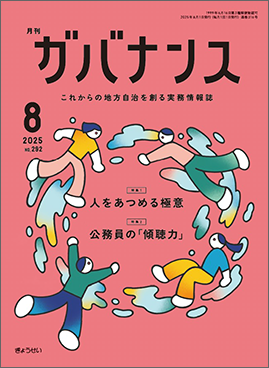
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【ガバナンス・トピックス】
政策サイクルの実践と議会DXについて議論
──(公財)日本生産性本部「政策サイクル推進地方議会フォーラム」公開セミナー(報告会)
(公財)日本生産性本部は5月24日、都内で「『地方議会からの政策サイクル』と成熟度評価モデル、議会DXのミライ」をテーマに、公開セミナー(報告会)を開催した。政策サイクル推進地方議会フォーラム(座長=江藤俊昭・大正大学教授)による、「地方議会成熟度評価モデル」の実装化の事例報告と議会DXの現在地についての議論が行われた。
成熟度評価モデルの到達点を報告
日本生産性本部は、2020年に「地方議会成熟度評価モデル」を開発。22年には「政策サイクル推進地方議会フォーラム」を発足し、より多くの議会での評価モデルの実装化の推進と政策サイクルの構築・作動に向けた取り組みを行っている。今回のセミナーは、24年度の同フォーラムの取り組みの報告会を兼ねて開催された。

報告会とセミナー・パネルディスカッションの2部構成で開催。
福島県会津若松市議会の実践報告
第1部は報告会。同フォーラム事務局の同本部から活動報告が行われたあと、実践報告として松崎新・福島県会津若松市議会議員が登壇した。
同市議会では、前任期から試行的に成熟度評価モデルに取り組み、内部評価を実施。3人の学識経験者による外部評価(*)を経て、その結果も踏まえた総括評価を行った。
* 外部評価のようすは、小誌2023年6月号p32-33「議会評価における外部評価ヒアリングを実施――会津若松市議会」にて紹介している。
改選後の23年10月に議会評価特別委員会を設置。特別委員会は、委員を各常任委員会等から1人ずつ選出し、委員会審査や所管事務調査等と議会評価の連動を意識した検討体制としたことが特徴だ。
議会評価の基本的な考え方
同委員会では、次の3つの区分による視点を議会評価の基本的な考え方とした。
1つ目は「議会」で、具体的には①議会基本条例に基づく議会運営の評価(議会の作動の評価)と②議会からの政策サイクル自体の評価。2つ目は「執行機関」で、「市長側と議会との善政競争により、良い政策が実現できているか」。3つ目は「市民」。市民と住民団体について、議会が関与することで①住民福祉が向上しているか②住民の政治参加等が進み、住民が自律的に地域課題を解決するための自治力が向上しているか──と整理した。
評価に向けた手法のバージョンアップ
さらに、評価の実施に向けた手法をバージョンアップ。24年8月に委嘱された「議会モニター」は、議会広報紙のみだった「広報議会モニター」に代えて、設置された。高校生から70歳代までの44人がモニターとなり、「(議会モニターは)定点チェックの役割を果たす」(松崎議員)という。議会評価への活用可能性だけでなく、「地区別(分野別)の市民との意見交換会」とは異なる視点からの広聴ツールとしての活用が期待されている。
「議会白書」のリニューアル
また、4年おきに作成し全戸配布してきた「議会白書」を25年3月に「議員参加ガイドブック」としてリニューアルしたことも発表した。
議会DXの今とこれから
「議会からの政策サイクルと議会DX」
第2部の公開セミナーでは、議会DXをテーマに議論が展開された。まず、江藤教授が「議会からの政策サイクルと議会DX」と題して講演した。
第1部からの議論の流れを受け、政策サイクル構築の重要性を強調。その上で、「DXを住民自治の充実に活用することが大切だ」とし、各地で進む議会DXの現在地を再確認した。
「議会DXとDC(デジタルコミュニケ―ション)」
続いて、「議会DXとDC(デジタルコミュニケ―ション)」と題して河村和徳・拓殖大学教授が講演した。
河村教授は、コロナ禍では、接触確率を減らし、デジタル技術の活用が進んだが、コロナ禍が収束した今、「どう克服するか」と問題提起。全国の市区議を対象にした調査では、年代が高くなるほどデジタル活用に否定的な割合が増え、旧来型の選挙運動が主流であることを説明した。河村教授は、
■効率性ではなくデジタル・インクルージョンという発想(開かれた多様性のある議会の創出)
■自然災害など危機下においてもプレゼンスを提示できる(危機に強い議会)
■ペーパーレス化、オンラインによる参考人招致などにより議会費を抑制する
──などのDC活用の論点を示した。「アナログか、デジタルか、ではなくアナログも、デジタルも」という考え方が重要と話した。
茨城県取手市の実践報告
最後に、岩﨑弘宜(ひろまさ)・茨城県取手市情報管理課長(元議会事務局次長)が実践報告を行った。
取手市議会では、民主主義と技術を掛け合わせた造語「Demo Tech(デモテック)」に挑戦。オンラインによる副委員長互選や一般質問(会議規則改正)、AI字幕、会議録視覚化システム、タブレットとZoomによる現地調査──など議会でのDX導入事例を紹介した。
岩﨑さんは「今までの議会改革では切り拓けていなかった場所・人にも可能性があるとわかった」と振り返った。そして、スピーディーに進められた背景には、議員と事務局職員による「チーム議会」の醸成、そして「まずはやってみよう」と一歩踏み出したことにあると語った。
「デジタルは難しくなく、慣れ」と強調し、「住民の皆さんがいることを忘れないことが重要だ」と付け加えた。
パネルディスカッション
セミナーの後半は、報告・講演を行った4氏が登壇し、パネルディスカッションを実施。議論の中で、河村教授は議会DXを進めるにあたってのポイントとして「成功体験を可視化し、それによって正のサイクルに入ることが重要だ」とコメントした。

登壇者らによるパネルディスカッションでは、参加者からの質問にも答えながら進められた。
各地で多様な方法で進む議会DX。デジタルを議会活動、そして議会からの政策サイクルにいかに活用していくかを考える会となった。
(本誌/浦谷 收)
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
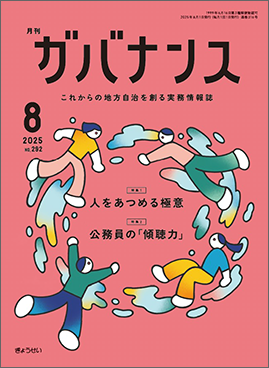
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫