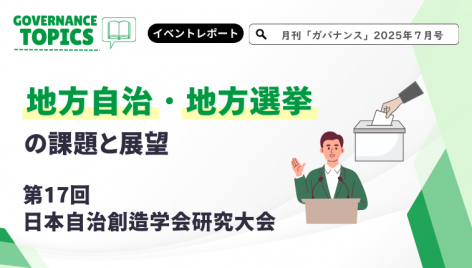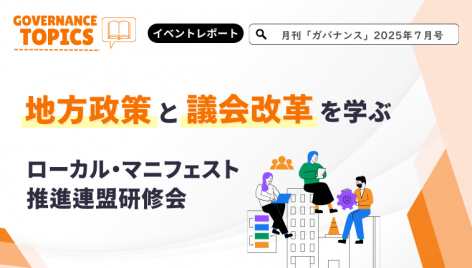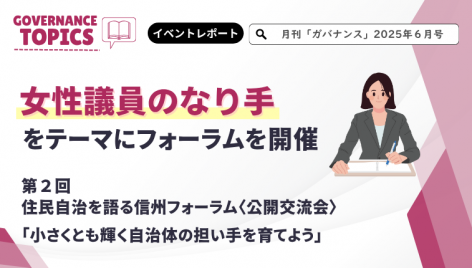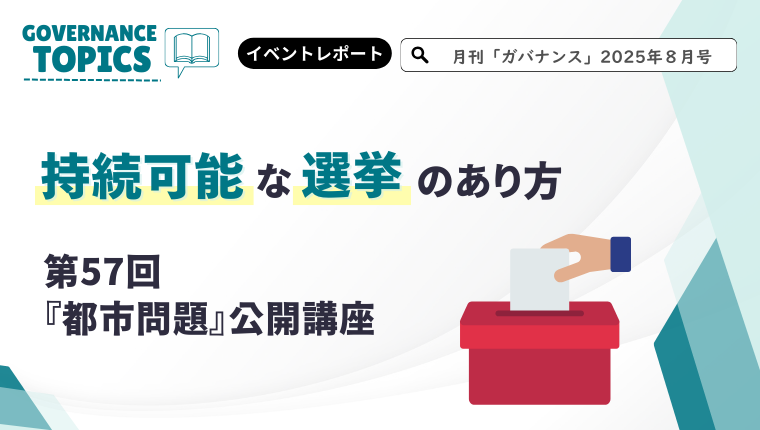
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
第57回『都市問題』公開講座【持続可能な選挙のあり方】/イベントレポート
地方自治
2025.09.04
目次

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年8月号
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
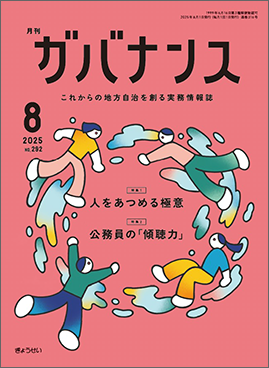
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【ガバナンス・トピックス】
持続可能な選挙のあり方を議論
──第57回『都市問題』公開講座
都市政策のあり方や社会的課題などについて議論をする、第57回『都市問題』公開講座((公財)後藤・安田記念東京都市研究所主催)が6月21日に都内で開催された。昨今の選挙ではSNSが有権者の投票行動に影響を与えはじめるなど、これまでとは様相が変化してきた。民主主義に関わる重要な装置である選挙のあり方を探った。
変化する選挙環境
2024年に行われた東京都知事選挙および兵庫県知事選挙では、SNSの影響力が有権者の投票行動に広範な影響を与えはじめた。また、近年の都市部を中心とした選挙では、いわゆる「選挙ハック」勢力の存在感が徐々に増してきた。それ以外にも、選挙をめぐっては、選挙運動に関するルール、供託金制度、電子投票や記号式投票、人口減少地域における選挙管理事務の維持など、選挙の運営・実施過程には多くの論点がある。
今回の講座では、民主主義に関わる重要な装置としての選挙のあり方を議論しようと、「選挙を守る―持続可能(サステナブル)なあり方を求めて」と題して開催された。同研究所の小早川光郎理事長のあいさつに続き、パネルディスカッションが行われた。

今回の公開講座はパネルディスカッションのみ。パネリスト同士の議論の時間を多く設けた。
パネルディスカッション
登壇者
小島勇人氏(一般社団法人選挙制度実務研究会理事長)
山口真一氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授)
河村和徳氏(拓殖大学政経学部教授)
司会
谷口尚子氏(慶應義塾大学法学部教授)
パネルディスカッションの趣旨と論点
まず、谷口教授が、
①日本の選挙を巡る諸課題とは何か
②民主主義の重要な装置である「選挙」をどう守っていくか
③今後重要となるポイントは何か
の3点のパネルディスカッションの趣旨を提示。
その上で、
■情報環境の変化が選挙に影響?(多次元の対策、ルール化、リテラシー教育の必要性)
■政治参加をどう活性化させるか?(主権者教育、選挙環境の改善、選挙制度・選挙活動)
■日本の選挙にとって今後重要なポイントとは?(普遍化、危機管理、技術進化)
の論点を整理した。
「持続可能な選挙のあり方―制度論と投票参加」
続いて、登壇者らが選挙についてそれぞれの視点から話題提供を行った。まず、小島さんが「持続可能な選挙のあり方―制度論と投票参加」と題し、発表した。
総務省管理執行アドバイザー、主権者教育アドバイザーを務め、選挙制度・実務に精通する小島さんは、①選挙制度 ②有権者の投票参加 ③立候補者 の3つの側面から紹介。現行の選挙制度を整理し、共通投票所制度創設等のこれまでの投票環境向上の動きや、様々な主体による主権者教育の状況も紹介した。
小島さんは、最近の選挙事例も取り上げつつ、「議員のなり手不足が深刻化する一方で、中核市・特別区など定数過多の選挙も存在し、有権者の負担が大きくなりすぎてしまっているのではないか」と指摘した。
「SNS時代の選挙をどう守るか:制度とリテラシーの再設計」
次に、山口准教授が「SNS時代の選挙をどう守るか:制度とリテラシーの再設計」として、発表した。山口准教授は、「2024年は“SNSと選挙”の転換点だった」とし、東京都知事選や兵庫県知事選ではSNSや動画共有サービスが大きな力になり、それと連動するように支持が変化したと紹介。「インフルエンサーが選挙結果を左右するほどの力を持った」と振り返った。
そして、SNS選挙の課題として、「多く人がフェイク情報を信じてしまっている」と指摘。その拡散スピードは事実の6倍の速さだという。「フェイク情報は人の考えを変え、特に選挙においては“弱い支持”をしている人ほどフェイク情報によって支持を下げやすい」という分析結果も紹介し「『既得権益と闘っている』などの『正義と悪』のようなナラティブ、対立構図や、怒り・正義などは拡散しやすい」と述べた。
「with フェイク2.0時代のメディアの在り方」
さらに山口准教授は、アテンション・エコノミーなどの問題にも言及した上で、「withフェイク2.0時代のメディアの在り方」として、マスメディアへの課題と期待についても触れ、課題として
■中立を意識していることもあり、報道が中途半端になった
■短くてわかりやすい・センセーショナルなコンテンツは動画共有サービスとSNS、深堀りはネットメディアになり、マスメディアは中途半端な位置となった
■真偽不明情報への迅速なファクトチェックができていなかった
点を挙げた。
そして、
①有権者が冷静に政策から投票先を検討できるコンテンツの充実
②真偽不明情報・疑義言説への迅速なファクトチェック
③各サービスの特徴を踏まえた効果的な配信
を期待した。
「フェイクニュースに特効薬はなく、『自由・責任・信頼があるインターネット』を築くために、ステークホルダー間の連携が必須だ」と強調した。
一方で、「(マス)メディア vs SNSの勝ち負けではなく、人類総メディア時代で情報収集のチャネルが増えただけだ」とし、政治への関心を高め、裾野を広げるというメリットもあることも付け加えた。
「選挙における持続可能性―東日本・熊本・能登、そしてコロナパンデミックの教訓を踏まえて」
最後に、「選挙における持続可能性―東日本・熊本・能登、そしてコロナパンデミックの教訓を踏まえて」として、河村教授が発表した。
河村教授は、選挙ガバナンスから考える持続可能性として「法律的に選挙ができることと、選挙が実際にできることは違う」と話し、「大規模災害やパンデミックなどの“危機”はこれまでの選挙のあり方への挑戦であり、それに法改正や運用の見直し、新たな技術の導入など、どう対峙するかを考える機会だ」と述べた。
そして、日本の選挙ガバナンスの課題として「機動性の欠如とPDCAサイクルの機能不全」を挙げ、
■新しい技術に対応しづらい環境
■マンパワーが抱える課題
を示した。
さらに、SNSを利用した選挙運動で生じている課題として、
■視聴数を稼ぐことで個人的に恩恵が受けられる環境の登場
■選挙管理機関に求められるスキルの向上
を挙げた。
最後に、
■選挙民主主義を支える制度(選挙制度・議会制度)の制度疲労(歴史が長いが故に改革が難しい構造)
■五月雨式の選挙実施(改革が進みにくい一つの原因(大合併の弊害))
■中央選管なき選挙管理体制をどう考えるか?(デジタル化など改革は中央集権的な方が進めやすい)
―などの「選挙管理のリデザインの必要性」についても言及した。
これからの選挙のあり方をディスカッション
後半は、3人からの話題提供を受け様々な議論が交わされた。投票率の低下の議論では、小島さんが「出前授業など発達段階に応じた選挙啓発は必要だが、選挙のときだけでなく、選挙がないときの常時啓発を行うことで個々の政治意識を高めていくことが重要だ」と強調した。
SNSと選挙については、山口さんは「2024年は衆院選もあったが、それ以上に都知事選や兵庫県知事選がSNSでは盛り上がった。それは首長選というたった一人を決める選挙だから。対立構造を描きやすく、過激な言説で対立を煽りやすいからだ」とSNSが影響を与えやすい選挙の傾向を紹介。また、フェイク情報についても山口さんらが関わった研究では、わずか14.5%の人しかフェイク情報と気づかないという結果が出たという。「自分は批判的思考・態度が取れていると自信がある人ほど騙されやすい」と話し、「謙虚な気持ちで情報空間に接してほしい」と呼びかけた。そして、SNSで拡散しようとしたときは「一歩立ち止まって情報検証をしてほしい」と話した。
河村さんは、「SNSの法規制の話がうまく進まないのは、議論できる専門家が限られているからだ。選挙空間は、選挙区など物理的な空間に情報空間も加わってきた。技術面と立法や行政運営、制度面のそれぞれの立場を超えたコミュニケーションの場を作る必要があるのではないか」と提案し、多面的に展開されたディスカッションを締めくくった。
2025年は、普通選挙法ができて100年。選挙のありようが急激に変化をしている中で、選挙を取り巻く現在地とこれからの選挙の持続可能性を探る場となった。
(本誌/浦谷 收)
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
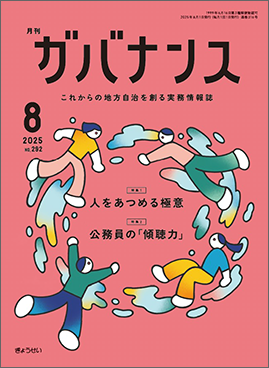
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫