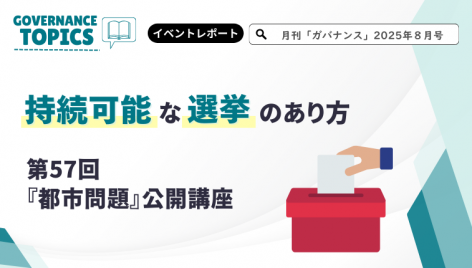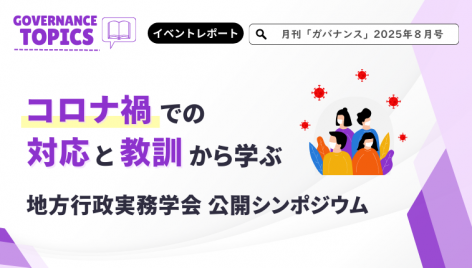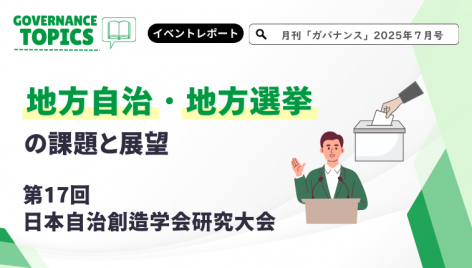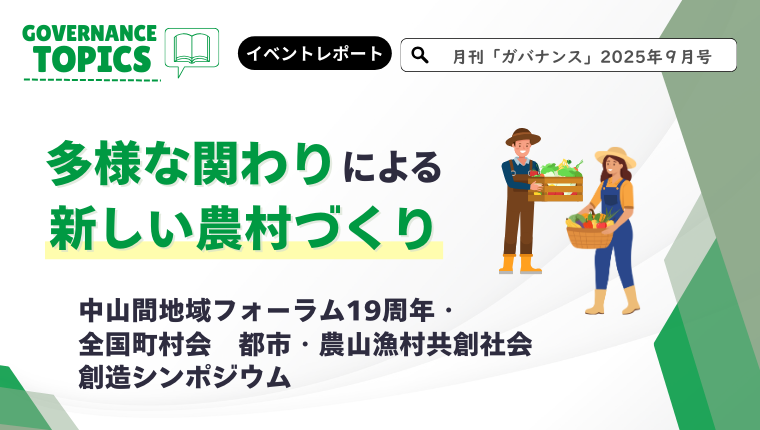
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【共催シンポジウム】多様な関わりによる新しい農村づくり/イベントレポート
地方自治
2025.09.11

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年9月号
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
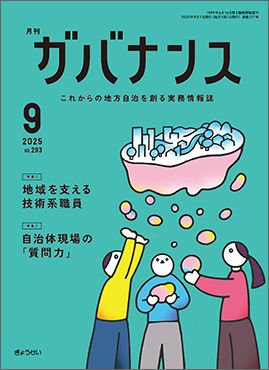
月刊 ガバナンス 2025年9月号
特集1:地域を支える技術系職員
特集2:自治体現場の「質問力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【ガバナンス・トピックス】
新しい農村づくりについて多彩な議論
──中山間地域フォーラム19周年・全国町村会都市・農山漁村共創社会創造シンポジウム
「中山間地域」を支援するNPO法人中山間地域フォーラム(会長=生源寺眞一・東京大学名誉教授)と全国町村会は共催で6月29日にシンポジウムを開催した。各地から農村づくりに関わる実践者らが登壇し、多様な立場から現在地と将来像を議論。人口減少が急激に進む中、新しい農村づくりのあり方を探る場となった。
希望の解像度を上げる場に
今回のシンポジウムは「多様な関わりによる新しい農村づくり~実践から探る 都市農村共創社会~」と題し、中山間地域フォーラム設立19周年シンポジウムと全国町村会の都市・農山漁村共創社会創造シンポジウムが合同形式で開催されました。


約180人が参加し、登壇者だけでなく、会場も巻き込んでの議論が展開された。
多様な「関わり」と農村 ―地域再生の新課題―
生源寺会長の開会挨拶に続いて、同フォーラム副会長の小田切徳美・明治大学教授が登壇し、解題「多様な『関わり』と農村―地域再生の新課題―」として今回のシンポジウムのテーマについてまず整理をした。
小田切教授は、「多様な関わり」に注目する背景として、
①関わり主体(関係人口、関わり事業体)の前進
②農村問題の推転
③地域政策の新展開
の3つの変化を提示。
「関わり」には人、地域、国土の3つのスケールがあるとし、そのすべてに「国、自治体、企業、中間支援、RMOはどのような役割を果たしうるのか、という論点が考えられる」と述べた。
そして、各スケールに、
■人:特に新しい主体としての企業の役割は何か
■地域:本質的に重要な関係人口(企業)と地域住民のごちゃまぜのために必要な場、人材、仕組みは何か
■国土:「関わり」が導く地域未来像(都市農村共創社会)の解像度をさらに上げることはできないか
という論点を提示した。
その上で、シンポジウムへの期待として、「解答ではなく、解法を学び合い、『希望の解像度』を上げる場としてほしい」と呼びかけた。
農村への多様な関わり
パートⅠ
パートⅠでは、様々な立場から地域に関わる方々が登壇し実践報告。そして報告ごとに「私の見方」として専門家らがそれぞれの視点からコメントを加える形式で行われた。
報告1 農村RMOの役割
報告1(農村RMOの役割)では、豊田市の農村RMO(農村型地域運営組織)・しきしまの家運営協議会の鈴木辰吉事務局長が登壇し、地域運営組織がもたらした「小さな変化」を紹介した。鈴木さんは「人口減少、超高齢化を受け止め、都市部の関係人口を地域自治の主体に加えることの大切さを見つけた」と、活動を通した実感を話した。そして、農村RMOを法人化し、地域を経営することなど今後の展望についても紹介した。農業ジャーナリストの榊田みどりさんが「住民自治から関係人口も共に主体となる関係自治への構造改革へと進化している。取組みで、多様性を受け入れる地域住民の意識改革にも寄与していることが素晴らしい」と「私の見方」をコメントした。
報告2 自治体の役割
報告2(自治体の役割)は、岐阜県飛騨市総合政策課の上田昌子(しょうこ)さんが、同市の関係人口を可視化する「飛騨市ファンクラブ」や2020年からスタートした地域課題解決の都市住民とのネットワーク「ヒダスケ!」などのプロジェクトについて紹介。上田さんは、「継続すること」や「現場のリアル感と対話を重視すること」などの重要性を語った。平井太郎・弘前大学教授が「市外のファンの声に応えながら、対話、学習、共創型の政策をつくり、連結をさせていっている」と評価した。
報告3 中間支援組織の役割
報告3(中間支援組織の役割)では、NPO法人bankup(鳥取市)代表の中川玄洋(げんよう)さんが、学生などの外部人材をマッチングし、農作業のサポートなど地域につなげる活動について紹介した。中川さんは、「『つなぐ』『翻訳する』『伴走する』機能を果たしてきた。つなぐ両者の目線を意識することがポイント」と話し、「どちらかが我慢しないように歩み寄る設計、長期目線・続け方を意識することも重要」と述べた。筒井一伸・鳥取大学教授が、「中間組織の存在によって、行政組織、そして職員の意識変容にもつながっている。課題解決だけでなく主体形成になっている」とコメントした。
パートⅡ
パートⅡでは、民間企業や政策の視点からの農村への関わりについて話題提供が行われた。
日本航空株式会社 能登復興事業
まず、日本航空株式会社能登復興事業統括の上入佐(かみいりさ)慶太さんが登壇した。同社は「関係・つながりの創出」を中期経営計画の柱に掲げ、都市―地域間での「新しい人流」を生み出す取り組みを行っている。
同社が取り組む地方留学プログラム「青空留学」や社内ベンチャーW-PITの能登復興事業ユニットについて紹介し、「『社会的価値×経済的価値』により、地域との関係性(資産)を将来的には事業へと反映させていきたい」と抱負を語った。
ふるさと住民登録制度
次に政府の有識者会議の委員も務める高橋博之・株式会社雨風太陽代表取締役社長が登壇。同氏が提案した「ふるさと住民登録制度」について説明した。「都市と地方を行き来しながら同時並行に生きていくことを、国が国民運動として展開していければ」と、提案者の視点から想いを語った。
「『農山漁村』経済・生活環境創生プラットフォーム~企業と連携した農村活性化に向けて~」
最後に、朝日健介・農林水産省農村活性化推進室長が「『農山漁村』経済・生活環境創生プラットフォーム~企業と連携した農村活性化に向けて~」と題して、今後の農村政策の視点、官民共創の農業・農村の課題解決の取り組みを紹介した。
パネルディスカッション
その後のパネルディスカッション(モデレーターは小田切教授)は、前半で実践報告、話題提供をした鈴木さん、上田さん、中川さんと、朝日さんが登壇して行われた。小田切教授は、「都市と農村の共創社会という方向性は、具体的な風景として確かに見えてきた」とまとめ、多様なステークホルダーらによるこれからの農村のあり方、都市と農村の関係性について考える場となった。
(本誌/浦谷 收)
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
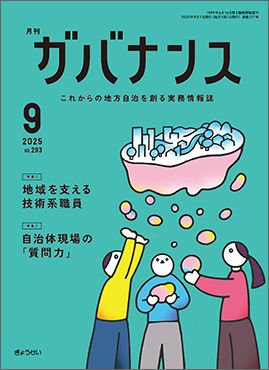
月刊 ガバナンス 2025年9月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫