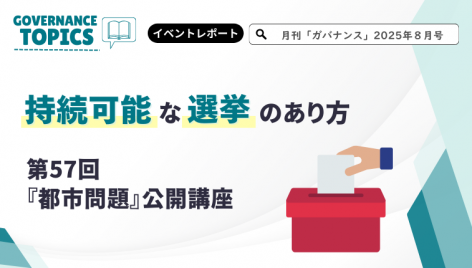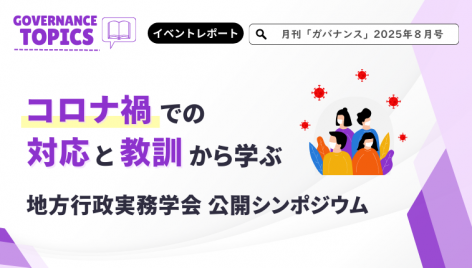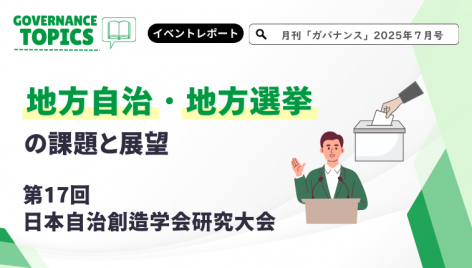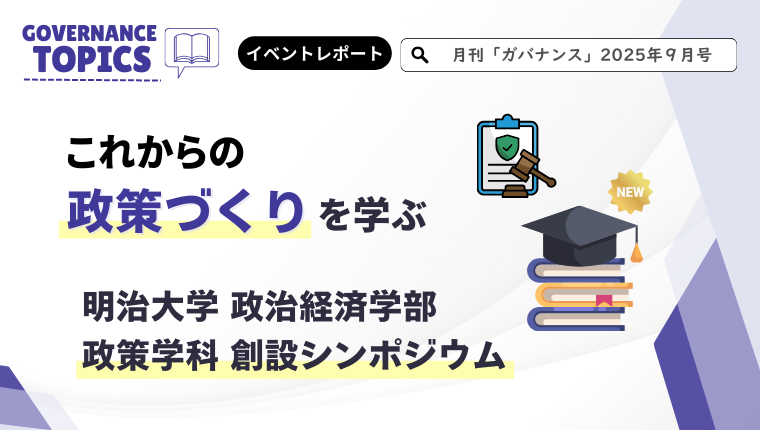
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
明治大学 政治経済学部 政策学科 創設シンポジウム/イベントレポート
地方自治
2025.09.12

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年9月号
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
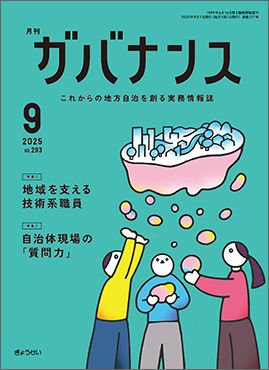
月刊 ガバナンス 2025年9月号
特集1:地域を支える技術系職員
特集2:自治体現場の「質問力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【ガバナンス・トピックス】
これからの政策づくりを学ぶ
──明治大学政治経済学部政策学科創設キックオフシンポジウム
明治大学政治経済学部は2026年4月に新学科「政策学科」を創設する。そのキックオフシンポジウムが8月7日、同大オープンキャンパスの一環として開催された。「課題解決のプロが語る政策 ~自治体・政府・街づくりの視点から~」をテーマに、これから政策づくりを学びたい高校生らに向けて登壇者から多くのメッセージが送られた。

多くの学生が集まり、活気ある雰囲気の中で議論が展開された。
「課題解決のプロ」に
プログラムは牛山久仁彦教授(明治大学政治経済学部)の挨拶から開始。「2002年、政治経済学部に地域行政学科が設立された。その20数年にわたる実践を背景に、新設される政策学科では地域から世界へ、行政から民間へ、領域を超えて活躍する“課題解決のプロ”を養成していきたい」と意気込みを話した。
埼玉県が抱える課題とその政策
続いて登壇者から、自身が関わった政策や取り組みについてのプレゼンテーションが行われた。
まず大野元裕埼玉県知事が、県が抱える課題とその政策について紹介。課題として①人口減少・超少子高齢社会の到来 ②激甚化・頻発化する災害危機 の2点を挙げ、「人口が減ること、災害が起こることを前提に政策を考えるべき」と強調した。政策面では、持続可能なまちづくりを目指す「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」や、DXの導入による行政改革について取り上げた。
政策紹介:地方創生/東日本大震災からの復興
次に末宗徹郎さん((一財)地域総合整備財団理事長、元復興庁事務次官)が、自身が携わった政策から、
①地方創生(魅力ある大学づくりと23区の大学定員抑制)
②東日本大震災からの復興(福島研究教育機構の創設)
の2点を紹介した。
例えば①では、人口減により地方大学が経営破綻へと追い込まれるのを防ぐために、地方への交付金や23区への規制を法整備したという。
研究者から見た都市政策
続いて野澤千絵教授(同大政治経済学部)が登壇。「研究者から見た都市政策」をテーマに発表を行った。
具体的には
■土地利用と災害ハザード(農地の宅地化による内水氾濫リスク)
■都市づくりの高コスト化(価格高騰等により「手が出せる・手を出したい家」がない現状)
■都市と地域の隔地連携(被災地での政策提案や社会起業)
などの研究を紹介。
これら研究から導かれた提案が、国の政策に生かされているという。
野澤教授は、「土地や住宅の分野は、民間に動いてもらわないと実現できないものが多い。民間にどうやって動いてもらうか、経済的価値と公共的価値を相互に向上させる工夫が、今後の政策づくりに必要なのではないか」と話した。
未来を担う学生に向けて
その後、各登壇者が「政策づくりの面白さ・難しさ」を紹介した。
末宗さんは「国の課題解決ができる点」を面白さとして挙げる一方、「利害調整が難しい。課題の本質を見極め政策をつくる力が必要になるが、この困難さもまた、面白さにつながる」と話した。大野知事は「政策をつくる際にはエビデンスが必要。その際に、必要なデータをすべてそろえること、土地や人々が持つ“隠れたエビデンス”(一見気づきにくいが、課題に影響を与えている特有の条件など)を見逃さないことが大切で、難しい点」と話した。
最後は、登壇者から会場を訪れた高校生にメッセージが送られた。新設される政策学科は、日本の未来を形づくる学び場となるだろう。
(本誌/森田愛望)
最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!
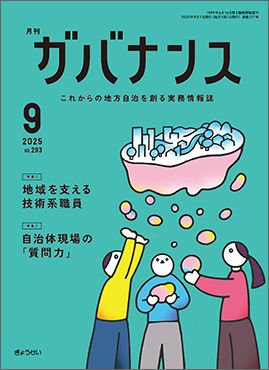
月刊 ガバナンス 2025年9月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」 編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫