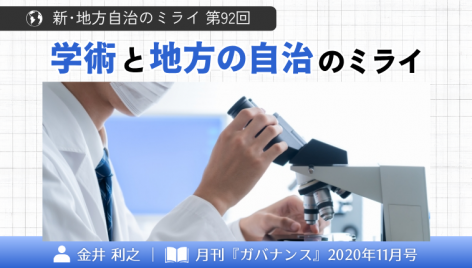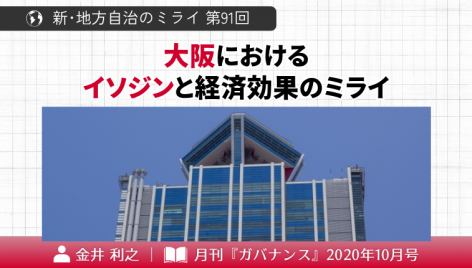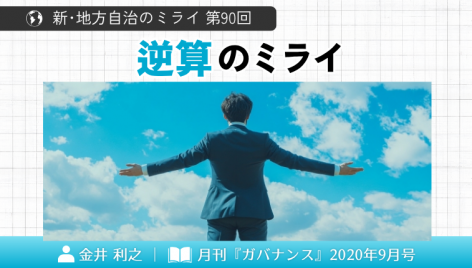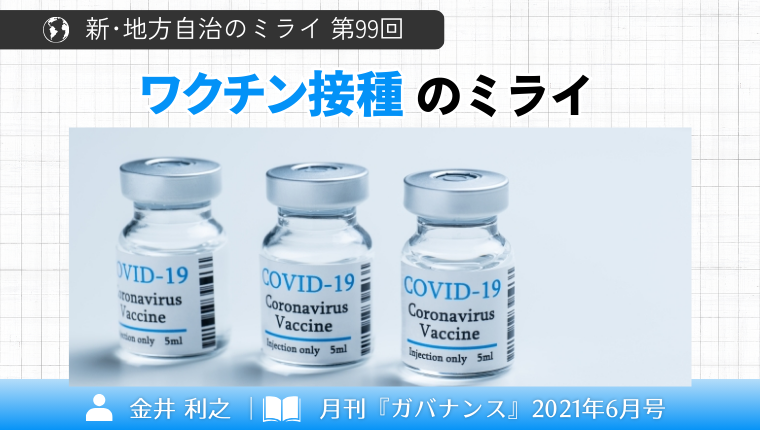
新・地方自治のミライ
ワクチン接種のミライ|新・地方自治のミライ 第99回
地方自治
2025.09.16

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年6月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
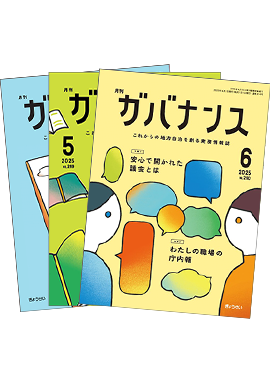
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年6月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

すでに感染が蔓延してから1年以上経ったが、日本の国・自治体にとって、COVID-19対策には、ほとんど打つ手がないのが実情である。そのため、人流・外出・会食などを抑制・自粛する措置と、その反作用として経済活動を活発化させる措置との、「ストップ&GoTo」あるいは「反復横跳び」をしている。「ハンマー&ダンス」とも称されていた。もっと言えば、「マッチ・ポンプ」という。行政・専門家・マスコミなど、関係者自体が厄災禍を煽り、それによって対策を執る演出をして、自らの役割を顕示する。
昨年の今頃は、アベノマスクと特別定額給付金の「遅延」が起きていた。今年は、ワクチン接種の「遅延」と「混乱」が生じた。国の急変転する政策決定によって、業務現場が疲弊することが繰り返されている。デジャヴュである。今回はこの問題を採り上げてみたい。
悉皆事務と人口規模

1億人以上を超える日本において、短期間にほぼ全ての人に、カネ・モノ・サービスをあまねく行き渡らせることは、実に厄介である。こうした、悉皆事務は難しい。
第一の要因は、人口規模である。人口が大きくなればなるほど、悉皆事務は困難になる。しかし、日本より人口の大きなアメリカや、日本と人口の大した違いのないヨーロッパ諸国でワクチン接種が「順調」ならば、日本の人口規模の大きさは言い訳にならない。じっくりと事後検証することが大事である。
実際の接種調整の業務は、最終的には市町村単位で行われている。市町村単位の限られた人口規模であっても、悉皆事務は困難である。
行政能力構築の必要性
国民皆保険・国民皆年金のような悉皆事務は、日本でも導入されている。国民皆就学の小中学校は、学齢層に関して言えば悉皆的である。近年で言えば、2000年の介護保険制度は、主に高齢者世代(被保険者は40歳以上)に限定された悉皆事務を新たに導入した。その意味で、悉皆事務ができないわけではない。しかし、介護保険制度の施行に3年も要した。保育園入所のマッチングは、悉皆事務として機能していない。乳幼児全戸訪問も至難の業である。要するに、日本行政は、もともと悉皆事務を行う能力が低い。「コロナ場のバカ力」が急に発揮できるわけではない。
日本の為政者・民衆などが認識すべきことは、行政体制の脆弱性である。日本国政の為政者や専門家やマスコミは、政権・政治がリーダーシップを発揮して政策決定すれば、自治体などを通じて自動的に政策配送されると勘違いしている。
しかし、これは「昭和の幻想」である。「先沈国」日本は、(衰退)途上国であることを認識し、行政の脆弱性を前提に対策を考えるしかない。併せて、今回の問題を契機に、行政体制の能力を高めることに、中長期的に取り組む必要があろう。
残念なことに、為政者・机上専門家はデジタル化の遅れが失敗を招いていると誤解して、離散変態(DX)に邁進している。しかし、実は、マスクもワクチンも、現物のロジスティクス(兵站)が必要である。配送・仕分けの管理をスマート化することは重要である。しかし、より重要なのは、行政が配送業務できる体制を、日常的に構築することである。今回には役立たないが、中長期的には必要なことである(注1)。
注1 いわゆる2040構想も国政のための行政体制を構築する試みである。
竹槍作戦と精神論の限界

結局、兵站において、必要になるのは、ヒト、モノという、旧来からの行政資源である。オリンピック開催時期までの日数と高齢者人口数から、「1日100万回接種」が必要という、机上の数字をはじき出しても、兵站は付いてこない。なぜならば、ヒトとモノは湧いてこないからである。本当のことを言えば、カネも必要であるが、日本政府は借金が可能なので、カネは湧いてくる。
現状では、ワクチン接種に必要な兵站は、残念ながら全くない。日本企業がワクチン開発をできず、日本政府が早期・大量のワクチン調達に失敗したからである。官民ともに無能である。しかし、仮にワクチン(モノ)が調達できても、それを打つ従事者の確保が困難である。
今の段階で、急な思い付きにより、ワクチン接種に頼る対処は、成立し得ない竹槍作戦である。「ハンマー&ダンス」の「反復横飛び」で、感染拡大・医療苦境を甘受するしかない。もちろん、莫大に感染させて、深刻に医療崩壊を招くことを傍観するわけにいかない。一定程度の感染状況・医療限界状況に抑えつつ、ジリ貧経済のもとでも生活保障を実現するしかない。
無謀な作戦のなかで
ABCD包囲網に囲まれ、ヒト・モノでジリ貧状態になった大日本帝国は、まさにヒト・モノがないがゆえに乾坤一擲の作戦に打って出た。当然ながら、ヒト・モノが不足するので、物量作戦の米中に大敗した。ヒト・モノがないときに出てくるのが、竹槍作戦と精神論である。必敗は自明である。ただし、軍部という軍事専門家や東条英機首相は、内政的には「幕府的存在」の権力を恣(ほしいまま)にしたように、専門家や政権幹部という権力者の地位は安泰である。
自治体現場や民衆や現場医療従事者は、このような政権・自治体幹部・非現場型専門家・医師団体幹部・マスコミなどの竹槍作戦に付き合うと大きな被害に遭う。外見的には「コロナ禍対策」などと行動しつつも、実質的にはサボタージュするのが最も合理的である。つまり、真面目にワクチン接種の早期完了の作戦を遂行するのではなく、世間並みに適当にお付き合いをするにとどめるべきである。
空回りする自称リーダーたちに対する現場の辟易感・忌避感・嫌悪感は、その場限りでは合理的である。アピールだけの政権が進める「ワクチン接種大作戦」を換骨奪胎して、現場でゆっくり着実・公正・安全に進めるのが望ましい。実際、時間を掛ければ、ある程度の接種は進む。その頃には、ワクチンの効かない変異株が増えているかもしれないし、接種した人への効果が消えているかもしれない。現段階では分からないので、接種に関する時間的な順番付けを、公平に進めることの方が、重要なことである(注2)。
注2 各地で余ったワクチンを無駄にしないとか、(準)医療従事者などの名目で、首長・三役や職員に「優先」接種していることが明らかになった。小さい団体・会場で接種すると余りが生じやすい。ともあれ、「キャンセル待ち」の公平な配分という課題が浮上した。
ただ、深刻なことに、こうした辟易感の繰り返しが、日本の行政能力構築を絶望的に困難にしている。将来の為政者が、DXのような場当たり的思いつきではなく、行政建設を真摯に目指すことに取り組んだとしても、それに真面目に付き合う現場の志気が下がっているのである。
おわりに
ワクチンは知見=治験が乏しいのであるから、結果的には先走って接種をするよりも、様子を見ることが合理的かもしれない。イスラエルのように、国民の大半に早期接種をして、製薬会社にデータを供して、結果的に大変な副作用があったら、取り返しが付かない。待つことも作戦としてはあり得る。COVID-19は、致死率が異様に高い疾患でもないので、あえて作為リスクを冒さない選択肢もあり得た。
しかし、現状の自粛論では、あまりに社会・経済・文化・生活に与える打撃が大きく、ただジリ貧を待つことはできない。だから、別の意味で、精神論が求められていた。「ゲームチェンジャー」祈願である。
精神論なので、実際に効こうと効くまいと、どうでもよい。ただ、何でもよいから活動再開の決断への「パスポート」のための「免罪符」が重要である(注3)。しかし、開催期間がすでに決まっている東京五輪の前には「免罪符」を配給する、という自縄自縛に陥った。
注3 日本以上に膨大な感染者を出しているアメリカは、ワクチン接種によって経済再開を目指している。
あるべき「免罪符」は、兵站の合理性を考えて、もっと簡単に入手して迅速に悉皆配布できるモノ(注4)を選択しなければならなかった。しかし、そのようなモノがなければ、そもそも「ゲームチェンジャー」は存在しない。長期持久戦ならば、体力温存が大事である。
注4 マスク、イソジン、アルコールとか、いろいろあり得た。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
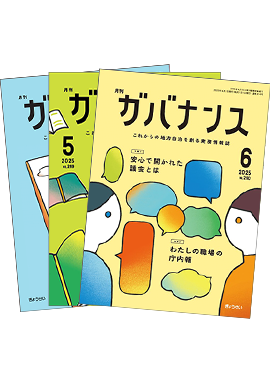
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫