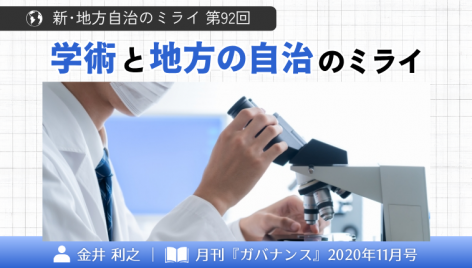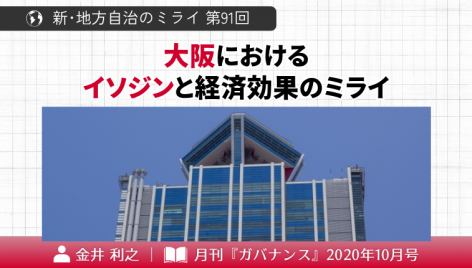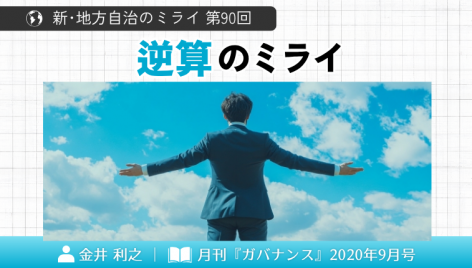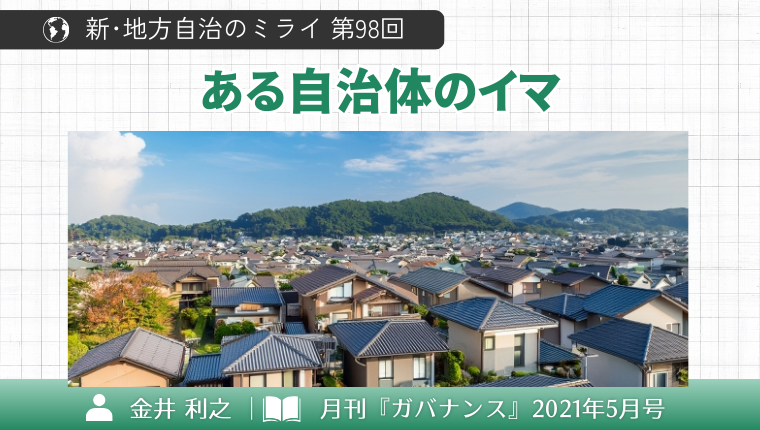
新・地方自治のミライ
ある自治体のイマ|新・地方自治のミライ 第98回
地方自治
2025.09.08

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年5月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
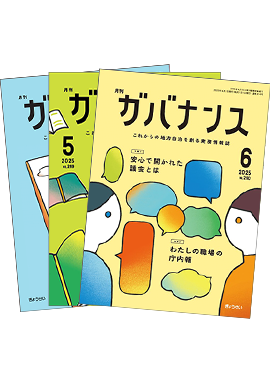
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年5月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに
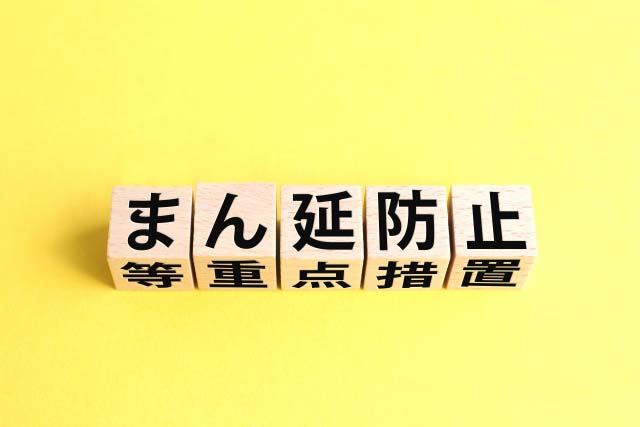
COVID-19で揺れたコロナ2(2020)年度がようやく終了した。3月21日には第2次緊急事態宣言も明けた。もっとも、東京都庁は、あえて宣言終了間際の3月18日になって、営業時間短縮命令を出し、29日には過料手続に入った。また、大阪府庁は4月5日からの「まん延防止等重点措置」(いわゆる「マンボウ」)と飲食店見回りに踏み切った。さらに、4月12日から東京都・京都府・沖縄県にも「マンボウ」の適用が拡大した。このように、依然として、自治体為政者はコロナ対策に権力を揮っている。
さて、表面的なコロナ対策禍のなかで、自治体の構造的病理は粛々と進行している。それは、人口減少・少子化・高齢化であり、男女・所得格差社会である。今回は、この問題を採り上げてみよう。
ある自治体のイマ
ここで事例として採り上げるのは、ある基礎的自治体である。仮に、「D体」と呼んでおこう(注1)。D体は、大都市圏郊外の自治体である。もともとは農村的な側面もあり、農産品でも全国シェアの高い比率を占める特産品もある。しかし、大都市中心駅まで鉄道が直結しており、速い電車を使えば1時間も掛からずに到着するので、通勤圏でもある。また、郊外型工場も存在し、そこでの就業も可能である。このため、近年、全国的には例外的に人口が増加している。企業城下町としてみることもできる。
注1 市区町村のどれかを採用すると、それだけ匿名性が低くなるからである。
それゆえに、財政事情も悪くはない。もちろん、急速な人口増加は、元々の畦道が舗装化されたような道路しかないために、インフラ整備を必要とする。駅前広場の整備などの区画整理事業も重要である。また、目に見えるところでは、小中学校の増設が不可避である。とはいえ、全体としては景気のよい話である。ふるさと納税の寄付額も順調である。
もっとも、商業や医療などは区域内に充分にあるとは言えない。しかし、車で10分程度の近隣自治体に、巨大ショッピングセンターや巨大病院があり、それなりに住民の用は果たせている。
ある自治体の首長

以上のような小康状況は、日本経済全体のなかでの、単なる僥倖であり、必ずしも、歴代D体の施政が適切であったからというわけではなさそうである。もちろん、周辺の丘陵斜面地などでは空き家なども散在しているので、D地域に課題がないわけではない。しかし、潤沢な財政状況を背景に、首長以下は、住民のいろいろな要望や陳情に、カネで応じることができている。
例えば、空き家の改修や維持管理に財源投入を行う。また、コロナ対策と称して、上乗せ的なクーポン券を発行する。もっとも、D地域内では、めぼしい飲食店や商店もないので、D地域外でも利用できるようにせざるを得ないのが、惜しいところである。また、商業施設の誘致のために、駅前一等地の整備も積極的に行う。もっとも、前記の通り、D地域外の大規模商圏に組み込まれているため、必ずしも出店状況は芳しくはなく、整備をしても区画・店舗は空いてしまう。そこで、対策として、D体自体が施設を穴埋めすることで、事業の「失敗」を糊塗する。
このような大盤振る舞いは、自然にできることではないので、首長の「手腕」と言えば、手腕である。すなわち、一般的には、財務省や自治体財政部局が予算管理をしているため、こうした大盤振る舞いをしないように精査している。特に、2000年代の地方財政ショックを知る世代からすれば当然である。また、人口増加も一時的であるし、日本経済の先行きが厳しいことも見えているからである。さらに言えば、いくら財源が潤沢であったとしても、理由の立たない財政支出はよくない。
そこで、首長は、財政部局を意のままに操ろうとして、ミニ官邸よろしく、側近を周りに配置する。こうして、首長の言うとおりに財政出動ができるような人事を行うことが、人事権を持っている首長の方策である。住民からすれば、首長に陳情すれば予算が付きやすいので、首長とコネのある住民からの「支持」は厚くなる構図もある。
ある自治体の議会
議会の活動は沈滞している。前記のような、妥当性に懸念のある案件に関しては、議会でも様々な議論や疑義が巻き起こるが、最終的には議会は明確な対処をすることが容易ではない。理屈上は、減額補正をするのが筋であるが、政治権力の弱さからそこまで踏み込めない。せいぜい、意見書の提出や、付帯決議である。もっとも、意見書を提出しても、首長は回答もしないのが、実際の権力関係である。
首長専横には、本来、議会の監視牽制機能が期待される。D体は、実は、同規模人口の他の自治体に比べて、議員数は多くない。というのは、人口が急増してきたからである。議員定数は、時間的な経緯の積み重ね(経路依存)的な側面が強く、かつての小規模団体時代の議員定数を前提に、近年の議員不信を反映して、むしろ定数削減を行っているからである。議員定数が少なくなったからといって、少数精鋭になるとは限らない。それどころか、無投票や定員割れを起こしている。議会のなり手不足は、地方圏の小規模町村だけの問題ではない。
ある自治体の住民

農村部の自治体らしく、行政区(地区または自治会・町内会)の存在が大きい。議員になるためにも、行政区での様々な役職を経た上で、行政区推薦により後継者が絞られてくる。地区推薦的な議員の全員が中高年の男性である。しかも、日常活動の蓄積を必要とするので、男性「新人」議員、すなわち、当選1期目ですでに、多くは年金生活の高齢世代である。議員を長く続ける気力・体力もないし、首長にとって代わろうという、若く野心ある政治家も輩出されない。
また、これと同じ理由から、D体では、女性議員は、いわゆる二つの「組織政党」系の議員を除いて、存在しない。もっと言えば、この二つの組織政党でさえ体力があまりないので、折角、定員割れにもかかわらず、追加的に議員候補を立てられない状況である。
人口増加は、農村部の自治体に勤め人世帯が外部から流入しているから起きている。こうした、いわゆる新住民にとって、行政区を中心とする地域活動は、「余計な負担」以外の何物でもないので、自治体施政へ関心を持つと面倒である。現状では、旧住民が仕切る行政区を通じてしか、施政への発言ルートがない。旧住民のフィルターを通ると、新住民の要望は伝わらない。商業も医療もD地域外に期待する新住民としては、居住地のD体の施政に期待することは、ほとんどない。
ある自治体のミライ
こうして、首長専横と沈滞議会という「成人病」が粛々と進行する。マスコミの関心もほとんど存在しない。そもそも、マスコミが関心を示すのは、いつもは「平穏」な自治体が、何か揉めたときであるので、マスコミの調査報道が先に問題を掘り起こすことは少ない。大きな事件が登場しない限り、「メタボ」的な首長の「我が世の春」が続く。
これを可能にしているのが、住民の無関心である。とはいえ、小春日和である以上、ある程度の無関心は必然である。また、施政に関心のある一部住民の陳情・要望に対しては、首長による恣意的な財政出動で慰撫が為される。
政治主導の悪弊に一定の牽制を行うのが、中立性をもった官僚制の役割なのであるが、人事権を掌握する首長は、諌言を厭わない職員を、いくらでも左遷できる。
要するに、個々の住民への細かい現世利益の配分と、反対する行政職員への見せしめ人事という、ミニ官邸化が進行している。自治体は、ミイラになる前に、「発作」や「梗塞」の危険を増やしながら、老化していくのである。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
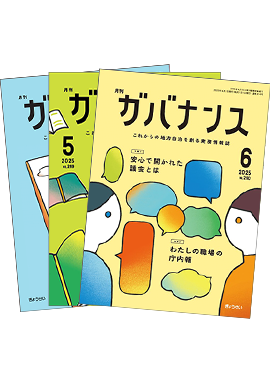
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫