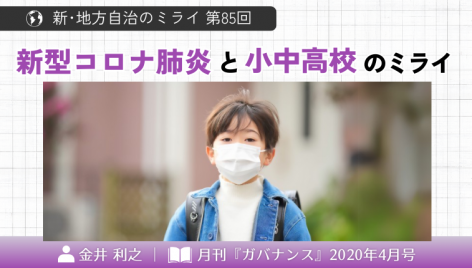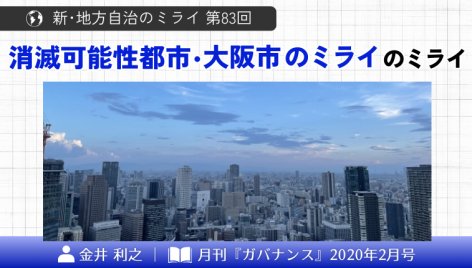新・地方自治のミライ
第三波を迎えた「大阪都構想」のミライ|新・地方自治のミライ 第93回
地方自治
2025.07.28

出典書籍:『月刊ガバナンス』2020年12月号
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
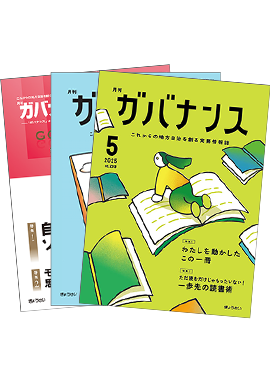
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年12月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

2020年11月1日に、いわゆる「大阪都構想」、すなわち、大阪市廃止と4特別区設置およびそれに伴う大阪市の事務・財源・人員の一定部分の大阪府への吸い上げ、を問う市民投票が行われた。5年前の2015年5月の橋下徹・大阪市長時代に行われた市民投票に続き、2回目の試みであった。結果は、前回に引き続き、僅差で否決された。2回の市民投票の賛否分布は、ほぼ変わらず、5年たっても民意が二分される状況は継続していたと言えよう。
投票結果を受容することの難しさ
民主制の一つの約束事は、選挙や住民投票の結果を、「敗者」側が受容すること、である。これは当たり前のようで簡単なことではない。アメリカ大統領選挙では、「敗者」であるトランプ大統領が、依然として「敗北」声明を出さず、法廷闘争を続けている。結局、各国首脳からの「祝電」という「承認」に支えられて、バイデン氏が次期大統領として認められるに至っている。国家の独立に外国の承認が必要な状況に似ている。この点、前回の橋下市長も、今回の吉村洋文・大阪府知事も松井一郎・大阪市長も、市民投票の結果を受け入れて、「敗北」を認めている。
しかし、「大阪都構想」は前回否決されたにもかかわらず、そこで最終決着がつかず、「敗者」側が「敗者復活戦」を続けてきたことも事実である。戦いに勝つ秘訣は簡単であり、〈勝つまで続ける〉ことであり、〈勝ったら戦いを止める〉ことである。「大阪都構想」に勝つためには、市民投票で負けても、勝つまで何回も続けることが、必勝の極意である。市民投票で勝ったら、二度と市民投票をしない。実際、大都市地域特別区設置法に基づく市民投票は、拘束型住民投票であり、一度でも市民投票で多数を得られれば、大阪市は永久に廃止され、大阪市復活に向けた再挑戦はあり得ない仕組なのである。その意味で、二度あることは三度ある、かもしれない。
投票結果という「錦の御旗」

民主制のもう一つの約束事は、選挙や住民投票の結果を、「勝者」側が「勝てば官軍」のごとく、「錦の御旗」にしないこと、である。「勝者」は、「敗者」の側も含めて、民衆や社会全体のために、その後の施政を進めなければならない。投票結果が僅差であれば、社会の分断状態や投票戦のしこりを癒やさなければならない。投票結果が大差であれば少数派に対して、多数派専制にならないように、より繊細な配慮が必要である。「勝者総取り」ならば、「敗者」の側は投票結果を受容する動機がそもそも存在しないので、「勝者」の謙抑と、「敗者」の受容とは、表裏一体である。
2回とも否決側が市民投票での「勝者」であるとしても、半数近くは賛成側であった以上、市民投票で否決されたとしても、「勝者」が「都構想」論議を打ち切ることは適切ではないとも言える。否決後も「敗者」側の「維新の会」が、しつこく、「大阪都構想」を訴えることも理解できよう。もっとも、市民投票の場合には、「敗者」が知事・市長職を握り続けており、「勝者」は多数派専制をできない。
実際には、大阪府民・市民は、いずれも市民投票後に、2015年11月の府市合わせ選挙でも、2019年4月のスワッピング選挙でも、「大阪都構想」を掲げる「維新の会」の松井・吉村両氏を当選させてきた。その意味では、「直近の民意」では「勝者」である。そのため、「大阪都構想」はミイラのように甦ってきた。市民投票での「敗者」は、同時に、首長選挙での「勝者」である。首長選挙の「勝者」が、「直近の民意」を「錦の御旗」にして、「大阪都構想」を続けてきた。「維新の会」は、自分たちが勝利した投票結果を多数派専制に利用してきた。
バーチャル「大阪都構想」の継続

市民投票運動の過程では、「維新の会」が大阪の知事・市長職を握っているので、実質的な「ONE大阪」が実現できている。それゆえ、「大阪都構想」という制度改革の必要はないという反対論があった。これに対して、推進派は、府市首長を「維新の会」がとれなければ、大阪府市衝突(いわゆる「二重行政」)は制度的に起こり得るのであり、こうした弊害を制度改革で根元から絶つことができるという。
「大阪都構想」の本旨は、仮に大阪府民と大阪市民の民意が乖離したとしても、民意に基づく声を上げる権利を大阪市民から剥奪し、大阪府政が常に独断できる制度を作ることである。市民から声を奪えば、大阪府市間の対立は制度上あり得ない。
もっとも、この理屈から言えば、国政と大阪府政の対立可能性を制度的になくすためには、大阪府を廃止するしかない。大阪府が制度的に存続する以上、大阪府政を握る「維新の会」は、国政与党の補完勢力である「癒党」にならざるを得ないし、実際、そのように行動している。バーチャル「大阪直轄特区」である。
現行制度のもと、大阪府市衝突を避けるには、「維新の会」が、政治的統合主体として府市の政権を担い続ければよい。両者が密接であれば府市統合は政治的に進み得るし、実際、進めてきた。「維新の会」が府市政権を担い続けることで、バーチャル「大阪都構想」が進められる。もっと言えば、「維新の会」の府市掌握が、制度改革としての「大阪都構想」を不要のものとした。
そして、仮に、大阪市民が大阪府政への大阪市政の上納を拒否し、府市衝突が望ましいと考えれば、大阪市政を選挙で変え得る。その意味では、バーチャル「大阪都構想」の方が、より市民の民意に応答的であり、制度的な大阪市廃止よりは望ましい。「維新の会」も、それを逆手にとって、府市政権を掌握し続ける理由を動員できる。
政令指定都市・大阪市の事務・権限を大阪府に吸い上げ、関連する人員・財源を移転すれば、大阪市政の持つ行政資源を大阪府政が牛耳ることができる。そのうえで、大阪市民へのサービスを削減し、「ONE大阪」全体や広域を睨んだ開発政策(例えば、万博やカジノ、インフラ投資、個人情報利活用産業など)に流用できる。府県事務を市町村に移管するのが事務処理特例制度であるが、その逆のベクトルである。市から府に事務の委託や府庁内に機関の共同設置をしてもよいし(規約には両議会議決が必要)、府市間の一部事務組合(但し、意思決定権を制度的に府政が握ることは難しい)でもよい。実際、吉村府知事は、市民投票で否決されたのちに、事務・権限を吸い上げる「広域行政一元化条例」を提唱している(注1)。〈勝つまで続ける〉ようである。
注1 日本経済新聞電子版2020年11月6日19時31分配信。
おわりに
バーチャル「大阪都構想」は、制度改革「大阪都構想」と、広域開発行政を府政が握る点では同じだが、特別区レベルの住民自治がない点で、そして大阪市という帰属先(アイデンティティ)の象徴が残る点で、大きな違いがある。大阪市民は、特別区での自治の実よりも、名としての大阪市を選んだと言える。
もちろん、松井市長は〈勝つまで続ける〉主義に立って、大阪市の行政区の統合と事務・権限の強化を図る「総合区」条例を目指すという(注2)。しかし、市民投票運動でも明言されていたように、区長・区議会を住民が直接公選できる完全な基礎的自治体である特別区と、単なる大阪市の内部機関である総合区とでは、本質的に異なる。
注2 毎日新聞電子版2020年11年11日21時29分配信。
市民投票での制度改革「大阪都構想」の否決は、バーチャル「大阪都構想」で広域開発行政の府への一元化は進めるが、住民に身近な区への分権は実現せず、「維新の会」に永続的な府市政権掌握の動機を与える。市中蔓延率31%(注3)の「大阪都構想」の根治は難しく、「ポスト大阪都構想」の「新しい日常」は到来しない。大阪市民はミイラのような「大阪都構想」第三波を甘受して、「ウィズ大阪都構想」で蟄居逼塞(ステイ・ホーム)していくしかない。
注3 投票率62.35%で賛成票が49.37%であるため、絶対得票率は30.78%である。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
★「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
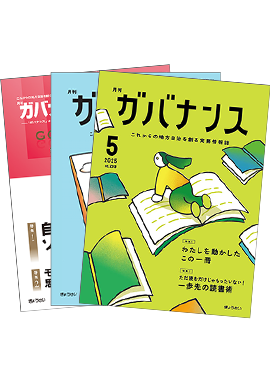
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫