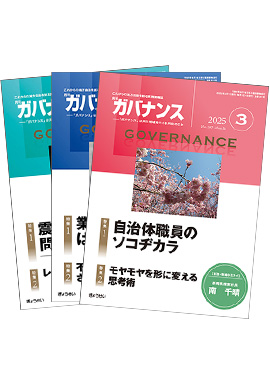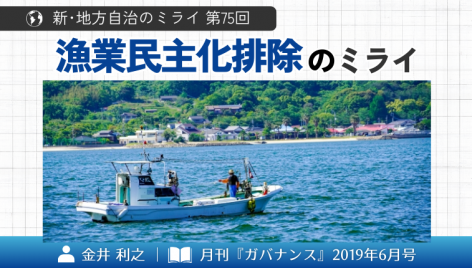新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第82回 行政情報の外部委託のミライ
地方自治
2025.05.02
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年1月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに
納税などに関する大量の個人情報や秘密情報を含む神奈川県庁の行政文書が蓄積されたハード・ディスク・ドライブ(HDD)が、ネットオークションを通じて転売され、実質的に、県庁外に行政情報が「流出」したことが明らかになった(注1)。県庁のサーバーから取り外されたHDDのデータ消去が不充分なまま、簡単に復元可能な状態で、中古品として出回っていたのである。
注1 朝日新聞デジタル版2019年12月6日05時00分配信。
富士通リースは、2019年春に神奈川県庁にリースしているサーバーから、交換時期を迎えていたHDDを取り外し、契約に基づいて、HDDの処分をブロードリンク社に委託した。ブロードリンク社員が、HDDを持ち出して、ネットオークションサイトで転売したものである。購入者が、HDDの中身を確認したところ、神奈川県庁の公文書と思われるデータを発見し、事件が発覚したものである。
神奈川県庁によると、「流出」した情報量は54TBの可能性があるとのことである。フクシマ苛酷事故以来、久しぶりに「テラ」という単位が一般社会に流布した。世界最大級の情報「流出」事件とも言われる。もっとも、サイバー攻撃などによってデータ流出した21世紀的事件ではなく、HDDというモノを盗んで、金銭動機で転売した極めて20世紀的事件とも言える。今回はこの問題について考えてみたい。
外部委託のヤミ

行政機関の根幹に関わる情報処理は、電子データ化されており、しばしば、外部民間事業者に委託されている。行政情報に、外部民間事業者が触れられる状態である。「法的」には、民間事業者に適切に情報を処理・保秘するように契約で義務を課せば、問題はないはずである。
仮に、不適切な情報処理をすれば、契約違反や不法行為であるから、債務不履行や損害賠償などの「法的」制裁を課すことができる。もちろん、情報「流出」などが起こってから、事後的に制裁を加えても、漏洩情報を回収できなければ、無意味である。しかし、このような事件があれば、民間事業者の信用はガタ落ちであり、企業経営にも深刻なダメージとなる(注2)。それゆえ、「法的」制裁が抑止力となって、民間事業者は適切に対応することが、一般的には期待できる。
注2 下請業者のブロードリンク社は、12月9日に、榊彰一社長が再発防止策の完了後、辞任する意向を示した。また、同社は営業活動を1か月間停止する。産経新聞デジタル版2019年12月9日15時40分配信。
これは、あくまで蓋然性の問題である。「潰れても構わない」民間事業者であれば、「法的」制裁は全く役に立たない。とはいえ、実際、民間事業者に情報処理を外部委託している行政機関は多く、必ずしも、その全てで事件が発覚していないから、「法的」な契約が一定程度は機能していよう。
しかし、むしろ、今回のように入手した人物が公益通報せずに、発覚しないまま「ヤミからヤミへ」と、個人情報等の行政情報を転売・転写しているだけかもしれない。もちろん、気付かない程度ならば「問題はない」のかもしれない。しかし、流出源が分からないまま、売られたデータに人々は被曝して、対処不能になっているのかもしれない。
人間のヤミ
民間事業者に対しては、行政は契約によって「法的」に適正処理を担保することはできるかもしれない。しかし、実際に情報データや、情報データが登載されているHDDなどのモノを処理するのは、結局は個々の人間である。個人をどのように監督するのかは、民間事業者の経営である。民間事業者は、個人認証をしなければ入室できないところでモノを保管し、出入の際の手荷物検査などをして、物理的な対策を執っている。とはいえ、今回の事件では、単純にHDDを持ち出せたので、全く機能していなかった。
組織は個人を外的に統制しきれないので、個人を内面的に規律付けようとする。これも「法的」には可能である。組織と個人は雇用契約であり、不適切な行為をすれば、解雇などの制裁がある。従って、通常は企業で働き続けたい従業員は、仮に物理的な対策がなくても、解雇などの制裁を恐れて思い留まることが期待されるわけである。
このような個人的規律付けは、非正規労働者には弱くしか働かない。行政が民間事業者に外部委託するという傾向は、民間企業が非正規労働者によってコスト削減できることを前提にしていることが多いので、なおさら危険は高まる。真面目に働いても、雇用期間は有期に限られ、いつでも雇い止めされるならば、解雇は制裁としては機能しにくい。また、非正規労働者は賃金が安価であることが多いので、解雇によって失うものは相対的に少なく、転売などで得られる利益は相対的に大きい。その意味で、規律付けが必要ならば、正規化が必要である。それでも、今回の事件は、中途採用とはいえ正規従業員であったので、正規ならば安全というわけでもない。
民間事業者は信用できない?

結局のところ、いくら契約で「法的」に義務を課しても、全く意味がないということである。実際、防衛省などでは、業者に廃棄に出す前に、行政内部でHDD等をドライバーで穴を開けるなど、物理的に破壊してから、廃棄を委託するなどの対処をしているという(注3)。さすが、南スーダンPKO日報を「消去」し切れずに「苦労」しただけのことはある。要するに、民間事業者は信用できないので、行政内部で処理するしかない、ということである。
注3 時事ドットコムニュース2019年12月6日21時33分配信。
もっとも、民間事業者と従業員・非正規労働者の関係と同様に、行政の内部で処理するとしても、行政職員が適正に処理するとは限らない。保管庫に立入できる人間を制限するとか、持ち物検査をするとか、様々な物理的対処は有り得るだろうが、必ずしも十全になるとはいえない。となると、職員個人の内面的規律付けが必要であるが、結局は、懲戒免職や刑事罰の可能性による制裁に過ぎない。民間事業者やその従業員・非正規労働者が信用できないのは、防衛省の考える通りであるが、そのことは、行政機関や行政職員が信用できることを意味しない。問題が「盥回し」になるだけである。
さらに言えば、民間委託であると、HDDが遠方にあって、現実的には行政職員が廃棄・消去する作業が困難ということも多い。
壁に耳あり、障子に目あり

このように考えると、行政の持つ情報は、ある程度は漏れるものである、という諦観が必要なのかもしれない。情報流出を前提とするならば、行政に情報をできるだけ保有させないことしか、対策は有り得ない。もっとも、行政が必要な情報を持たなければ、適切な業務遂行ができなくなるから、人々や事業者は行政に情報を提供せざるを得ないし、行政も情報収集をするしかない。結局、行政の持つ情報をゼロにできない以上、やはり行政からの情報流出は避けがたい。
とはいえ、情報流出を減らす点からは、必要もなく行政が情報収集を進めることを避けることは必要であろう。たとえば、個人番号カードを人々に持たせようとして、税金を投入してまで、買い物にポイントを付与するなど、取引情報を収集することは、誠に危険である。個人番号が行政運営(税・社会保障・災害対策)に必要な情報だとしても、それはすでに強制的に国民等に付番されている。個人番号カードがなくても、個人番号を含む本人確認は可能になっている。それが面倒だと思うのであれば、人々は個人番号カードを自発的に入手するだろう。
情報流出を前提にすれば、行政からの個人情報の流出で、個人がどの程度の不利益を被るかを、アセスメントすることが必要になる。攻撃対象になっている個人であれば、攻撃者が入手すれば深刻である。また、一人の情報では大した不利益はなくても、ビッグデータになれば、加速度的に不利益が大きくなろう。情報流出の被害に対して、行政は住民などにどのように賠いを行うのか、また、事後的な対策では償えないならばどのように対処するのか、行政に課された課題であろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。