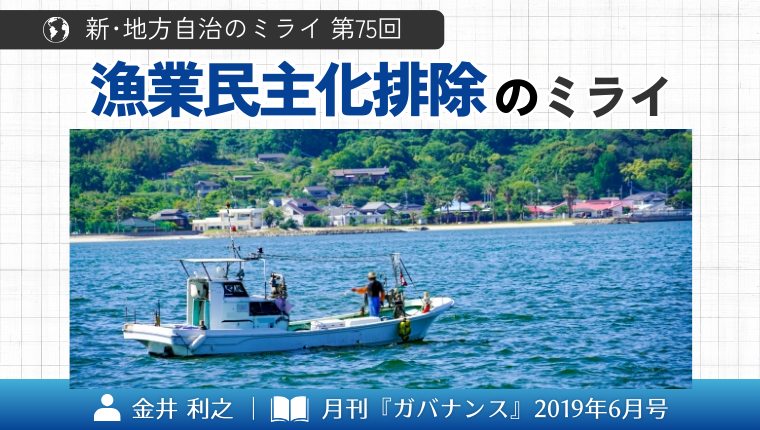
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第75回 漁業民主化排除のミライ
地方自治
2025.02.12
本記事は、月刊『ガバナンス』2019年6月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

2018年12月8日に「70年ぶり」と称する漁業法改正が行われた。1949年制定の漁業法では、「漁場の総合的・高度利用」と「漁業民主化」の二つが目的とされてきた。これに対して、2018年6月に政府「農林水産業・地域の活力創造本部」が「水産政策改革」を決定した。資源管理、養殖・沿岸漁業、遠洋・沖合漁業、水産物流通・加工の4点について、規制改革のために漁業法改正をするとされた(注1)。
注1 WWFジャパン「【解説】70年ぶりの「漁業法改正」をどう見るか」
https://www.wwf.or.jp/activities/opinion/3814.html
水産政策・漁業法は自治体の一般住民には縁遠いテーマであるとも言えるが、漁業には多面的機能があって地域住民・社会に無縁ではない。しかし、水道・カジノ・外国人材受入れなどに隠れて、あまり注目を集めなかったかもしれない。そこで、遅ればせながら、今回は漁業法改正問題を検討してみよう。
漁業法改正の要旨

農林水産省の法律案概要の資料に拠れば、改正の趣旨は以下の通りである。水産資源の減少などにより生産量や漁業者数は長期的に減少傾向にあるが、日本周辺には広大な漁場が広がっており漁業の潜在力は大きい。そこで、適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、資源管理措置、漁業許可・免許制度などの漁業生産に関して基本的に一体的に見直すという。
具体的には5本柱である。第1に、新たな資源管理システムの構築である。資源評価に基づく漁業可能量(TAC)による管理を、個別の漁獲割当(IQ:Individual Quota)によって行う。農林水産大臣または知事が、漁獲実績などを勘案して、船舶などごとにIQを設定する。加えて、IQを一定条件の下で他者に移転できる。
第2に、生産性の向上に資する漁業許可制度の導入である。随時の新規許可を推進する。
第3に、養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度への見直しである。知事は海面が最大限に利用されるように、漁業者や漁業参入希望事業者などの意見を聴いて、海区漁場計画を策定する。既存の漁業権者が漁場を適切・有効に活用している場合には、その者に継続免許する。しかし、既存漁業権者がいない場合などには、漁業生産の増大、漁業所得の向上、就業機会の確保など、地域水産業の発展に最も寄与する者に免許する。つまり、地域社会に配慮した既存の優先順位を廃止する。漁業権者には、漁場の適切・有効に活用する責務を課し、漁場活用に関する報告を義務付ける。都道府県の指定を受けた漁協などが、沿岸漁場の保全活動を実施する。
第4に、漁業・漁村の活性化と多面的機能を目指す。
第5は「その他」である。海区漁業調整委員会については、漁業者代表を中心とする行政委員会の性質を維持しつつ、現行の漁業者委員の公選制を廃止し、知事が議会の同意を得て任命する仕組(任命制)にする。併せて、「漁業民主化」という目的規定を削除する。
公選制から任命制への「民主化削除」
戦後日本には行政委員会制度が導入され、自治体の場合には執行機関多元主義と呼ばれる。行政委員会が公選首長から独立性を確保するには、首長の人事権に服してはならないと設計するのは自然であって、行政委員を公選制にするのは一つの見識だろう。こうして、教育委員会、農業委員会、海区漁業調整委員会などでは、公選制が導入されてきた。その意味で、戦後漁業法は「漁業民主化」を謳っていた。ただし、この「民主化」とは、多くの事業者に対する業界ボス支配の排除という意味であって、広く一般住民による公選制のイメージではない。むしろ、業界民主化と呼べるものであろう。
しかし、戦後逆コースのなかで教育委員の公選制が廃止された(注2)。任命制の行政委員会は、一概に「反民主的」かというと、そうとは限らない。なぜならば、首長は一般住民による公選制のもとにあるので、首長を通じた「民主化」と言える。むしろ、既存の業界関係者による独立した決定が一般住民から乖離しているのであれば、業界民主化の方が「反民主的」という見解も有り得るからである。
注2 1951年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)による。農業委員の公選制の廃止は、2015年農業委員会法改正による。
とはいえ、行政委員会といえども、予算・条例を握る首長・議会から完全に独立しているわけではないので、業界関係者・ステークホルダーの代表を保証する業界民主化が、一般住民の利益に係る民主性を否定しているわけではない。むしろ、首長・議会が「多数派専制」の虞を持つとすれば、利害関係者の発言を保証する公選制委員会は「民主的」と言えよう。こうして、政府は公選制の廃止の漁業法改正を「反民主的」であると自認して、今回の改正漁業法では「漁業民主化」という目的を削除したのである。
規制改革という産業統制

既存の漁業権者が免許を継続し、漁業権者の公選代表からなる海区漁業調整委員会を介して、業界調整をするのが、戦後漁業法の仕組である。改正漁業法は、外部からの大規模事業者などの新規参入に道を開くことで、強い漁業を作ろうというものである。一見すると、既得権者の自主規制を廃止して、市場開放を図る規制緩和・自由化・市場化を目指すようにも思われるが、改正法の内容はそうではない。
むしろ、知事に権限を集中し、知事の下で漁業権の免許を行政的・政策的に配分するという、官僚制的規制の強化を目指したものである。知事が海区漁場計画という計画を策定し、知事が免許を与え、大臣・知事が最善と思う事業者にIQを配給する。典型的な計画経済である。これは、戦間期から戦後にまでみられた「産業統制」である。
産業統制や計画経済が、一概に悪いということはできない。既存の漁業権の配分は、「合理」的決定に拠らず、従前からの継続という「伝統」的配分であったからである。しかし、産業統制・計画経済が「合理」的にできるかには、大いなる疑念が呈されているのも事実である。実際、日本では資源管理の成功実績がないにもかかわらず、諸外国の風評を元に一気に改革をしようとしている。当然、「合理」的な配分の名目で、実体は非科学的で恣意的な配分にもなり得る。特に、行政当局者から見て「評判」のよい、一見すると威勢と活きの良さそうな元気で能力のありそうな、しかし、実態としては政官への陳情と忖度に長けた、政商的事業者に優先的に配分されることも、充分には有り得る。
それゆえに、官僚制的な決定を行う際には、首長・議会という上からの民主的リーダーシップに加えて、関係者の参加と熟議と合意形成という下からの民主主義も必要である。公選制委員会は、まさにそのための仕組であった。任命制委員会は、審議会(附属機関)と本質的に異ならない。そのような舞台で充分な合意形成が可能かどうかは、疑問もあろう。納得ある配分と納得なき配分は、意味が違うのである(注3)。
注3 竹田有里「70年ぶりの漁業法改正、崖っぷち水産業はどう変わる?」WEDGE Infinitity、2018年12月11日付配信。
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/14738?layout=b
おわりに
改正漁業法は、簡単に言えば、従前からの沈滞した漁業者から免許を取り上げ、漁業生産・所得を拡大できる事業者に免許を付与し、漁獲実績に応じて大規模漁業者に漁獲量を割当て、さらに、割当移転によってそれを集積できるようにするものである。つまり、政策的な大規模事業者による大規模化・カルテル化である。産業統制的な計画経済の論理である。
しかし、漁業・漁村は地域社会でもあり、多面的な機能を持つ。また、小規模伝統漁業の保護は国連FAOなどでも重要な行動規範となっている。しかし、こうした配慮は改正漁業法には欠けている。その意味で、改正漁業法は様々な悪影響を地域社会や浜・浦にもたらす虞もあろう。漁業活性化と資源管理を目的としつつも、結果的には、外来漁業者によるハゲタカ的な乱獲漁業のミライになるかもしれない。それゆえ、知事・海区漁業調整委員会の政策判断の是非が問われてくる。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。






















