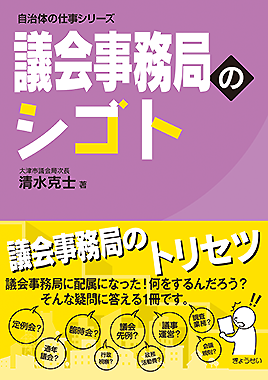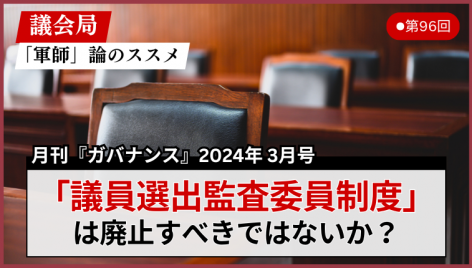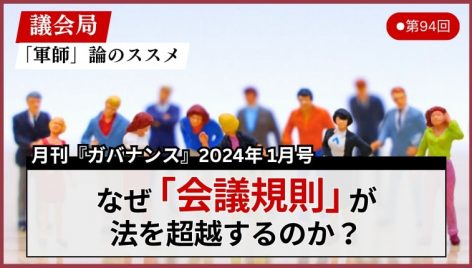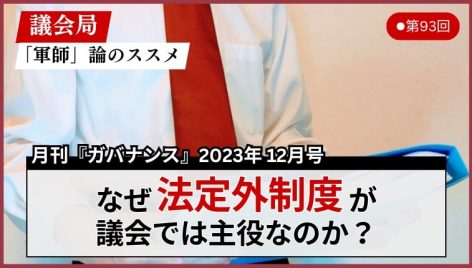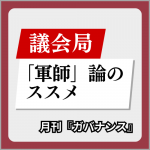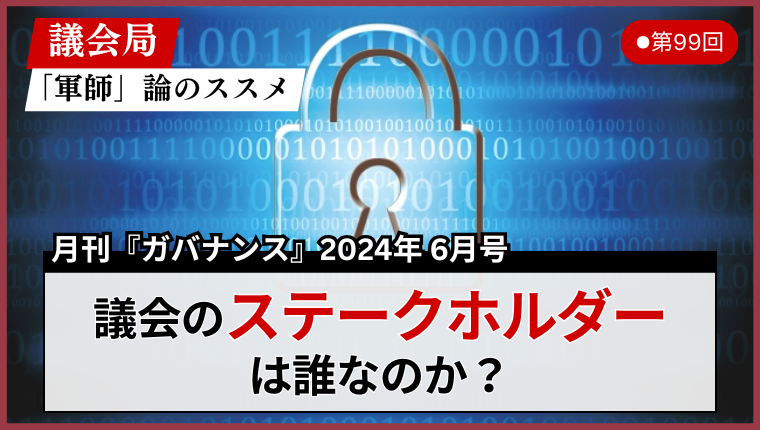
議会局「軍師」論のススメ
議会局「軍師」論のススメ 第99回 議会のステークホルダーは誰なのか?
地方自治
2025.02.13
本記事は、月刊『ガバナンス』2024年6月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
今号では、政務活動費(以下「政活費」、注1)についての新聞記事(注2)に関連して、議会の課題への議会(事務)局職員の関与のあり方について考えてみたい。
注1 地方自治法100条に基づくもので、国における「政策活動費」とは異なる。
注2 京都新聞「調査報道 政治とカネ・8議会 領収書ネット公開せず」(2024年4月16日)。
■局職員のひとごと意識の罪
記事は、県内の議会における政活費に係る領収書のネット公開の有無を調査し、14議会中、県を含む8議会がネット非公開である事実を伝えた調査報道であった。
興味深いのは非公開理由で、「公文書公開請求により公開しているから」、「現在の公開方法で不都合はないから」、「議会の規定にないから」、「公開すべきとの議論がなかったから」など様々であった。
だが、既存の制度があろうと、新制度によって公開レベルが飛躍的に向上するのであれば、導入に向けて努力すべきではないか。来庁を前提とした制度とウェブ上で目的を達せられる制度では、公開レベルの差は明白であり、そもそも既存制度の不都合の存否は市民が決めることであろう。
また、法規定にない制度であろうと、独自に規定すれば良いだけのことであり、先行事例が多い領収書のネット公開であれば、法制執務上の難易度も高くはない。
さらに本稿で指摘する本質としては、政活費を使う立場からは面倒は避けたいとの心理は当然であり、むしろ議員よりも局職員から、ネット公開導入を提案すべきではないだろうか。それは局職員も議員と同じく、市民福祉増進のために仕事をする存在であり、市民視点からは傍観は許されないと思うからだ。
■局職員はステークホルダーたれ
古い話で恐縮だが、富山市議会での政活費の不適切支出が報じられていた頃、大津市議会における局職員のスタンスについて、富山のチューリップテレビの番組公開収録(注3)で話す機会があった。
注3 チューリップテレビ「地方議会の改革を問うⅡ~政治とカネ 不正の深層~」(2017年8月5日、ボルファートとやま)。
同席した鋪田(しきだ)博紀・富山市議会副議長(当時)からは、「大津市議会と富山市議会では、事務局の果たしている役割が根本的に違う」とのコメントがあり、富山市議会では局職員が議会に発意することなどない現状を認めていた。
最後のコメントでは「政務活動費で大津視察」とエールを送ってくれた松原耕二・TBSテレビキャスターからも、「議員と局職員が切磋琢磨して何が変わったのか?」と質問を受けた。確かに任命職が公選職と対等に議論するということは、まだまだ「普通」ではないようである。
だが、北川正恭・早稲田大学名誉教授は、議会改革を進めるには、議員と局職員とのフラットな関係性を前提に、政活費の適正化においても局職員の主体的な関与が必要との脈絡で、「局職員も議員と対等に議論できる議会のステークホルダーであるべき」との見解を示されていた。
■議会改革推進のための課題
まさに局職員の主体的関与が、議会における政活費適正化の必要条件であり、ひとごと意識で臨むことは許されないということだろう。
そして議会改革推進にあたっても、議会における局職員の主体性こそが大きな課題である。
このことについては、筆者も委員として参画している政策サイクル推進地方議会フォーラム「議会(事務)局分科会」(日本生産性本部主宰)の提言書(注4)でも、「議会(事務)局職員の『補佐の射程』」として問題提起している。課題の詳細については、是非そちらでご覧いただきたい。
注4 全文は日本生産性本部地方議会改革プロジェクト
https://www.jpc-net.jp/consulting/mc/pi/local-government/parliament.html 参照。
第100回 「能動提案型事務局」に求められるものは何か? は2025年2月27日(木)公開予定です。
Profile
早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員・前大津市議会局長
清水 克士 しみず・かつし
1963年生まれ。同志社大学法学部卒業後、85年大津市役所入庁。企業局総務課総務係長、産業政策課副参事、議会総務課長、次長、局長などを歴任し、2023年3月に定年退職。著書に『議会事務局のシゴト』(ぎょうせい)。