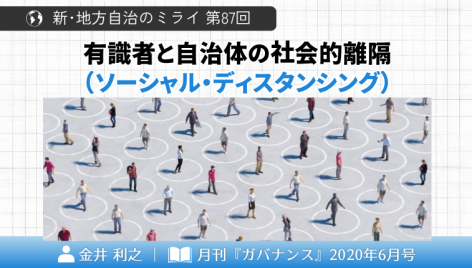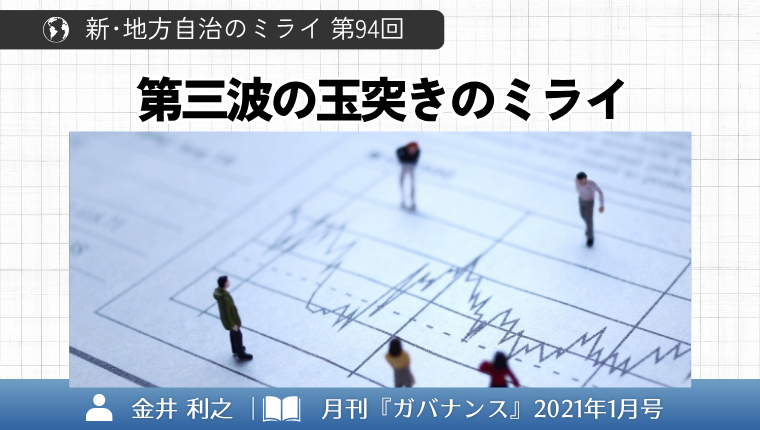
新・地方自治のミライ
第三波の玉突きのミライ|新・地方自治のミライ 第94回
地方自治
2025.08.04

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年1月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
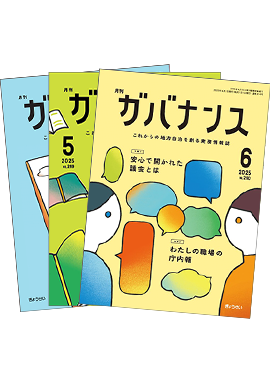
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年1月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

COVID-19は、20年11月以降、新規感染者・重症患者数が増えて、第三波とも言われている。そのため、12月に入って、医療現場は逼迫しているようである。
例えば、北海道旭川市では病院での深刻な集団感染が発生している。大阪府でも病床建設・転換などを進めたが、看護師不足が顕在化した。そのため、他の自治体や自衛隊に応援派遣を求めている(注1)。また、神奈川県では、入院優先度を点数化する運用を開始した。これまでは国の基準に従い「65歳以上」「基礎疾患あり」「妊婦」の感染者は無症状でも原則入院させていた。県独自基準により入院患者が半分に減り、病床の確保につながるという(注2)。
注1 2020年12月6日10時に旭川市(保健所)は、北海道に対して看護師の派遣要請を行ったが、同日13時に困難とされた。そこで、翌7日に自衛隊への派遣要請を決定した。旭川市ホームページ参照。また、大阪府は「大阪コロナ重症センター」を建設したが、必要看護師が50人ほど確保できないため、全国知事会を通じて派遣を要請し、まず、12月7日までに13府県から看護師26人が派遣された。同日、自衛隊にも派遣要請を行った。ABCニュース2020年12月8日12:51配信。TBSニュース2020年12月7日23時43分配信。
注2 東京新聞デジタル版2020年12月7日21時05分配信。
今回は、この自治体現場の苦境を生み出した要因を、総合的・構造的な観点から、見てみよう。
医療崩壊を避けるための介護崩壊
北海道札幌市の介護施設では、20年4月からの集団感染において、最終的には入所者71人、職員21人が感染し、入所者17人が死亡した(注3)。市の検証によると、4月12日からの初動の段階で感染状況の把握に手間取り、デイケアセンターと入所施設での往来やロッカー共用があることが見逃されて濃厚接触者の範囲を見誤り、疫学調査が遅れたという。
注3 札幌市保健福祉局『介護老人保健施設「茨戸アカシアハイツ」における新型コロナウイルス感染症集団発生に係る検証報告書』2020年10月。
4月26日には、入所者から患者が発生し、また、入所者に複数の発熱者がいたため、施設から保健所へ相談の申出があった。ところが、陽性者の入院調整を行っている札幌市からは、市内医療機関の病床が逼迫しているため入院調整が困難であり、入院先が決定するまで施設内療養を継続する方針が、翌4月27日には示された。その後、医師・看護師がわずかに派遣されたもののマンパワーが足りず、介護崩壊という深刻な結果を招いた。
医療・介護へのアクセスの保障と需給調整

医療・介護サービスは行政による介入が強い。自由診療制(医療)と「措置から契約へ」(介護)と、利用者と提供者の関係は市場取引的な側面はある。しかし、均衡「価格」よりも具体的なサービス利用時の自己負担は安価である。それだけでは医療・介護提供者の経営は成り立たないので、保険制度などからの報酬が支払われる。民衆全体から見れば負担は安価ではない。利用者自己負担以外は、保険料・租税から負担しており、総計では民衆負担と事業者収入は同じである。しかし、実際にサービスを受けやすいよう、利用時負担が安価に設定されて、必要と判断されたときに医療・介護へのアクセスが保障される。
利用時自己負担を抑えると、過剰需要になる懸念がある。もちろん、介護では要介護認定がある。また、利用者がコンビニ受診しても、医師は専門家として過剰診療をしない建前である。濃厚診療に対しては、診療報酬が事後的に支払われないチェックもある。とはいえ、全体的には需要は増える傾向を内在している。そもそも、無保険制度と比べて需要が増えなければ、アクセスが保障されたとは言えない。
政策的に需要を増大させた以上、アクセス実現には供給増加しかない。すると、社会全体では、医療費・介護費が膨張する傾向がある。そこで、保険料・租税負担の可能な範囲内に、サービスを減らす圧力が掛かる。とはいえ、単純に費用を抑制するとサービスの質が下がるので、ギリギリの線で提供するように、効率的な医療・介護サービスの連携が図られる。例えば、かかりつけ医に受診させ、専門病院に集中することを防ぐ。長期・社会的入院を避けるために、急性期が終わったら速やかに退院させ、受け皿として、回復期・慢性期の病院、介護施設、在宅に割り振る。こうした需給調整がうまく行けば行くほど、限りある医療・介護資源は効率的に活用される、はずである。
感染症パンデミックの発生
こうした医療介護体制のうえに、COVID-19が蔓延した。治療は原則公費の完全な統制経済である。理屈上は需要が増える(注4)。行政が行き先を振り向ける入院(需要)調整をしなければいけない。受入先(供給)がなければ、需要を公式に引受できない。例えば、受診・入院やPCR検査の需要が増大しても、そのまま鵜呑みにすれば、検査・入院の供給能力を超過して医療崩壊する。そこで、需要を「水際」段階(注5)で抑えるしかない。
注4 但し、感染症の患者などへの差別という日本人の特性を前提にすれば、必ずしも需要が増えるとは限らない。むしろ、自由診療制では、差別を恐れて、受診・検査を手控える可能性もある。つまり、あるべき需要が生じないので、政策的に価格をゼロにして、必要性に応じたあるべき需要を顕在化させているだけかもしれない。
注5 国境で感染者の入国を阻止するという意味ではなく、保健・医療機関へのアクセスを阻止するという意味である。
しかし、水際作戦で医療崩壊を防ぐことは、行き先の目詰まりであって、サービスを受けたい人が漂流する。こうして入所施設の介護現場が崩壊したのが、前記事例である。本来は、介護施設に必要な医師・看護師・介護職員などを派遣して、介護施設で介護しながらの感染症医療を確保しなければならなかった。
集団感染が発生すれば、介護施設の職員は濃厚接触者になって現場から離れ、また、実際に感染して、介護供給能力が低下する。そのような厳しい労働環境は、介護職員の心身を蝕み、離職を増やし、加速度的に施設能力は低下する。医療崩壊を避けるための施設内治療を、介護崩壊を回避しながら継続するには、それを打ち消すだけの膨大な資源投入が必要になる。しかし、医師・看護師・介護職員などを投入できる余裕があるとは限らない(注6)。
注6 実は、自宅療養でも、理屈上は同じであり、家庭崩壊が起きる。ただ、世帯は人数が少ない。介護施設入所者に比べて、平均年齢が若いため相対的に重症化しにくく、日常的介護ニーズも少ない。そのため、クラスターとして目立たないだけかもしれない。
介護崩壊を避けるための医療崩壊

介護崩壊・家庭崩壊を避けるには、速やかに入院させるしかない。ところが、医療供給体制は、精妙な需給調整と効率的連携を想定して、ギリギリの水準で抑制されてきた。医療現場の過重労働は、COVID-19以前から深刻であった。そこに、プラスアルファの入院需要が発生すれば、医療崩壊は避けられない。
そこで、全員入院ではなく、軽症者・無症状者を病院外に振り分ける。軽症者・無症状者は借上ホテルや自宅での療養を行う(注7)。それでも、重症者数が増えれば、供給能力を超過して医療崩壊が起きる。その場合には、以前ならば重症=入院とされた患者を、人為的・政策的に「重症ではない」=入院不要と基準を変更する。この区分変更が、単に医療崩壊を名目的に防ぐだけならば、介護・自宅崩壊につながる。
注7 もちろん、ホテル崩壊・自宅崩壊の可能性があるから、入院が必要なときには速やかに搬送できなければならない。
そもそも、要介護者を入院診療することは、看護師などが介護しながら、医療・看護を続けることでもある。要介護者は、入所・通所・在宅ともに介護サービスを受けて生活しているが、その機能をも病院が追加的に担う。院内での介護人材も欠乏している。医療崩壊も起きやすい構造にある。
おわりに
既存の医療・介護資源を効率的に活用すべく精妙に入院調整をマネジメントしても、無から有は生じない。そのため、急遽、COVID-19病棟を建設する対策や、他の病床を転換することは有り得る。しかし、医師・看護師を急速には育成・現役復帰できない。他地域や自衛隊への派遣要請で、地域的な急場を防ぐことが為されているが、あくまで現有総量の範囲内である。また、他の診療科からの病床・物資・人材の転換は、そもそも簡単ではないが、仮にできても、分娩、癌治療など、感染症対策以外の医療崩壊を玉突き的に生みかねない。
限られた資源を効率的に利用することは重要である。しかし、感染症パンデミック対策のように、一時に急速に需要が伸びるときには、ある程度の資源の余裕が日常的に存在してなければ、可能な対策には限度がある。とはいえ、病院・医師・看護師などを冗長に確保しておくことは、「無駄」とされかねない。行政改革・社会保障改革をするほど、感染症危機は構造的に深刻になる。日常的に膨大な病院・介護施設があれば、経営難になって維持できない。経営を成り立たせようとすれば、財政危機になる。財政危機を避けようと改革をすると、医療・介護崩壊を生む。こうして、構造的に出口のないまま、日々の玉突き的皺寄せの入院調整がなされる。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
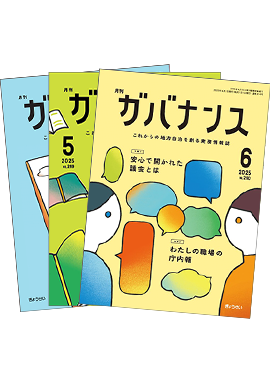
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫