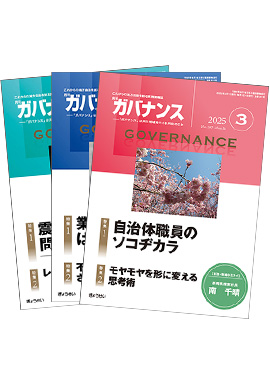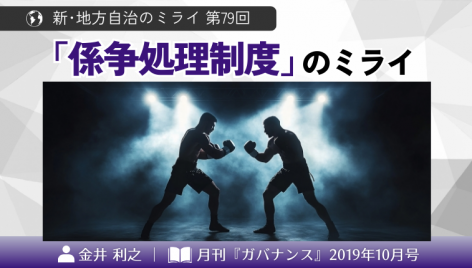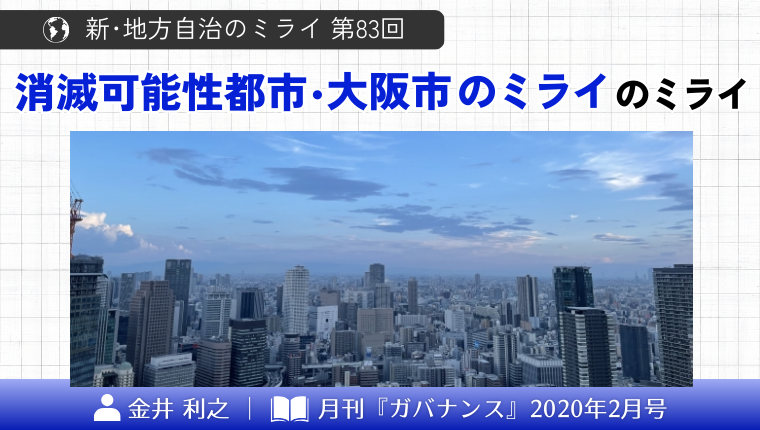
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第83回 消滅可能性都市・大阪市のミライのミライ
地方自治
2025.05.09
本記事は、月刊『ガバナンス』2020年2月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

本欄第25回(2015年4月号)では、同年5月の市民投票を見据えて、「消滅可能性都市・大阪市のミライ」と題して、「大阪都構想」を論じた。結果的には、僅差で「大阪都構想」は否決され、橋下徹大阪市長が政界引退を表明するなど、一時は「大阪都構想」は沈静化した。
しかし、「維新の会」にとって、「大阪都構想」は未完のプロジェクトである。同年11月の大阪「府市合(ふしあ)わせ」選挙では、橋下氏引退後も大阪知事・市長を手中に収めた。「維新の会」は、橋下個人商店から組織政党に転化し、その後も国政・地方選挙の双方で強さを発揮していく。大阪市会は小選挙区制ではなく、「維新の会」が多数を持たず、「大阪都構想」は停滞していた。しかし、局面打開のための2019年4月の松井一郎・吉村洋文両氏の知事・市長スワッピングによって「維新の会」が大阪知事・市長を継承し続けると、選挙の民意に反応した公明党が、「大阪都構想」へ賛成に転じた。
こうして、「大阪都構想」はミイラのように復活し、急速に現実味を帯びてきた。2019年12月26日の第31回大都市制度(特別区設置)協議会(いわゆる法定協議会)において、「特別区設置協定書(案)の作成に向けた基本的方向性」が可決された。「大阪都構想」の現時点での概要は「特別区制度(案)」(注1)の通りである。2020年6月ごろに法定協議会で正式案を決定し、両議会の議決を経て、同年11月ごろに市民投票に掛け、2025年1月1日に移行するスケジュールが想定されている。今回は、久しぶりに「大阪都構想」を採り上げることにしよう。
注1 大都市制度(特別区設置)協議会事務局(副首都推進局)「副首都・大阪にふさわしい大都市制度《特別区制度(案)》」。
東京都区制度の特徴
「大阪都構想」を考えるには、東京都区制度との比較が重要である。東京都制が、帝都の国直轄を徹底する構想でありながら、結果としては、自治体=東京市が、国から自律して、東京府を飲み込む、基礎的自治体=東京都になったのは、二つの要因がある(注2)。
注2 戦後の都区制度改革は、基礎的自治体としての東京都が、自重に耐えかねて自己崩壊し、特別区が自治権拡充により基礎的自治体に自立していく過程である。
第1は、戦後改革により、都道府県の完全自治体化が行われたことである。仮に、東京府が東京市を飲み込んだ東京都制または東京都区制度であっても、国が旧東京市を支配するのではなく、東京府が自治体としての東京都になったのである。
第2は、東京における人口比重の問題である。戦後改革は民主化であり、簡単に言えば人口比例で権力が配分される。戦後直後には旧東京市域(特別区の存する区域)の人口は激減していた。しかし、闇市経済と復員・帰京によって、旧東京市域は人口を回復していく。つまり、東京都政は、「三多摩」住民ではなく、旧東京市域の区民に顔を向けた。このため、東京都政は旧東京市の主導の下で運営された。この状況は今日も続いており、東京都人口1394万人(2019年10月1日現在)に対して、東京特別区人口964万人(同)である。
「大阪都」のミイラ化

翻って「大阪都構想」を見ると、どうなるであろうか。
第1の要因は、表面的には同じである。もっとも、「大阪都構想」を推進している「維新の会」や公明党は、国政と府政・市政の連携の強い組織政党である。従って、制度的には官治でなくても、組織政党制の論理で国政の影響下に押さえ込まれ得る。特に、両党が官邸とのパイプを重視し、官邸への寵愛競争をすれば、国政の介入は容易になる。また、官邸の意のままになる国家戦略特区を活用すれば、「大阪都」(注3)は「大阪城代」(注4)となろう。
注3 法制的には「ふ」のままなので、「と」(「大阪都」)に成金できない。但し、現「大阪府」と区別するためには「新・大阪府」と呼ぶ必要があろう。
注4 中之島にある大阪市庁に対して、大阪府庁は大阪城の近くにある。大阪城主は徳川将軍なので、大阪城代は大阪における官選長官である。
第2の要因は、大阪における人口比重の問題である。大阪市人口は274万人(2019年12月1日推計値)で、大阪府人口は883万人(同)である。つまり、大阪市域での「二重行政」を解消すると称する「大阪都」政は、大阪市域外の利益を中心に動く。「大阪都構想」が、大阪市域を経済成長のエンジンにするのは、無理である。むしろ、大阪市域外の利益を「広域行政」の名の下に推進し、大阪市域に迷惑を押し付け(注5)、経済果実を収奪する方向に進むのが必然である。
注5 たとえば、カジノとギャンブル依存症患者である。あるいは、オスプレイと在日米軍海兵隊員である。
「大阪都」政に任せると、大阪市域は成長のエンジンにはならないから、「大阪都構想」推進勢力は、その意を実現するために、「大阪都」政の主導権を郊外に握らせないように、国による統制を求める。第1の要因と結合し、「大阪都」政の自治も失われる。「大阪都」は国政の出先機関になる。残されるのは、限られた「大阪4区」の自治である。維新政府が、郡区町村編制法・市制特例で、大阪市の自治を認めず、東西南北4区を設置したことと、期せずして同じ状態に復古(いしん)する。
大阪特別区のミライは蜃気楼 ~行けども行けども近くならない~
「大阪都」への移行に伴い、大阪特別区は以下のようになろう。
第1に、「ニア・イズ・ベター」の目的は実現できない。大阪市は近接性が欠けていた。しかし、設置される「中核市」規模の特別区は4ないし6程度であるため、一向に近接性が高まらない。地域自治区を置いて対策を取るならば、大阪市の行政区で充分である。
270万都市を、人口50万人の「中核市」に分割するならば、確かに4ないし6にならざるを得ない。また、近接性ある特別区に多くの事務が残らなければ、現行大阪市の事務は、「大阪都」に移管され、今以上に近接性は失われる。しかし、東京特別区は、人口4万人であっても、保健所・建築確認など一般市を超えた事務を大きく担っている。「大阪都構想」は東京からは学ばなかった。「ニア・イズ・ベター」は看板倒れである(注6)。
注6 なお、特別区の数を少なくするのは、この他に、規模の経済の観点からの経費節減の要請、さらには、特別区間の財政力格差をできるだけ抑え、財政調整への負荷を下げようとする配慮など、様々な要因が作用しており、その限りでは充分に有り得る選択ではある。しかし、それによって、近接性という最大の目標が阻害されたわけである。
大阪特別区はミイラ化せず腐敗する

第2に、公務員制度の破壊である。東京特別区には、共同で設置する特別区人事委員会が存在し、採用・昇進・分限や給与・勤務条件などについて、各区長の専横を防ぐ仕組がある。また、各区が職員採用に支障を来さないように、共同採用をしてきた。ところが、「大阪都構想」には、大阪市人事委員会が果たしてきた役割への賢慮が全くない。
もともと、「維新の会」は、入れ墨身体検査などの公務員バッシング、政治主導の介入(左遷・深夜早朝メールなど)等への指向が強い。また、大阪市民の間でも職員厚遇への批判が強いため、こうしたことはポピュリズム的に支持されてきた。しかし、そこには、適切な公務員制を構築するという発想はない。また、行きすぎた政治主導によって、行政職員が忖度と追従に走りがちなことに対する、自覚も自戒もない。要するに、行政を創る自覚と、公権力を担う謙抑と、権力分立に対する必要性の理解が欠けている。
大阪特別区に蔓延るのは、職員人事への政治家区長の介入と、職員による区長や与党勢力への忖度と追従である。あるいは、権力者の幇間となる「芸人職員」である。「芸人職員」は、激しい競争を厭わず、低い身分保障、劣悪な処遇、恣意への諦観などを備えた存在である。そのために、笑いと愛想はあるが、諫言を上申できず、区長以下幹部の機嫌をとるだけの腐敗が横行する。こうした事態は、大阪特別区の自治能力に対して、府民・市民や国政・国民・有識者の「笑い(ちょうしょう)」を生み出す。それは、大阪特別区の自治権剥奪の口実を形成していく(注7)。
注7 東京の特別区にとってもマイナスの影響もあるだろう。
おわりに
大阪は、近代化・産業化に当たり、東洋のマンチェスターとして工業化を進め、また御堂筋の整備など近代的都市計画の先鞭を付けてきた。課題尖深(せんしん)国の21世紀日本は、国政も含めて、少子高齢化による消滅に向けて加速している。そのなかで、大阪は消滅時代の流れを先取りし、住民の意向を動員して、自らの自治の消滅の道を開きつつある。香港人・台湾人が自治を守ろうと「倒行逆施」するのに対して、大阪人は自決しようとしている。ミライの世界に、どのようなミイラ=大阪が残るのか、全国の自治関係者は刮目すべきだろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。