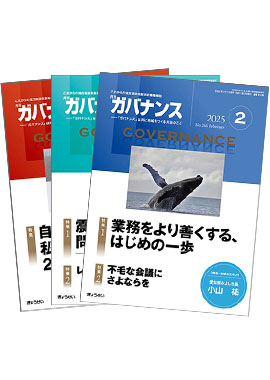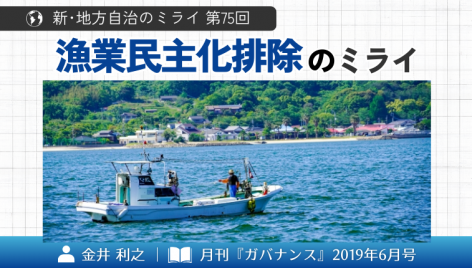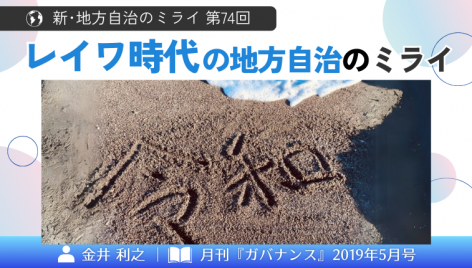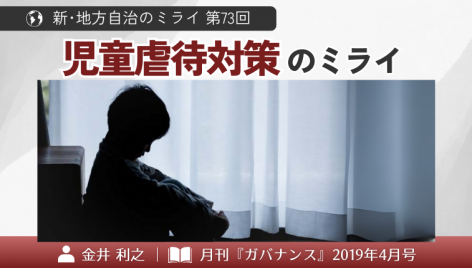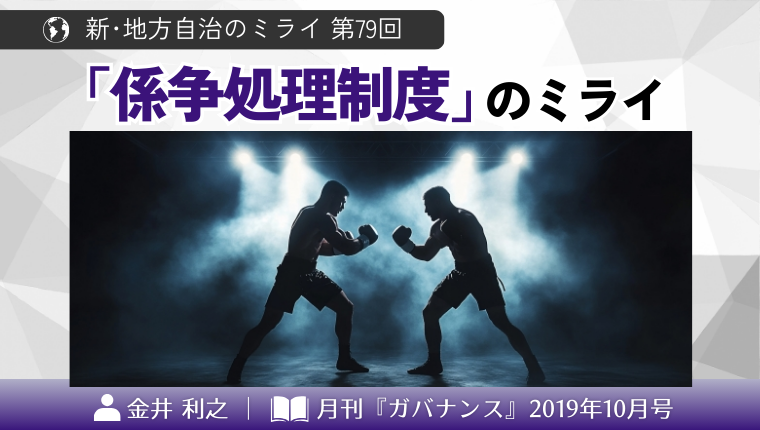
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第79回 係争処理制度のミライ
地方自治
2025.03.24
本記事は、月刊『ガバナンス』2019年10月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに
ふるさと納税をめぐる泉佐野市と総務省の紛争(ふるさと納税対象団体としての指定の有無)は、国地方係争処理委員会(以下、「係争委」)に持ち込まれた。2019年9月3日に係争委は、「本決定の趣旨に従い、再度の検討を行った上で、その結果を理由とともに泉佐野市長へ通知することを勧告」した。実質的には泉佐野市(注1)の勝利である。今回はこの問題を採り上げてみよう。
注1 法的には「泉佐野市」ではなく「泉佐野市長」であるが、あくまで、組織としての行動なので、「泉佐野市」と組織名で表記する。同様に、法的には「総務大臣」の箇所も「総務省」と表記する。もっとも、実態は、「総務省自治税務局」である可能性もあるが、この点は後述する。
若干の留保

本連載欄でたびたび触れてきたように、筆者はふるさと納税制度自体に否定的であるので、泉佐野市の勝利を政策的に妥当だとは考えていない。また、そもそも、総務省が本年の地方税法改正によって「ふるさと納税指定制度」を導入したことも、根本的に瑕疵のある制度の存続を目的とする意味で、有害無益だと考えている。つまり、どちらが勝っても政策的には無意味だと考えている。
しかし、分権・自治思考とは、論者にとって政策的に不当であるとしても、自治体の裁量を許容することである。もちろん、ふるさと納税制度は、公害排出企業と同様に外部性が強く、ある自治体やある個人の利己的行動が他の自治体・住民に不利益を与える面は否定できない。それゆえに、国が一定の規制・介入をすることは充分に有り得るし、集権的要請とのバランスは問われる。
係争処理制度の機能

係争処理制度は、2000年分権改革の制度資産であり、本制度が機能するかどうかは分権・自治にとって極めて重要な論点である。これまでも散発的に活用されてきたが、横浜市場外馬券税事件、辺野古基地建設事件などでは、必ずしも自治体側の主張が通る結果にならず、早くも負の遺産になりかねなかった。
本件も、「再度の検討」を総務省に求めた「差戻し」的なものであって、明確に取消勧告をしたものではないし、ましてや、「義務付け」的に指定を勧告したものでもない。しかし、不決定を取消しても係争委が決定を代行できない以上、実質的には取消と「再検討」は同じである。もちろん、再検討を経ても総務省は指定をせず、さらに裁判所で争われるかもしれないので、最終決着について、現時点で予断を持つことはできない。
独立第三者機関の行政学
係争処理は、あくまで法的論議の世界である。その内容については、行政法学からの検討が今後進むであろうから、筆者の論じるべきところではない。ただ、係争委のような独立第三者行政機関がどのような政治力学のなかで生息しているかを論じるのは、行政学の領分である。
法的論議に基づいて結論Aが出そうなときに、そのまま決定Aを出せるかどうかは、政治力学次第である。関係諸権力の反応を予期し、それを踏まえて自省した上で、結論を採択する。端的に言えば、結論Aが政治力学的に許容されると予期するときに、あたかも、政治的考慮をせずに純粋の法的に専門的な見地からの検討であるかのごとくに、決定Aを出す。もし、政治的に結論Aが許容されないとするならば、許容できる範囲を予測しなければならない。それは、結論A´程度の微修正で済むのか、正反対の結論Bでなければならないのかは、状況次第である。そして、結論Bでなければならないとすれば、独立第三者行政機関の法的な理論構成の知恵が問われる。つまり、普通に考えれば結論Aになるところを、敢えて結論Bにしつつ、あたかも政治的考慮をしていないかのごとくに演出する技量も求められる。あるいは、結論Aでも結論Bでもどちらでも理路整然と理論構成する能力が必要である。
今回の係争委の決定は、純然たる法的論議の世界の結論かもしれない。過去の募集態様が、処分時における諸事情を総合する際の考慮事項であるならば適法であるが、不指定を導く一律の要件であるならば、法律の委任を超えるおそれがあるとする。また、過去の技術的助言に反する募集行為を理由とする不利益な取扱と評価される余地を生じるのはよくないとする。さらに、将来の不指定の要件に延長される点で、国の関与を必要最小限にすべきという基本原則に抵触するおそれがあるとしている。しかし、重要なことは、こうした「おそれ」「余地」から、再検討(実質取消)という決定Aに至れたのは、それが諸権力から許容されると係争委が予期したと言うことである。
係争委判断の推定

係争委の判断過程は、当事者(係争委委員や同事務局)が守秘義務に基づいて弁明できない以上、外部者が推論するしかない。そこで、いくつかの仮説を提示してみよう。
第1は、係争委諦観説である。先の辺野古基地建設事件において、裁判所から、係争委の判断では終局的解決をできず、裁判による決着しかないと判示されている。泉佐野市・総務省の両当事者の意志が固いのであれば、係争委ではいかんともしがたく、「ああでもない、こうでもない」として(注2)、当事者にボールを投げ返すのも、独立機関としてのあり方である。
注2 返礼品等を提供しないとの申述をした指定申出につき、法定返礼品基準の適用を審査すべきかという論点について、係争委は審査不要説と要審査説を並列したまま、勧告としている。これは法令解釈の問題であるが、当事者の主張が尽くされていないとしている。当事者から主張を尽くさせればよいだけであるが、「審理期間の制約」としている。
第2は、総務省内権力闘争説である。係争委の事務局は自治行政局である。実は、2000年分権改革において、財政的な決定については、大半は周到に権力的関与からは排除され、それゆえに係争処理に掛からないように設計されていた。にもかかわらず、自治税務局はふるさと納税という歪んだ制度を設計した。さらに、返礼品競争を制限する制度設計の機会が与えられたにもかかわらず、特定自治体を狙い撃ちするような、前世紀的な集権方策を採った。このことに対して、自治行政局として匙を投げたのかもしれない。
第3は、政治的忖度説である。簡単に言えば、ふるさと納税制度は、菅義偉氏が総務大臣時代に創設させ、官房長官に就任してから運用額を急増させた、政(マルセイ)ものである。しかし、自治税務局はふるさと納税制度の拡大には消極的であり、官邸と自治税務局幹部職員との暗闘(左遷人事など)を招いてきた。自治行政局はこうした政治環境を注視し、幹部職員は官邸との平穏な関係づくりに腐心してきた。係争委はこのような政治力学を見て来た。
さらに、本件については、松井一郎・大阪維新の会代表(大阪市長)、吉村洋文・同副代表(大阪府知事)が泉佐野市を擁護する発言をしている(注3)。千代松大耕・泉佐野市長も同会のメンバーである(注4)。そして、同会は国政政党・日本維新の会と不即不離であり、安倍首相・菅官房長官など官邸との強いパイプを持つ。その意味で、係争委勧告の泉佐野市勝利は、行政府の一員である総務省の敗北のようには見えても、安倍・菅官邸に弓を引くものではない。それどころか、官邸の支援者を援護するものである(注5)。
注3 時事ドットコムニュース2019年9月3日18時24分配信。
注4 大阪維新の会公式ホームページ(2019年9月18日閲覧)
https://oneosaka.jp/member/detail/chiyomatsu_hiroyasu.html
注5 もっとも、官邸に追従する自治体のみ救済されるのは、分権・自治の理念には反している。その意味で、官邸への権力集中状態は、分権・自治にとって望ましい政治環境ではない。
おわりに
独立第三者機関の決定は、あくまで政治力学のなかで成立する。純粋無垢に法令の文理や趣旨目的の理念に沿った法律論議に基づく結論そのものではない。しかし、分権・自治とは、それぞれが権力志向の多種多様な我欲追求機関が、相互に分立・競合することで、住民の権利利益を守ることを期待するものである。係争委の判断を導いた政治力学が何であろうと、自治体側勝利を導いた先例として遺産となる。
全国の自治体にとって重要なことは、係争委の勧告で分権・自治に有利な結論Aを導いた論理構成を活用することである。もちろん、政治力学がそれを許さなければ、法律論議の論理構成などはいとも簡単に変更されて、結論Bが押し付けられるだろう。現実主義(リアリズム)行政学からすれば当然である。結局のところ、いかに自己に有利な政治環境を作っていくかという努力が大事になってくる。その意味で、泉佐野市の先例から学ぶべきことはある。分権は善人だけではできない。もっとも、それは強い権力に阿ることでもあり、ミイラ取りがミイラになる危険もある。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。