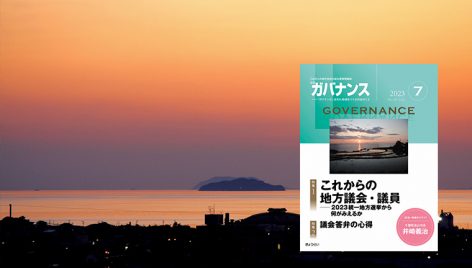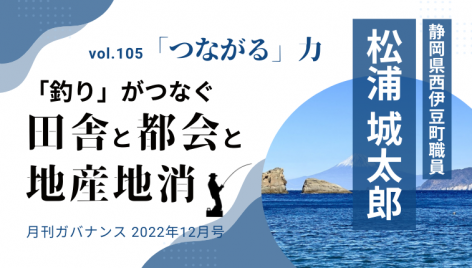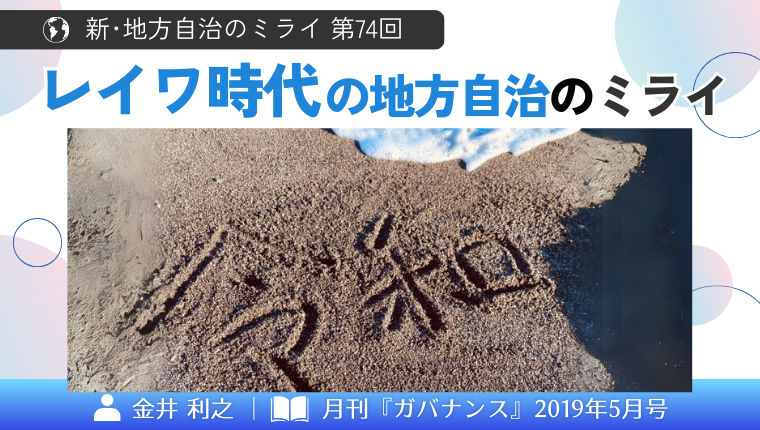
新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第74回 レイワ時代の地方自治のミライ
地方自治
2025.02.05
本記事は、月刊『ガバナンス』2019年5月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

4月1日に新元号が「令和」に決定したという。元号・和暦は世界標準の西暦との換算が厄介で、行政非効率の原因ではある。ただ、「レイワ・元年=西暦20(レ)1(イ)8(ワ)+1年」ということで、換算は便利であるといわれている。
3月上旬に絞られていたのは、「久化(きゅうか)」「英弘(えいこう)」「広至(こうし)」「万和(ばんな)」「万保(ばんぽう)」の5案であったといわれる。首相は『古事記』由来の「英弘」を気に入っていたようであるが、「栄光」などを想起させるということから、さらに日本古典(国粋派は「国書」という)由来の3案を追加提出することを求めたという。そのなかから、「令和」を3月最終週に首相が選択し、上記5案に加えて6候補としたという。こうして、4月1日の有識者懇談会に提示された(注1)。
注1 産経新聞電子版2019年4月3日5時00分配信。
人々の営みは、改元で特に大きく激変しないのであるが、平成時代の終焉を記念して、今回はレイワ時代の地方自治を展望してみよう。
多重意味の時代 ~巧言令色鮮仁~

ひとつの言葉に二重・三重の意味があるのは、ダブルスピークといわれる(注2)。日本語は音声が少ないこともあり、掛け言葉は一般的である。また、集団の同調圧力も強いので、本音と建前が区分される。政治や行政の政策言説も、表面的には耳障り良く見た目も麗しく提唱されるが、実体的には真心の乏しいものになることがある。「巧言令色、鮮し仁」(『論語』)といわれてきた。ここでは、「令」は良い意味ではない。
注2 例えば、「きれい」は「きたない」とか「平和」は「戦争」とかを意味する表現がある。
「まち・ひと・しごと創生」なども、地方圏の自治体に対して配慮をしているように見せながら、実際には自治体に弱肉強食を迫る。政治・行政は多重意味との戦いでもある。
そもそも、「令和」自体が、多重意味の争いである。「命令」の「令」でもあり、人々をして「和」せ「令(し)」むことを期待するニュアンスがあり、それゆえに、扶翼の指向性の強い人々には、心地よく受け入れられるだろう。もっとも、それを露骨に表現しないのが二重意味の世界である。
それゆえに、「レイジョウ」(注3)と同様の「美しい」というような意味での「令」であると解説する(注4)。しかも、『万葉集』での「初春の令月」とは、「厳しい寒さ」の後の春の訪れのなかで「人々が美しく心を寄せ合う」という意味だそうである(注5)。平成時代は戦争がなかったが、それに「厳しい寒さ」を読み込めるようなっている。
注3 発音だけでは、「令嬢」なのか「令状」なのかは不明である。
注4 外務省が「令和」を「beautiful harmony」という翻訳に統一したのは、その現れである。なお、BBC放送は「order and harmony」、AP通信は「pursuing harmony」と翻訳していた。毎日新聞電子版2019年4月3日18時18分配信。
注5 2019年4月1日安倍首相記者会見談話。官邸ホームページ。なお、「美しい」は同首相のよく使うフレーズである。「命令」は「美しい」ということである。
また、『万葉集』という「国書」から「初めて」採用されたという触れ込み自体が二重の意味である。『文選』その他の漢籍の用例を読み込める(注6)。深い学識は、素人の浅薄な智恵をも凌駕しうる。
注6 毎日新聞電子版2019年4月1日20時54分配信。
例話時代の地方自治
レイワ時代に向けて、例話が横行する。かつて、「後発国」日本では、先進国を例に「○○では」という言説が多かった。いわゆる「ではの守」である。ところが、「厳しい寒さ」の先沈国レイワ日本では、そうはいかない。そこで、国内で「成功事例」を探し、「例えば、○○という地域では××でうまくいった」と紹介する例話が基本となる。
理屈上は、成功事例を国が政策として採用し、全国で制度化すればよい。しかし、例話が成功物語や奇譚に留まるのは、そもそも、それが全国展開できるものではないからである。他の自治体や地域にとっては、学習・参照できるような先行事例にはならない。「カジノで当たった人がいる」という「話」は、私がカジノで当たることには全く繋がらない。しかし、例話は、根拠はないが気休めになる。国が「成功事例集」をとりまとめるのは、政策がないからであり、自治体が成功事例に引っ掛かるのは、対策がないなかで何とか救いを求めるからである。
例話自体に罪はない。成功物語を示すことで、個々の地域・自治体がその固有の問題に立ち向かうことを忘却し、同時に、国全体の枠組という基盤問題に取り組むことを忘却することが、問題なのである。
零和時代の地方自治

経済停滞の零和(ゼロサム)社会のなかで、自分や自分たちの暮らしを向上させるには、他者から取ってくるしかない。経営層・富裕層が報酬を増やすには、労働者層から搾取する格差社会しか解決策がない。そのために、労働規制・働き方を「改革」する。また、まともな仕事がなければ、オレオレ詐欺などの特殊詐欺に走るしかない。
自治体は、成長社会の昭和時代から水平的競争として、補助金・箇所付け獲得競争や企業誘致競争をしていた。それでも、全体としてパイが増えていれば、絶対水準は何とか向上する。しかし、零和社会では、自治体間・地域間で文字通りの奪い合いの弱肉強食になる。
国としては、弱肉強食の枠組を設定することが、疑似政策になる。例えば、移住者獲得競争となった「まち・ひと・しごと創生」や、自治体間で税収を奪い合い、結局は、富裕層のネットショッピングに利益提供をする「ふるさと納税」などである。そして、水平的競争の行動原理が染みついた自治体は、こうした競争原理を仕組まれると、レースに乗らざるを得ない。こうして、お互いに傷つける。
そして、このような零和競争は、例話の成功物語で脚色される。例えば、「○○では、××をして若い世代の移住者がどんどん増えた」とか、「△△では□□を返礼品にしたのでふるさと納税が莫大に集まった」などである。
隷輪時代の地方自治
2000年分権改革は、分権・自治という山頂を目指す過程の「ベースキャンプ」のはずであったが、実際には、例話と零和のなかで迷走している。そのなかで、同じく1990年代から進行した内閣機能強化と大政党執行部強化(小選挙区制度)の結果として、官邸主導の長期政権が出現するようになってきた。国政政権の意向が強くなるなかで、自治体は厳しい状況に囚われている。
一方では、自主性を重んじて国の政策に異論を唱える自治体には、国から発せられる投げ輪が絡まり、自治体の首は絞められ、隷従への道に陥っている。例えば、国の構造改革のなかで地域振興を頑張った結果、財政的に破綻をした北海道夕張市は、財政再建(再生)の投げ輪のなかで、隷従を迫られている。また、沖縄県などが、基地移設に反対しても、それに対して、裁判所、機動隊、巡視船、工事車両・船舶・ダンプカーなどの法力・実力によって、隷従させる。
他方では、国政為政者の方向性を先取りし、国政ではできないことを地域の権力者として実行し、国政の威令に、自治体から「自発」的に唱和するようなる。まさに、国の命令を、国の明示的な指示や介入なしに、自治体が競って「心を寄せ合う」忖度をもって、「自治」と理解するようになる。
例えば、国土強靱化に向けて巨大な公共事業を進める。規制改革の方向を受けて様々な事業を民間事業者に供与する。原子力発電所の再稼働・建設を求める。五輪・万博・カジノの誘致に奔走し、基地新設に賛成する。こうして隷輪に「心を寄せ合う」かもしれない。
おわりに ~冷倭時代の地方自治~
「地平らかに天成る」という語源を持った平成時代は、結果的には、地震などの天変地異が相次ぎ、一億総中流の平等と国富は失われて格差社会となり、平穏というより改(壊)革が続いたともいえる。
レイワ時代の地方自治は、平成時代から零和・例話・隷輪の傾向を引き継ぐ。春は花粉症、夏は酷暑、秋は台風、冬は豪雪という四季の巡りのなかで、「令月」などと脳天気なことをいえない、厳しい異常気象のなかで、ミライを迎える。新たな道を開くクールジャパンの冷倭に向かうのか、熱が冷えきった高齢・過疎の矮小化した冷倭になるのか、地方自治は岐路にある。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。