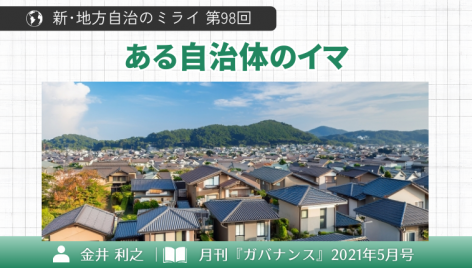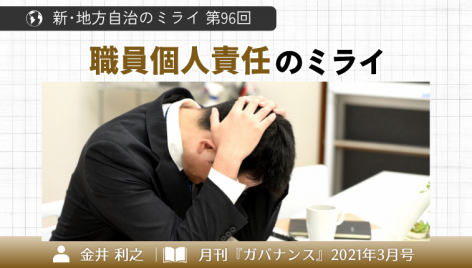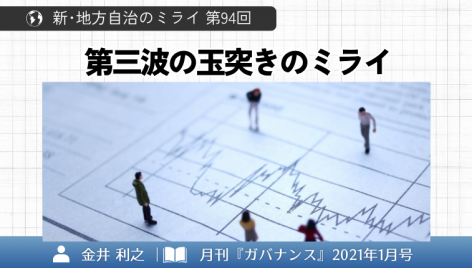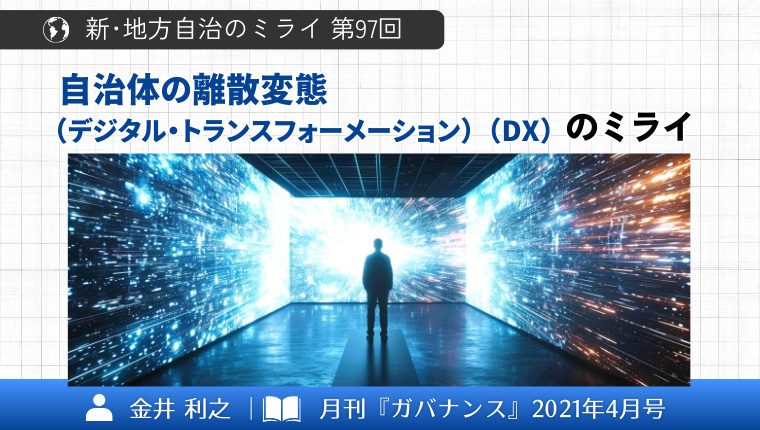
新・地方自治のミライ
自治体の離散変態(デジタル・トランスフォーメーション)(DX)のミライ|新・地方自治のミライ 第97回
地方自治
2025.09.03

出典書籍:『月刊ガバナンス』2021年4月号
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
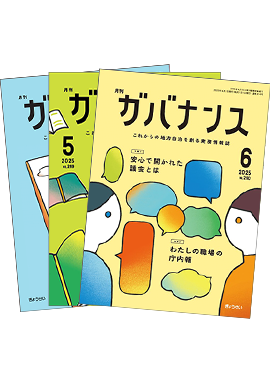
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫
本記事は、月刊『ガバナンス』2021年4月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
はじめに

情報技術が経済の駆動力となり、GAFAM・BATHなどの巨大情報産業企業の権力が拡大している。自動車・和食などのものづくり産業は、こうした情報企業の蜘蛛の巣に捉えられ、栄養分を吸収されてしまう。にもかかわらず、「時代の流れ」として、対応せざるを得ない、となる。しかし、ICT化の掛け声は、1980年代の「地域情報化」(注1)の提唱や、1990年代からの電子政府・電子自治体、e-Japan構想など(注2)、「昭和・平成からの懐メロ」でもある。
注1 郵政省の「テレトピア構想」などであり、キャプテンシステム、CATV、地域VANなどが推進された。また、NHKなどを中心に、アナログ・ハイビジョンを普及させようと企図もした。
注2 高度情報通信社会推進本部(1994年)、行政情報化推進基本計画(1994年)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)(2000年)、IT基本戦略(2000年)、e-Japan戦略(2001年)、など。
さらに、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延は、対人接触が避けられるリモート方式への移行(トランジション)を、移行管理(トランジション・マネジメント)なきまま、多くの人に実質的に強要する契機となった。火(禍)事場泥棒(ショックドクトリン)的に、菅義偉政権では、「デジタル・トランスフォーメーション」(DX)が推進されるに至った(注3)。
注3 デジタル・ガバメント実行計画(2020年12月25日閣議決定)など。
総務省は2020年12月5日に「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」を策定した。同計画は、2021年1月から2026年3月までの5か年強を対象とする。今回は、この古くて新しい情報化の動きを論じてみよう。
なお、情報化の領域は様々なカタカナ用語やアルファベット略語が頻用されている。カタカナは長いので不便である。そこで、「DX」と略されるが、「X」という未知数・中身不明を意味する略語は、行政としては極めて不見識である(注4)。そこで、本論では直訳し、デジタル=〈離散的〉、トランスフォーメーション=〈変態〉という点から、以下、「離散変態」と訳しておく。
注4 「DX」は、しばしば、「デラックス(deluxe)」の略語でもある。印象操作も兼ねているのであろう。
離散変態推進計画の意義

計画によれば、自治体の離散変態(デジタル・トランスフォーメーション)により、住民の利便性を向上させ、業務効率化・行政サービスの向上につなげる、とする。データが、価値創造の源泉であるという認識を共有し、様式を統一化して多様な主体間のデータの円滑な流通を促進し、行政の効率化とともに、民間ビジネスでの価値創出が期待される、とする。つまり、情報が経済を推進する時代において、経済政策に自治体が貢献することを期待している。
自治体情報システムの標準化・共通化などを進めるため、国が主導的な役割を果たして、自治体全体として足並みを揃えて取り組む必要がある、という。つまり、その観点から本計画を策定したのであり、分権型社会として自治体の自律的取組を支援するのではない。統一的・画一的な基盤構築を目指す。経済に奉仕する全国画一的な地方の取組は、日露戦後の「地方改良運動」以来、しばしば繰り返されてきた。
離散変態推進計画の概要
離散変態推進計画は、以下のような推進体制の構築を求めている。
①首長、CIO、CIO補佐官などを含めた全庁的マネジメント体制の構築
②デジタル人材として、総務省・デジタル庁・都道府県の連携による外部人材確保の仕組、総務省・デジタル庁の連携による共創プラットフォームの創設と自治体職員への研修
③総務省が示す推進手順書を踏まえ、工程表などの策定による計画的取組
④都道府県による市町村への支援
である。
また、重点取組事項は以下の六つである。
❶自治体情報システムを標準化・共通化する。法改正を行い、自治体の主要業務システムの標準仕様を定め、予算支援をし、国は「(仮称)Gov-Cloud」を構築する(注5)。
❷個人番号カードを普及促進する。人件費や窓口増設には国は補助金を出す。
❸自治体行政手続をオンライン化する。個人番号カードを用いて申請を行う31手続(注6)について、個人番号ポータルから可能とするように整備する。
❹自治体のAI・RPA(注7)を利用促進する。総務省は導入ガイドブックを策定し、標準モデルを示す。
❺テレワークを推進する。総務省はLGWAN-ASP(注8)によるテレワーク環境の提供と、導入事例の提供を行う。
❻セキュリティ対策を徹底する。総務省は、セキュリティポリシーガイドラインを改定するとともに、新たなセキュリティ対策を検討する。また、次期自治体情報セキュリティクラウドへの移行を補助金で支援する。
注5 「cloud」とは「雲」である。行政文書が雲散霧消する日本政府の実態を表現したいのかもしれない。
注6 子育て、介護、被災者支援、自動車保有などの行政手続が想定されている。
注7 RPAはロボティック・プロセス・オートメーションであるが、工場生産現場ではロボットの活用は以前から普通なので、ここでは、パソコンでの事務作業など、ホワイトカラーの業務を自動化するシステムを指す。
注8 LGWANとは、自治体の組織内ネットワーク(庁内LAN)を相互に接続した、高度なセキュリティを維持した行政専用閉域通信ネットワークである。LGWAN-ASP(Application Service Provider)を介してインターネットなど外部と接続されるので、両備システムとも言われる。
さらに、自治体離散変態と併せて取り組むべき事項として、(1)地域社会のデジタル化と、(2)デジタルデバイド対策が指摘されている。後者は、携帯ショップ等が主体となるデジタル活用支援員によって、オンライン行政手続・サービスの利用方法に関する助言相談などをする(注9)。
注9 かつて、文書手続が煩雑で厄介だったときに、行政書士制度が作られたようなものである。
離散変態への移行管理
目指すべきデジタル社会への変態に、1980年代以来の情報化の動きと同様に、自治体は動員される。大きな負担と混乱が予想される。例えば、個人番号カードの交付は、散発的に作業を続けて、徐々に普及させてきたが、短期間で急速に進めると、事務的に無理が生ずる。しかし、普及率が低ければ、デジタル化の「恩沢」を押付できないために、国は、個人番号カードの普及に躍起になっている。
ある程度の住民多数が個人番号カードを持てば、少数を無視できるようになる。こうなると、最初の個人番号カードの設計の良否が、社会のあり方を呪縛してしまう。家庭用ビデオで、β方式よりも質が悪くてもVHS方式が普及したのと同じである。そして、DVDやネット配信のように、新しい技術に置き換わらなければ、建増し的に、質の低いサービスを続ける悪弊になる(注10)。置き換わるためには、さらなる変態が必要になる。技術革新は速く、行政が普及に成功した頃に、時代遅れになり得る。しかし、自治体は不承でも付き合わざるを得ない。
注10 オンライン行政手続のために、現在は個人番号カードをスマホにかざす。そこで、電子証明機能をスマホに搭載すべく「移動端末設備用電子証明書」を創設する。ならば、個人番号カードも不要である。しかし、個人番号カードの署名用電子証明書を用いて発行させ、また、個人番号カード用電子証明書と紐付け、個人番号カード制度を維持する。
情報技能格差社会

より深刻なのは、デジタルデバイド(情報技能格差)である。仮にスマホ・個人番号カードなどのモノが普及しても、それを使いこなせるとは限らない。取扱説明書だけでは無理で、インターネットQ&Aや自動音声回答やチャットボットでも何を言っているか判らず、人間が懇切丁寧に教示するカスタマーセンターが不可避である。民間サービスならば利用しない生活も有り得るが、行政手続は全住民が悉皆的に利用可能でなければならない。
デジタル化により、結局は人々の一定部分は不便になり、便利さを回復するための別途の対人サービスが必要になる。支援員を廃止するために、個々人を教育するならば、支援員が教員に変わるだけである。
現在が一人ひとりを取り残す社会ならば、離散変態したのちも、一人ひとりを取り残す社会に変態する。現在でも一人ひとりを取り残さない社会であれば、デジタル化で特に便利になることはない。しかし、離散変態しても、取り残さない社会のままである。つまり、変態前の現在の社会のあり方を不問に付している離散変態は、結局、目指した建前・理想を実現できない。情報技術は自動的には便利さを生み出さない。
おわりに
情報・知識による支配は、権力の本性であり、官僚制の本質であるから、情報技術が進めば、為政者あるいは権力追求者や起業家・富裕層はそれを追い求める。そして、自治体や住民などの被治者は、自らが情報権力を目指す側に回ろうとするかもしれないが、情報権力という新たな為政に振り回される。
いずれにせよ、情報化によって、利便性の高い社会になるとは限らない。監視社会になると決まったわけでもない。ただ、便利・不便や監視・自由について、権力に翻弄されることが続く。離散変態する前の現在の日本社会のあり方を前提に変態していく。国の方針だけでは、すでにミイラ化している日本社会の場合、情報技術を活用してもミイラ状態のままである。
著者プロフィール
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。
主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)、『行政学講説』(放送大学教育振興会、24年)、『自治体と総合性』(公人の友社、24年、編著)。
「新・地方自治のミライ」は「月刊 ガバナンス」で過去に掲載された連載です。
本誌はこちらからチェック!
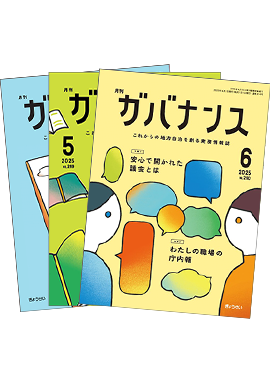
ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。
月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編
詳細はこちら ≫