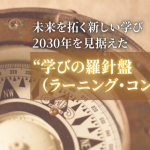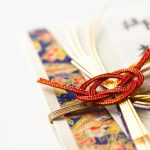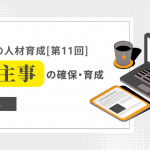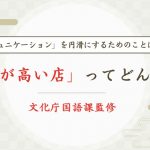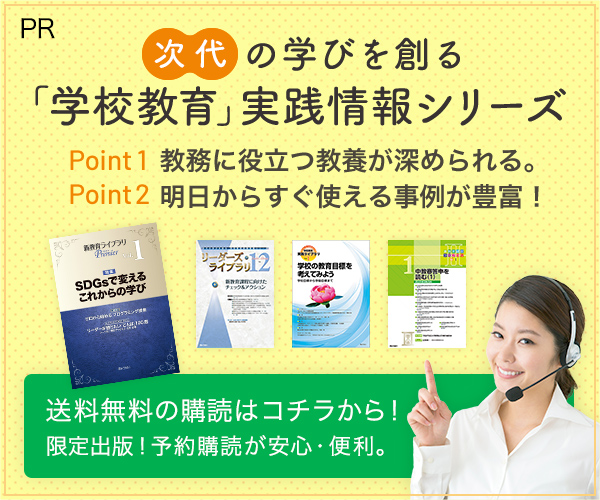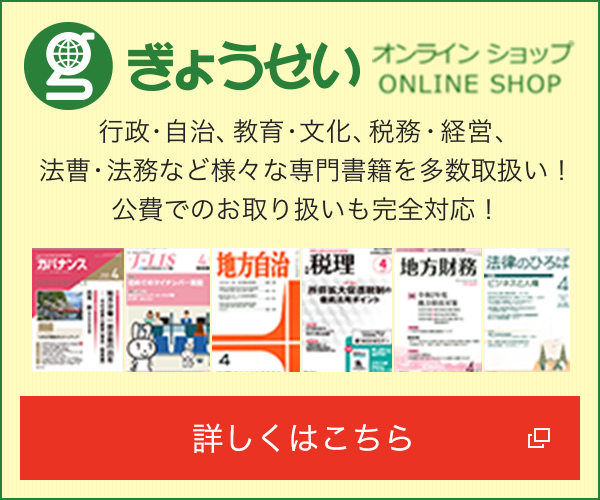学校改革の新定石
学校改革の新定石 第9回 授業づくりのガイドブックをつくろう
トピック教育課題
2019.07.16
学校改革の新定石
第9回 授業づくりのガイドブックをつくろう
(『新教育課程ライブラリ Vol.9』2016年9月)
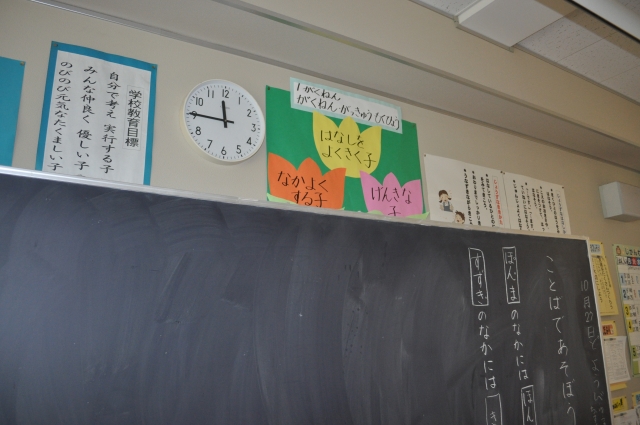
私が関わっている高知県の越知町、津野町、安田町の学校で教科横断型の授業改善が進み、その成果として学力が向上している。こうした学校が出てきた背景には、私自身の苦い体験がある。元勤務校は、年に60回以上もの研究授業を行っていた。だが、これはと思える授業はほとんどなかった。確かに一部の教師は育ったが、全教師の授業力の向上までには至らなかった。当時のメモに、「授業の限界」とまで書いたほどだ。こうした実態を分析すると、次のようなことがあることに気付いた。
・教師がよくしゃべる授業を当たり前としているので、子どもが受け身の授業となっている。
・教科書の内容を解説するような授業が多く、教師が教えよう教えようとする授業が多い。
・学習が分からない子への手立てが少なく、分かる子を中心とした授業が続いている。
・教科横断的な視点の授業ではなく、教科の専門性にこだわる授業が多い。
これらの原因に、教師が学習指導要領の総則を丁寧に読み込んでいないことが分かった。授業を行う際、学習指導要領の教科の目標や解説は見るが、肝心な総則を見ていないのだ。専門とする教科の研究には熱心だが、教科横断的な視点で指導方法を学校全体で統一しようとする意識が弱い。学習指導要領で指摘する「見通し」「振り返り」「言語活動」「課題学習」「問題解決的な授業」等が徹底されていない。こうした元勤務校の実態を分析し、高知県の学校を指導した。その中心となったのは、次の2点である。
・子どもの自主的・自発的な学習を促す(総則第4の2(2))
・教科横断的に学び方を指導する(解説総則編第3章第5節2)
この2点を強力に進めるために、①1校だけでなく町や地域全体の学校で授業改善を進める、②教師の自己流の授業から、学習指導要領が示す「問題解決的な学習過程」の授業へ統一する、③子どもの学習意欲を高めること等を柱にし、授業改善を進めるよう促した。その中心となったのが「学習過程スタンダード40」と「高知県授業づくりBasicガイドブック」だ。
「学習過程スタンダード40」

学習指導要領総則に記述してある「問題解決的な学習」を教師に定着させるためにはどうしたらよいか幾度も悩んだ。これまでの学習過程「導入、展開、終末の3段階」「問題把握、自力解決、集団解決、まとめの4段階」を導入しても全教師が習得するまでには至らなかったからだ。この反省に立ち、まずは子ども・教師に授業内での動きを学ばせることが重要と考え、詳細な問題解決型の学習方法の7項目の習得を促した。効果はすぐに出た。子どもが授業での動き方をマスターすると、教師の指示言葉も減り、自ら学習するようになった。教師も授業に手ごたえを感じるようになった。
なお、子どもがただ動くだけの授業、情報交換がたくさんあるだけの学び合いの授業は避けるよう助言をした。子どもの動きがあると授業は一見よく見えるが、付けるべき力が付かないこともある。課題解決の見通しが立つかどうかの確認、学び合いで分からないところがあると教え合い、仲間から学んだことの「振り返り」を確実に記述する授業過程を行うよう促した。この学習過程スタンダードに全教師が取り組むことにより、どの教科でも同じ水準の授業ができる。学習過程スタンダードには、40項目(具体的な学習指導25+事前指導15)が記載してある。具体的な学習指導25項目には、①前時の振り返り、②問題の提示、③問いをもつ、④問いの共有、⑤課題の設定、⑥日付け・縦線、⑦課題の青囲み、⑧課題の3回読み、⑨シラバスの提示、⑩言語わざ、⑪自力解決、⑫自力解決困難対策、⑬集団解決、⑭ペア学習、⑮班学習、⑯教科進行係り、⑰学び合い1「単純意見交換」、⑱学び合い2「考察」、⑲教師の修正、⑳まとめ(価値の共有)、㉑まとめの発表、㉒まとめのまとめ、㉓振り返り、㉔振り返りの発表、㉕振り返りの振り返り等がある。各学校は、この学習過程スタンダードを参考にして、学校独自の「○○学校学習過程スタンダード」を作成するとよい。なお、学習過程スタンダード40は、高知県越知町教育委員会HPで公開している。
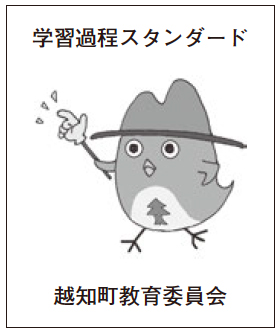
高知県授業づくりBasicガイドブック

高知県の小学校や中学校の各教科等で、子どもが主体的・協働的に学び合い、自ら考え表現しながら学習を進める授業の基礎・基本となる内容を「Basic」として示している。特徴は、①アクティブ・ラーニングの視点から、学習指導方法等の改善を行うことができるようにする、②各学校や子どもの実態、状況に応じて指導の工夫や改善を図ることができるようにする、③学力の定着が十分ではない子どもを含む全ての子どもが、授業で主体的に学習できるようになるための指導方法等の工夫を提案している等だ。高知県「授業づくりBasicガイドブック」は、高知県教育センターのHPで公開している。こちらも参考にしてほしい。
これまでの授業スタイルを変えるには迷いがあるだろう。だが、教師が話さなくても授業が進む。子どもが主体的に動くような授業となることを思い浮かべて欲しい。子どもの学ぶ意欲も出て、授業が充実し結果的に学力が向上することになるだろう。

Profile
西留安雄
にしどめ・やすお 東京都東村山市立東萩山小学校長、同大岱小学校長を経て、東京都清瀬市の清瀬富士見幼稚園長。大岱小では校長在任中に当時学力困難校といわれた同校を都内トップ校に育てた。現在、高知県・熊本県など各地の学力向上の指導に当たり、授業・校務の一体改革を唱える。主著に『学びを起こす授業改革』『どの学校でもできる! 学力向上の処方箋』など。