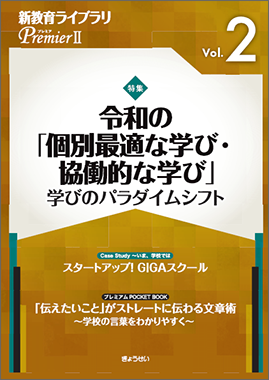異見・先見 日本の教育 外国語を学んでこそ気づく日本語の特質と豊かさ
『ライブラリ』シリーズ/特集ダイジェスト
2021.09.16
目次
異見・先見 日本の教育
外国語を学んでこそ気づく日本語の特質と豊かさ
日本文学研究者・早稲田大学特命教授
ロバート キャンベル
(『新教育ライブラリ Premier II』Vol.2 2021年6月)
“文脈依存度”が高い日本語

日本の生活言語というのは非常に“文脈依存度”が高いということが言われて久しい。つまり、実際に発話する言葉の構文や単語、論理構造とは別の観点で、“文脈”によって伝わるか否かがかなり左右されるというところに一つの特徴がある。それは他の言語に比べて優劣であるとかとはまったく異なる次元の話であり、非常に豊かな可能性を含んでいるものだと思う。
先日、私はたまたま動画で小津安二郎の『秋刀魚の味』を見ていたのだが、小津映画では、畳の上に座ったまなざしの角度からワンシーン、ワンシーンを構築的にずっと見せられており、ほのかな人々の表現やちょっとしたしぐさ、語り切れない人間の言葉、普遍的な真実というものが字幕であっても吹替であっても伝わるのである。
これを同じように英語でできるかというと、8畳か10畳くらいの日本間の中でちゃぶ台があって、3人、4人が出たり入ったりするような人間模様は、脚本の字面だけを読んでもよくわからないのではないだろうか。空間であったり人の関係性であったりしぐさであったり、年齢差、目上・目下という関係性の中から多くのことが実際に伝わったり伝わらなかったりする。それがまさに文脈依存度が高いということなのである。
外国語教育の現場においては、日本語を母語として語り合っている自分たちが、実はそういう特徴がある言葉の中で物事を考えたり世界を見たり感じたり他者と渡り合おうとしているということを、過大にも過少にも評価せず一つのファクトとしてそれに気づかせるというのがまず大事であろう。
外国語を学ぶことによる母語への気づき

日本の英語教育はあまりにも他の教科から切り出して英語を習得させるので、それぞれ別々の部屋で扉もないかのようだ。外国語を学び、自分で文を作り、聴き取れるようになる経験を重ねていくことによって、空気のように思って使っている母語が相対的に違って感じられる。日本語がどういう特性や素質を持っている言語なのかと考えるとき、外国語を学んだことのない人にはいくら問答をそこで繰り返しても見えてこないはずだ。それは外からしか感得することができないものだと思う。
私自身にも7歳、8歳くらいの頃からそういった経験がある。カナダとの国境に近いニューハンプシャー州のサマーキャンプに毎年行っていたのだが、そこにはケベックからフランス語を母語とする子供たちがたくさん来ており、集団生活の中でその子たちとフランス語や英語を少しずつ混ぜながらしゃべるということをしていた。また、14歳のときには両親の仕事の都合でフランスにしばらくいたので、そこでフランス語をかなり集中的に学び、戻ってからも中学・高校時代はずっとフランス語を学んでいた。
それらの経験を通して、透明なトタンのような建材が英語だと思っていたものが実はすごく屈折しており、光の通し方に自分の認識が支配され、作用がそこにあるということに気づいた。そして、心の中で思っていることをフランス語で英語のように言おうとすると全然違う受け止め方をされ、きょとんとされたり怒られたりということがあったのだ。
その後、19歳から日本語の学習を始めたのだが、日本語で訥々としゃべり始める自分が少しずつ上達していくにしたがって、そもそも英語では表現しようとは思わないこと、英語に逐語訳すれば逆に誤解されるかもしれないというようなことが口から出ることがあった。いわばフランス語のときと逆の現象が起こったわけである。
英語では性別によって人称が変わることはまずないが、日本語では男性は男性らしく女性は女性らしく自己表現をするということが中学校くらいから叩き込まれ、大学生に至って自分というものを確固たる存在にしていく過程が今でもあると思う。私にはそれがボディブローのようだったのだ。
私としゃべっている同年齢の女性が「“男性性”が足りない」と言う。私が「ぼく」とか「おれ」とか言わないとなんかもどかしい、事務的な話に聞こえると直接言われたり、それとなく伝えられたりすることもあった。「もうちょっと男っぽく話してくれない?」「ここでは『わたし』ではなく『ぼく』でしょ?」……。それはルールとしてはどこにも書かれていないし、明確に誤りを指摘されるようなことはわりと少なかったのだが、そのようにして脛に小さな傷ができていき、傷が癒えるごとに自分の日本語がよくなっていくということを経験したのだ。
言語活動においては、学ぶ中でそういった違い、異なる在り方があるということに気づき、それをかき消すとか抑え込むということではなく、受け止め納得することが大切だ。英語と出会って英語の中で学び、言葉を聴き取ったり書いたり読んだり話したりする。それぞれのスキルにおいて昨日できなかったことが今日はできた、ちょっと自分が変われたというのは楽しいと感じられるようになるだろう。
外国語教育におけるアクティブ・ラーニング

例えばアクティブ・ラーニングでは、単に教科書で学び知識を身に付けるということではなく、生徒たちが自ら問いかけを探し、その問いかけが浮かんだときに何を調べてどういう資料を集めるか、考えて対比させることによって自分で一つ一つ判断し取捨選択をする。それをまとめてレポートや作文といった形にしていき、そして今度は口頭発表であったりディベートだったりと、人に伝えていく。それを受け止めて自分はどう反応するのか。これらは言語習得にはすごく大切なことだ。
一つの連環として考えるとすると、英語の時間の中だけではなく例えば国語教育と英語教育とが、ある時間、あるトピック、ある教室のタスクにおいてはかすがいのようにつながっていると思う。日本語が持っている言語としての素質と異なるコミュニケーションが求められるとき、スキルだけではなく感性・感覚が異なるものが英語にあるとすると、どこかで川が合流する河口のようなものを作ったほうがよいのではないか。
例えば、宇宙飛行士の野口聡一さんが地球に戻ってきたことを一つのきっかけにとらえて、はやぶさについてでも星についてでも何でもよいが、同じ宇宙という素材を国語の中でも、英語の中でも並行して取り上げる。同じテーマを取り上げていても、それが日本語ではどうなっているか、英語ではどうなっているかということを生徒たちが自由に往還できるような、あるいは相乗的な効果を目指すことがアクティブ・ラーニングそのものを実体化させる一つの有効な方法ではないだろうか。
母語と外国語とは二項対立的ではない

母語である程度しっかり足組ができてから外国語を学ぶべきという考え方がある。片方を学ぶあるいはそれに接して身に付けることで片方が引き算される、つまりキャパシティには限界があるというものだ。しかし、私の周りには母語が日本語の親と異なる母語の親とのもとに生まれた子供たちがたくさんおり、それぞれの家庭のポリシーや事情によって縫い目なく段差なく二つの言語で育っている。基本的な話す、聴き取る能力に関しては、必ずしもキャパシティの限界はないと思う。ただ、それが国語であるとか算数であるとか、他の科目に食い込んで重要な知識、基礎的な学力を損なうようなカリキュラムの立て方はもちろんすべきではないだろう。
始める時期が遅いとか早いというのもあまり関係ないのではないか。ある程度早いうちから身に付けるほうがよいというのはあるが、そうしなかったからといってその言語の中に入っていって自己実現が十分にできないというわけでは決してない。ただ、子供たちが自分にとって英語とはどういうものかを考え、選択のパイを広げるという意味では、若いうちに始めるに越したことはないと思う。
読むこと、書くことは、小学校高学年からになってくるが、これも必ずしも二項対立的な関係にあるのではない。外国語に接することによって日本語に対する自覚、深い親近感が生まれ、日本語は実は一枚岩ではないということに気づかされるかもしれない。英語やハングルやロシア語を学ぶことによって、実はそれらの中にはいくつもの言語が折り畳まれているのに気づくだろう。
『トレインスポッティング』という映画では、スコットランドの俳優が機関銃のように会話を交わすのだが、字幕がなければ私はまったくわからないというくらいに、さほど広くない英国の島の中にもさまざまな英語がある。ロンドンを中心とする英語とスコットランド英語、海峡を越えたアイルランド英語とはまるっきり違うものだ。日本語においても、いま日常的に使われている日本語はとくに1980年代頃から共通語が完全に一人勝ちだが、少しでも古い日本語に触れるとミルフィーユのように複層的な言葉だということに気づく。
そのように、いろんな英語があることに気づくことによって、翻って日本語も時代によって地域によっていろんな違いがあるということに気づき、自分の思考を前に進めさせ、深く豊かにしていくきっかけになると思う。
外国語ができることによって開かれる扉
「外国語を学ぶのは目的ではなくて手段である。外国語を使って何を伝えるのか、何をするのかのほうが大事だ」というのもよく聞かれる言説である。私はどちらかというと、この点に関してはあまりお世話を焼かなくてはよいのではないかと思う。
自分自身の経験なのだが、日本語の日常会話ができてやさしい小説や随筆が読めるように少しずつなっていくにしたがって、それを使って何をするのかという考えがどんどんわいてきた。それはある時期悩みの種にさえなったが、日本語が運用できるスキルがあれば結構何でもできる、いろんなチャンスの扉があるわけだ。おそらく誰からアドバイスをもらってもどの扉がよいのかという悩みは消えなかったと思うし、あのとき悩んだことはすごく貴重なことであり、ある意味覚悟にもつながったと思う。
子供は子供で、スポーツが好きな子は海外のサッカー中継を見ているだろうし、ソーシャルゲームが好きな子は英語でゲームをやるだろうし、物語が好きな子は図書館に行って英語の小説を借りてきて読んでいるだろうし、そこにあまり積極的な介入はしなくてもよいだろう。
ただ、どういう扉があるか示してあげること、英語ができることによってどういう自分になれるのか、どう楽しめるのか、どう人を助けられるのかを教えてあげることは必要だ。私たち世代以上に今は扉がたくさんあるし情報があふれているので、沈没せず衝突しないように情報の海を自分で航海できるよう導いてあげることは、ますます重要になってくる。
外国語習得は身体的な学び

算数や社会などと違って外国語習得は極めて身体的な学びである。これは私の学問的根拠のない持論なのだが、スポーツや楽器とほとんど一緒だといえる。ベンチプレスでフォームを間違えば、場合によっては腱や靭帯を傷つけて大けがをする危険性があるし、少なくとも自分が強化したいと思っている筋肉に負荷は伝わらない。楽器もまったく一緒である。私は子供の頃フルートを吹いていたのだが、唇で形(アンブシュール)を作って細い入り口から空気を出さないといけない。人はそれぞれ唇の形が異なりこの辺りは筋肉も複雑なのだが、一定の空圧を絶えずある一方向に出さないとフルートの音は出ず、優れた音を作ることもできない。間違ったフォームのアンブシュールを身に付けてしまうと、いくら譜が読めていくら複雑な曲が吹けてもだめなのだ。
このように、身体的な反復練習ということが外国語においても非常に重要だと思う。思考を深めていくことと同時に、きちんとした型を示すことができる師範が最も求められているわけで、基礎的な英語能力、発音を含めて、教える資格のある人が教えるべきだ。だから、担任と専門教員やALTとのチーム・ティーチングであるとか、先生たちの中でどのようにカリキュラムを組み立てるか、組み替えるかというのがやはり重要になってくる。そこで初級英語に触れた子供たちが、中学校、高等学校へ行ったときには取り返しがつかないことになってしまう、あるいは完全に脱輪をして英語アレルギーになってしまうリスクがあるわけだから。
外国語学習でいうところの「フォーム」は、最終的に目指す成果によっても違うと思うが、私としては、言葉というのは透明なガラス1枚のようにすることが理想である。レースカーテンでも外の木々の樹形がわかるし隣の建物の輪郭はわかるが、向こう側に人が立っていても表情は読めない。言葉というのは、自分のその時の目的や相手によっては曇らせることもできるしそれも大切な能力だとは思う。日本語でいえば、敬語を使って距離を作ったり、あるいは敬語を取り払って相手をぐっと懐に引き込んだり。ただ、できるだけガラス板のような、水のようなものにしていくのがやはり私としては基本なのである。雑味を削り取って削り取っていく精米のように、あるいはレースカーテンのレースを取っ払うように。相手に言語が道具だと意識させることがマイナスだと思うので、まずはそこを目指す。
このように考えるならば、「フォーム」として発音はとても大事だ。発音だけでなく、間の取り方など音声的な文の運び、音を含めた談話の仕方というのは、構文や単語と同等に重要だと思う。
もう一つは、豊かに記述された英語を読むことによって間違いなく自分の話し言葉が豊かになるということがいえる。私自身、日本語が読めるようになってからいろんな人の日本語を読むことによって、自分の語る日本語に奥行きが生まれていったという過程(今でもその過程だと思うが)ははっきりと思い出せる。このような体験をぜひこれからの子供たちにも味わわせてあげてほしいと願っている。
(談)
Profile

ニューヨーク市生まれ。カリフォルニア大学バークレー校卒業。ハーバード大学大学院東アジア言語文化学科博士課程修了、文学博士。1985年に九州大学文学部研究生として来日。同学部専任講師、国立・国文学研究資料館助教授を経て、2000年に東京大学大学院総合文化研究科助教授に就任。2007年から同研究科教授。2017年4月に国文学研究資料館館長就任。2017年から文部科学省中央教育審議会教育課程部会委員。2021年4月から現職。近世・近代日本文学が専門で、とくに19世紀(江戸後期〜明治前半)の漢文学と、それに繫がる文芸ジャンル、芸術、メディア、思想などに関心を寄せている。テレビでMCやニュース・コメンテーター等をつとめる一方、新聞・雑誌連載、書評、ラジオ番組企画・出演など、さまざまなメディアで活躍中。