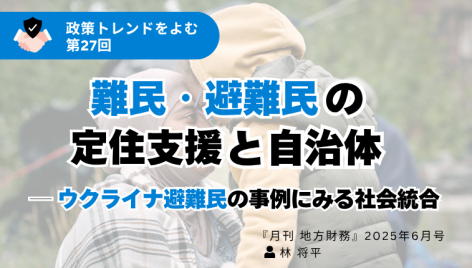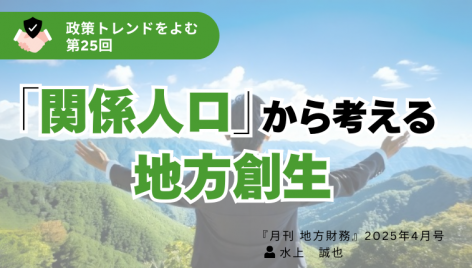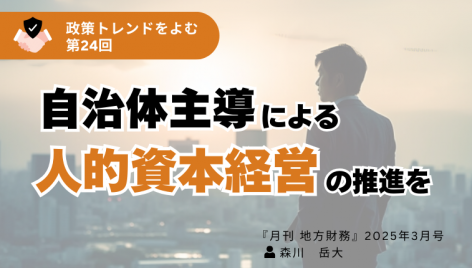政策トレンドをよむ
都道府県や地方公共団体と大学の連携 ― 大学視点の背景認識|政策トレンドをよむ 第30回
地方自治
2025.10.07
目次

この記事は4分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊 地方財務』2025年9月号
★「政策トレンドをよむ」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年9月号
特集:過疎対策のまがり角―計画見直しを見据えて」
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,870 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【政策トレンドをよむ 第30回】
都道府県や地方公共団体と大学の連携 ― 大学視点の背景認識
EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部
ガバメントパブリックセクター
マネージャー
郷田 秀樹
※2025年8月時点の内容です。
都道府県や地方公共団体と大学が連携して地域の活性化を推し進めることは、大学の保有する貴重な知的・人的資源をより効果的に活用するという観点で期待されている。特に近年では厳しい地方財政、少子高齢化といった基本的な課題に加えて産業衰退、環境問題など、地域が直面する課題は多様かつ複雑化しており、これらの課題解決に向けてはより多くの知を集結して課題に向き合うことが求められる。実際に2024年に内閣府により実施された「地域における産官学連携の取組等に関する調査」では、アンケート対象とした都道府県・地方公共団体の約70%が大学と連携した産業創生に係る予算事業を保有しており、その注目度の高さが伺われる。
本稿では都道府県や地方公共団体と大学との連携について、相手方である大学側の視点で連携に関する背景を整理することで、今後連携を企画・推進する上で参考となる情報を提供できればと考える。
大学がこのような連携を模索する背景は大きく4つあると考えられる。1つ目が大学に対する、地域貢献や社会的責任が強化されていることである。これは近年の社会的な風潮だけでなく、実際に文部科学省による大学評価にも反映されている。例えば大学評価を申請する大学の「点検・評価項目」の中に、基準9として社会連携・社会貢献の項目が挙げられていることからもその重要性がうかがえる。本基準では大学は、その知的資源をもって学外の教育研究機関、企業その他の団体、地域社会等との連携を推進する必要があること、大学が生み出す知識、技術等を社会に有効に還元するシステムを構築し、社会に貢献することが必要であることが記載されている。
2つ目は研究の社会実装、その実証機会の場としての地域への期待である。研究成果の社会実装は研究の価値を実社会で証明するという研究の実行面だけでなく、研究資金の獲得という観点でも重要である。研究成果の社会実装を求めている競争的資金も多く、社会実装の検討は研究者にとっては研究を継続的に推進するための取り組みの1つとなっている。このような傾向は第4期科学技術基本計画で社会実装に関する記載がなされるようになってから継続的に続いており、実証の場としての地域への期待は高いと考えられる。
3つ目は学生の地域定着・就職支援の観点である。少子化により大学間の学生獲得競争が激化する中、地方大学の生き残り戦略の1つとして、地域に根ざした人材育成と定着が重要なミッションとなっている。また、文部科学省では、総務省と連携して地域の中核として高度化を担う科学技術分野の人材養成が必要との課題感のもと、地域と大学等が一体となって分野横断的に課題解決に挑む地域人材の育成を目的とした地域活性化人材育成事業を展開。このような事業を通じて地方公共団体と地方大学の連携を支援している。
4つ目は財政的な側面である。大学の法人化以降その基盤的経費である運営費交付金は削減傾向にあるとともに、令和元年度予算からその一部を成果や実績をもとに評価し分配する「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の仕組みが導入されている。運営費交付金の削減分を埋める施策の1つとして、大学は企業との共同研究等による外部資金の獲得を目指している。企業にとって、前述の地域を巻き込んだ社会実装の場は多くの場合魅力的であり、大学にとっても外部資金獲得の貴重な機会となりうる。また評価指標の中には常勤教員当たり受託・共同研究等受入額や常勤教員当たり科研費獲得額・件数も含まれており、大学として高い評価を獲得する観点からも、地元企業や地方公共団体との連携はメリットがある。
これらの背景を踏まえ、地方公共団体が、具体的に大学との連携を企画・推進する際の考慮事項を以下に述べたい。まずは目的のすり合わせである。多くの場合行政側は即効性や実務を重視する一方で、大学は教育・研究重視の傾向があり、目的のすり合わせが必要となる。また目的のすり合わせに向けては大学側が上述の4つの背景の内どこに比重を置いているのか理解することが肝要であると考える。次に目標の設定である。目標の中に大学評価の指標と関連する具体的な数値目標がある方が、大学側にとっては望ましいことを考慮すべきと考える。最後に時間軸と体制面の検討である。地域課題に即した研究は長期的視点が必要であり、教員の移動などにより連携が途切れないような工夫や実証フェーズごとに例えば民間企業も巻き込んだ実証体制の方が有効となるケースがあること等を考慮した体制構築が求められる。
より円滑に連携を推進するための工夫としては、地方公共団体の職員を大学に派遣し大学側の事情に精通した人材を育成することが挙げられる。前述の内閣府によるアンケート結果には、職員の派遣は、技術シーズの把握、政策課題と研究者のマッチング等に効果があったことが記載されている。また、地域の抱える課題は複雑であり、1つの大学にシーズを求めてもマッチングしないケースが想定される。例えば、複数の大学が連名で参画している組織の「大学等連携推進法人」等を対象に、より面を広げた連携を検討することも有効な手段であると考えられる。
#1:責任ある研究活動支援 ~大学・研究機関のガバナンスの強化に向けて
https://www.ey.com/ja_jp//industries/government-public-sector/responsible-conduct-of-research
#3:イノベーション・科学技術政策策定・事業運営支援
https://www.ey.com/ja_jp/industries/government-public-sector/science-technology-and-innovation-policies
#4:起業家・スタートアップ支援
https://www.ey.com/ja_jp/industries/government-public-sector/support-for-entrepreneurs-and-startups
★「政策トレンドをよむ」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年9月号
特集:過疎対策のまがり角―計画見直しを見据えて
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,870 円(税込み)
詳細はこちら ≫