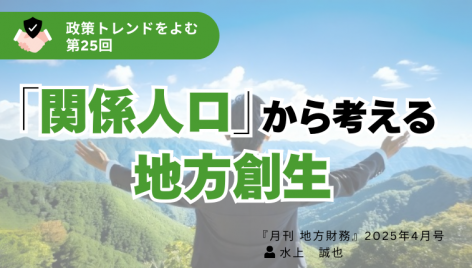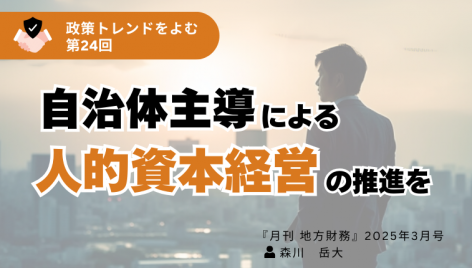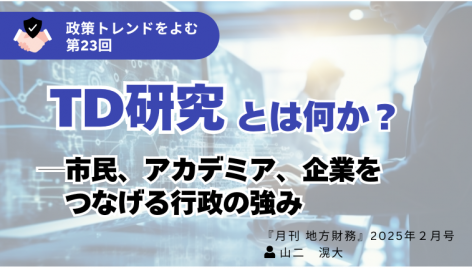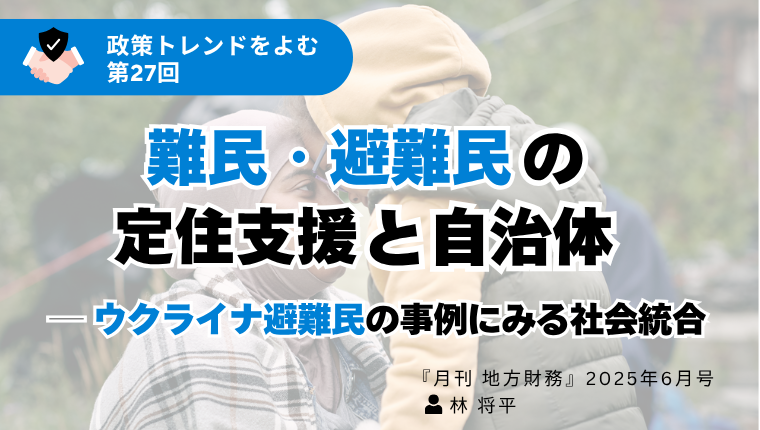
政策トレンドをよむ
難民・避難民の定住支援と自治体 ― ウクライナ避難民の事例にみる社会統合|政策トレンドをよむ 第27回
地方自治
2025.07.10
目次

この記事は4分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊 地方財務』2025年6月号
★「政策トレンドをよむ」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
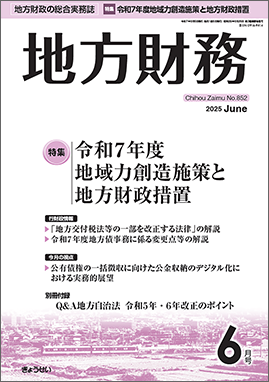
月刊 地方財務 2025年6月号
特集:令和7年度地域力創造施策と地方財政措置
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:2,750 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【政策トレンドをよむ 第27回】
難民・避難民の定住支援と自治体 ― ウクライナ避難民の事例にみる社会統合
EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部
コンサルタント
林 将平
※2025年5月時点の内容です。
2023年末時点で、紛争や迫害により故郷を追われた人々は1億1730万人を超え、難民・避難民等の数は12年連続で増加している。日本は1981年に難民条約へ加入し、インドシナ難民の受入れを契機に、第三国定住などの支援枠組みを拡充してきた。2023年には、条約難民に該当しないものの保護を要する外国人を「補完的保護対象者」として保護する制度が創設され、2024年にはウクライナ避難民等1661人がこの制度により保護された。今後、人道的理由で来日する外国人の増加が見込まれる中、定住支援を担う自治体の役割は一層重要性を増す。本稿では、ウクライナ避難民の受入事例から自治体が直面する課題と対応策を考察し、実務に携わる自治体職員の方々に有益な知見を提供する。
日本におけるウクライナ避難民の受入れは、2022年3月2日の岸田文雄首相(当時)による受入表明以降、今年3月末までに2768人が来日。約2000人のウクライナ避難民に住環境整備費を給付してきた日本財団は、避難民を対象とした国内最大規模の実態調査を踏まえ、人道的な背景で来日した外国人が日本で共生・活躍できるようにする支援制度の提言を発表した。提案書では、難民・避難民等の統合プロセスを「Arrival(来日直後)」「Settlement(生活基盤づくり)」「Integration(社会統合)」の3段階に分類し、各フェーズの課題を明らかにしている。Arrivalにおける主な課題は、身元保証人への依存である。約8割が個人保証人に頼っており、その多くがSNS等で知り合った面識のない人物であることから、トラブルに発展した例も散見される。Settlementでは、公的住宅や日本語教育などの支援は受けているが、就労、交流、医療・福祉などの分野では依然として支援ニーズが高い。避難体験に起因する精神的ストレスも深刻で、不眠に悩む人が7割、子どもの2割が不安感を訴えるなど、メンタルヘルス支援が求められる。Integrationでは、日本語教育体制は自治体間で差があり、保証人の有無によって格差も生じている。ボランティア主体の教室では十分な学習機会が得られず、言語力不足が職業マッチングの障壁となっている。日本財団は、全3フェーズに共通する重要な工夫点として、以下の4点を提案している。
1 日本人の外国人理解の促進
学校教育や地域イベントなどを通じた啓発活動により、外国人への偏見や誤解の解消が求められる。
2 関係者間のネットワーク形成と支援者の育成
行政、NPO、企業等の関係者が連携し、情報共有や相互研修で支援の質と持続性を高める必要がある。
3 共助コミュニティの育成と外国人の支援者化
外国人自身が地域社会で支援者として活躍することにより、相互理解と地域の一体感が促進される。
4 デジタル技術の活用
多言語対応の情報発信ツールやオンライン相談窓口の整備など、言語・地理的障壁を越えた支援提供が可能になる。
4つの工夫点を横断的に実施することにより、個々の避難民の実情に合わせた、切れ目のない支援を提供できる。
最後に、これらの工夫点を組み込んだ受入れを行う自治体として、名古屋市と佐賀県を紹介する。名古屋市では、ウクライナ人コミュニティ、災害支援NPOレスキューストックヤード(RSY)と連携し、「あいち・なごやウクライナ避難者支援ネットワーク」を設立した。行政・NPO・当事者団体の3者が週に1度の連絡会議を実施し、役割分担と情報共有を行っている。さらに、名古屋市からRSYへ状況調査票の個票の作成を委託しており、個別ニーズに応じた支援を提供している。佐賀県では、佐賀市、認定NPO法人地球市民の会、佐賀県国際交流協会が「オール佐賀」で連携し、来日直後から地域における社会統合を一貫してサポートしている。役割分担としては、地球市民の会が来日前面談や国際移動の手配等を行い、佐賀県国際交流協会が生活全般の支援を実施。佐賀県は全体的なサポートを行い、佐賀市は学校の入学手続きや就労支援などに取り組む。定期的に連絡会議を開き、情報共有と支援の検討を行っている。両自治体の取り組みは、行政、NPO等の関係者の緊密な連携体制を構築することで、個々の避難民のニーズを的確に把握・情報共有し、来日から社会統合までを一気通貫で支える優良事例である。
ウクライナ避難民の支援事例は、難民や避難民のみならず、今後の外国人定住支援のあり方を考えるうえで多くの示唆を与えている。また、難民・避難民等の受入れは、人道的責務にとどまらず、地域の持続可能性を支える戦略ともなり得る。自治体の果たす役割は、さらに重要になるだろう。
〔参考文献〕
(1)国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)「グローバル・トレンズ・レポート2023(Global Trends 2023)」(2024年6月)
(2)出入国在留管理庁「令和4年における難民認定者数等について」(2023年3月)
(3)出入国在留管理庁「補完的保護制度について」(2023年12月)
(4)日本財団「ウクライナ避難民支援の現状報告および避難民等の共生・活躍のための支援制度に関する提案書」(2023年9月)
本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。
★「政策トレンドをよむ」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
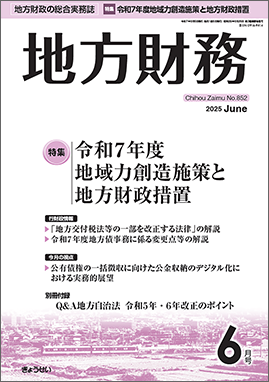
月刊 地方財務 2025年6月号
特集:令和7年度地域力創造施策と地方財政措置
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:2,750 円(税込み)
詳細はこちら ≫