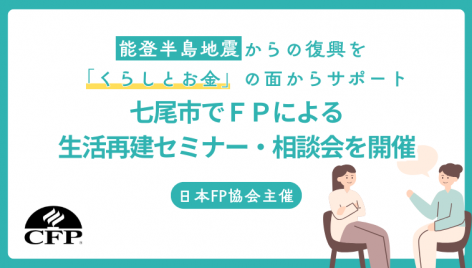『スマート防災』のススメ
【リスク管理】 大規模地震における災害弱者対策と、求められる「公助の限界」克服 山村 武彦〔防災システム研究所 所長〕
地方自治
2020.02.26
新型コロナウイルスに関連する経済への影響、イベント中止など、連日さまざまな報道が飛び交っています。もしこの局面で大地震が起きたら、特にどのような注意が必要なのでしょうか。『災害に強いまちづくりは互近助(ごきんじょ)の力~隣人と仲良くする勇気~』(ぎょうせい、2019年)の著者で、防災システム研究所 所長の山村 武彦氏は、災害弱者の側に立った生活環境の整備などの震災関連死を食い止める取り組みが重要だと説きます。ここでは、第一人者からみた感染症リスクへの対応や、国が自治体に向けて取り組むべき課題について紹介いただきます。
(本稿は2020年2月26日現在の知見・情報に基づく)

1.感染症と震災関連死
連日、新型コロナウイルスの感染情報が伝えられている今、もし大規模地震が発生したら、避難所などで多数の災害関連死が出る危険性がある。25年前の平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の時も季節性インフルエンザが蔓延していた。兵庫県の調べによれば犠牲者6,402人のうち、3か月以内に亡くなり震災関連死と認定された人は919人(14.35%)に上る。当時、震災関連死の認定基準は明確にされておらず、神戸、尼崎、西宮などの6市では認定委員会が設置され、医師や弁護士などによって判定された。
震災関連死の名付け親でもある神戸協同病院の上田耕蔵院長によれば、関連死に至った被災者は60歳以上が89.6%を占め、死亡主因別では循環器系疾患が37.9%(心疾患28.8%、脳疾患9.1%)、呼吸器系疾患35.0%(肺炎26.2%、その他の呼吸器疾患8.8%)、消化器系疾患3.6%、血液造血器疾患2.0%、自殺0.7%、既往症の悪化が21.0%であった。とくに循環器系疾患、呼吸器系疾患、既往症悪化が全体関連死の約93%を占める。その大半はインフルエンザがトリガーになったものと推定されている。
高齢者がストレスと感染症に見舞われると合併症などを発症し重篤になりやすく、せっかく震災から生き残った尊い命が無残に奪われてしまう。これからの防災・危機管理の重点課題は、関連死ゼロを目指す避難所環境の改善と共に、感染症蔓延時における避難所運営マニュアルの策定が急務だ。そして、家の安全が確保出来た元気な人は在宅避難の奨励など、事前のレクチャーと地域防災計画の見直しが迫られている。

2.避難所の良好な生活環境?
阪神・淡路大震災の16年後に発生した東日本大震災では死者・行方不明者は22,000人を超えた。そのうち3,739人(16.7%)が震災関連死と認定されている(令和元年12月27日現在・復興庁調べ)。この関連死の中には災害直後の避難所生活だけでなく、応急仮設住宅、みなし仮設など1都9県での避難所や県外滞在なども含まれている。特筆すべきは震災関連死の88%が66歳以上ということである。過酷な避難生活環境やストレスにより、高齢者などの災害弱者が次々に犠牲になるという哀しい現実である。
東日本大震災でクローズアップされた避難所等の課題を踏まえ、2年後の平成25年6月に災害対策基本法が改正され、同法86条の6で避難所における生活環境の整備などが定められ、避難所以外の場所に滞在する被災者への配慮については同法86条の7に規定された。併せて市町村(特別区を含む)等には、避難所の良好な生活環境の確保に努める取り組みを求めるにあたり「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」が策定され、より具体的対応について「避難所ガイドライン」「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」「避難所におけるトイレの確保・運営ガイドライン」が次々に作成された。
しかし、その3年後に発生した平成28年熊本地震では、地震による直接死は50人だったが、震災関連死と認定された人が220人と4倍以上にもなった。指定避難所における避難者の生活環境改善のための施設(空調・Wi-Fi・バリアフリー化に係る施設等)整備に、国は一部財政支援をしているがあまり進んでいない。とくに今後も懸念される感染症蔓延時を想定した準備が欠かせない。あるべき姿を提示することは容易だが、それを具現化させる自治体のひっ迫財政や万年人手不足状態では限界がある。そうした基礎的課題が改善されない限り、良好な避難所への生活環境改善など絵に描いた餅である。あれから9年目の今、国に求められているのは一歩踏み込んだ具体性のある自治体支援策ではなかろうか。

3.災害弱者を守る防災隣組
東日本大震災では、被災地全体死者数のうち、65歳以上の死者数が約6割。障がい者の死亡率は全体死亡率の2倍に上った。その実情を踏まえ、国は災害対策基本法を改正し「災害時避難行動要支援者名簿」策定を自治体に義務付けた。だが、その教訓はまだ充分活かされていない。
その5年後の平成30年7月豪雨(西日本豪雨)のとき、岡山県倉敷市真備町における犠牲者の約80%が件の名簿に登載されていた自力避難困難者だった。倉敷市だけでなく、自治体の多くが名簿は策定していても、個別の避難支援計画づくりは進んでいない。災害発生時、児童・民生委員、自治体職員、消防団、自主防災組織などですべての要支援者を助けることは難しい。平成30年7月豪雨では、防災拠点となる真備支所や消防署など防災関係機関までもが浸水し、過去のリスクアセスメントを超える大雨に対する「公助の限界」を露呈させた。
こうした「公助の限界」を補うには、従来の防災関係者や広い地域の「みんな」ではなく、顔の見える近くの住民同士が互いに助け合う「互近助」という考え方が重要となる。自主防災組織や町内会の中に、向こう三軒両隣で「防災隣組」をつくり、平時の見守りや発災時の安否確認及び同行避難などを担う最小コミュニティを組織し利活用すべきである。

東京都は石原慎太郎都知事の時、筆者の提言を採用し「東京防災隣組認定制度」をつくった。町会、企業、学校などそれぞれの地域や主体ごとに防災隣組を認定し、発災時に安否確認、応急対応、避難行動などが迅速にできるようにしている。
*東京防災隣組認定制度の詳細はコチラ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kyojyo/1003719/1001291/index.html
例えば、水害のおそれのある葛飾区東新小岩7丁目町会の「東京防災隣組」は、過去の水害水位表示板を設置したり、ゴムボートを自前で買っていざという時の救助訓練を行っている。東京駅周辺では、国、都、区、地域と連携した企業約80社が東京駅周辺企業防災隣組を結成し、いざという時に帰宅困難者の受け入れや情報提供などの支援訓練を続けている。こうした防災隣組の考え方がようやく各地に広まりつつある。これからは、地域特性、災害特性に合わせ、掛け声だけでなく地に足の着いた現実的な災害弱者対策を進める必要がある。

(本稿は2020年2月26日現在の知見・情報に基づく)

防災システム研究所 所長 1943年、東京都出身。新潟地震(1964)を契機に、防災・危機管理のシンクタンク「防災システム研究所」を設立。以来50年以上にわたり、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や日本各地での講演(3,000回以上)、執筆活動などを通じ、防災意識の啓発に取り組む。また、多くの企業や自治体の防災アドバイザーを歴任し、BCPマニュアルや防災マニュアルの策定など、災害に強い企業、社会、街づくりに携わる。著書は、『災害に強いまちづくりは 互近助の力 ~隣人と仲良くする勇気~』『南三陸町 屋上の円陣』『スマート防災 災害から命を守る準備と行動』(以上、ぎょうせい)、『新・人は皆「自分だけは死なない」と思っている』(宝島社)など多数。