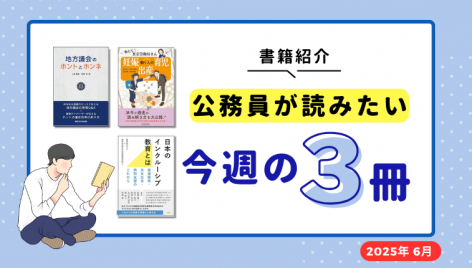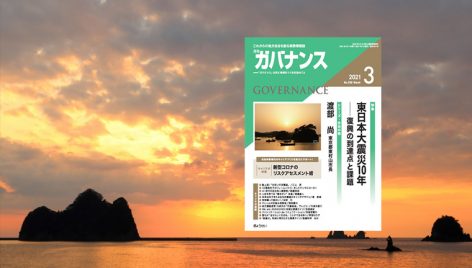自治体最新情報にアクセス DATABANK
自治体最新情報にアクセス|DATABANK2019 月刊「ガバナンス」2019年8月号
地方自治
2019.08.28
目次
自治体最新情報にアクセス DATABANK
月刊「ガバナンス」2019年8月号
博物館施設の一体運営に地方独立行政法人を設立
大阪市(270万2400人)は、4月に市立の博物館施設を一体運営する地方独立行政法人として市博物館機構を設立した。これまで指定管理者制度で運営してきた博物館施設を地方独立行政法人化することにより、柔軟で効率的・効果的な運営と経営を図っていくのがねらい。①大規模展覧会の誘致・開催等による魅力の向上、②自主性の発揮や民間等の積極活用による利用者サービスの向上、③サービス向上による増収、④業務改善サイクルの確立と成果公表による透明性の向上、⑤各館の活動成果の継承・発展及び文化資源の蓄積――が図られると期待されている。
地方独立行政法人化したのは、市立美術館、市立自然史博物館、市立東洋陶磁美術館、市立科学館、大阪歴史博物館の5館。21年度開館予定の大阪中之島美術館(近現代美術・デザイン中心の美術館)の開館準備も一体的に進めていく。理事長には西日本旅客鉄道株式会社取締役会長の真鍋精志氏が就任した。
市の16年の試算では、地方独立行政法人化による地域経済等への波及効果は10年間で約54億円、うち各館の入館料等の収入増は約13億円と見込んでいる。また、指定管理者制度下における期間の制約がなくなり、地方独立行政法人化に伴って経営と運営の一元化が実現したことから、長期的視点に立った展覧会等の企画や安定的な人材の確保が可能となった。
今後は、各館の特色を活かし、かつ、複数の施設が連携することによる相乗効果を発揮して、また、マスメディアとの連携や戦略的な広報による効果的な情報発信に努め、ミュージアムビジョンに掲げられた「都市のコアとしてのミュージアム」の実現を目指していく。
博物館・美術館の地方独立行政法人化は全国では初めての取組みとなる。
ブロックチェーン技術を活用したポータルサイトを開設
石川県加賀市(6万8000人)は、株式会社スマートバリューと共同で、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を活用した住民ID基盤「GaaS」を5月31日から稼働。同時に、利用者の属性に応じて地域サービスをマッチングさせ提供するポータルサイト「加賀POTAL」を公開した。同サイトで氏名や生年月日、興味のある分野などを入力してプロフィール登録を行うと、個人に即した行政やイベント等の情報が自動的に表示される。ブロックチェーン技術の行政サービスへの活用は全国初という。
市とスマートバリューは、「ブロックチェーン都市」の形成を宣言し、改ざんが難しく安全性が高いといわれるブロックチェーン技術とICT技術を活用した産業・雇用の創出や電子行政の推進などを展開。今後は各種行政サービスを電子化し、サイト上で受けられることを目指している。
 宮元陸市長(右)とスマートバリューの渋谷順社長
宮元陸市長(右)とスマートバリューの渋谷順社長
SNS活用のいじめ相談モデル事業を開始
山口県宇部市(16万6800人)教委は、SNSを活用したいじめ相談のモデル事業を始めた。
市立中学校の1年生全員を対象に生徒のSOSの出し方に関する教育や、脱いじめ傍観者教育を内容とする意識啓発授業を実施。匿名で報告・相談が可能なアプリ「STOPit(ストップイット)」を試験的に導入して、いじめを受けている生徒からの相談やいじめを目撃した生徒からの通報を受け付ける。
アプリで学校名と学年は分かるので、緊急性がある場合には学校に連絡することにしている。
無作為抽出の区民と区職員のワークショップを開催
東京都中野区(33万4000人)は、無作為で抽出した区民と区職員によるワークショップ、「中野の未来をともに考えよう」を実施した。
同区は現在、まちの将来像を描く新しい基本構想の策定に取り組んでいる。基本構想を区民の意見や生活実態を反映したものとするため、基本構想審議会をはじめ、区民と区長のタウンミーティングやアンケート調査を実施するなど、より広範な意見の聴取に努めているが、今回のワークショップはその一環となる新しい試み。ワークショップは2回実施され、それぞれ36人、37人の区民が参加。1回目は「自治・共生・活力」と「子育て・教育」、2回目は「健康・医療・福祉」と「都市・防災・環境」をテーマに、グループで話し合った。出された意見は、基本構想審議会に報告するなど、今後の検討材料にしていく。新たな基本構想策定は、20年7月の予定。
妊娠した人に「初たまご」をプレゼント
茨城県小美玉市(5万1700人)は、妊娠した人に「初たまご」をプレゼントする「ダイヤモンド・エッグ プレゼント事業」を実施している。
市の若手職員研修「政策形成実践研究」で提案された事業を採用したもので、妊婦にたまごをプレゼントするのは全国初。同市が鶏卵の産出額が全国一であることを広くPRするとともに、生まれてくる新生児に祝福と、同市に生まれてきた感謝の気持ちを伝えることが目的。
初たまごとは、産卵を始めた鶏が1か月以内に産んだ卵のこと。昔から「出産を控えた人が初たまごを食べると安産になる」という言い伝えがあり、現在でも縁起物として重宝されているという。初たまごは、ひなの時から蓄えてきた栄養素を凝縮しており、小ぶりで殻が固く、濃厚な味が特徴。市の名前からイメージされる「小さく美しい玉」を宝石の王様であるダイヤモンドに見立てて、市産の初たまごを「ダイヤモンド・エッグ」と名づけ、元気で「玉」のような子どもの誕生を願い、プレゼントすることにした。
母子健康手帳の交付を受けた人が、申請窓口で引換券をもらい、市の施設「空のえき そ・ら・ら」で初たまご約30個を受け取ることができる。
ベイスターズとの協力で「家事シェアシート」を配布
横浜市(373万7800人)は家族・パートナーと「家事シェア」について話し合い、2人の役割分担の宣言などを書き込める「家事シェアシート」を作成した。男性の家事・育児参画を進めるのがねらいで、6月の男女共同参画週間に合わせ、区役所や地域子育て支援拠点、民間の協力施設などで配布した。
シートはA3判二つ折りで、横浜DeNAベイスターズが制作に協力。監督や選手が写真入りで登場し、自ら実践する家事シェアなどを紹介している。また、「パラレル家事」「家事の断捨離」など家事シェアのヒントも掲載。そのうえで「月に一度家事フリーデーを作る」など新しい具体的なチャレンジを2人の署名入りで宣言するページを設けた。シートは市のHPからダウンロードできる。

「外国人材受入れの法務・労務のポイント」セミナーを開催
2019年7月2日と9日、都内で「外国人材受入れの法務・労務のポイント」セミナーが開催された。4月から施行された改正入管法を受け、在留資格制度や外国人材受入れ制度についての変更点や注意点を中心に解説。企業や外国人材登録支援機関、自治体の関係者など2日間で延べ200人が参加した。
講師は、『改正入管法対応 外国人材受入れガイドブック』(ぎょうせい)の著者で、外国人材受入れに関して現場での助言などを行っている弁護士の杉田昌平氏。杉田氏は、はじめに技能実習生の脱走など最近の問題に触れ、「外国人材を共に成長していく仲間として受け入れることが重要だ」と述べた。
セミナーは2部制で、1部は出入国関連法令についての解説。改正法によって新設された「特定技能」を含む個別の在留資格について詳細に説明した。また、高度専門職を取得する際、19年3月末から優遇対象の大学が13校から114校に拡大することもあわせて紹介。杉田氏は、「地方の大学に枠を広げ、留学生が地元で就職しやすくする措置」とその意義を強調した。
2部では労働関係法令(労働基準法、労働契約法等)に関する解説。日本人と同様に労働関係法令が適用されることを踏まえ、採用時や勤務時の注意点などを説明した。その後、質疑応答が行われ、「基本給はいくらが妥当か?」「繁忙期に内勤人材を現場に派遣するのは違法か?」といった具体的な質問が殺到し、実務面での関心の高さをうかがわせた。

(月刊「ガバナンス」2019年8月号・DATA BANK2019より抜粋)