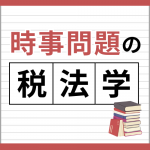時事問題の税法学
時事問題の税法学 第36回 電子マネー
地方自治
2019.08.29
時事問題の税法学 第36回
電子マネー
(『税』2018年10月号)
現金不要の時代

レジなどで釣り銭が出ないように1円単位までキッチリ支払うのを目にする。それに対して、財布から紙幣を無造作に取り出す人も少なくない。こんな行為は老化につながるといわれたことがあったので、やはり無頓着に小銭入れが膨らむことには、用心しなければいけない。もっとも電子マネーを利用することでさらに老化の危険度が増す恐れがあるだろうか。
都市部で電車による通勤通学をするために定期券を購入している人は、鉄道系電子マネーとセットになったICカードを保持している。定期券を持っていなくても無記名の電子マネーのICカードやクレジットカード付の電子マネーを持って、電車やバスを利用することは定着してきている。全ての機能をスマホにインストールしている若い世代もかなり見かける。
若者に限らず愛知県名古屋市では、65歳以上が対象となり、市営地下鉄・バスが無料で利用できる敬老パスは、マナカという市営地下鉄をメインとする鉄道系電子マネーにセットされている。市営の交通機関は無料であるが、電子マネーに入金しておけば、他の鉄道線は切符を購入することなく、電子マネーで支払い、改札口を通過できる。つまり鉄道系電子マネーは全国共通であり、ほとんどの交通機関を、いわばチケットレスで利用できる。
もちろん電子マネーの活用は、チケット購入だけではない。コンビニなど全国展開しているチェーン店では当然、利用できる。ただ車社会の地域では、鉄道系が中心となっている電子マネーの普及は遅れているような気もする。
首都圏の私鉄沿線では小規模な飲食店でも電子マネーが利用できる店舗もでてきた。やはりサラリーマン客が多ければ、需要が大きい。しかし、手数料としてクレジットカードの手数料並みの金額を店舗が負担するため、零細な商売では及び腰かもしれない。いまでも歓楽街では、クレジットカード利用客には、手数料を上乗せして請求する悪質極まりない店がある。わが国でクレジットカードが普及していないのは、現金主義的な利用者のポリシーもあるが、諸外国に比べ、カード会社の高額な手数料を指摘した識者の発言を聞いたことがある。
SFのような管理社会

少額取引が多い電子マネー決済では、手数料を加算するような阿漕な商売はできない。携帯電話料金のように政府主導で値下げを推進する手法も疑問があるが、手数料問題は電子マネーの普及に影響を及ぼしているはずである。
そんなおり、「決済電子化で税優遇」「政府検討、QRなど導入促す」「利便性向上、海外が先行」という報道がでた(日経新聞8月21日)。
それによれば、「政府はモノやサービスの決済の電子化(キャッシュレス化)を進めるための支援に乗り出す。スマートフォンで読み取るQRコードを使った決済基盤を提供する事業者に補助金を供与し、中小の小売店には決済額に応じて時限的な税制優遇を検討する。急速なIT(情報技術)の進化により、世界的な決済手段の標準となりつつあるキャッシュレスで日本は出遅れている。政府は消費者の利便性や企業の生産性向上につなげるため、普及を後押しする」としている。
やはり、「経済産業省の調査によると、クレジットカード決済を導入しない理由について、42%の企業が手数料の高さをあげる」というわけで、「政府はQRコードの表示などキャッシュレス決済を新たに導入する企業を対象に、一定期間は減税する仕組みを検討する。小売店や飲食店の手数料負担を抑え、2020年の東京五輪までの普及に弾みをつける」という。
キャッシュレス決済といっても、最終的には各自の銀行口座で出納される。今後、銀行口座とマイナンバーの突合により、国内における資金の動きは、全て政府に捕捉される可能性が高い。このことは、防犯カメラのプライバシー侵害論と同じように、真っ当な生活をしている庶民には、痛痒は感じないといっていいだろうか。少なくとも未来は、SF映画と同様に管理社会となることは間違いない。