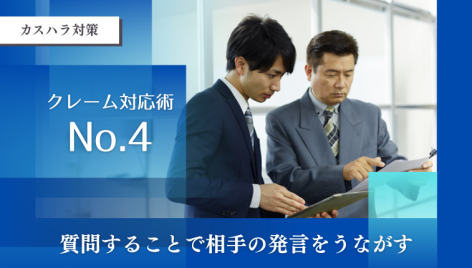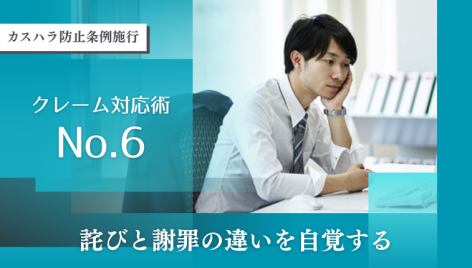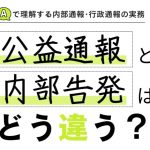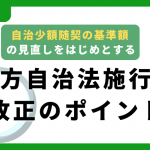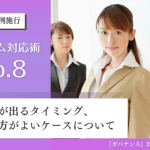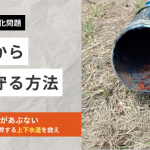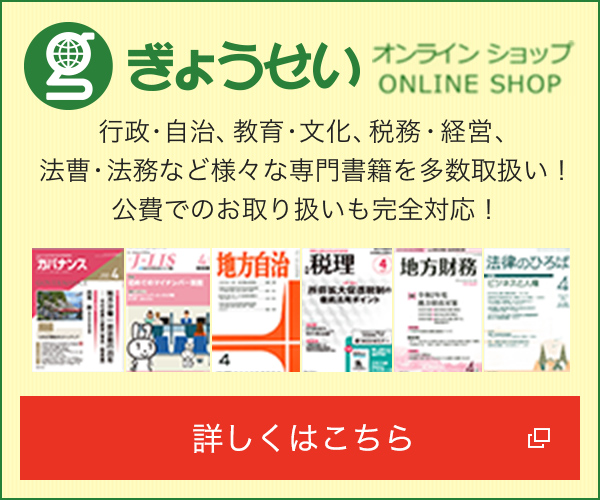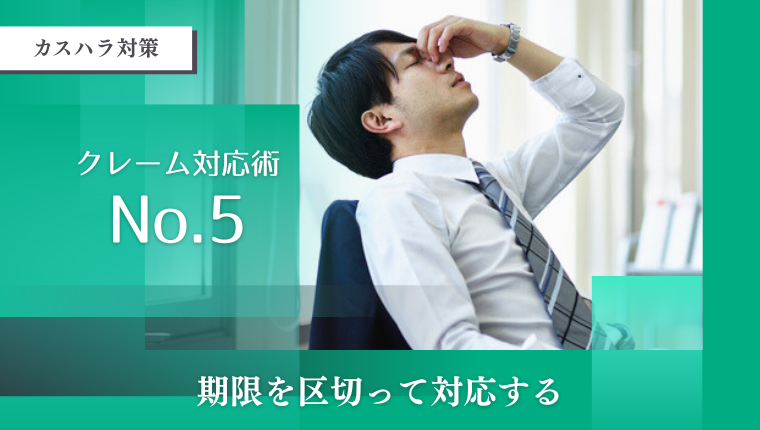
クレーム対応術
期限を区切って対応する|クレーム対応術5【カスハラ対策】
キャリア
2025.03.21

この記事は5分くらいで読めます。

出典書籍:『ガバナンス』2014年8月号
今さら聞けないクレーム対応術 5
『話が長いお客さまに対し、どうやって話を切り上げればいいの?』 /月刊ガバナンス 2014年8月号
2025年4月1日、東京都などで「カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例」が施行されました。
これにより、企業や自治体にも適切な対応策の整備が求められています。
本サイトでは、月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」の内容を引用して掲載。
第5回目の本記事では話が長いお客さまの切り上げ方を解説します。
カスハラ・クレーム対応の参考としてチェックしてください!
この記事で分かること
・話が長いお客様の特徴
・会話の主導権を握る方法
・話を切り上げるコツ・例文
話が長いお客さまの特徴

話が長い人には、一般的に二つの特徴がある。
一つは、話を効率的にまとめることができない人だ。同じ趣旨の話を何度も繰り返したり、さまざまな論旨を積み重ねたりする。聞く側にとってはくどい印象を受けるが、本人に悪意はない。むしろ、丁寧に説明しようとする善意から、結果的にそうなっているのだ。
二つ目は、主張したい気持ちが強すぎる場合だ。興奮により時間の感覚がなくなってしまったり、正しいことを話しているという自負から、主張することに快感を覚える人もいる。自論を展開するときには、誰でもいくらかこの傾向がある。
これらのことは、主張する立場の人が自分の考えや気持ちをわかってほしいと思うからこそである。相手方がこちらの気持ちをわかってくれていないと感じると、何とか理解してもらおうとして、ますます気分を高揚させ話が長引くことになる。したがって、この二つの事情は、聞く側の聞き取りの姿勢や聞き方の能力によっても違ってくる。
会話の主導権を握る

一方的に話をされて、こちらが会話を切り上げたくても、なかなか切り上げることができないということは、言葉を変えれば、その場のコミュニケーションが “聞いている” のではなく “聞かされている” といったニュアンスに近い場合だろう。
つまり、会話の主導権が、聞く側ではなく、クレームを言う側に握られている状況だ。
たとえ相手方の発言が長くても、いやいや聞かされているのではなく、こちらが相手方に “話をしていただいている” “聞かせていただいている” ことを意識できれば、ストレスは軽減される。つまり、会話の主導権をこちらが握り、会話をコントロールすればよい。
そのことの基本は、前回にも述べた「相づち」と「逆質問」の活用にある。
的確に相づちを打てば、的確に聞いていることをアピールできる。感情を込めて、オーバーリアクションを心がけながら相づちを打つことで、相手方の話を誘導できる。そして、時には驚きのニュアンスを入れて、より深く受け止めたことを表す。
特に、こちらが質問することで相手方は、それに答えることになる。その答えに関連して何度も質問すれば、相手方は何度も答えることになるので、質問することで会話の主導権を握ることができるわけだ。相手方に質問をさせないような雰囲気があれば、それはまだ話したい気持ちがあふれている。しばらくは相づちを打ちながら聞けばよい。
すべての会話を、始めから最後までこちらのペースで進めるには無理がある。相手方に有無を言わせずに、法律や条例、自分の権利を前面に出して会話を進めれば、相手方の感情を害することは必至である。相手方にも人格がある。少なくとも、話の内容は真摯に受け止めることが大切である。
切り上げるコツは
会話の流れをこちらが主導できれば、「では、その点については検討して、後日こちらから……」などと切り上げるチャンスをとらえやすい。しかし、クレームを言う人は、そもそも不満を持っていることが多いので、あまりに早いタイミングで切り上げようとしても、それでは納得しない。相手方が主張したい気持ちを満たすには、こちらの感覚以上に時間がかかることも現実である。
そこであえて時間をかけて対応し、相手方が主張することについて達成感、満足度を見極める。言葉は悪いが、相手方のあきらめ感を見極めるのだ。相手が主張することについて、満足している様子が見受けられたら、「わかりました。では、……させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか」などと主張して切り上げる。
この時のコツは、多少強引に言うことである。遠慮していると、先に述べたように、一方的に話をされ、聞かされるイメージになる。「ちょっと、ごめんなさい」 「本当に、すみません」 「申し訳ない」などの言葉を連発して挟む。その上で、「……ということが言いたいわけですね」 「こちらには……の事情があって……」などと、これ以上この状況を続けられないことを告げて、詫び言葉を10回くらい挟んでから会話を打ち切る。状況にもよるが、単に打ち切るよりも、できれば「再度考えて、また来てください」などと、今後のことを示すとよい。
お客さまにしてみれば、単に会話を打ち切られたのでは面白くない。しかし、こちらとしては切り上げたいのだから、多少の軋轢は仕方がないと割り切ることが大切だ。強引に、かつ丁寧な感情を込めて言葉を挟み、「では、こちらでも検討しますので……」 「○○日までに、必ずご連絡しますので……」などと、期限を区切って、後のことを約束する。その上で、とにかくこの状況を続けることができないことをアピールする。
お客さまが十分に発言されていれば、それなりに満足感もあるだろうから、あきらめてくれる可能性が高い。 お客さまがまだ言い足りないにもかかわらず、それでも話を切り上げたいときには、「……の業務があるので、あと○○分にしていただけませんか」などと、時間を区切る。
月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」を加筆修正、再構成し単行本化
クレーム対応のさまざまな悩みを解決!
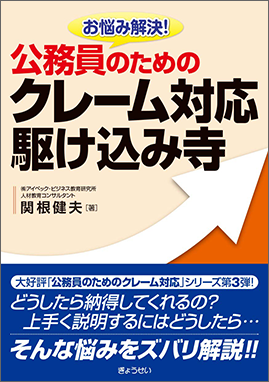
お悩み解決!
公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 編著者名:関根健夫/著
販売価格:2,420 円(税込み)
試し読みはこちら ≫
【こちらもおすすめ】
カスハラをはじめとする不当要求行為等について、実際の事例から対応を学ぶ!

自治体職員のための
不当要求行為対応ブック
-事例からわかるトラブル回避策- 編著者名:宇都木法律事務所(代表弁護士 宇都木 寧)
販売価格:3,080 円(税込み)
試し読みはこちら ≫
次のページ ≫ 【コラム】「今度は自分かも」という危機感を持つ