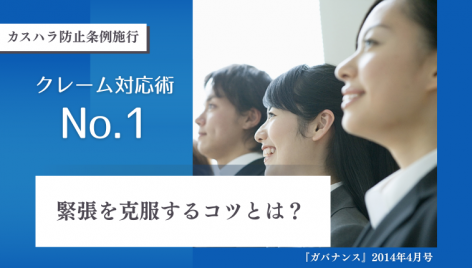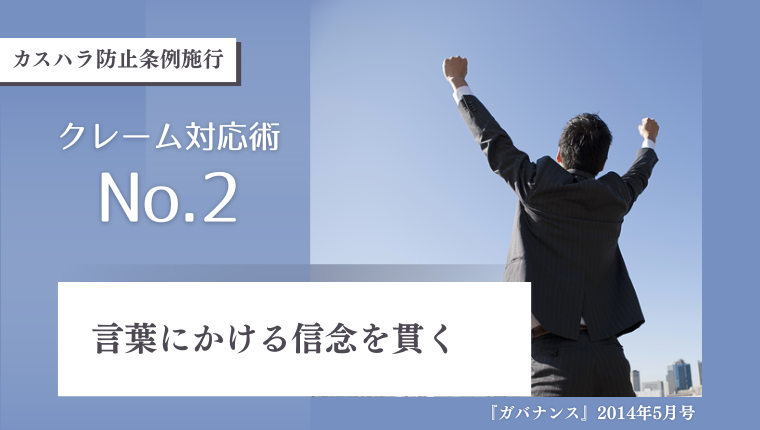
クレーム対応術
言葉にかける信念を貫く|クレーム対応術2【カスハラ対策】
キャリア
2025.03.21
【コラム】クレームは生きた学習材料

クレームは、いつ、誰から、どんな内容が、どのように持ち込まれるかわからない。したがって、予定して万全の準備を整えること は難しい。
しかし、まったく準備ができないかというと、そうではない。クレーム対応の実績を次につなげる努力をすることが大切だ。
同じ組織でありながら、その時々や対応者によって説明内容や結論、条件が違ってしまっては、そのこと自体が不審を招く。お客さまにも公平性が保てないし、ときには社会的正義に反することにもなる。
したがって、クレームに対応して一定の結論を得たら、それを記録として残すことが大切だ。いつ、どこで、どんなことが起きたのか。 その事実について、お客さまの言い分、要求は何か。そのお客さまには、どんな事情があるのか。そのことで当方は、誰が、どんな説 明をしたか。どんな条件を認め、どんな条件は断ったのか。結果として、どんな結論に落ち着いたのか、などを記録する。
大切なことは、その記録を職員が共有し、組織としての経験として活用されているかどうかだ。同じような人、案件はまた来るかもしれない。その緊張感をもって、部課ごとに職員全員が参加して、事例研究会議を定期的に開くことが大切だ。一部の企業では、これを1日に何度も開くという。それだけクレームに問題意識を持っているのだ。自治体でも、月に数回は行ってほしいし、長年続けて習慣化することをお勧めする。その積み重ねが組織の危機感、一体感を醸成する。クレームに強い組織づくりの第一歩といえるだろう。
月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」を加筆修正、再構成し単行本化
クレーム対応のさまざまな悩みを解決!
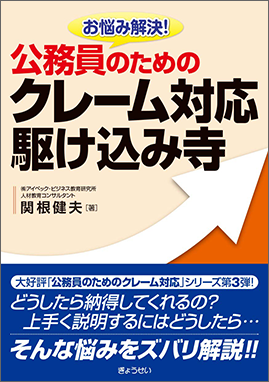
お悩み解決!
公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 編著者名:関根健夫/著
販売価格:2,420 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【こちらもおすすめ】
弁護士が相談を受けた“現場の困った”要求にどう対応するか(業界別に)分かる!!

Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック
-平時の備えと有事の対応- 編著者名:日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会
販売価格:3,630 円(税込み)
詳細はこちら ≫
カスハラをはじめとする不当要求行為等について、実際の事例から対応を学ぶ!

自治体職員のための
不当要求行為対応ブック
-事例からわかるトラブル回避策- 編著者名:宇都木法律事務所(代表弁護士 宇都木 寧)
販売価格:3,080 円(税込み)
詳細はこちら ≫