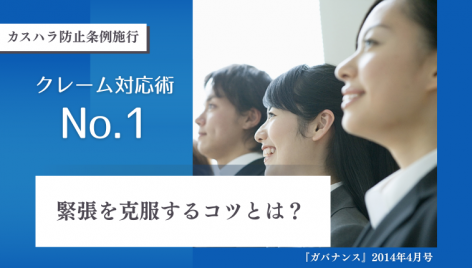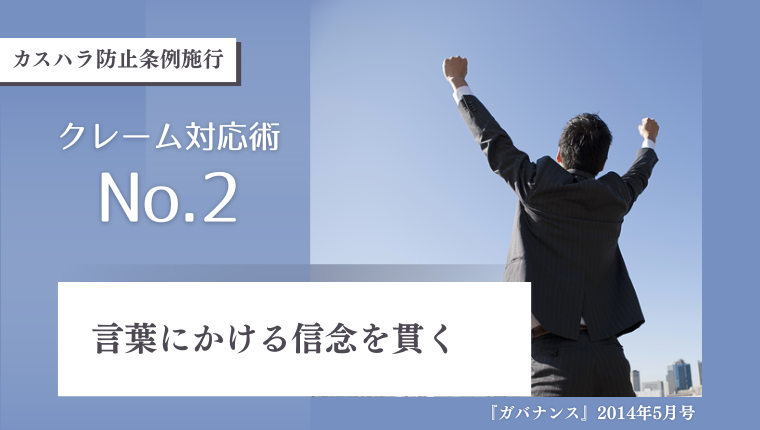
クレーム対応術
言葉にかける信念を貫く|クレーム対応術2【カスハラ対策】
キャリア
2025.03.21

この記事は5分くらいで読めます。

出典書籍:『ガバナンス』2014年5月号
今さら聞けないクレーム対応術 2
『「お客さま」「ありがとうございます」と言ったら、叱られました……』 /月刊ガバナンス 2014年5月号
2025年4月1日、東京都などで「カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例」が施行されました。
これにより、企業や自治体にも適切な対応策の整備が求められています。
本サイトでは、月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」の内容を引用して掲載。
第2回目の本記事では言葉遣いについてクレームを言われた時の対応を解説します。
カスハラ・クレーム対応の参考としてチェックしてください!
この記事で分かること
・言葉遣いを指摘されたクレームの事例
・「お客さまと呼ぶな」と怒られた時の対応・例文
・「申し訳ございません」以外の伝え方
・「確認します」以外の伝え方
・クレームに強い組織づくりの方法
結構気になる言葉づかい

日常の生活では、たった一言の言葉づかいから、その場の人間関係、コミュニケーションのあり方が変わってしまうことがあるものだ。このことは、クレーム対応に限ったことではない。
それはなぜか。人は言葉を使って物事を考え、自分の意思を表現する。反対に、言葉を使わなければ考えることも、自分を表現することもできない。すなわち、言葉は “その人そのもの” ということができる。お互いにそれを知っているからこそ、言葉づかいが気になるのだろう。
適切な言葉づかいは、場面や話す相手によって変わる。庶民的な会話を好む人たち同士が、たわいない会話をする場面で、堅苦しい敬語でばかり話していては、周囲の人は気が詰まるばかりである。反対に、相手方に迷惑をかけているような状況で、こちらが説明責任を負っているような場面では、それなりの言葉を選ばなければ、相手方にさらに不快感を与えることになるだろう。
こうした傾向は、知識や学歴の問題ではない。むしろ、周囲への心配りがあるかないかだ。少しばかり偏向した自尊心を持っていることなどから、相手方に不快感を与えてしまうことも少なくない。
言葉は万能ではない
本誌読者の皆さんは、クレーム対応でお客さまに対してため口を叩くとか、攻撃的な言葉をあえて使うといったことはないと思われる。しかし、こちらは誠心誠意をもって言葉を選んで、常識的な敬語、丁寧な言葉づかいをしているにもかかわらず、お客さまを不快にさせてしまうことがある。
・窓口で「お客さま」と呼びかけたところ、「役所に来る人は『お客さま』ではない」などとクレームを受けた。 ・「『お客さま』と呼ぶのは失礼だ」とクレームを受けたので、「○○さま」と呼んだら「名前を呼ぶな」と叱られた。 ・帰りがけに「ありがとうございます」と声をかけたら、「こちらは来たくて来たのではない」と皮肉を言われた。 ・「少々おまちください」と言ったら、「俺に命令する気か」と怒られた。
以上は、筆者が自治体職員の方々から受けた相談の一部である。言葉が相手に何をイメージさせるかは、相手の問題でもある。したがって、これらの事例からいえることは、言葉は万能ではないということだ。
言葉は記号である
言葉は、二つのことを表す記号である。第一に、どういう気持ちでその言葉を発したかの感情。第二に、意味、内容である。
人を呼ぶときに「○○さま」「お客さま」と呼びかけても、「おい」「お前」と呼んでも、相手を呼んでいるという意味は通じる。しかし、前者は尊敬の念を感じるが、後者はそれを感じない人が多いだろう。役所の窓口では、常識的に後者は使わない。しかし前述のとおり、友人同士での会話など、状況によっては後者を使うこともある。
そうなると、言葉の選択は、基本的に広いことに優位性があると言わざるを得ない。言葉が記号であり万能ではない以上、例えば、こちらが「○○さん」と呼んで相手に叱られたら、「不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。この後は『お客さま』と呼ばせていただきます」などと言い直せばよい。
例えば、お詫びや謝罪の言葉でも、単に「申し訳ございません」を繰り返すのではなく、「ごめんなさい」 「失礼しました」 「ご迷惑をおかけしました」 「ご心配をおかけしました」 「お手数をおかけしました」 「只々、恥じ入るばかりでございます」 「何と申し上げてよいか、返す言葉もございません」 「心より、お詫び申し上げます」など、いろいろある。
言葉にかける信念を貫く

言葉は言霊などといわれる。その言葉にどのような思い、信念を込めたかが大切だ。
「お客さま」と呼んで叱られたら「私が『お客さま』と申しましたのは、市民の方を大切に思っている気持ちを表したかったからです。商売上の売り買いを意図したとか、媚びを売ったつもりは決してありません。不快な思いをさせたとしたら謝ります。申し訳ございません」などと、プライドを持つことだ。しかし、これを声に出すかどうかは状況によるだろう。
「ありがとうございます」なども同様だ。どういう気持ちで「ありがとうございます」と言ったのか、信念を持っていれば、そこでクレームを言われてもこちらのストレスの何割かは流せる。
そういう意味で、よほどでない限り、こんな言葉はダメだ、あるいはこれは正しいといった正解はない。あえて言うなら、漢字の熟語は要注意である。なるべく平易な表現に置き換えるとよい。
お客さまの言い分に対して「確認します」と応えると、相手方がウソを言っているかのように受け取られることがある。事務的に聞こえ、あまりいい感じを与えない。「そのようなことがあったことを、書類で確かめてまいります」などと、少し言葉を変えると印象が変わる。確認という言葉を使った本来の意味を伝えることができる。
月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」を加筆修正、再構成し単行本化
クレーム対応のさまざまな悩みを解決!
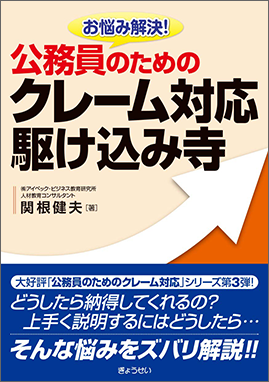
お悩み解決!
公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 編著者名:関根健夫/著
販売価格:2,420 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【こちらもおすすめ】
弁護士が相談を受けた“現場の困った”要求にどう対応するか(業界別に)分かる!!

Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック
-平時の備えと有事の対応- 編著者名:日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会
販売価格:3,630 円(税込み)
詳細はこちら ≫
カスハラをはじめとする不当要求行為等について、実際の事例から対応を学ぶ!

自治体職員のための
不当要求行為対応ブック
-事例からわかるトラブル回避策- 編著者名:宇都木法律事務所(代表弁護士 宇都木 寧)
販売価格:3,080 円(税込み)
詳細はこちら ≫
次のページ ≫ 【コラム】クレームは生きた学習材料