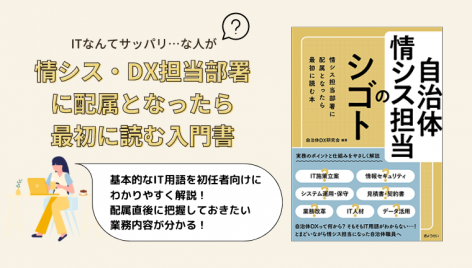政策課題への一考察
行政におけるテクノロジー活用を失敗に終わらせないために(下)|政策課題への一考察
地方自治
2020.04.04
政策課題への一考察 行政におけるテクノロジー活用を失敗に終わらせないために(下)
石井 大地(株式会社グラファー代表取締役CEO)
本記事では、前回の記事に続き、行政におけるテクノロジー活用を進める上で欠かせない、現場への導入についての考え方・原則を紹介していきたい。
1 現場に入り込み、現場から発想する
行政におけるテクノロジーの活用が、政策企画などの企画職に留まることはほとんどない。多くの場合、現場で運用を行う職員や、窓口にやってくる市民が直接テクノロジーに触れることになる。現場担当者や市民からのヒアリング、テスト運用の実施、そして何より密なコミュニケーションが不可欠なのは自明である。
しかし現実には、現場の運用に関する知識や具体的なイメージがないまま、企画・構想が先行する形でプロジェクトが動き出してしまうケースが少なくない。業務改善のためのプロジェクトが、結果的に現場に混乱をもたらしてしまうとすれば本末転倒だ。「現場は知らないが、コンセプトとしてはこんな感じ」といった抽象的な企画より、「こんな機能が1つあるだけで現場はすごく助かる!」というような実務的な要求こそが重要なのだ。
多くのITシステムに共通する真理の1つは、「一部の重要な機能が、大半の価値を生み出している」ことだ。100の機能を持つシステムであっても、そのうちほんの2~3の機能が、そのシステムがもたらす価値の大半を支配している。絶対に欠かせない重要機能のためには高いプレミアム価格を支払う顧客が存在する一方、使うか分からない機能がいくつあっても、顧客はそれに対しお金を払おうとはしないものだ。
テクノロジー活用を進めるのであれば、そのような重要機能を確実に、かつ品質の高い状態で使えるようにする必要がある。そしてこの種の判断を下すためには、現場の運用実態に明るくなければならない。キーボードの打ちやすさや、画面遷移のスピード感といった使い勝手1つで生産性やサービス品質が大きく変わる。現場を知らない企画者が考えることは、そのような細部を欠いた机上の空論になりがちだ。
システムの世界では、総論が正しくても、最終的な成果が芳しくないことが非常に多い。それは企画者の能力の問題ではなく、現場についての知識や実感の欠如によるものであり、究極的には人事・組織の問題である。現場担当者と、企画担当者のキャリアパスが別れており、前者が後者の言うことを実行する、という組織は非常に危険だ。そうではなく、企画立案をする人間こそ、現場に入って手を動かす経験をたくさん積むべきである。民間の業務用ウェブサービスの開発現場では、企画者や開発者が現場に入り込んで運用を学ぶことは常識となっている。
テクノロジー活用のプロジェクトを推進する担当者が現場の知見を十分に持っていない場合、プロジェクトの企画段階から現場担当者とのコミュニケーションを行い、必要に応じて現場常駐・現場視察を行っておくべきである。プロジェクトが動き出してから、現場で想定外の事実が次々と明るみになる、といった事態に陥ると、プロジェクトの進捗が止まってしまうことが多い。
このようなコミュニケーションが面倒だからといって安易に外注をしてしまうことは、もっとも価値ある知見を外部業者に渡してしまうことに等しい。行政サイドが外部の事業者に弱みを握られてしまうことにもなるため、重要な知識・知恵は可能な限り内部に持っておくべきだ。

2 できるだけ小さく始め、頻繁に改善する
行政におけるテクノロジーの活用は、できるだけ小さく始め、その後、段階的に規模を拡大していくことが望ましい。しかし規模を拡大するにしても、適用範囲は考えうる最小の範囲に限定する方が良い。そして、限定された範囲のなかで、できるだけ頻繁に更新・改善を行うべきだ。
「既存のシステムを全面刷新する」といった野心的なプロジェクトは高確率で失敗する。大きな組織であるほど、業務システムの刷新には長い年月がかかるものだ。筆者がかつて勤めていた上場企業でも、内部の基幹システムのリプレイスには兆円単位のコストがかかると見積もられ、古いままのシステムをなかなか刷新できないでいた。
多くの企業や官公庁が、システムをハードウェアや設備と同等の資産とみなし、「古くなったら作り直す」という考えで扱っている。まずは予算をかけてシステムを開発し、そのあとは運用保守費を払ってメンテナンスし、耐用年数が切れたら新規開発プロジェクトを動かそうとする。そのようにして立ち上がる新規プロジェクトの大半が、正確なコストを見積もることもできないまま長期化する。そうして出来上がった新しいシステムにも問題が山積みで、現場は混沌の渦に飲み込まれる。
このような状況を招く原因はただ1つ、一度開発したシステムをアップデートすることなく使い続けるという旧来型の発想だ。情報技術は日々急速に進化しており、1~2年もすれば、開発者が扱う技術は大きく変わる。今では当たり前となったパブリッククラウドやコンテナ型仮想化などの技術も、10年前はほとんど使われていなかったし、5年前でも使っているのは先進的なスタートアップ企業に限られていた。今では、大企業を含めたほとんどの企業がこうした技術を当然のように使っている。
一度開発したシステムは、使い始めた瞬間から急速に陳腐化が始まる。数年前には一般的であった技術も、現在から見ると古臭く、洗練されていないように見える。あえて厳しい言い方をすれば、継続的にアップデートすることのないシステムを使うということは、利用期間の大半にわたってレガシーシステムを使うことに等しい。
技術の陳腐化スピードがこれほど早くなっている現代では、大規模な新規開発プロジェクトでは最先端の製品は作れない、ということも生じてしまう。何しろ、開発期間が1年だとすると、開発を始めた際に念頭に置いていた「現代的な技術」が、開発が終わる1年後には古びてしまうのだ。
こうしたすべての要素を加味すると、開発プロジェクトは常に小さければ小さいほど良く、また更新サイクルは短ければ短いほど良い、という結論になる。小さく、頻繁に改善されるプロジェクトは、その時点におけるベストプラクティスをほとんどタイムラグなく反映できるため、利用者にとって使いやすいサービスを実現しやすい。数年に一度のリプレイスを繰り返すような開発方針に比べ、常に優れたものを提供し続けられる。それは、開発者のスキルや、事業者の規模、費やすコストには関係がなく、純粋に開発方針の違いがもたらす構造的な優位性なのである。

3 流行に乗るのではなく、地に足をつけて考える
これまでに提示した「凡庸な技術を適切な課題に適用する」「現場に入り込み、現場から発想する」「できるだけ小さく始め、頻繁に改善する」といった原則は、いずれも華やかな新技術の導入プロジェクトに似つかわしくないほど地味な考え方である。しかし、このような地味で退屈な考え方こそが重要なのだ。
流行はやがて過ぎ去る。一時の熱もやがては醒めてしまう。
行政サービスは、そのような一時の情勢に過度に左右されてはならず、安定的に運用され、住民のために適切に機能し続けなければならない。政治のリーダーシップは重要であるし、時代に即した改革は必要だ。しかしそのことは、流行り言葉に惑わされ、瞬間的な熱量で物事を動かすこととはまったく違う。
国民主権、住民主権の考え方が浸透したわが国では、行政サービスはすべて人々のものであり、人々のために機能しなくてはならない。テクノロジーのために人々がいるのではなく、人々のためにテクノロジーがある。
テクノロジーを正しく使いこなすためには、地に足をつけ、現場で起きている様々な課題を認識し、絡み合った糸を1つ1つほぐす努力を地道に続けていくしかない。導入した瞬間に多くの課題を一挙に解決してくれるような簡単な方法はない。テクノロジーの世界では、多くの問題を一挙に解決してくれる魔法のような手段が存在しないことをたとえて、「銀の弾丸はない」という慣用句が使われる。
一つの技術によって世の中が一変することは確かにある。しかし往々にして、その技術が登場してから、それが世界を変えたことが明らかになるためには、最低でも数十年の時間が必要だ。ある技術が「銀の弾丸」だったとしても、そのことに我々が気づくころには、その技術は既にありふれたものになっている。つまり、銀の弾丸は、弾速がとても遅いのだ。
2019年の現在、「インターネットは世界を変える」と語ることに面白味はまったくない。しかしその命題は、まさに2019年の現在こそ、明らかに真実に最も近いところにある。行政サービスのデジタル変革は、勢いや焦りで進める必要はない。信頼のおける技術を段階的に導入し、現場とのフィット感を確かめながら試行錯誤していけばよい。
あなたが「革命だ」と思う銀の弾丸が標的を撃ち抜くまでには、まだたっぷりと時間がある。
著者プロフィール
石井 大地 (株式会社グラファー代表取締役CEO)