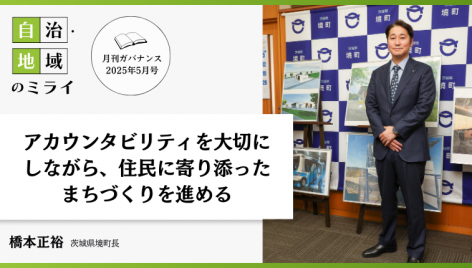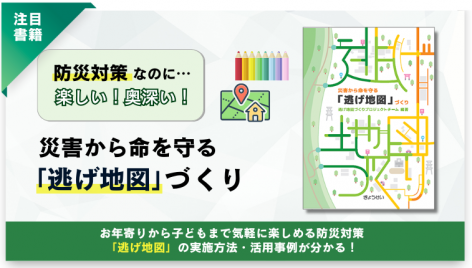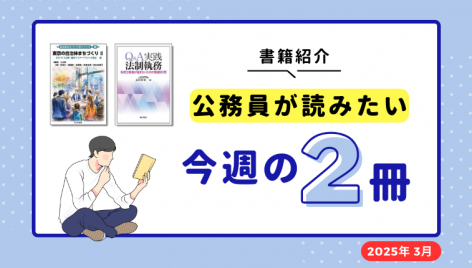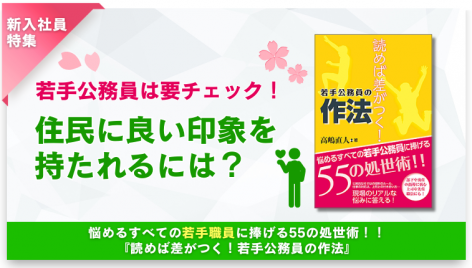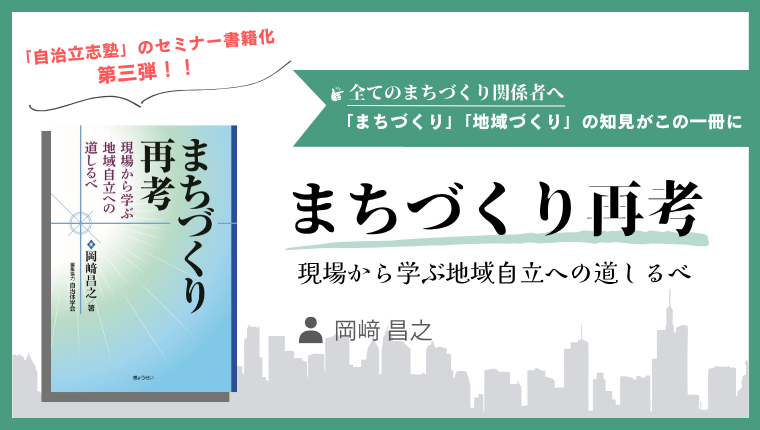
【新刊紹介】『まちづくり再考―現場から学ぶ地域自立への道しるべ』岡﨑昌之/著・自治体学会/編集協力(ぎょうせい、2019年)
地方自治
2020.01.23
まちづくり関係者必読!

まちづくり再考 ―現場から学ぶ地域自立への道しるべ 編著者名:岡﨑昌之/著、自治体学会/編集協力
販売価格:2,200 円(税込み)
ご購入はこちら ≫
自治体学会の蓄積してきた体系的叡智を次世代に引き継ぐことを目的とした「自治立志塾」のセミナーを書籍化!
西尾勝氏の『自治・分権再考』、大森彌氏の『自治体職員再論』につづく第3弾として、このほど『まちづくり再考―現場から学ぶ地域自立への道しるべ』が刊行されました。
ここでは本書第4講の冒頭をなす「1 団塊の世代とそのジュニア」の一節を抜粋してご紹介いたします。(編集部)
1 団塊の世代とそのジュニア

集落を担う団塊世代
秋田県旧阿仁町根子集落や山梨県小菅村もそうであるが、全国の農山漁村の集落、都市部の地域社会において、現在、その運営や活動の中心となっているのは、団塊世代の人たちが圧倒的に多い。彼らは現役時代の経験をフルに生かして、自治会やNPO、地域づくり組織等で中核的存在になっている。農山漁村においては、日常の農作業や季節ごとの行事、祭りなど、親から伝えられたことを受け継ぎ、これまで続いてきた集落をなんとか維持している。都市部においても、現役時代に培ったマネジメント能力や専門知識を活かして、自治会や管理組合などの運営を担っている。
福島県喜多方市旧高郷村小土山(たかさとむらこつちやま)集落も、そんな山村集落の一つである。2012年から3年間、福島県の「大学生の力を活用した集落復興支援事業」に参加して、学生たちと頻繫に通った。21世帯、72人(2012年6月)で、75歳以上が25%、90歳代も4名という高齢化した山間部の集落である。集落から下の南斜面には、ゆるやかに棚田が広がり、そのずっと遠方には、磐梯山が望める気持ちのいい集落である。季節によっては、早朝、眼下の棚田を雲海が埋め、絶景が広がる。集落の公民館に泊り、村の行事へ参加し、耕作放棄地の草刈りや雪降ろしの手伝いをし、その後の懇親会への参加を重ねるうち、学生たちも住民とずいぶん打ち解ける関係となった。集落の区長や県庁、市役所職員の支援もあり、手分けをして、ほぼ全戸を訪問し、聞き取り調査もできた。
この集落でも、区長や副区長、区長経験者、主要な役職者は、例えば役場の元収入役とか職員、農協の元幹部といった団塊の世代前後の人たちである。彼らが集落行事の中心となり、高齢者を支え、地域をとりまとめ、県庁や市役所との交渉や近隣集落との調整などにあたっている。しかし小土山集落もそうだが、こうした集落活動の中心を担う団塊の世代も、いまや70代前半となってきた。2025年にはこの世代が75歳を超え、後期高齢者となる。これまでは地域社会や集落の主要な担い手で、地域の高齢者を支えてきたが、これからは家族や地域社会の手助けを必要とする、要支援者となってくる。集落の様子は大きく変化しようとしている。

団塊世代を支える団塊世代ジュニア
そうした団塊の世代を気遣って手助けをしているのが、子ども世代のいわゆる団塊世代ジュニアたちである。ほぼ40代前半となった彼らは、親と同居している人たちもいるが、多くが育ってきた地域社会や集落を出て、20キロ、30キロと離れた地方都市に、親とは別に居住しているケースが多い。親と同居していれば当然、親や集落の支援をしている。しかし少し離れた地方都市に居住する団塊世代ジュニアたちは、週末に集落に帰り、親たちを支援している。お盆や正月には、やや長期に親元に帰り、農作業や集落の行事にも参加している。小土山集落でも、学生たちとの懇親会に集まってきてくれる若い人たちのうち何人かは、約15キロ離れた喜多方市、25キロ離れた会津若松市に、現在は住んでいるという。そこで家庭をもち、市役所や消防署、民間企業に勤め、週末や夏休み、正月に小土山に帰り、親や集落の支援をし、行事に参加すると話していた。
全国的にも、団塊世代ジュニアたちは後期高齢者直前となる親たちをみて、悩みも深い。多くは家庭を持ち、子どもの学校や病院のことも考える。結婚相手の職場のことやその親の問題もある。生まれ育った集落へ帰り、親と地域社会を守り、そこから地方都市へ通うか、それとも親を自分たちの住む地方都市へ呼び寄せて、そこでの生活に踏み切るか、気持ちが大きく揺れている。
ここ数年で団塊世代ジュニアが、全国で一斉にこの問題に直面する。とくに山間部に点在する集落、地域社会がこの時期を迎え、もし団塊世代の親も含めて地方都市への移住が進むことがあれば、山間部の集落は雪崩を打つように無住化が進むことが予想される。これまでの集落の状況は前述したように、簡単には消滅しなかったが、この団塊世代ジュニアをめぐる状況は、これまでにない厳しい状況といえる。日本の山間部の集落がどうなるか、その命運がかかった時期が間近に迫っている。

団塊世代ジュニアの地方志向
他方で、この団塊世代ジュニアが社会人となる頃に、農山漁村や地方都市に関心を持つ人たちが多くあらわれてきた。このことは、これまでの若者になかった新しい傾向である。表4―1は内閣府の調査で、都市部に住む住民に「農山漁村地域への定住願望の有無」を聞いたものである。2014年時点の30 代、40代世代、すなわち団塊世代ジュニアは、10年前の2005年の20代の頃も地方志向は高い。そして2014年調査時点でも、その志向は高いまま引き継いでいる。単なる地方指向の希望や意識だけでなく、実際に地方都市や農山漁村に移住し、そこでのNPOや地域組織に参加し、活動を担っている。そうした実例は全国にみることができる。例えば岩手県遠野市のNPO法人遠野 山・里・暮らしネットワーク(菊池新一会長)、山梨県早川町のNPO法人日本上流文化圏研究所(大倉はるみ理事長)、新潟県上越市のNPO法人かみえちご山里ファン倶楽部などは、全国から注目される組織であるが、その活動の中核を団塊世代ジュニアが担っている。

それらの組織では、地元自治体や集落のまちづくり支援、新しいグリーンツーリズムの構築や農泊の立ち上げ、小中学生たちの自然環境教育や農林業体験、大学生たちのインターンシップの受入れなど、多様な活動を展開している。それぞれの組織の中核を担う人材の多くが、大学院卒など高い学歴や社会人経験を有し、専門性をもちつつ、地域に根付いて活動をしている。彼らの姿をみて「こういう生き方や暮らし方があるんだ」と勇気づけられた、若い世代が多いことも確かである。
団塊世代ジュニアがなぜこのような地方志向をもち始めたのか。そこには第2講で述べたように、地域への関心が社会的に高まったことや、自然環境への配慮、脱大都市生活、脱大組織など、高度成長期以降の既存のライフスタイルの再考なども大きな要因となったと考えられる。また大学生時代のインターンシップ等による、農山漁村との触れ合いや交流の経験が、直接的な経緯となっている場合も多い。
またこの世代を巡る状況については、労働環境や家族形態の変化が進み、これまでの世代が前提としてきた標準的なライフコースが揺らいできた。そのなかで、若者層を中心に多様な生き方を求める時代となり、自らのライフコースを作り出す場として農山漁村を志向する若者が増えた、という指摘もある*。
* 坂本誠「自律と支え合いによる農村の再生」(神野直彦他編『分かち合い社会の構想』岩波書店、2017年)。
「まちづくり」「地域づくり」の知見がこの一冊に!

まちづくり再考 ―現場から学ぶ地域自立への道しるべ 編著者名:岡﨑昌之/著、自治体学会/編集協力
販売価格:2,200 円(税込み)
ご購入はこちら ≫