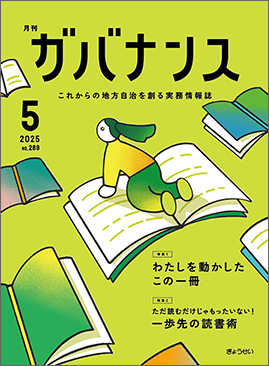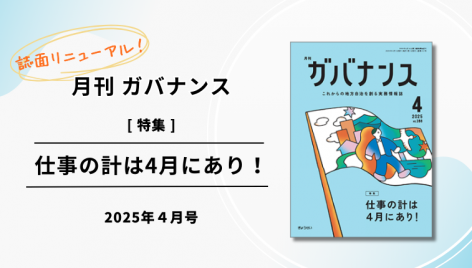自治・地域のミライ
自治・地域のミライ|アカウンタビリティを大切にしながら、住民に寄り添ったまちづくりを進める 茨城県境町長 橋本正裕
地方自治
2025.04.28

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年5月号
茨城県境町長
橋本正裕
2014年に地元・茨城県境町長になった橋本正裕氏。就任以来、ふるさと納税額が関東1位、移住者の人気ランキングで1位になったほか、地域公共交通の課題解決を目的とした全国初の自動運転バスの定期運行や小中学生の英語力向上を目指す「スーパーグローバルスクール事業」など多角的な施策を次々と打ち出し、全国から注目を集めてきた。どういう思いや考えでまちづくりに取り組んできたかを聞いた。

町長室にて。境町で行われているさまざまな取り組みのパネルや新聞記事などが掲げられる。いかに多角的な施策が展開されているかがわかる。
茨城県の南西部、関東平野のほぼ中央に位置。利根川と江戸川の分岐点に位置し、豊かな水の流れと緑あふれる田園が広がる。利根川を挟むと千葉県野田市に面する。2004年に現在は坂東市となった岩井市及び猿島郡猿島町との合併が検討されたが、住民投票の反対多数により単独町制継続となった。2015年3月に圏央道境古河ICが開通。2025年4月1日現在、人口2万3899人、9444世帯。2025年度の当初予算一般会計は159億2600万円。
真似をしてまちが良くなるためならなんでも積極的に取り入れていく
危機を脱するために
――2003年、27歳で町議選に出馬し、当選。その間議長も経験し、2014年町長に初当選した。どのような思いで町長になったのか。
私はもともと境町で生まれ育った。祖父が町長を6期務めており、その姿を小さいころから見て育ってきた。大学を卒業後に、境町役場に入庁した。
27歳の時に、まちの現実に目を向け、正しいことに取り組もうと町議選に出る決意をした。そのとき、『ガバナンス』で「東葛ステイツマンクラブ(TSC)」(千葉県北西部を中心とする超党派の若手地方議員によるネットワーク)の記事を見た。勉強をしようと、当時千葉県流山市議会議員だった松野豊さん(現境町参与)の選挙のお手伝いをして、選挙、政治のイロハを学んだ。当時は、後援会をしっかり組み、振舞いなどしながらの組織的な“田舎の選挙”が当たり前の時代。松野さんの選挙を手伝うことを通して、駅立ちや自転車遊説など“今時の選挙”を学ぶことができた。私は幸いにも選挙の三バン(地盤、看板、カバン)があったが、それでもとにかく今時の政治に変えていかなければならないとの思いで町議選に出馬し、当選した。
町議会議員1期目28歳の時、明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科の1期生として入学した。成澤廣修・東京都文京区長なども同期だ。明治大学では中邨章先生、拓殖大学では竹下譲先生などから多くのことを学ぶことができた。今も明治大学とは牛山久仁彦先生に政策アドバイザーとして助言いただいている。
町議は4期務め、2011年には、35歳で全国最年少議長にもなった。その後2014年3月に町長選挙に挑戦し、38歳で町長となった。

はしもと・まさひろ
1975年生まれ。茨城県境町出身。芝浦工業大学工学部建築工学科卒業。明治大学大学院ガバナンス研究科修了。1999年境町役場に奉職。2003年~13年境町議会議員(2011~13年議長)。2014年境町長に就任し、現在3期目。デジタル庁「デジタル交通社会のあり方に関する研究会」構成員、内閣府「地方創生SDGs金融調査・研究会」委員を務める。
――町長就任後にさまざまな施策を打ち出し実行。全国から注目されている。その施策のきっかけは。
町長選挙に挑戦しようとした当時、2013年度の境町の将来負担比率は184.1%で、北関東104市町村ワーストだった。人口も減り、借金も増え、若い人だけでなく、年配の方々までも動けるうちに引っ越そうと、近隣の春日部市(埼玉県)やつくば市に行く人たちが出てきた。ここでテコ入れをしないと このまちが終わってしまうという危機感を持っていた。
最初に着手したのが「財政再建」だった。全国を研究する中で北海道夕張市のような行政改革は必要ではあると感じながらも、関東のど真ん中でそれをやると住民は引っ越してしまう。行政サービスに差が出るのであれば、サービスが良いところに移ろうとするのは当然のことだ。当時境町は、ふるさと納税や企業誘致をしないまちといわれていたが、企業誘致を始めた。さらに独自財源と して、新たな補助金の獲得や、太陽光発電事業を行う茨城さかいソーラー株式会社を作るなどした。
財政破綻寸前の状況を打開するための立て直し策としてふるさと納税に目を付けた。制度開始から6、7年経過していたが、町長就任当時の寄付金額は6万5000円だった。
ふるさと納税の寄付について全国の例を調べる中で、岐阜県各務原市が2012年度の79万円から2013年度には1億2400万円を超えていた。「何かがある」と思い視察に行った。2013年に就任したばかりの浅野健司市長がふるさと納税専任の職員を置き、力を入れていた。
これを見て、そのまま境町でも真似をさせてもらった。返礼品の開発とマネジメントを徹底し年々増加。あれよあれよと2024年度には寄付額が99億円にまでになった。
自治体にもマネジメントは必要だ。持続可能でないと住民サービスも低下する。だからこそ、最初にふるさと納税に力を入れて、そのお金を原資にできることに力を入れてきた。
さらに行政は前例踏襲主義だ。その考え方も見直していかなければならないと、電気代や契約の見直しなどの財政改善を資金確保と同時並行で進めた。この感覚は、民間企業や自分の家庭であれば当然のように行う節減だろう。境町では収入を増やす施策に力を入れた。好循環を生み出すための最初の一歩だった。
――「財政再建」のほかに「人口増加政策」や「ひとの創生」としてさまざまな施策を展開してきた。
移住定住ではマーケティングが長けていた千葉県流山市や、子育て支援で有名だった兵庫県明石市や北海道東川町など先進的な自治体を見に行った。そして、ふるさと納税同様、真似ることから始めた。境町であれば、これを真似をすればまちが良くなるのではないかというものを取り入れていった。
その一つが定住促進住宅だ。ある時、関東町村会の研修で隣の席が神奈川県山北町の湯川裕司町長だった。「何か良い施策はないですか」と聞くと、「関東で初めて地域優良賃貸住宅という制度をやっている」というので、見に行った。その後、佐賀県みやき町を見に行くと良いとアドバイスをもらい、出かけた。山北町もみやき町もPFI事業(*)による定住促進住宅の整備を行う先 行自治体だ。みやき町には、議会だけでなく、地元の建設業者など民間事業者も連れて行き学び、境町でも2017年に事業を始めた。最初は共同住宅整備から始まり、今は戸建て住宅整備を進めている。入居率100%で、倍率も高い。今では、近隣のつくばみらい市や五霞町、八千代町(いずれも茨城県)にもノウハ ウを横展開し、波及している。良いことはみんなでやろうというのが境町のスタンスだ。境町だけが良くなるのではなく、他の自治体も取り組んで良くなっていけば全国の自治体も良くなっていくのではないか。
移住定住には三つのポイントがある。一つ目は「仕事」だ。可能な限り、今ある仕事のままで引っ越したいという人が多い。第一次産業しかないところだとどうしても厳しい。二つ目は、「住居」だ。今の住居より広いことや庭がほしいなど、住居環境が良くならないと引っ越して来ない。そして、最後は「教育」だ。私たちが力を入れたのが英語教育だ。2018年度から「スーパーグ ローバルスクール(SGS)事業」を進め、小学1年生から日常的に英語に慣れ親しみ、小中学校9年間で英語力の向上を図り、グローバル社会で活躍できる人材育成を目指している。
多くの自治体はゼロからイチを生み出すことが苦手だ。しかし、境町はそれが得意だ。近隣に限らず全国各地の離れていても同じ思いを持っている自治体や人に教えたり、教わったりしながらやっている。
*低廉かつ良質な公共サービスを提供することを目的に、民間事業の経営ノウハウ・資金を活用した公共施設等の設計・建設、維持管理を行う公共工事の手法。
持続可能にするために
PFI事業で山北町やみやき町の先行自治体が、広く企業を求めている一方で、境町では代表企業を地元企業に限定しているのが特徴だ。地元を支えなければならないという考えからだ。そうすることで地元事業者にもノウハウが蓄積される。持続可能なしくみにするためだ。
地場産品に限定されたふるさと納税も、境町に3割のお金が落ち、まちづくり公社などが儲かり、雇用も生まれ好循環が生まれている。
――民間企業と連携した多様な事業が展開されている。
境町のような人口は減り、借金が多いまちに来てくれる企業は、ありがたい企業だと思っている。その結果が、都心の有名店の出店や、企業誘致、アーバンスポーツパークをはじめとした「スポーツを核としたまちづくり」などにつながっている。
境町が特殊なのは、本来住民のみなさんに対してお金を使うところを、まずは外から人を呼び込むために投資をしている点だ。そして、それによって良くなってきた地域経済の中で住民に向けたサービスを充実させていっていることは他の自治体とは違うかもしれない。
多くの民間企業と連携した取り組みをメディアなどでもたくさん取り上げていただいているが、常に営業に行っている結果だ。いつでも情報収集をし、企業に出向き、境町とマッチングするかどうか営業をし続けている。これも民間なら当たり前の感覚だろう。営業をして、境町に来て投資してもらい、住民のシビックプライドにつながればいいと思っている。
町議時代に通った明治大学大学院ガバナンス研究科で学んだのは、「アカウンタビリティ(説明責任)」の重要性だ。さまざまな工場誘致などもしてきたが、まちへの効果を住民に知らせることは大切なことだ。また、マスコミなどで何かを表明する際も、事前に議会にも共有し、許可を取っている。視察に行く際も議員のみなさんにも声をかけるようにしている。そうすることで合意形成も早くなる。町長就任以来、行政も議会も同じ方向を向き、良い関係性の中でまちづくりを進めることができていると感じる。
施策も、高齢者、子育て世代、より若い世代、その世代ごとにフィットしたものがある。自治体として初めて公道での定期運行をしている自動運転バスは、利用し買い物をする方々がいる一方で、それだけでは使い勝手が良くない人もいる。AIオンデマンドバスを走らせるなど、次の手を打っている。適材適所で今ある技術を入れていけば、それがモデルになっていくのだと思う。
人工サーフィンやアーバンスポーツパーク、そして自動運転バスやさまざまな実証実験などの取り組み、まちなかに点在する建築家の隈研吾氏が手掛けた建築物などもあくまで一事業すぎない。それぞれを組み合わせていくことが重要と考える。
境町から東京まで高速バスが1日8往復している。2万4000人のまちからすると珍しいことだろう。おそらく境町だけでなく、近隣の坂東市や八千代町、古河市の方々も利用しているのだろう。境町に行けば便利だ、境町からバスに乗って東京に行こうとなる。近隣の自治体の取りこぼしている部分を我々が拾ってあげればいいと思っている。
あらゆる連携での経験を他の自治体に伝えることでモデルの自治体になればと思っている。

町長になっていの一番に取り組んだのが財政再建。施策の多くは先進自体から真似て、境町にフィットするものを実行してきた。
丁寧な説明を大切に
――「ひとの創生」では、「プロフェッショナル職員」を育てること注力してきた。
たとえ良い政策であっても、新たな首長が就任するとストップすることがある。そのようなとき、これは住民のためにやらなければならないと言えるような職員を育てたい。国や県への職員派遣などの人事交流を通して横の連携も図っている。
また、境町に視察が来た際、私が講演するときには、必ず職員にも5人くらいずつ参加してもらうようにしている。そうすることで、2年くらいで約230人の全職員が境町では何をやっているがわかるようになる。小さい組織だからこそ、何をどこでやっているか、財源はどうなっているのかということを漠然とでも理解するべきだろう。
――自治・地域のミライをどのように描いているか。
企業誘致やあらゆる投資をしてきた。財政予測では2028年度には将来負担比率が27.6%になる見込みだ。180%を超えていたころからすると抜群に改善する予測だ。
私はいつ辞めてもいい、日々が勝負だと思って町長をやっている。住民の暮らしが良くなるか、ならないかという判断基準で動いてきた。
そして大切なことは、まちの規模の大小ではなく、やるかやらないかだ。失敗を恐れるのであれば、真似から始めると良い。批判を恐れず、良いことであれば周りは納得してくれる。だからこそ説明しながらやっていくことが重要だろう。
――自治体職員にメッセージを。
まず、全国の首長のみなさんには、ぜひ境町に職員を送っていただければと思う。こういうやり方があるのかということを知る機会にもなるのではないだろうか。
そして、自治体職員のみなさんには、良いことだからと一方的に進めるのではなく、住民の皆さんの声に耳を傾けながら、説明責任をしっかり果たしながら仕事をしていってほしいと思っている。
(取材・構成/本誌 浦谷收、写真/加藤智充)