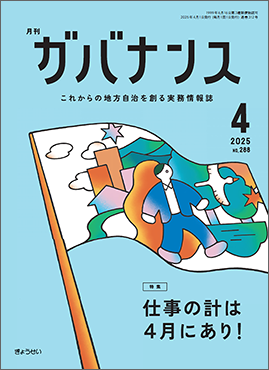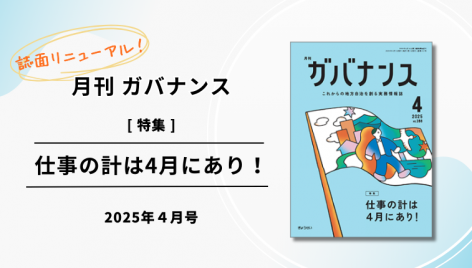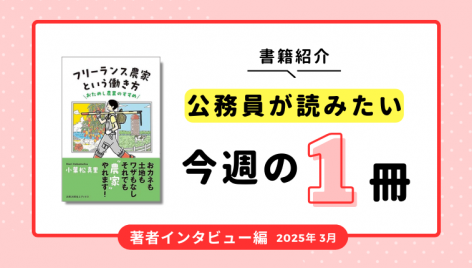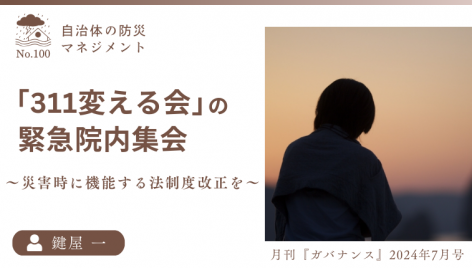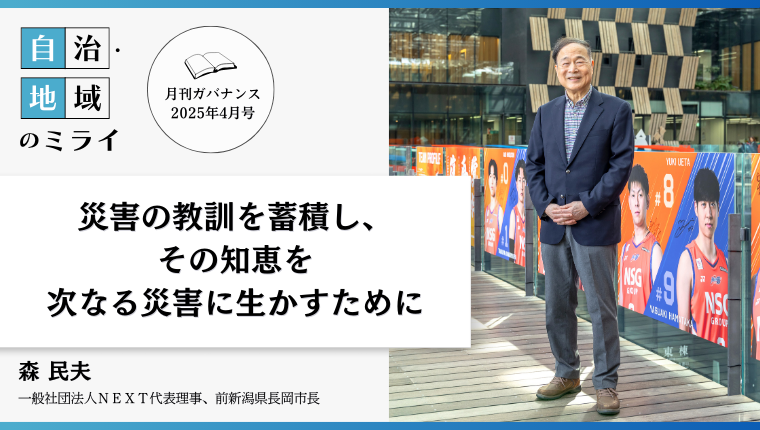
自治・地域のミライ
自治・地域のミライ|災害の教訓を蓄積し、その知恵を 次なる災害に生かすために 一般社団法人NEXT代表理事、前新潟県長岡市長 森民夫
地方自治
2025.04.11
目次

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年4月号
一般社団法人NEXT代表理事、前新潟県長岡市長
森 民夫
1999年から5期にわたり新潟県長岡市長を務めた森民夫氏。2009年からは7年3か月全国市長会会長も務めた。その間、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震をはじめとした大規模災害にも対応してきた。このほど、森氏が中心となり各地での災害対応をした首長らの経験が『首長たちの戦いに学ぶ 災害緊急対応100日の知恵』という一冊の書籍にまとめられた。

市長時代の2012年に完成したシティホールプラザ「アオーレ長岡」で。市役所と、アリーナ、そして開放感のあるナカドマ(屋根付き広場)が一体となった全国初の複合型施設。設計は隈研吾氏が手掛けた。JR長岡駅からは、屋外を歩かず連絡通路で直結する。「アオーレ」とは、長岡地域の方言で「会いましょう」の意。広場には、子どもたちをはじめ多くの市民が行き交っていた。撮影日は天気が良く、「日の光が差し込んで良いでしょう」と森さん。
実際に震災が起き、とにかく物事を即断即決しなければならない時、私には “参考書” がなかった
近年国内で頻発する災害。それらの最前線で対応してきた首長や、関係団体や民間企業ら関係者の経験と知恵をまとめた『首長たちの戦いに学ぶ 災害緊急対応100日の知恵』がまもなく発刊される。
本書を中心となってまとめたのが、前新潟県長岡市長で現在は一般社団法人NEXT代表理事を務める森民夫さんだ。森さんに、本書に込めた思いや災害時に必要と考えるリーダーとしての姿勢などを聞いた。
現場の声が原点
――まず、本題に入る前に、建設省、長岡市長時代の話をお聞かせください。
1999年に長岡市長になる以前は、建設省の官僚だった。官僚時代は、市町村よりも都道府県とのやり取りが多かった。市町村でも政令市が中心で、特に町村と付き合うことはほとんどなかった。口幅ったいようだが、当時は霞が関の官僚として国がしっかり主導権を握って指導しなければいけない、という意識を持っていた。全国各地からユニークな政策や情報を集めて、それをまた全国の都道府県などに流すという、まさに“中央集権”が当然のように思っていた。
1999年、初めて地元の長岡市長選に立候補した。政党の支援も受けず、組織もない、まったくの草の根運動的な選挙戦を展開した。朝早く起きて、たとえば農家へ上がり込んだりしながら、さまざまな人のところへ直接行ってお話をうかがうことを続けた。そのときに感じたことは、「現場の人が一番物事を知っている」ということだった。
一方で、まだ市長でもない「市長候補」という肩書でも、「 “市長” という名の付く人が来てもらってありがたい」という人や、トイレを借りただけで喜んでくれるような人もいた。
行政はずいぶん一般の人から離れた存在なのだと実感した。
この時の経験が私にとっての原点だ。現場には知恵がたくさんあり、本当に良い感覚を持った住民の方々がいる。現場のニーズを拾い上げ、それを政策まで昇華させるのが行政の仕事だと思いやってきた。
行政の仕事としてもう一つ大事なことが、個別の分野に横ぐしを通すことだ。それぞれの現場の人は、自分の現場のことはわかっている、これを統合すると面白いことができる。つまり、これがイノベーションだ。
市長に当選してからも、地域のお祭りや懇親会や会合に顔を出し、さまざまな話を伺うように努めた。現場の声の重要性を市長就任前に強く実感したからだ。
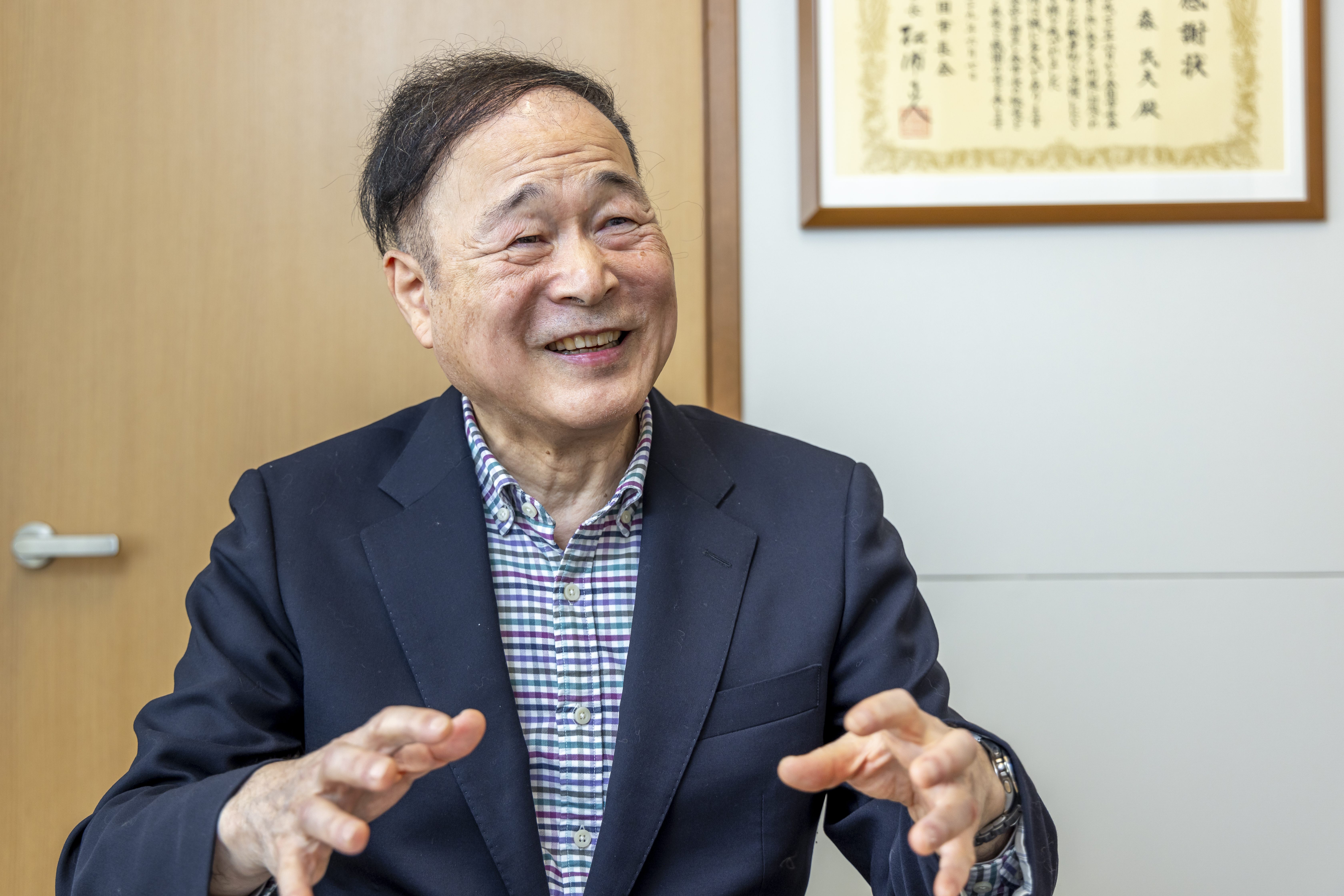
もり・たみお
1949年長岡市生まれ。1972年東京大学工学部建築学科卒業。1975年建設省入省。1999年長岡市長に当選(以降5期)。2009年全国市長会会長に就任(以降4期)。中央教育審議会委員、東日本大震災復興構想会議部会長代理、中央防災会議専門委員等を歴任。2016年長岡市長退任。以後、近畿大学、筑波大学客員教授、東京大学非常勤講師、(一社)NEXT代表理事等を歴任。
いざというときになかった “参考書”
――2004年10月23日、市長2期目の途中に新潟県中越地震が起きた。この時の話をお聞かせください。
今となっては恥ずかしい話だが、当時は災害対策基本法も災害救助法もしっかり読んで理解していなかった。しかし、実際に震災が起きてしまい、とにかく物事を即断即決しなければならない時に、私には “参考書” がなかった。神戸市や兵庫県の阪神・淡路大震災の記録などはあったが、すぐに読むには大変なくらい細かい内容だった。私が欲しかったのは、リーダーとしての心構えや判
断のポイントだったが、国などにもなかったため、手探りでなんとかやった。
その後ある程度落ち着いてから、被災者に対しての思いや応援職員に対する感謝、あるいは自然災害へのやり場のない怒りなどさまざまな感情が入り混じり、徹底的に書き残したくなった。この後に同じようなことに遭遇した人のためにと思って書き溜めた。さらに自分だけでなく、担当職員にも書いてもらいまとめたのが、2005年に発刊した『中越大震災─自治体の危機管理は機能し
たか─』(長岡市災害対策本部・編集、ぎょうせい)だった。その後の災害時にも被災地の首長の方々に配った。熊本地震の際は、熊本市の大西一史市長らからも大変評価をいただいた。
――2009年には全国市長会会長(第28代)に就任。2016年9月まで7年3か月務めた。
市長として現場で見聞きしたたくさんの実情が、市長会会長に立候補する動機にもなった。特に、まちづくりや福祉などは現場(市町村)の話だ。現場が頑張らなければならないということが身についていた。
当時は、地方分権推進の熱気がある中での会長就任だった。3か月後の2009年9月に政権交代が起き民主党政権が誕生した。陳情窓口の一本化などこれまでと大きく変わったことで難しい局面もあったが、現場の話を聞くという観点では、「国と地方の協議の場」の法制化は非常に大きなトピックだった。
――全国市長会会長在任中の2011年3月11日には東日本大震災が発生した。
被災エリアが広大であり、メディアに取り上げられる自治体に支援が集中する一方で、そうでない自治体には支援が届きにくいような状況があった。支援を要請する自治体と応援を申し出る自治体をマッチングする「緊急災害支援掲示板」を設け、支援体制を作った。また、この時に被災自治体に対する職員派遣のスキームもできた。人的支援の仕組みはその後の各地の大規模災害時にも生
かされている。
現地に直接行くこともあったが、国交省東北地方整備局が衛星携帯電話を被災自治体に配布したことで、各市長と直接電話で話し、状況やニーズ、本当に困っていることを把握することができた。この時も、これまでと同様に現場の声を重視した私なりの行動だったように思う。
──長岡市長としての新潟県中越地震、全国市長会会長としての東日本大震災をはじめとした「災害の現場」を最前線で経験した。
たとえば、自動車で避難している人は「エコノミークラス症候群になる恐れがある」と言われるが、ではどうしたら自動車での避難をやめてもらえるかという教科書はない。また、指定避難所はあるが、いざ災害が発生するとそうではないところに避難所ができてしまった、ということも実際に被災地で起きた話だ。
お役所的な発想だと、なんとかこれらをやめさせなければならないという思考になるのは当然だが、現地に行くと、それぞれにはそんな行動を取らざるを得ない状況があったりする。机上での想定とは違う現実があるからこそ、こういう現場の実情を理解、把握している人が次にどのような手を打つかを考える主体とならなければならないと思っている。
今は各地で災害が頻発し、首長のみなさんはいつ降りかかってくるかわからない災害対応について勉強される機会も多いと思うが、それでも現実に災害が起こったら、目の前で判断をしていくのは大変なこととだろうと想像する。
新潟県中越地震から20年以上も経ち、昨年は能登半島地震が起きた。各地で災害を目の当たりにした首長や関係者の経験を、また新たな本としてまとめなければならないと思い、今回の書籍の企画となった。
現場の首長としての心構え
――新著では、森さんだけでなく、東日本大震災や熊本地震、豪雨災害、そして能登半島地震などの被災自治体の首長らが当時の経験を語っている。災害など非常事態時のリーダーのあり方や心構えをどう考えるか。
物事を俯瞰的に見る立場の人に見えることと、現場で見えることは違う。だからこそ、現場から遠い人と現場とが嚙み合わなければならない。それがうまく噛み合うと良い政策になる。だからこそ現場にいる市町村長の役割はとても重要だ。
今回の書籍では、さまざまな災害、そしてそれを経験した多くの首長の生の声が入っている。これを “参考書” として、読者のみなさん、特にリーダー層の方々には、読み取っていただいて、考えて行動してもらえたら嬉しい。
災害対応には、正解はない。100%確実ということもない。だからこそ、リーダー(特にも首長)は「いつでも責任を取る」という気持ちが大切だろう。
加えて、被災者の方にはサポートが必要となるご高齢の方や障がいがあるなどさまざまな人がいる。そういう方々であっても、みな人間としての意思がある。それをどれだけくみ上げることができるかが重要となってくる。中越地震で大きな被害を受けた山古志地域(旧山古志村)の集団移転がなかなか決まらず何十回も協議を重ねた。でもそれは強制しては決してならない。自分の意思で決めて帰った人は強いと感じた。被災したことに対して一方的に「かわいそうな人たち」と思うのではなく、手を差し伸べる時に、相談に乗り、意思を尊重し、そしてその人の持っているパワーをどう引き出すかということが一番大事ではないかと思っている。

アオーレ長岡のアリーナは、男子プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」に所属する新潟アルビレックスBBのホームアリーナ。最大約5000人を収容できる。この日は、シニアグループがソフトバレーボールを楽しんでいた。
生々しい経験が次の参考書となる
――書籍では13人の現職首長を含むリーダーらが各地での災害時の経験を紹介している。読者にメッセージを。
今回の書籍では、規模も種類も異なるさまざまな災害事例を盛り込むようにした。どの災害の例も貴重な記録である。
東日本大震災で被災した岩手県宮古市の山本正徳市長は、被災直後から住民に毎朝呼びかけをした。防災行政無線を使い、直接声を届け、励まし続けたのだ。福島県相馬市の立谷秀清市長は、市長は最終責任者だからと、自衛隊や警察などの組織を超えた対応をとった。
広島豪雨では、同市の松井一實市長が豪雨災害への対応の困難さと反省点を率直に述べるとともにその改善策をわかりやすく示してくれた。
能登半島地震では、石川県珠洲市の泉谷満寿裕市長が地震と水害の二重災害に直面した状況と、岡山県総社市の片岡聡一市長が石川県七尾市に100張りテントを贈る水平支援を紹介した。
また、首長だけでなく、その他の団体や民間企業の方にも登場いただいた。頻発する災害に対応するためには、市町村の首長らのリーダーシップと住民に寄り添う「現場」へのまなざしが不可欠だ。私は中越地震を経験した際に、さまざまな決断を迫られた。その時、何よりも欲しかったのは、細かい災害法制の知識よりもリーダーとしての心構えだった。
本書に収められた生々しい経験の数々は新しい “参考書” となるだろう。今後起こるだろうと予想されている大規模災害がいざ起きたときに最善の対応を取れるよう参考になる書だと思う。ぜひ、多くの人に手に取ってもらいたい。
(取材・構成/本誌 浦谷收、写真/五十嵐秀幸)
【新刊紹介】

首長たちの戦いに学ぶ
災害緊急対応100日の知恵
編集代表 (一社)NEXT 代表理事・前長岡市長 森民夫
出版社:ぎょうせい
A5判・定価3,850円(10%税込)
詳細はこちら ≫
7つの大規模災害において、最前線で災害対応にあたった13人の現役首長をはじめ関係者の経験と知恵を集約!
今後発生が予想される大規模災害に向けて、最善の対応を図るための防災関係者必読の書!