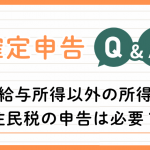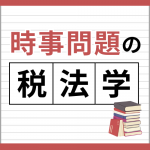時事問題の税法学
時事問題の税法学 第14回 領収書
地方自治
2019.07.10
時事問題の税法学 第14回
領収書
(『月刊 税』2016年12月号)
領収書は支出の証明

「財布の中の領収書、万の位にチョイト棒引けばみごとにふえます領収書」「ボールペンの色がちがいます」
コミックソング「領収書」の1節である。接待に明け暮れているサラリーマンの悲哀を唄ったバブル時代の唄である。筆者の周囲では、カラオケの定番となっているが、YouTubeでも容易に検索できるので試してほしい。
こんな歌詞を彷彿させた富山市議会補欠選挙が終わったと思っていたら、詐欺罪視野に警察の本格的捜査が始まると報じられた(読売新聞11月7日)。政治資金がらみのパーティーの会費に関するニュースでも、領収書の授受が話題となったが、多くの批判は、政治の世界の常識と一般常識の乖離を指摘するものだった。
税法の領域に限ってみても、領収書は支出の証明として極めて大きい。申告納税制度の下では、法人税における損金、所得税における必要経費、消費税における仕入税額控除、そして相続税における葬式費用など税額の計算上、控除対象となる費用性の立証は、納税者自身の責任であり、その手段は領収書の提示に尽きるのである。
日常生活のなかで領収書が授受されない取引はわが国にはないと言っていい。納税者が帳簿に計上した取引に係る領収書がないと言うときは、領収書をもらい忘れた、もらった領収書を紛失した、架空取引だから領収書がない、という事情が想像できる。領収書がないのに必要経費に算入していたと国税当局に指摘された申告漏れ報道も少なくない。少々、古い話題であるが、著名人のなかにも、関西芸能界で女帝と評される上沼恵美子女史(朝日新聞平成17年8月4日)やあの橋下徹弁護士(毎日新聞平成18年5月23日)がいた。
白紙領収書で有罪判決

もっとも上沼女史は、「税理士にすべてまかせているので、詳しいことはまったくわからない」とコメントしていた。これを読んだとき、同業者として同情を禁じ得なかった。いうまでもなく領収書を受け取るのは納税者自身だからである。それでも領収書を偽造する方が罪は重い。最近でも実際にある企業名を使ってニセ領収書を提出していた議員がいた。まだ自分で作っているから許されるというわけではないが、ニセ領収書を偽造し、売るという業者は悪質である。いわゆるB勘屋と呼ばれる商売である。BとはBlackのBなのか、それともBackのBかは判然としないが、いわば隠語のたぐいだったこの不法なビジネスも、経済小説にも登場するようになった(佐藤弘幸『税金亡命』ダイヤモンド社)。ただ、現在のようなネット社会では架空企業などすぐバレてしまうような気がする。今後、領収書に導入された法人番号の記載が義務化するかもしれないし、消費税制度にインボイスが実施されれば、ニセ領収書など存在価値も消滅するだろう。
コミックソングの「領収書」では、「白紙で下さい領収書、できれば下さい2〜3枚」「もらった白紙の領収書、やさしい女将の思いやり」と歌詞は続く。確かに白紙の領収書を顧客に渡すことは、実際、見うけられる。渡す方にすれば、サービスの一環のつもりだろう。販売促進といった行為といえる。
しかし大阪高裁平成26年5月13日判決は、金額白地の領収書多数を提供した行為について、法人税逋脱(ほだつ)行為の幇助行為を認めて、白紙領収書の提供者に対し、懲役6月執行猶予3年の有罪判決を言い渡している。裁判所は、被告人は、会社の経営者として税務申告の経験も有しており、取引先の代表者であるcに対して金額白地の領収書を交付すれば、経費の水増し等による脱税に悪用される可能性があることは当然認識していたものと認められ取引先に対して金額白地の領収書を交付すれば、法人税の逋脱を行う蓋然性が高いことを認識、認容していたことを強く推認することができると言及している。
もちろんこの事案は継続した取引を行っている企業間の話である。判決には、一罰百戒の感じもするが、歌詞のように不特定多数の顧客に白紙の領収書をばらまく行為とはいささか異なる。そうはいっても領収書のもつ重要性は変わらない。たかが領収書、されど領収書ということだろう。