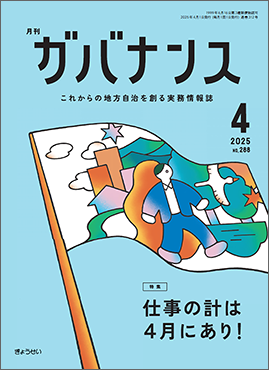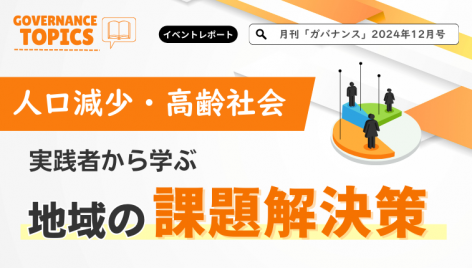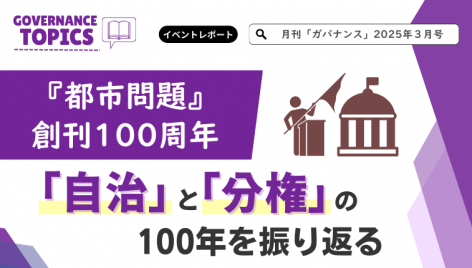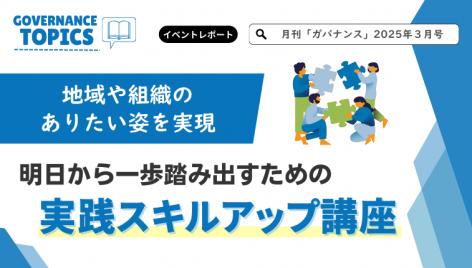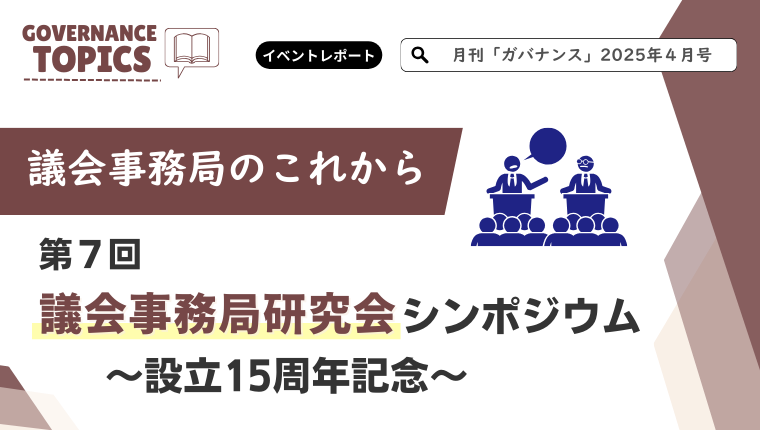
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【議会事務局のこれから】第7回 議会事務局研究会シンポジウム~設立15周年記念~/イベントレポート
地方自治
2025.04.24
目次
(『月刊ガバナンス』2025年4月号)
【連載一覧はこちら】
【ガバナンス・トピックス】
議会事務局のこれからを多面的に議論
──第7回議会事務局研究会シンポジウム~設立15周年記念~
学識経験者と議会事務局職員(経験者)、議員らによって構成される「議会事務局研究会」のシンポジウムが2月15日に大阪府内で開催された。「議会の機能強化と議会事務局の未来」をテーマに、関西圏を中心に多くの議会関係者参加し、活発な議論が交わされた。
従来のイメージを払拭するために
同研究会は2009年に設立。議会改革における議会事務局のあり方を検討し、事務局の任務やその役割を分析するとともに、それらにおける課題を提示することを目的に、2010年3月にそれまでの議論をまとめた中間報告書(「今後の地方議会改革の方向性と実務上の問題、特に議会事務局について」)を発表。さらに2011年3月には「議会事務局新時代の幕開け─議会事務局研究会最終報告書─」をまとめました。以降も、年数回研究会を重ね、折々でシンポジウムを開催してきました。


会場は大阪市の立命館大学大阪梅田キャンパスで行われた。
基調講演/駒林良則・立命館大学特任教授
まず、同研究会共同代表を務める駒林良則・立命館大学特任教授が基調講演として、同研究会発足のきっかけから会の特徴や機能、そして活動の成果と今後への期待を発表した。
研究会設立のきっかけ
研究会設立のきっかけは、議会改革が各地で進む中、議会事務局の力が必要不可欠にもかかわらず、持てる力を発揮していないのではないかという問題意識と、目立たない存在の議会事務局にスポットを当て、議会事務局を「認知」させる目的があったという。
研究会の特徴や機能
同研究会の特徴は、議会事務局職員が中心になり、研究者や議員、首長が対等に関わっている点だ。自らの議会(議会事務局)のことを他で話すことに対するタブー意識が強い中で、ある議会事務局が抱えている問題や課題は他の議会事務局にも共通のものがあるという認識のもと、意見交換の場としての機能を果たしてきた。
活動の成果と今後への期待
活動を通した成果としては、
「議会の機能強化における事務局の役割と限界」
「議会の様々な問題状況における事務局の役割と限界」
「議員と事務局の関係はどうあるべきか(チーム議会)」
「事務局職員の意識改革の必要性」
などについての学びが得られたという。
研究会での活動を経て、駒林教授は、今後への期待として次の3点を表明した。
①従来の「議会は異質なところ」というイメージの払しょくのために、住民が議会に対して関心を持つことも重要だが、議員の側も「常識が通用する議会」への努力が必要なこと
②議会事務局の真の充実強化につなげること
③異動希望先として議会事務局が挙げられるように、執行機関の職員の意識を変え、役所内での「地位」の上昇を求めること

共同代表の駒林良則教授は、議会事務局研究会の活動を振り返った。
それぞれの視点からみる議会事務局
次に話題提供として3人が登壇した。
最終報告書に込めた思いと今後の課題
まず、盛泰子・佐賀県伊万里市議会議員が「最終報告書に込めた思いと今後の課題」と題し、発表した。
東京出身の盛さんは、縁のない伊万里の地で議会に飛び込み約30年。まだ議員歴が浅いときに、ある議員研修で全国都道府県議会議長会議事調査部長の野村稔さんから聞いた「古いものを見たければ、博物館か議会へ行け」という言葉が非常に印象に残ったと紹介。この言葉に、議会がどのように見られ、言われているかを知ったという。
盛さんは、議員になってしばらくは「議会事務局は市役所の一部署である」という認識で距離を置いていたが、様々な経験をする中で一番の仲間であると確信し、事務局についてもより学びを深めたいとの思いで研究会に参加したことを振り返った。
最終報告書の作成にも携わった盛さんは、報告書で具体的な提言としてなされた
①議長の人事権行使(自治法138条5項)
・一部独自採用
・議会事務局の共同設置、全国議長会による事務局スタッフの共同採用
・公共政策大学院、法科大学院とのインターンシップ契約
②議会予算の編成権および執行権を議長に
③住民への情報提供など窓口機能の強化
に触れ、
「①については意識の高い議長によって実施されている事例もあるが、②の議会予算の件と含めて提言が生かされている状況にはない。その原因は、議長や議員の意識の低さではないか」と指摘した。また、③の情報提供については、「時代の要請や議員からの要請もあり、提言当時に想定されていなかった多種多様な情報提供がなされている。議会事務局が架け橋となり、住民が気軽に議会に参画できる仕組みづくりも進んでいる。議会と議会事務局こそが車の両輪だ」と述べた。
最後に盛さんは、「最終的には議長のリーダーシップに懸かっている内容が多い。議長会などでの主体的かつ具体的な議論の必要もあるのではないか」と投げかけた。

盛泰子・伊万里市議会議員は、研究会最終報告に込めた思いを語った。
局職員が超えるべき『補佐の射程』~職員に求められるものとは~
次に、清水克士・元滋賀県大津市議会局長が登壇。「局職員が超えるべき『補佐の射程』~職員に求められるものとは~」と題し、発表した。
「チーム議会」の確立
清水さんは、多くの地方議会は議会報告会など法定外の仕事に力を入れているとし、住民とともに「未来を語る議会」になるためには、
■行政監視機能偏重から政策立案機能の発揮 ■住民意見は、公式の議会の場で聴取し公式会議録に残す ■議員間討議をし、機関として合意形成した結果としての政策立案をすること ──を挙げ、「『チーム議会』の確立がポイントだ」と述べた。
また、「チーム議会」の必要条件として、
①議会としての合意形成力(会派を超えた議員間討議ができる文化)
②議員と局職員の協働体制(議員と局職員の間でのフラットな議論)
の二つを挙げた。
協働体制の構築
さらに、協働体制を構築するための必要条件についても言及し、「ひとごと意識や指示待ち職員を美徳とする文化といったチーム化を阻害する要因をなくし、議会や議員へ発意する局職員になる必要がある」とし、「議員のためではなく、住民のためという職員自身の意識改革が必要だ」と訴えた。
「補佐の射程」の改革
そして、局職員の「補佐の射程」の改革には、「執行部職員よりも萎縮的な行動を当然とする議会の常識を変えることが必要だ」と述べた。

清水克士・元大津市議会局長は、事務局職員の「補佐の射程」について言及。
終わりなき議会改革〜議会愛は永遠に〜
最後に岩﨑弘宜・前茨城県取手市議会事務局次長(現情報管理課長)が「終わりなき議会改革~議会愛は永遠に~」として、話題提供。現在は議会事務局を離れているものの、事務局時代の実績から、長野県千曲市・諏訪市の議会改革アドバイザーを務めている。
“議会愛” があふれる議会
岩﨑さんは「取手市議会は議員のみなさんが目線を下げ、職員とともに議会をそして市を良くしていこうという“議会愛”があふれる議会だ」と話し、その「愛」とは、
■押し付けないこと ■相手の言葉に耳を傾けること ■包み隠さず共有すること ■非難せずに話すこと ■文句を言わず楽しむこと ■惜しみなく与えること ──と紹介した。
事務局職員の議長との位置関係
同研究会の最終報告のポイントを引用しながら発表し、事務局職員の議長との位置関係については、
■任命権者と職員 ■唯一の秘書業務対象(「議員の」ではない) ■議長へのメニュー(食材)出しと調達(調査) そして何よりも最強のサポーターであり、議長にとっては最恐の苦言者集団 ──と述べた。
事務局職員と議会との位置関係
また、事務局職員と議会との位置関係は、
■議長を代表とする集団と職員 ■議会を構成する議員は直接的な秘書業務対象ではないが、議会が決定したことにはサポーター業務が発生 ■議長同様メニュー(食材)出しと調達(調査) ■議会だよりやHP、SNSによる情報発信、会議録の作成(取手市では音声認識システムによりリアルタイム認識)など、最強の広報グループ ■議会や委員会活動の補佐 ■議会の関心向上施策立案、実施サポート(住民との意見交換会、学生との対話事業など) そして議会にとっても最強のサポーターであり、最恐の苦言者集団であるべきだと述べた。
Demotechの取り組み
取手市議会のDemoTech(デモテック)(Democracy(民主主義)× Technology(技術))の取り組みとして、「AI音声認識字幕表示」、「360度カメラによるインターネット配信」、「会議録視覚化システム」、「議事録要約システム」など、次々とチャレンジしている様子を紹介した。岩﨑さんは、「こうした取り組みを事務局職員が提案し、議員が協議、決定し実践している。これこそがチーム議会だ」と述べた。そして、「議会改革に情熱をもつ職員の育成が必要だ」と話した。

岩﨑弘宜・前取手市議会事務局次長は、「議会愛」を強調 した。
議会事務局について多面的に議論
議会事務局の目指すべき未来とは?/パネルディスカッション
後半は、盛さん、清水さん、岩﨑さんをパネリストに会場の参加者らも交えて「議会事務局の目指すべき未来とは?」というテーマでディスカッションが行われた。
議会改革と議会事務局の役割
コーディネーターを務めた谷畑英吾・元滋賀県湖南市長からの「議会改革と議会事務局の役割」について問いかけに、清水さんは「一般質問中心主義が根付きすぎ、公開での場の議員間で何を討議すべきかわかっていないことも多い」と、自身の議員研修講師先での例も交えながら紹介。話題提供の際も言及したように、「住民意見を議会として聴くために法定されている公聴会などを活用すべき」と述べた。
岩﨑さんは、「公務員である事務局職員は議会が頑張れば最大限支えたいと思うもの。職員が伴走したいと思うような議会が良い議会では」と会場に投げかけた。
議会事務局の人事
「議会事務局の人事」の話題では、盛さんが「議長や議員の事務局に対する意識の高まりがまずなければ、いくら良い人材を首長部局から送られてきても活かしきれない」とし、他の議会を見て自分の議会でやりたいという人を増やしていく必要性を強調した。清水さんは、「執行部の職員は前例踏襲では仕事ができないというレッテルが貼られるが、議会に来たとたん先例主義を取るのが優秀な議会局職員だとされる」と取り巻く環境の違いも指摘した。
執行部局・住民との関係
そして、執行部局・住民との関係の話題では、岩﨑さんが「異動したいと思われる魅力ある議会事務局にするには、リーダーの存在が重要だ」と話した。
自己評価と外部評価の重要性
また、清水さんは、自己評価と外部評価の重要性についても言及し、「マニフェスト大賞のような評価を得ると対外的な目線が入り、恥ずかしい行動が取れなくなる」と経験を交えて紹介した。

ディスカッションでは、会場も交えて活発に意見交換が行われた。
谷畑さんが、会場参加の元首長や議員、事務局職員らにマイクを回すと、それぞれの自治体、議会でどのような運用が行われていたかなどが会場全体で共有され、有意義な空間が作られた。
最後に駒林教授が、「議会を取り巻く環境は変化し、課題も多い。議員は4年に1度変わるため、より一層議会事務局のサポートが重要だ」と述べ、充実したシンポジウムを締めくくった。
(本誌/浦谷 收)