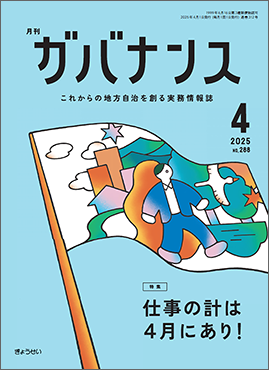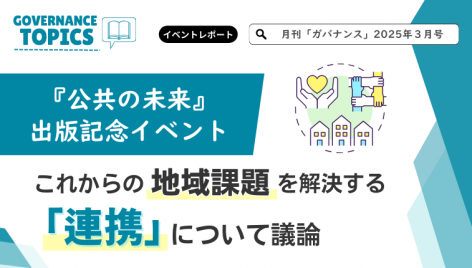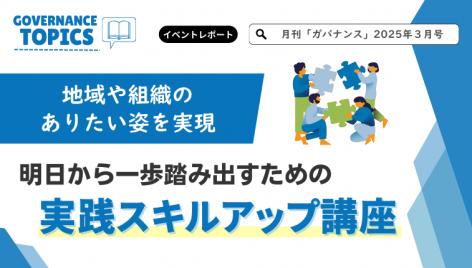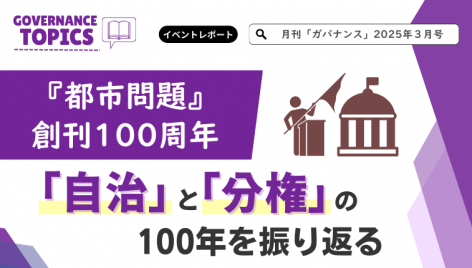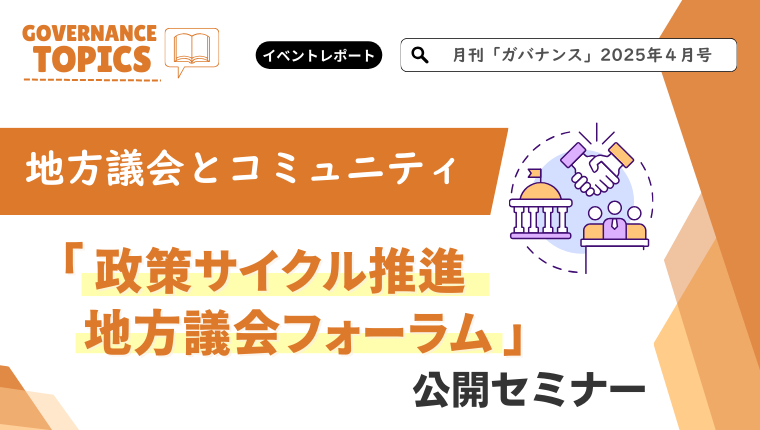
ガバナンスTOPICS【イベントレポート】
【地方議会とコミュニティ】「政策サイクル推進地方議会フォーラム」公開セミナー/イベントレポート
地方自治
2025.04.25
目次
(『月刊ガバナンス』2025年4月号)
【連載一覧はこちら】
【ガバナンス・トピックス】
地方議会とコミュニティとの関係を考える
──(公財)日本生産性本部「政策サイクル推進地方議会フォーラム」公開セミナー
(公財)日本生産性本部は2月2日、都内で「ミライの議員・議会のために第2弾!!~コミュニティと『地方議会からの政策サイクル』」をテーマに、公開セミナーを開催した。セミナーでは、地方議会とコミュニティの関係などを議論。長野県宮田村議会、兵庫県西脇市議会の実践事例も紹介され、住民福祉の向上に資する議会のあり方を探った。
コミュニティと議会
同フォーラム(座長=江藤俊昭・大正大学教授)は22年7月に発足。地方議会成熟度評価モデルの実装化とともに、地方議会における政策サイクルの構築と作動に向けた取り組みを行っています。

今回のセミナーは「本格化する人口減少社会の中で、コミュニティのあり方が議会のあり方を決めるのではないか、そして議会のあり方がコミュニティのあり方を決めるのではないか、という問題意識が出発点」(千葉茂明・日本生産性本部上席研究員)とし、地方議会とコミュニティの関係についてより深く議論をしようとテーマが設定された。
ミライを展望した地方議会の政策サイクル―到達点ともう一歩
セミナーでは、まず江藤教授が、「ミライを展望した地方議会の政策サイクル―到達点ともう一歩」と題し講演。江藤教授は、00年の地方分権一括法によって議会の重要性が増したと指摘。議会基本条例が各地に広がり、住民参加や議員間討議、執行機関との政策競争などが明確に位置付けられ、議会のイメージを変えたが、あくまで議会運営や議員活動のルール化であり、「住民の福祉の向上という成果につなげていくことが重要」と強調。そのためには、議会からの政策サイクルの構築が必要だと話した。
また、「執行機関は4年間、当たり前のようにサイクルを回している。議会側も年間の行動計画を立て、執行機関と政策競争するかどうかが問われている」と指摘した。さらに、コミュニティとの関係については、住民と議員(議会)、執行機関の三者で議論する「フォーラムとしての議会」の必要性を訴えた。

全国各地の議会から参加。熱心に講演に耳を傾けた。
コミュニティ自治の変容とミライの地方議会・地方議員~コミュニティを議会からの政策サイクルへ!~
次に、大杉覚・東京都立大学教授が「コミュニティ自治の変容とミライの地方議会・地方議員~コミュニティを議会からの政策サイクルへ!~」と題して講演した。大杉教授は、ミライの地方議員は、地域づくりの先導役・伴走役・媒介役として「コミュニティ・リーダー」、ミライの地方議会は、コミュニティ自治との連携・協働の実質化を図る「コミュニティ・ガバナンスの舵取り役」であると述べた。
さらにコミュニティ自治については、
①「担い手不足」以前に、「とりこぼし」されがちな若者・女性・社会的弱者の包摂
②若年世代を軸に多世代・多分野・多地域間での「人財の好循環」の形成
③「巻き込む」ではなく「誘い出す」へ(「課題解決」よりも「楽しい」「没入感」が場づくり“成功”の共通項)
──という構造転換が求められるとした。そして、手続の中で「参加」や「協働」などが語られることはあっても、特にコロナ禍を機に「魂の入った住民自治が干からびてしまっていないか」と危機感も添えた。
大杉教授は最後に、「コミュニティと議会は『合わせ鏡』の関係。だからこそ、両者を政策・人材の両面から接続することが重要だ」と述べた。
2つの議会の取り組みを紹介
実践報告「コミュニティと議会の関係──その現在地と展望」では、2議会が登壇した。
「むらづくり基本条例」の制定
まず、長野県宮田(みやだ)村の上條雅典・同村議会事務局長が発表。同村は、17年12月に「むらづくり基本条例」を制定(18年1月1日施行)。この条例は住民、議会、行政の3者がワークショップや会議を繰り返して部会案を作成したのち、全体集約、調整を図って策定したもの。条例に基づき、村議会では条例検証委員会やむらびと会議、議会なんでも相談室など住民参加の多チャンネル化を進めていることを紹介した。
議会は住民自治のプラットフォーム
次に、兵庫県西脇市議会の林晴信議員(前議長)が「議会は住民自治のプラットフォーム」と題して、同議会の取り組みを紹介した。
同議会の議員定数は16人、21年10月の前回の市議選では新人7人が当選。「安心・信頼・対話」をキーワードに議会活動に取り組んでいる。
コミュニティとの接点では、同議会は、「議会と語ろう会(議会報告会)」を年間20自治会を対象に実施し、市内活動団体とも年間10~12回程度実施しているという。常任委員会では「課題懇談会」として、市内活動団体と特定課題についての意見交換会を年間8~10回程度実施している。
参加者の偏りがあったり、議論ではなく文句などに終始する場となってしまったりすることから議会報告会をやめてしまう議会もある中で、林議員は、ターゲット層がいる場所に出かけることでこの課題が解消したという。また、それでも出てくる要望やクレームについては「それらから課題を抽出することが議員の仕事だ。その背景を考えることが大事だ」と参加者に呼びかけた。
林議員は、「住民自治にとって議会はなくてはならないものだ。住民自治は議会が根幹となって進展していく。乗る人も降りる人も行き交う土台だ。議会は住民の中にあることを全議員で共有することが大事だ。みなさんの議会はそうなっているか」と問いかけ、締めくくった。
2040年のコミュニティと地方議会/パネルディスカッション
後半は、登壇者らが揃い「2040年のコミュニティと地方議会」というテーマでパネルディスカッションが行われた。講演や実践報告の内容を、会場からの質疑も受けながら深めた。会場には全国から約70人の議員が参加、その他にオンラインでも多くが参加した。人口減少が急激に進み、地方議会のなり手不足が問題となる中で、今の地方議会の当事者が未来の地方議会と真摯に向き合う機会となった。

パネルディスカッション(コーディネーター・千葉茂明上席研究員)では、思考実験的なアイデアも披露されるなど、未来の議会・議員について議論した。
(本誌/浦谷 收)