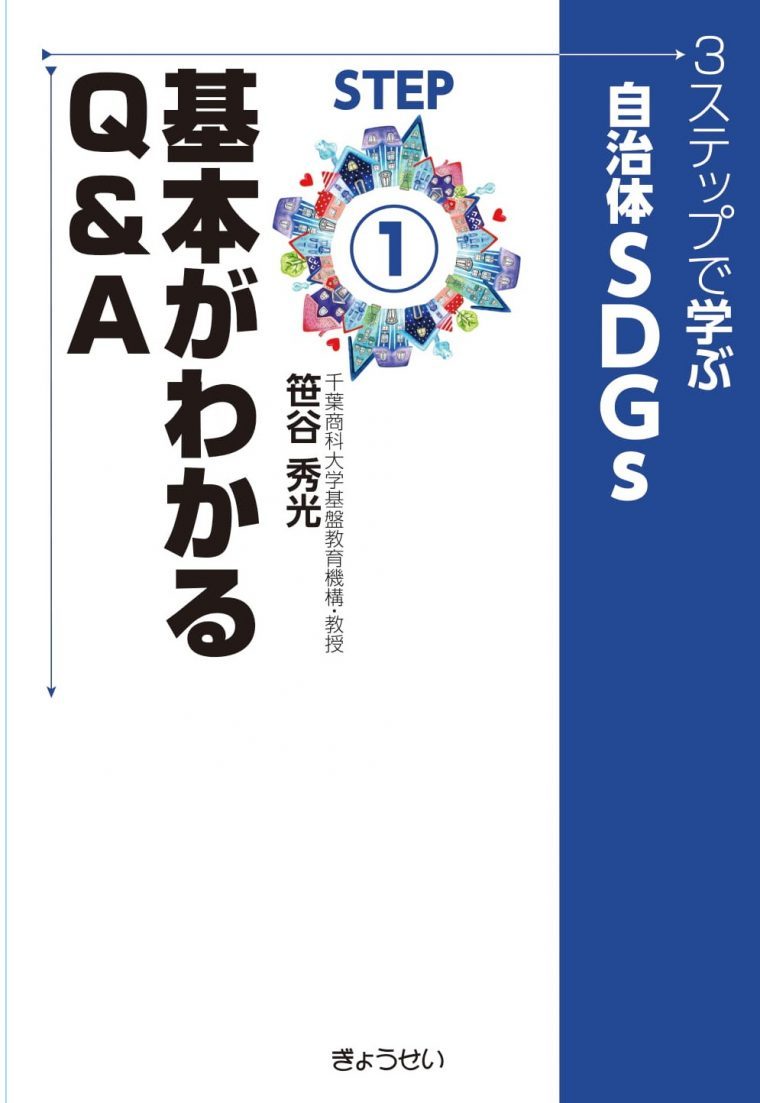「サステナビリティが主流の時代、羅針盤『SDGs』で協創力」をテーマに「第6回未来まちづくりフォーラム」を開催
時事ニュース
2024.03.26
目次
「第6回未来まちづくりフォーラム」(実行委員長:笹谷秀光千葉商科大学教授)が2024年2月21・22日、東京都内の会場で開催された。
同フォーラムは、持続可能なまちづくりの実現を志す自治体、企業、関連セクターが一堂に会し、最新事例の共有を通じてお互いの理解を深めるとともに、ネットワーキング企画を通じて新たな「協創力」を生み出すプラットフォームだ。
第6回目となる今回のテーマは、「サステナビリティが主流の時代、羅針盤『SDGs』で協創力」。サステナビリティが経営の主流であるという価値観がスタンダードになった今、持続可能な未来のまちづくりには、SDGsによる経済・社会・環境の三位一体の解決が必須であるとして、フォーラムを開催した。自治体の首長が登壇したプログラムを中心に紹介する。
官民連携で整備した絶景スポットを拠点に観光誘客を図る~山梨県笛吹市
1日目の2月21日は、「自治体と企業による共創事例ピッチ」として、自治体と企業の共創の取組が紹介された。
冒頭、挨拶に立った笹谷秀光・未来まちづくりフォーラム実行委員長は、2024年をポストSDGsの検討元年として宣言し、持続可能な開発目標の年次である2030年に向けて、「皆さんとともに次のSDGsをどうするかについて考えていきたい。政府、自治体、企業がそれぞれ何をやるか、未来まちづくりフォーラムでヒントを見つけて帰ってほしい」と話した。
山梨県笛吹市の山下政樹市長と(株)JTBは、「三方良し 笛吹市における旅行者に魅力的な観光まちづくり」をテーマに発表した。
山梨県の河口湖は、多くの外国人観光客で賑わっているが、河口湖だけを観光して帰ってしまうケースが多く、どのように県内の他地域にも周遊してもらうかが課題となっている。そこで、インバウンド誘客に向けた魅力的なコンテンツとして笛吹市が設置したのが、「FUJIYAMAツインテラス」だ。眼下に広がる河口湖と、優美な富士山の姿が楽しめる2つのテラスがあり、絶景スポットとして話題を呼んでいる。
公共の資金によって民間が施設の設計・施工・維持管理・運営を行うDBO方式を採用し、(株)JTBが運営等を行っている。DBO方式により市としては、民間の優れた発想力やアイデアを活用でき、コストも抑えられるメリットがある。
観光の拠点として期待されるほか、山下市長は、「人口減少が進む笛吹市では、『FUJIYAMAツインテラス』を活かして移住・定住を後押ししていきたいという狙いもある」と話す。
売店などを含めた「FUJIYAMAツインテラス」の集客交流拠点が、いよいよ2024年4月にオープンする予定だ。「ぜひとも多くの皆さんにお越しいただいて、笛吹市の魅力を知ってほしい」(山下市長)。
会場では、笛吹市の新ソウルフード「ラーほー」が配布された。「ラーほー」は、山梨県の郷土料理である「ほうとう」をもっと気軽に、もっと多くの観光客らに楽しんでほしいという思いから開発した「ほうとう麺を使用したラーメン」。山下市長のアイデアから商品開発につながったという。
市長がリーダーシップを発揮し、民間と協創しながら魅力的な観光まちづくりを推進する笛吹市の取組は、大いに他の自治体にも参考になりそうだ。

市民がしあわせを実感できる都市の実現に向けてSDGsを推進~さいたま市
2日目の2月22日は、キーノート・トークとして、さいたま市の清水勇人市長が、「さいたま市 SDGs未来都市の挑戦」をテーマに登壇した。
さいたま市は、日本経済新聞社のSDGs全国市区先進度調査において、2020年、2022年と2回連続で総合ランキング第1位を獲得している。評価に至った理由として清水市長は、「SDGsの『誰一人取り残さない社会』という理念と、当市が以前から進めてきた『市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市』という理念とが合致した」ことを挙げた。
2019年にSDGs未来都市に選定されてからSDGsをキーワードに経済、社会、環境の3分野で様々な課題の総合的な解決に向けて取り組んできたという。
経済分野では、さいたま市に6つの新幹線が乗り入れている立地の優位性を生かして、東日本各地域との連携を進めている。
一方、社会分野では、市民満足度を市役所経営における最も重要な指標と位置付け、2030年までに市民満足度90%を目指す「さいたま市CS90+運動」に取り組んでいる。
環境分野では、脱炭素社会に向けて様々なごみ減量施策を推進中だ。また、今後は木くずやプラスチック等のリサイクル化を強化し、2030年度までに市の事業における温室効果ガスの排出量を51%削減することを目標に掲げた。
最後に清水市長は、「21世紀半ばを見据えた新時代にふさわしい都市へと進化させていくには、誰一人取り残さず、誰もが住みやすく、かつ持続可能な地域社会を創造していく必要がある。本市の新時代に向けて、たえず進化していかなければならない」として、「市民の皆さん、企業の皆さんのお力をしっかりと都市経営の中に取り込みながら、その力をフルに活用させていただき、さいたま市をさらに進化させたい」と締めくくった。

まちの活力維持に欠かせない地域人材の育成~岡山県真庭市
スペシャル・パネルディスカッション「未来の世界と日本のデザイン~ESGの本格化、VUCA時代をどう乗り越えるか―well-beingの実現と人的資本への対応―」には、パネリストの一人として、岡山県真庭市の太田昇市長が登壇した。
真庭市は、2005年に9町村が合併して誕生した。かねてより、木質バイオマスなどの地域資源を活用した自然再生エネルギーの創出を中心に、脱炭素のまちづくりに取り組んできた。2018年にSDGs未来都市に選定されたほか、2020年に「ゼロカーボンシティまにわ宣言」を行うなど、市民や企業とともに、持続可能な地域づくりに取り組んでいる。
太田市長は、「自治体の仕事は、幸せづくりの条件整備をすること」であるとして、「東京の真似ではなく、真庭にあるものを活用したまちづくりが大切だ」と話した。
真庭市出身で、京都の大学へ進学、京都府職員、京都府副知事経て2013年に真庭市長に就任した太田市長は、真庭市に戻ってきて改めて農山村の魅力を実感しているという。
「人口減少が進む中、まちの活力を維持していくには、『人口×1人の活動量』が重要となる」(太田市長)。そのための人づくりの取組として、「真庭なりわい塾」が2016年に開講された。真庭市をフィールドに農山村における新たな生き方と多様な働き方を模索し、創造する人材を育成する塾である。
塾の卒業生は、他自治体からの移住者、Uターン者、元真庭市地域おこし協力隊など多岐にわたる。それぞれ、地域のりんご農家を受け継いだり、真庭なりわい塾の運営に携わったり、真庭市役所へ就職するなど、真庭での新しい生き方“真庭ライフスタイル”に踏み出している。
また、全国で地域おこし協力隊が地域にうまく定着しないなどの課題が見られるが、真庭市では隊員の退任後の定着率は78.2%と全国平均の65%に比べて高い。在任中から地域課題にチームで向き合うことで、退任後は多様な起業につながっているという。
全国各地で人口減少・少子高齢化が進展する中、持続可能な地域づくりに向けては、地域人材の育成がキーポイントとなることを真庭市の取組を通じて実感させられる。

関連書籍
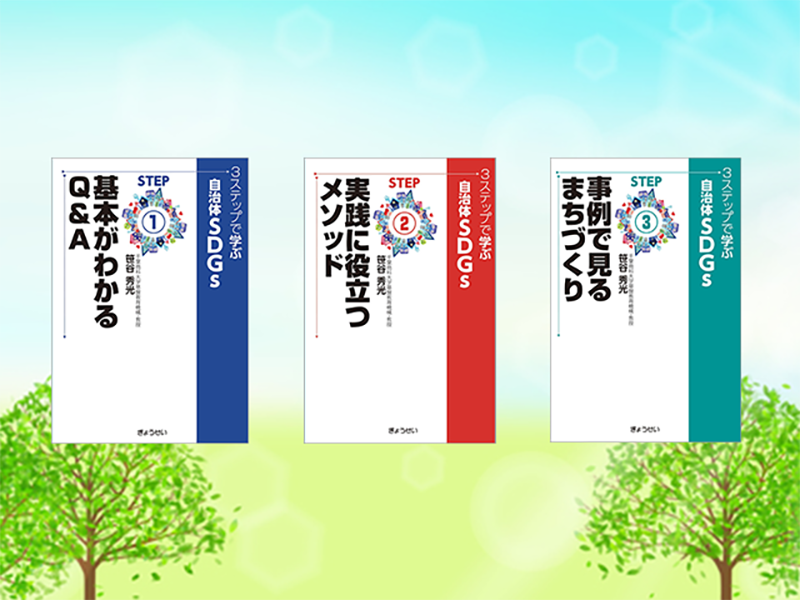
『3ステップで学ぶ 自治体SDGs』全3巻 笹谷秀光/著
(発行年月: 2020年11月/販売価格: 1,650 円(税込み))
▽SDGsの理解は、まずはここから!
3ステップで学ぶ 自治体SDGs 第1巻 STEP1 基本がわかるQ&A
https://shop.gyosei.jp/products/detail/10525
▽実際に取り組むためのヒントが満載!
3ステップで学ぶ 自治体SDGs 第2巻 STEP2 実践に役立つメソッド
https://shop.gyosei.jp/products/detail/10526
▽先進的な取組み事例からノウハウを学ぶ!
3ステップで学ぶ 自治体SDGs 第3巻 STEP3 事例で見るまちづくり
https://shop.gyosei.jp/products/detail/10527
▽全3巻セット
3ステップで学ぶ 自治体SDGs 全3巻セット
https://shop.gyosei.jp/products/detail/10524