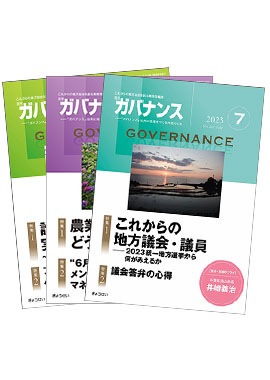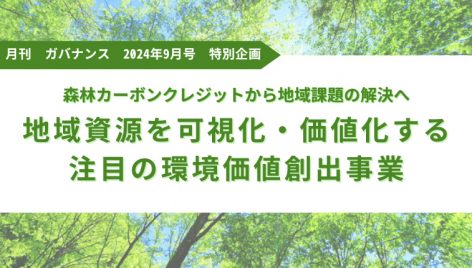新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第39回 熊本地震のミライ
時事ニュース
2023.09.26
本記事は、月刊『ガバナンス』2016年6月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
2016年4月14日21時26分に熊本県益城町で最大震度7を観測する地震が発生した。その後、4月16日1時25分に、同じく同県益城町などで最大震度7を観測する、よりマグニチュードの大きい地震が発生した。結果的には、後者の地震が、「熊本地震」の「本震」とされた。
一般の想定では、最初に大規模な「本震」があり、その後、「余震」が続くというイメージがある。ところが、今回は、本震クラスの「前震」に初動対応をしているところに、あるいは、初期の避難を終えて自宅に戻るなどをしていた矢先の深夜に「本震」が発生した。
自然の可能性は人知を超えるところがある。熊本県内・大分県内を中心とする被災自治体は、このような「想定外」に対して、取り組むことを迫られている。
地震の命名権

一般に、今回の地震は「熊本地震」と呼ばれている。これは、被害が熊本県内に限定されている印象を与えかねない。しかし、例えば、由布市や別府市では震度6を観測している。『大分合同新聞』16年5月3日付朝刊では、「熊本・大分地震」と呼称したうえで、大分県内の被害を集約して報道している(注1)。
注1 大分県庁ホームページは「熊本地震」と表記している。むしろ、「風評」を避けたいのかもしれない。
もっとも、この点は難しいことであり、例えば、多くの死者・行方不明者が出ている熊本県内と、そうではない大分県内とを(注2)、同列に呼称すべきかは、判断が分かれ得る。より大きな被災を受けたところにより多くの支援をすべきならば、熊本県内を優先すべきであり、名称も熊本が自然かもしれない。
注2 もちろん、被害の大小は死者・行方不明者だけで判別できるものではない。
ともあれ、自治体にとって最も重要な任務の一つは、被災しているという声を発することである。自治体は、災害の命名権(ネーミング・ライツ)を簡単に国(気象庁など)やマスコミに譲り渡してはいけない。
職員削減と災害対応現業の基礎体力低下

日本では、長期にわたって自治体の行政職員は削減されてきた。このようななかで災害に直面すると、自治体、特に第一線の市町村は圧倒的なマンパワー不足に至る。東日本大震災のように、自治体職員のかなりの数が被災することでマンパワーが減る事態は、熊本地震では顕著ではなかったかもしれない。しかしながら、もともと行政職員の人数が多くないので、大きな制約になる。
例えば、全国から支援物資が搬送されても、それを避難所や被災者に届ける人手が足りない。通常の自治体の行政改革のイメージでは、「物を運ぶ」現業的業務は、行政職員が直営せず、民間企業に委託に出すことが合理的だ、となる。あるいは、「ロジスティクス」業務は極めて高度のノウハウを要するから、専門能力のある民間企業に委託に出すことが合理的だ、となる。実際、物資を仕分け管理するのは、宅配業者などの方がはるかに長けていよう。
しかし、災害の初動段階では、必ずしもそうは簡単に行かない。民間自体も人手不足である。行政としては発注に出しようがない。民間企業/市場機構が、短期的にせよ、機能しなくなるのが災害である。市場機構が機能しなければ、行政で独自に対応するしかない。ところが、今の自治体はもともと人員が不足している。しかも、「物を運ぶ」現業的業務から縁遠くなり、行政でなければできない仕事─合意形成のような調整業務、権力を行使する業務、文書業務など─が中心となり、ロジスティクスのノウハウを鍛える機会が減っている。自治体の基礎体力は長期的に低下している。
それ以外にも、罹災証明・被災証明のように、現業的というよりは、いかにも「役所らしい」公証業務であっても、マンパワー不足は深刻である(注3)。
注3 市町村が行う応急危険度判定でも同じであるが、これはもともと、事務屋を中心とする行政職員には適した仕事ではないため、民間ボランティア的に応急危険度判定士が主力となる。
人員不足への対処
このように行政職員の能力に限界があるときに、防災の「教科書」的解答は、〈自助・共助・公助〉論である。つまり、公助=行政は、手が回るはずはないから、住民自身の自助や、住民同士・地域社会の共助が大事だ、ということである。一般論としては正しいが、公助ができないような状態では、自助・共助も大して期待できない状態である。自助・共助では対応ができないから、災害なのである。
そこで登場するのが、自治体間の広域・遠隔の職員応援である。警察・消防・医療関係者では、応援体制が先行して整備されてきた(注4)。東日本大震災では、自治体間の広域・遠隔の応援が展開された。恐らく、今後も、避難所設営や物資配分、罹災証明・被災証明など、初動段階から対応できる、自治体間の行政職員の即応援助システムの強化が求められよう。
注4 自衛隊や国土整備局などは、国からの支援である。
もっとも、そうは言っても、受援力を被災自治体が持っていることも重要である。受援計画だけではだめである。こうして考えると、ある程度、「無駄」に見えるような人員を、市町村は抱えていなければならないだろう。
非常災害への政令指定

5月10日に政府は、熊本地震を「大規模災害からの復興に関する法律」第2条第9号(特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害)に基づき「非常災害」とした。この結果、災害復旧事業に関して、被災自治体を補完するために、被災自治体の要請に基づいて、国などが工事を代行できるようになった。これは東日本大震災の教訓を踏まえた仕組みであり、同法に基づいて政令指定されるのは熊本地震が初めてである。実際、熊本県が政令指定を要望しており、前日9日にも、蒲島郁夫知事が各省庁に財政支援の陳情に回っていた。自治体が声を発したことの成果である。
「補完性の原理」から言っても、自治体ができないことを国が補完することは重要である。今後とも、災害に応じて、徐々に復旧できないインフラの放置が進むことが懸念される(注5)。あるいは、「ショック・ドクトリン」的に災害を契機として、インフラの集約・再編が住民合意のないままに進められる危険もある。その意味で、自治体側からの要請と発意によって、国が補完・支援することは重要である。
注5 民営化されたJR では、災害があると、線路の復旧が必ずしも迅速に行われないまま、運休・不通となることがある。例えば、三陸鉄道は復旧(2014年4月)しているが、山田線沿岸部(宮古・釜石間)は復旧していない。
しかしながら、東日本大震災の半面の教訓は、国の支援が、自治体や地元住民の意向と、いつしかかけ離れた事業計画になり得ることでもある。国には国の意思があり、それを実現しようとするだろう。それが自治体や地元住民の意向と合致していれば、問題はない。しかし、一致していない場合には、自治体や地元住民はハムレット状態に追い込まれる。国は、「国が考えるこのメニューならば提供できます。しかし、地元が要らないならば無理やりはしません。そのときは、地元が自力で頑張ってください」ということになる。
自治体・地元住民は、国からの支援を受けることを優先して自らの意に沿わない事業計画を受け入れるか、自らの意を重視して国から支援を受けられないで放置されるか、という苦渋の選択を迫られる。もちろん、国が自治体・地元住民の「意を汲んだ」(注6)事業計画を、最初から立ててくれれば問題はないのであるが、今のところそれを保証する手段も手続もない。
注6 月並みの実務用語では、「被災者に寄り添って」などと表現される。
おわりに
熊本地震の余震は長く続き、多くの被災者が「車中泊」を含めた避難生活を強いられている。復旧過程は息の長いものになろう。東日本大震災から5年であり、日本社会全体としては、「忘れたころに天災はやってくる」のではなく、災害の連鎖に直面する。その意味で、全ての自治体にとって、災害対応は日常業務となる。実際、地震・津波以外にも、豪雪、豪雨、洪水・氾濫、土砂崩れ、台風、竜巻・強風、超高温、渇水、噴火など、さまざまな形態で襲ってくる。自治体のミライのためには、国による補完だけではなく、相互に協力して、人員や財源のプールを作って、災害に備える必要が高まっているだろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。