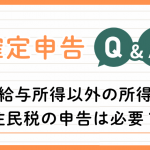新・地方自治のミライ
「新・地方自治のミライ」 第47回 辺野古紛争と地方自治のミライ
時事ニュース
2023.12.15
本記事は、月刊『ガバナンス』2017年2月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【連載一覧はこちら】
はじめに
この連載において、2000年分権改革後の地方自治における最大の問題の一つであるという観点から、辺野古基地建設問題を何度か採り上げてきた。この政治問題は法廷闘争に持ち込まれて法的問題の側面をもったため、第44回(16年11月号)および第45回(同12月号)では、16年9月16日の福岡高裁那覇支部判決について、政治学的観点から論評した。その後、16年12月20日に最高裁判決がなされた。口頭弁論が開催されないこともあり、沖縄県側敗訴の見通しは事前に明らかになっていたが、その通りの判決となった。
当該辺野古訴訟が「法力」装置によって、法的紛争としては「決着」した。沖縄県側は、仲井眞弘多・前知事による公有水面埋立の承認処分について、翁長雄志・現知事が取消した処分を、最高裁判決を受けて撤回した。これにより、前知事の埋立承認処分の効力が復活し、国側は直ちに建設工事を再開させた。いわば、法廷闘争以前の状態に復帰したといえる。そこで、辺野古紛争のミライを検討してみたい。
最高裁判決の「法力」

判決によれば、「その取消しにより名宛人の権利又は法律上の利益が害される行政庁の処分につき、当該処分がされた時点において瑕疵があることを理由に当該行政庁が職権でこれを取り消した場合において、当該処分を職権で取り消すに足りる瑕疵があるか否かが争われたときは、この点に関する裁判所の審理判断は、当該処分がされた時点における事情に照らし、当該処分に違法又は不当(以下「違法等」という。)があると認められるか否かとの観点から行われるべきである」(判決理由6頁)とする。「したがって、本件埋立承認取消しの適否を判断するに当たっては、本件埋立承認取消しに係る上告人(筆者注:現知事)の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用が認められるか否かではなく、本件埋立承認がされた時点における事情に照らし、前知事がした本件埋立承認に違法等が認められるか否かを審理判断すべき」(同6頁)とする。
そのうえで、都道府県知事の公有水面埋立承認権限は、「知事の裁量的な判断であることを前提に」しているのであって、公有水面埋立法は承認のための「最小限の要件を定めたものと解される」(同7頁)とする。つまり、最初の埋立承認処分については、知事の裁量権が大きく、「当該公有水面の利用方法として最も適正かつ合理的なものであることまでが求められるものではな」く、「総合的な考慮をした上での判断が事実の基礎を欠いたり社会通念に照らし明らかに妥当性を欠いたりするものでない限り」は、承認の「判断に瑕疵があるとはいい難い」(7頁)という結論になる。
以上のように、最高裁判決は、「法力」装置の本分に立ち返って、政治(統治)行為に踏み込むことを回避しながら、国側勝訴の結論を導いた。「法力」装置は、所詮は国家という統治権力の「御威光」に支えられたものであるから、正面から、国政政権の「御威光」を否定する判決を行うことは難しい。しかし、露骨に国政権力の意向に従ったかのように「誤解」を受ける判決は、「司法権の独立」という小威光を自ら否定することになり、ひいては、「法治国家(ごこうぎ)」の「御威光」を阻害する。そのような事態を回避しつつ、所期の結論を導いたという意味で、最高裁判所は、その璧を完うした。
「法力」と政治紛争

国と自治体との政策判断が異なる場合に、それに起因する政治紛争を、裁判所の「法力」によっては解決できない。国および自治体の政策判断は、それぞれの政治的基盤に支えられたものであって、政治紛争を解決することは、「政治交渉」による政治的解決しかあり得ない。「法力」によって法的紛争は「解決」され、「法力」に根拠を持って実力を行使することは法的には可能である。しかし、それは、政治紛争を解決することを意味しない。
重要なことは、政治的基盤に支えられた政策判断が、裁判後にどのようになるかである。実力・金力または「法力」などの権力資源は、広い意味での政治権力に繋がるのであって、それによって政治的基盤や政策判断が変化することはある。もっと言えば、政治的意向を変えさせるように権力を行使することが、広い意味での「政治交渉」である。権力行使は、結果的に、政治的意向を変化させることはあり得る。例えば、南沙諸島のように埋立工事が実力によって進行してしまえば、そうした「既成事実に屈服」しがちになることは、弱小政治主体の立場から言えば起こりやすい事態である。南西諸島での埋立工事も同様である。
「自治体が国に抵抗しても無駄だ」という諦観が生じれば、国と自治体の間の政治紛争は表面的には「消滅」する。自治体や住民が内面において、国の政策判断と同一化すれば、国によって意に反する判断を強要されることはない。同化をする方が、精神的にも政治的にも容易な道である。国から意に反した政策を強要されないという意味において、「自治」が開花する。しかし、それは自治そのものの否定である。国の政策判断に同化するだけならば、自治体に存立理由はない。なぜならば、国の意と異なる自治体の意を持つ自治が存在しないからである。
おわりに

自治体が国と異なる政策意向を、貫徹することは容易ではない。加えて、自治体は、本来の意に反した既成事実の蓄積のなかで、国と異なる政策意向を保持し続けることも、容易ではない。なぜならば、国は大きな権力を持っているからである。2000年分権改革の標語である「対等・協力」とは、あくまで「未完の目標」に留まる。
しばしば、権力があれば不服従は維持でき、権力がなければ服従になる、という二極の往復になりやすい。権力の弱小な側は、自大派と事大派、徹底抗戦玉砕派と無条件降伏派、反乱と奴隷、など両極に分裂しやすい。それは、弱小な自治体において、さらに内訌・内紛を生みやすく、ますます、自治体の政治的基盤を弱体化させがちな悪循環(国から見れば「好循環」かもしれない)に陥りやすいものである。
自治体は、権力的には劣勢であるがゆえに、国とは異なる政策意向の自治は保持し続けるという、「非権力・不服従」を持つことは容易ではない。それこそが、自治の難しさであり、また、必要性でもある。「非権力・不服従」に価値がないならば、近代立憲主義国家において自治は無用である。
権力があることが実力による反乱に直ちに結びつかないように、権力があることが直ちに他を服従させることにつながらないように、不服従が直ちに権力奪取を求めることにつながらないように、権力がないことが直ちに服従という隷属に結びつかないように、するのが、統治機構としての自治制度の役割である。
辺野古紛争のミライにおいて問われるのは、権力を持たない自治体側が、いかに内紛を避けて、「非権力・不服従」を維持し続けるかである。これは決して容易ではない。国側は、自治体の内紛を期待・助長し、あるいは、「懲罰」的な権力支配を試みるかもしれない。これに対して、自治体側には国への恭順を示す転向の主張が勢いを増すかもしれない。しかし、恭順したからといって自治体・住民側に国が充分な配慮をする保証もない。とはいえ、短期的には「面従腹背」の姿勢を採ることが、戦術的には必要になるかもしれない。いずれにせよ、こうした綱渡りが、自治における為政の苦心であり、やりがいなのである。
辺野古基地建設問題は沖縄県での問題であるが、同種同様の問題は、全国の自治体に不可避のことである。国の強大な権力の前に、自治体の政策意向を保持し続けることが難しい局面に立たされることは、いつでもどこでも生じうる。そのような厳しい条件のなかで、どのように振る舞うのかが、地方自治のミライを左右するのだろう。
Profile
東京大学大学院法学政治学研究科/法学部・公共政策大学院教授
金井 利之 かない・としゆき
1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学助教授、東京大学助教授などを経て、2006年から同教授。94年から2年間オランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書に『自治制度』(東京大学出版会、07年)、『分権改革の動態』(東京大学出版会、08年、共編著)、『実践自治体行政学』(第一法規、10年)、『原発と自治体』(岩波書店、12年)、『政策変容と制度設計』(ミネルヴァ、12年、共編著)、『地方創生の正体──なぜ地域政策は失敗するのか』(ちくま新書、15年、共著)、『原発被災地の復興シナリオ・プランニング』(公人の友社、16年、編著)、『行政学講義』(ちくま新書、18年)、『縮減社会の合意形成』(第一法規、18年、編著)、『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、19年)、『行政学概説』(放送大学教育振興会、20年)、『ホーンブック地方自治〔新版〕』(北樹出版、20年、共著)、『コロナ対策禍の国と自治体』(ちくま新書、21年)、『原発事故被災自治体の再生と苦悩』(第一法規、21年、共編著)など。