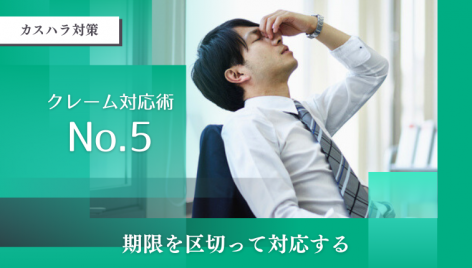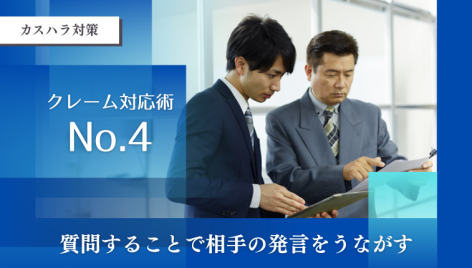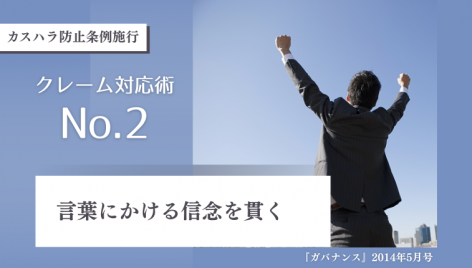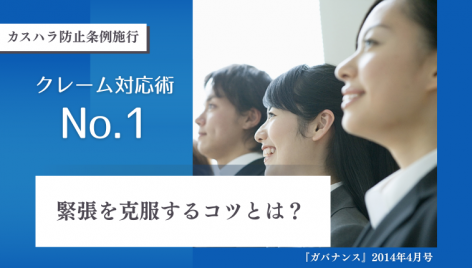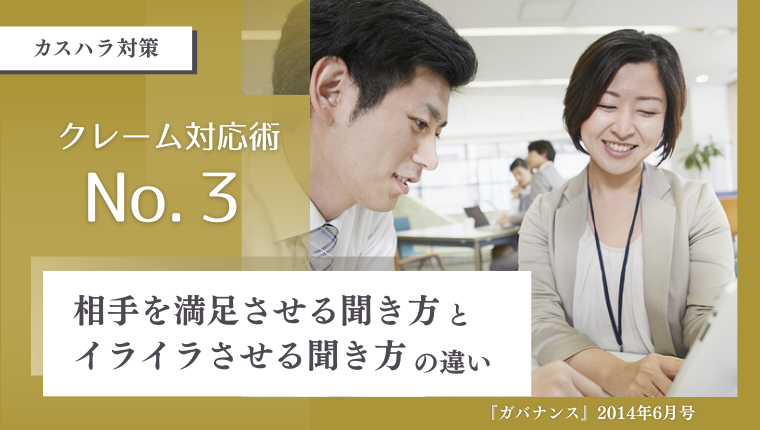
クレーム対応術
相手を満足させる聞き方とイライラさせる聞き方の違い|クレーム対応術3【カスハラ対策】
キャリア
2025.03.21
【コラム】クレーム対応の会議を定例化する

クレームは、いつ、誰から持ち込まれるかわからない。また、同じ用件でも、人によって主張の仕方やニュアンスが違うので、同じ状況は二度とない。では、クレーム対応には準備ができないかというと、そうではない。
多くの職場では、クレームで問題が起こった場合には当事者、関係者だけが話し合いを行い解決に導く。事態が収拾すると報告書を作成し、何事もなかったかのように元に戻る。これでは、当事者個人の経験にはなるが、組織としての経験値にはなりにくい。
ポイント2で述べたとおり、メモ程度でもかまわないし正式なものでなくてもよいので、クレーム対応の記録を残しておきたい。別途、組織に報告書や記録の決め事があれば、もちろんそれでもよい。
また、多く寄せられる案件、重要と思われる案件については、そのことを題材にして話し合いを持つとよい。クレームだけを取り上げる会議である。
つまり「この案件が、他のお客さまから持ち込まれる可能性がある」「次の対応者は自分かもしれない」「次に来たらどうする」という感覚で話し合う。次回以降に同じお客さまが同じ案件で来訪された場合には、前回と統一した見解を示し、対応策を一致させることができる。
これを、一般行政の窓口であれば、月に1〜2回、20〜30分程度行う。年間12 〜24 回、異動するまで3年とすると36〜72回できる。次に来たらどのように対応するか、現実味と興味が増しクレームに挑戦したい気にもなるだろうし、クレームを受けるストレスが軽減される。こういった話し合いの定例化が、職場のムード、風土を作る。
月刊『ガバナンス』で好評を博した連載「クレーム対応駆け込み寺」を加筆修正、再構成し単行本化
クレーム対応のさまざまな悩みを解決!
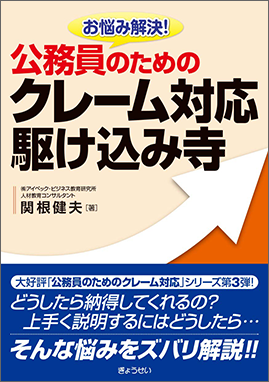
お悩み解決!
公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 編著者名:関根健夫/著
販売価格:2,420 円(税込み)
詳細はこちら ≫
【こちらもおすすめ】
弁護士が相談を受けた“現場の困った”要求にどう対応するか(業界別に)分かる!!

Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック
-平時の備えと有事の対応- 編著者名:日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会
販売価格:3,630 円(税込み)
詳細はこちら ≫
カスハラをはじめとする不当要求行為等について、実際の事例から対応を学ぶ!

自治体職員のための
不当要求行為対応ブック
-事例からわかるトラブル回避策- 編著者名:宇都木法律事務所(代表弁護士 宇都木 寧)
販売価格:3,080 円(税込み)
詳細はこちら ≫