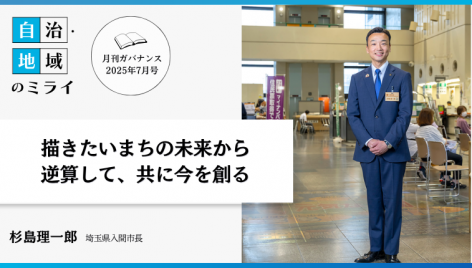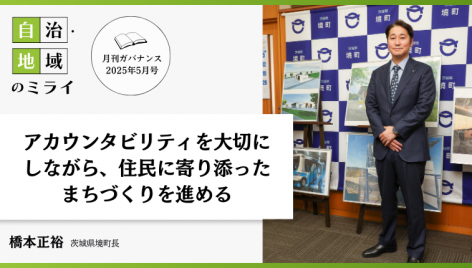自治・地域のミライ
自治・地域のミライ|私主語で描く多世代コミュニティの未来 株式会社三菱総合研究所 主席研究員 松田智生
地方自治
2025.07.30

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年8月号
★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
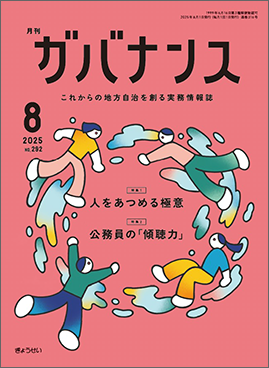
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫
株式会社三菱総合研究所 主席研究員
松田智生
高齢者が元気なときから介護時まで安心して暮らせるコミュニティ、CCRC(Continuing Care Retirement Community)。米国で始まったこの取り組みを2010 年にいち早く日本に紹介したのが、三菱総合研究所主席研究員の松田智生さんだ。その日本版CCRCはいま、地方創生2.0基本構想で日本版CCRC2.0として動き始めた。CCRCの普及のほか、都市部の会社員と地方をつなぐ「逆参勤交代」など、都市と地域が混ざり合う取り組みを提言。自らも実践してきた松田さんに、これまでの提言や地域への思いを聞いた。

生粋の東京生まれ東京育ちの松田さん。田舎がなかった松田さんにとって、地方での景色や食べ物、人とのふれあいは「第二のふるさと」を感じさせる。恩返しをしたいという気持ちなのだという。
普段出会わない人、普段行かない場所、普段しないような体験をすると、化学反応が起きる。
縁×運×恩
――松田さんが「地域」と関わりをもつきっかけは。そして、どのように「地域」と向き合ってきたか。
三菱総合研究所では、2010年にシルバー社会を超越した「プラチナ社会」を構想するために、プラチナ社会研究会を設立し、その構築に向けた研究を開始した。
私は生まれも育ちも東京。小さい頃に夏休みに祖父母のところへ帰省する、という経験がなかった。研究会のメンバーとなり、プラチナ社会の地方創生、活力ある高齢社会の研究をするために地方に出かけることが多くなったことが地域との関わりが増えたきっかけだ。
地域と関わる中で、世の中は「縁×運×恩」と強く思うようになった。良い縁ができれば、運が開ける。それに対して恩返しをしていく。私は取り組む中で地域と良い縁ができていった。とても運が良かったと思いつつ、自治体へのアドバイスや、様々な取り組みを通じて恩返しが少しでもできているのではないかと感じている。
明るいカルチャーショック
――その中で、松田さんが提言をし続けてきたのが「日本版CCRC」。その今日までの変遷は。
CCRC(Continuing CareRetirement Community) とは、高齢者が健康時から介護時まで継続的なケアを受けながら住み続けることができるコミュニティのことで、米国では約2000か所、約70万人が居住している。市場規模は約7兆円ともいわれている。
私は2010年に先のプラチナ社会構築のための研究の一環として、米国のCCRCを初めて訪問した。訪れたニューハンプシャー州ハノーバーでは、平均年齢84歳のシニアが約400人暮らしていた。8割が元気で、2割が重介護や認知症の方だった。まちにあるダートマス大学と連携し、生涯学習を学び、様々な委員会も皆で分担し、いきいきと暮らしていた。地域に約300人の雇用を創出している。また、居住者の健康データを解析し、元気でいられるような提案もしていた。介護にさせないで儲ける、健康にいてもらうために儲けるという仕組みを目の当たりした。まさに「明るいカルチャーショック」を受けた経験だった。CCRCは「個人のQOLの向上」、「地域活性化」、「新たなビジネス」という個人・地域・産業の三方よしだった。
米国でみた景色はたしかに素晴らしいもので、衝撃的なものだったが、そのまま受け入れるだけではだめだと感じていた。医療制度も社会保険制度も国民性も違うからだ。本来、CCRCは高齢者のQOL向上のためのものだったが、日本に合ったモデルとして、「多世代」というところに重きを置き、2015年に「日本版CCRC(*)」としてその有望性を提言してきた。基本理念は「カラダ・オカネ・ココロ」の3つの安心だ。
この日本版CCRCでは、「高齢者のQOL向上と多世代共創のコミュニティ」と定義した。住み替えは「近隣転居型」「コンパクトシティ型」「地方移住型」「継続居住型」などに類型化し、「地方移住ありき」ではないことを強調した。人のライフスタイルが多様なようにCCRCの立地や居住者像なども多様であるからだ。そして何よりも、「行政がー」「都市がー」などではなく、「私がワクワクする暮らしができるかどうか」(私主語)で語ることが重要とした。
2015年には、当時の安倍政権の「地方創生」と方向性が合ったことで、私も委員として加わった内閣官房まち・ひと・しごと創生本部の「日本版CCRC構想有識者会議」で検討が進められ、翌16年4月の地方再生法改正につながった。日本版CCRCは「生涯活躍のまち」と名付け、制度化された。
しかし、QOLの向上よりも地方創生政策としての文脈が強まり、有識者会議の最終報告(「『生涯活躍のまち』構想(最終報告)」)でも、「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や『まちなか』に移り住み、地域住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づくりを目指すもの」と定義され、「(特に東京圏の)高齢者が地方移住」というイメージが先行してしまい「姥捨て山を作るのか」という批判を受けたことで政策の見直しが行われた。
2018年に内閣官房に「生涯活躍のまちネクストステージ研究会」、2019年には「地方創生×全世代活躍まちづくり検討会」が設置された。いずれの会にも私も委員として参加した。このような経緯で、日本版CCRCは「高齢者の地方移住」から「地元住民を基点にした多世代コミュニティづくり」と政策が転換されてきた。また、2015年には(一社)生涯活躍のまち推進協議会が設立され、CCRC普及のためにこれまで地道な活動を続けてきた。
*日本版CCRCの実現を目指す政策提言(2015年1月)
https://www.mri.co.jp/news/press/20150128-01.html

まつだ・ともお
1966 年東京生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。専門は地域活性化、アクティブシニア論。高知大学客員教授、日本福祉大学客員教授。
2010 年からCCRC の有望性を提唱し、逆参勤交代による働き方改革と地方創生の同時実現を提唱し全国で展開。内閣官房・日本版CCRC 構想有識者会議委員、
内閣府・高齢社会フォーラム企画委員、美唄市・市政アドバイザー、笠間市・公民連携審議会座長、諏訪市・関係人口創出アドバイザー、京丹後市・新経済戦略推
進会議委員等を歴任する当該分野の第一人者。主な著書に『明るい逆参勤交代が日本を変える』(事業構想大学院大学出版部)、『日本版CCRC がわかる本』(法研)。
新たなCCRCとして
2025年3月15日に石破首相が「CCRCの取り組みを強化したい」と発言したことで、私は5月に開催された、新しい地方経済・生活環境創生会議に招致された。そこで、「CCRC2.0で加速する地方創生2.0の未来」という報告を行った。
実は、石破首相も地方創生担当大臣時代に、米国の別のCCRCを視察し、居住者も従業員も明るかったことに驚いている。
CCRC2.0は、約10年前の2015年頃の従来型のCCRC(CCRC1.0)ではなく、近年動き出している各地の特徴やニーズや地域資源を活かした多世代型のコミュニティをCCRC2.0とし、従来のRetirement(退職)でなく、Relation(繋がり)を重視した「継続的な共助と繋がりのある多世代コミュニティ」(Continuing Care“Relation”Community)と定義した。
そして、6月13日に閣議決定された『骨太の方針2025』(経済財政運営と改革の基本方針2025)に「日本版CCRC2.0の全面展開」が明記された。さらに『地方創生2.0基本構想』では「小規模であっても年齢や障がいの有無を問わず様々な人々が集い、それぞれがもつ能力を希望に応じて発揮し、生きがいをもって暮らすことができる場として、小規模・地域共生ホーム型CCRCを3年後に全国で100の展開を目指す」と明記された。
CCRC2.0は、米国の模倣でも、高齢者の地方移住でもなく、地元住民基点の居場所と役割のある多世代コミュニティ(ごちゃまぜのコミュニティ)だ。主語が「地元の住民」というところに意味がある。
そして、多様な事業主体や多様な立地による萌芽が各地で生まれている。行政主導、大学主導、社会福祉法人主導──様々な組み合わせで連携し、実装されてきている。
たとえば、行政主導型での取り組みを行っている愛媛県宇和島市は、2015年に愛媛県庁で講演したことをきっかけに伴走し続けている。地域の交流拠点をベースに高齢者の介護予防と子どもの放課後教室のごちゃまぜの場を創出している。廃幼稚園を活用したりするなどストックの有効活用もしている。また、青年海外協力隊の派遣前訓練を受け入れており、人口が減少する地域で担い手として、関係人口の拡大につながっている。そして何より、担当職員が約10年異動せずに力を入れている点も大きい。高齢化率が上がる中、これらの多様な政策によって介護認定率が低下し、実際に数字として表れている。

CCRC1.0では、地方の人口減少と東京圏の介護施設不足の解決にフォーカスされ手段が目的化された。2.0では、多世代が集うことを志向している。
関係人口をつなげる
――地道なCCRCの普及の活動と同時に2017年から「逆参勤交代」の提唱も始めた。
日本版CCRCでは、高齢者だけでなく多世代を強調してきた。一方で、移住者だけに頼るのでも持続可能性はないと感じていた。
また、CCRCを提言する中で、強く感じてきたのが「一人の実践者でありたい」ということだ。「あなたの地域はこうすべきだ」と外から言うのではなく、私自身が「私主語」で「こう関わる、行動する」ということを示すことの重要性を感じていた。
移住フェアなどが盛んに行われてきたが、結局は人の奪い合いだ。年間約90万人が減少する日本では、人材の争奪ではなく、循環・共有が大事だろうと考え、都市部の大企業勤務者などに地方での“期間限定型リモートワーク”を促す「逆参勤交代」を提唱してきた。
横文字では誤解を生む可能性もあり、日本語がわかりやすいと考え、そして歴史に学ぶべきだという思いからこのように命名した。江戸時代の参勤交代は、地方大名に負担を強いた一方、地方から江戸への人の流れを作った。これとは逆に、東京から地方への人の流れが生まれれば、地方にインフラが整備され、関係人口が増加するのではないか──そういうアイディアからだ。
これは、都市に集中している富の分散、そして都市部の大企業の人たちには地方に出かけて越境学習をする機会になるとの考えだ。
普段の私たちはある意味同じような“周波数”の中で生活している。働いている業界による習慣や、同じような価値観の中にいることで同質性が高まる。しかし、逆参勤交代で地方に行くと、普段出会わない人や行かない場所、できないような体験ができる。地域は地域で、決まった序列や習慣、価値観がある。よそから来た人によってまちの魅力に気づかされ、良い化学反応が起きる。生きる力が湧いてくる。まさに学び合い教え合うという福澤諭吉の「半学半教」が実践できている。
とくに、東京駅周辺の大手町、丸の内、有楽町(大丸有地区)は大企業が集積し、就労人口が35万人にもなる。まさに東京一極集中の象徴のような地域だ。このマスボリュームを動かすことが重要だと考えている。このうちの1割でも動けば、日本にとって大きな一歩になるのではないか。何より大丸有地区にあるレストランの食材はすべて地方のものだ。裏を返せば、地方が元気でなければ大丸有は成り立たないともいえるだろう。
市民大学の丸の内プラチナ大学をプラットフォームに、様々な参加者が逆参勤交代を実践している。CCRCの活動をきっかけにお付き合いのできた自治体を中心に、いまは25自治体で実施され、多様な事例が生まれている。
都市部で働いている人がお金を払ってでも地方に行きたい、関わりたいということは強い。これまでの関係人口やワーケーションで多かった“自分探し”をしている人がなんとなく地方に関わるというのとは違う手応えを感じている。
百人の有識者より一人の実践者
――これからの「自治・地域」のミライの姿をどう描いているか。
私たちはピンチをチャンスに変える好機にいると思う。チャンスに変えるには、繰り返しになるが、主語が「私」でなければならない。「国が─」「県が─」などと他人を主語にすることから脱却すべきだ。自ら何をすべきか(must)、何ができるか(can)、何をしたいのか(will)を明確化することが大事だろう。
私はアドバイザーなどで首長と関わることも多い。首長の皆さんも自分主語であってほしいと思っている。「国は─」「県は─」ではなく、「私はこうしたい」と、変に空気を読まずに自分がワクワクして楽しむことが重要ではないだろうか。
大切なことは、「続けること、深めること、広げること」だ。CCRCの活動も地道な活動を続けてきたことで、広がり、様々な実践が生まれてきた。一過性のイベントや施策にせず、政策を産官学で深め、広域で、さらには海外などとも連携することが重要だろう。
私は「百人の有識者より一人の実践者」という思いを胸にやってきた。これからも自らが現場に飛び込んで、自分が実践者としてやっていきたい。
(取材・構成/本誌 浦谷收、写真/五十嵐秀幸)
★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!
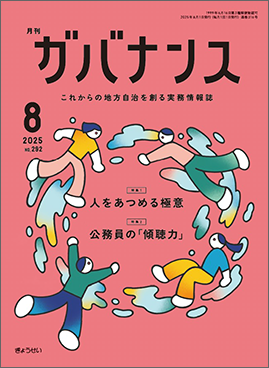
月刊 ガバナンス 2025年8月号
特集1:人をあつめる極意
特集2:公務員の「傾聴力」
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:1,320 円(税込み)
詳細はこちら ≫